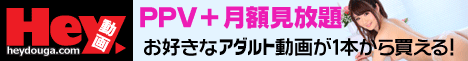新型コロナの影響で、あまり外食をしたり飲みに行ったりすることが減った。会社の同僚とのコミュニケーションも減ったが、元々そう言うのがあまり好きではなかったので、僕としてはラッキーだと思う気持ちもある。
緊急事態宣言などがなくなり、たまに外食に行ったりもするようになったが、家で食べて飲むことが多い。今日は、僕の高校のことからの友人の高広が、ウチに来ている。鍋パーティーだ。
「ホント、出歩くのが難しくなったよね。白い目で見られるし、すぐに職質される」
研二が、うんざりという顔で話す。まだ独身の彼は、コロナ禍にあっても外出していた。体力にも免疫力にも自信があるようで、あまり気にせずに出歩いているのを聞いていた。
「でも、研二さんは出歩いてるでしょ? じっと出来なさそうだもん」
七菜は、からかうように言う。研二も、笑いながら間違いないと言った。楽しい雰囲気だ。気心の知れた3人で食事をするのは、とても楽しい。妻の七菜と研二は、知り合ってからもう8年近く経つ。
3人とも、同じ大学出身だ。26歳の七菜と、28歳の僕と研二。大学でも、2年ほど一緒に過ごした。七菜と研二は、仲が良い。でも、性的な感じはないし、仲の良い友人関係にしか見えない。
「まぁね。でも、めっきり風俗とかは行かなくなったよ。さすがに濃厚接触過ぎるしね」
そんな事まで、さらっと話してしまう研二。
「もう、やめたら?研二くんだったら、普通に彼女出来るでしょ」
七菜は、研二が風俗に行くことは知っている。それを、当然のことながらあまり良いことだとは思っていない。ただ、お金を払って女性をどうこうすることに対してではなく、単にお金がもったいないという発想だ。風俗店に行く研二を、軽蔑している感じもない。そのあたりが、少し変わっていると思う。
「だって、面倒じゃん。バイクの練習でそんな時間ないし。サクッと終わらせたいじゃん?」
研二は、趣味のバイクレースに時間を費やしている。プロでもないのに、熱心に練習してレースにも参加している。そういうのも、趣味としては良いものだとは思う。でも、彼女くらいは作れば良いのになと思う。
「じゃあ、最近はどうしてるの? そっちの方は」
七菜は、好奇心いっぱいの顔だ。下ネタとかそういうのが好きなわけではない。でも、好奇心は強い。七菜は、本当に可愛らしい顔をしている女の子だ。見た目は純粋そうと言うか、無邪気な印象だ。身体はかなり肉感的でセクシーなスタイルだが、子供みたいな所のある女性だ。
「最近は、メンズエステかな」
「メンズエステ? なにそれ」
七菜は、さらに興味を惹かれた顔になっている。
「メンエスって、聞いたことない?」
「うん。聞いたことない。高広は知ってる?」
七菜は、僕に話を振ってきた。でも、僕もよく知らない。そのフレーズは聞いたことがあるが、マッサージとか整体みたいな感じなのかな? と思っている。
研二は、説明を始めた。それは、思っているのとはちょっと違った。ヘルスなんかよりもレベルの高い女の子に、際どいマッサージをしてもらうと言うものみたいだ。
「それって、余計に欲求不満がたまるんじゃない?」
七菜は、僕と同じ疑問を持ったみたいだ。
「いや、マジでレベル高いから。そんな子にマッサージしてもらうって、かなり良いよ」
研二は、力説している。それでも七菜は、腑に落ちないみたいだ。
「それって、気持ち良くなれないんじゃない? モヤモヤしないの?」
七菜は、かなりしつこく質問している。理解を超えているみたいだ。確かに、その話を聞く限り、ヘルスなどの風俗代わりになるとは思えない。
「そんな事ないよ。だいたいは抜きアリだから。手でしてくれたり、口でしてくれる子もいるよ。最後までさせてくれる子も、少ないけどいる」
研二は、そんな説明を始めた。それって、非合法な感じではないかと思う。
「えっ? そうなの? それじゃ、風俗と同じじゃん」
七菜は、かなり驚いている。それは僕も同じだ。
「いや、風俗と違って、抜きがあるかどうかは入ってみないとわからないし」
研二は、言葉に熱がこもっている。
「じゃあ、気持ち良くなれないときもあるってこと? それだったら、最初から風俗行ったら?」
七菜は、イマイチ納得していない。
「そこが良いんだよ。交渉したりの駆け引きも、楽しいからさ」
研二は、そんな説明をした。出来るかどうかわからないのが楽しい……それは、男の僕には理解出来た。でも、七菜は不思議そうな顔をするばかりだ。
「変なの。でも、エッチしちゃうんなら、濃厚接触じゃん。それだったら、風俗で良いのに」
七菜は、独り言のように言う。
「だから言ったじゃん、女の子のレベルが全然違うって。七菜ちゃんみたいに可愛い子がしてくれるんだよ」
研二は、さりげなく七菜を褒める。
「でも、気持ち良くなれないときもあるんでしょ? なんか、もったいないね」
七菜は、男寄りの意見を言う。
「そこが楽しいんだよ。ゲームみたいでさ」
研二は、本当にメンエスが好きみたいだ。
「変なの。メンエスって、どんなことするの?」
七菜は、話に食いついて離れようとしない。
「うん。まずシャワー浴びて、紙のパンツみたいなの穿かされて、施術台にうつ伏せで寝る感じだよ。それで、整体みたいにマッサージしてくれる」
「普通のマッサージってこと? エッチなことはなし?」
七菜の好奇心は止まらない。
「マッサージ自体は普通だよ。エッチなこともなし。でも、おっぱい押しつけてきたり、パンツチラチラ見せてきたりする」
研二は、少し興奮気味だ。話しているうちに、思い出したのだと思う。
「それで興奮しちゃうんだね」
「そうそう。背中におっぱい押しつけられたら、メチャクチャ興奮するよ」
研二は楽しそうに説明する。女友達に、メンエスのことを話すなんて、恥ずかしくないのだろうか?
「それで、今度は仰向けになるよ。もう、けっこうビンビンになっちゃってるけど、まずは普通のマッサージが続くよ。今度は、胸元を見せてくる。だいたいノーブラとかだから、乳首も見えてドキってする」
研二の話を聞いていると、僕まで興奮してしまう。
「それで、顔におっぱい押しつけてくる子もいるんだ。それで、マッサージ終わったら、今度はオイルマッサージが始まるよ」
研二は興奮気味に話しを続ける。七菜は、やっぱりキョトンとした顔で、オイルマッサージって? と質問している。研二は、オイルマッサージのことを詳しく説明する。もちろん、本当の意味でのオイルマッサージだ。健全なヤツだ。
「でも、このオイルマッサージで、だいたい抜いてくれる。ヌルヌル状態で乳首とか触られて、あっちの方もしごいてくれる子が多いかな?」
研二は、七菜が女の子だということを忘れているように、事細かく説明する。下ネタも良いところだ。でも、七菜は嫌がる素振りも見せず、さらに質問を重ねる。女の子は脱ぐのかとか、キスはアリなのかなどなど、思いついたことを全部聞いている感じだ。確かに、女性からしてみると未知の世界だ。
「脱ぐ子もいるよ。お願いしたら、おっぱいくらいはだいたい行ける。キスは嫌がる子が多いかな。なんか、キスがイヤで風俗で働かないって子も多いよ。でも、キスはダメでもセックスはOKって子も割といる」
研二は、専門家みたいだ。実際、どれくらいの頻度で行っているのだろう? 濃厚接触が怖いから風俗には行かないと言っていたが、同じ事になっている気がする。
「そうなんだ。でも、なんかわかる気がする。キスは、好きな人としかしたくないもん」
七菜は、そんな事を言う。
「え? キス以外は出来ちゃう感じ?」
揚げ足を取る研二。
「そ、そういうわけじゃないけど……」
七菜は、顔が真っ赤になっている。どぎつい会話をしているのに、可愛らしく恥じらっている。そのギャップに、僕はドキドキしっぱなしだ。
「まぁ、俺もそう思うよ。キス出来ないけど、入れて良いって訳わかんない。でも、セックスしてると、普通にキス出来ちゃうんだけどね」
研二はそんな事を言い始めた。
「え? どうして? キスはダメなんでしょ?」
七菜も、意味がわからないという顔だ。
「セックス始まったら、だいたいメチャクチャ感じてキスせがまれるから」
研二は、得意気になっている感じでもなく、淡々と答える。
「え? それって、研二くんがすごいってこと?」
「すごいかどうかわからないけど、メチャクチャ感じてくれるよ。連絡先渡されたりもする」
「え? それって、セフレになったりするの?」
七菜は、かなり驚いている。
「あんまりないかな。よっぽど相性が良い子だったらセフレにするけど。だいたいは連絡しないよ」
研二は、やっぱり淡々と答える。研二がそっちが強いなんて、長い付き合いなのに知らなかった。
「どうして!? もったいないじゃん。メンエスの子は可愛い子が多いんでしょ? そんな子からセフレになってって言われて、なんでならないの?」
あまりにももっともなことを言う七菜。僕も、まったく同じ疑問を持った。
「だって、面倒じゃん。本気になられたら、もっと面倒だし」
「本気になったら、付き合っちゃえば良いじゃん。彼女いないんでしょ?」
七菜は、まるでけしかけているようだ。
「まさか! メンエスのこを彼女にするなんて、あり得ないでしょ」
研二はそう答えた。確かに、職業に貴賎はないとか、差別するなとか、聞き心地の良いことを言う人は多い。でも、実際問題、風俗嬢やメンエス嬢を彼女にするのは、かなり抵抗を感じる。
「もったいない。付き合わないにしても、セフレにしたらお金かからないでしょ? 部屋に行けばホテル代もかからないし」
七菜は、どこを目指しているのだろう? ゴールがよくわからない。
「それもわかるけど、今はまだ楽しく遊びたいかな。七菜ちゃんは、遊びたいとか思わないの?」
「え? 結婚してるし、そんなのないよ」
七菜は、キョトンとした顔だ。本当にそう思っているみたいだ。僕は、少しホッとした。七菜は、僕にはもったいないくらいに可愛い女の子だ。その気になれば、いくらでも相手はいるはずだ。
「結婚してるから遊ばないの? 本当は、遊びたいって思ってるってこと?」
「う~ん、それはないかな。今幸せだもん」
七菜は少しだけ考えたが、結局そう言ってくれた。
「のろけるね~」
研二はからかうように言う。
「研二くんも、早く良い子見つかるとイイね」
七菜は、少しだけいじめるような口ぶりだ。それにしても、二人の仲の良いことに少し嫉妬してしまう。二人とも、本当に楽しそうだ。
そして、研二が帰った後、
「研二くん、そんなに上手なのかな? 女の子の方から連絡先渡してくるなんて、よっぽどすごいんだね」
良かったら「いいね」してください。誰でも「いいね」出来ます!