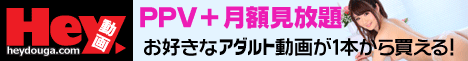ずいぶん昔の話だけど、興味があったら読んでみてほしい。
会社に入って2年目25歳の時だった。
12月初めのある日、会社の同僚の男4人(A・B・C・D=俺)で合コンに行った。
相手の女の子たちは、俺たちと同い年のなかなかカワイイ子ばかりだった。
女の子もかなり積極的で、合コンはかなり盛り上がった。
次の週末にも仕事で来られない女子1人を除いた7人でボーリングに行った。
更に、次の週末には、男たちは個人行動に走りだし、男女1対1で会ったり、男2女1で遊びに行ったり。
俺も女子のうちの1人、瑠璃という子に声をかけて自宅の電話番号を聞き出し、遊園地で初めてのデートをした。。
クリスマスイブの前日になって俺たちは女子たちからクリスマスパーティーに誘われた。
実は、瑠璃をクリスマスイブの日に誘っていたのだが、その日は「女子だけでクリスマスパーティーをするから無理。」と断られていた。
なので、Cからクリスマスパーティーの話を聞いた時は、よっしゃー!という感じだったが、実は問題があった。
なぜなら、実は男4人のうちAとBには、彼女がいたからだ。
彼女がいるのに合コンなんか参加しちゃいかんだろ?普通しないだろ?
俺もそう思ったが、そいつらは、「彼女がいたら、女の子の友達もいちゃいけないのかよ?」と、開き直っていた。
ちなみに、男2女1で遊びに行った、男2人AとBが彼女もちの男だった。
奴らの論理では、「1対1で会ったわけじゃないから、問題なし」ということらしい。
ただし、クリスマスイブの日は、当然のごとく、AもBも彼女と過ごすから、クリスマスパーティーには参加できない。
クリスマスイブは彼女と一緒にディナー。それが当たり前の時代だった。
と、いうわけで、女子の誘いを受けた俺は、困ってしまった。
この話をつけてくれたCは唯一の後輩。1対1で会ったやつで、水野さんという女の子にロックオンしていた。
Cも、水野さんをクリスマスに誘ったら、「女の子同士でパーティーだからダメ」と断れたのだが、Cが「じゃぁ、男子も全員呼んでパーティーしようよ」と粘りに粘って、水野さんが根負けし、女子たちの同意を得たらしい。
女の子4人のパーティーに男2人だけで参加するのも気が引ける。
さらには、「AとBには彼女がいる。」っていう真相を話すのもためらわれる。
ということで、俺は、「せっかくのお誘いだけど・・・」と断ることを提案したのだが、Cは「何言ってんすか?せっかく頑張って僕がセッティングしたのに、Dさん(俺)まで参加しなかったら女の子に失礼ですよ。僕は一人でも行きますけど、」と言われて、仕方なく、俺はCと一緒に参加することにした。
クリスマスパーティーの場所は、女の子4人のうち、唯一、一人暮らしをしていた「なっちゃん」という子の部屋だった。
中学から男子校、工学部育ちの俺にとっては、一人暮らしの女の子の部屋に行くのは初めてだ。
なっちゃんは、市電の駅の近くの、なかなかおしゃれなマンションに住んでいた。
夕方4時過ぎ、俺とCが、なっちゃんの部屋に行くと、水野さん、瑠璃、なっちゃんの3人がいて、笑顔で迎えてくれた。
AとBが来られないことは、Cが水野さんに伝えていたらしい。
久しぶりに会う、なっちゃんは少しさびしそうに見えた。
その前の週にAとBと一緒に遊びに行った女の子がなっちゃんだった。
クリスマスイブに、AとBが来ないという事実が意味することに、なっちゃんが気づいていないわけはなかった。
それでも「突然誘ってごめんね。さぁ上がって。 料理も、もうすぐ出来上がるよー。」
と明るくふるまう、なっちゃんを俺はいじらしいと思った。
もう一人の弥生ちゃんという子は仕事で遅れてくるらしい。
ボーリングに行った時も、弥生ちゃんだけは土曜日出勤だからと言う理由で不参加だった。
水野さん、そして瑠璃が、なっちゃんと一緒に料理を作っていた。
実際は、準備をしているのは、エプロン姿の水野さんとなっちゃん。
エプロン姿は女子力高くて、男子アピールが高いよね。
瑠璃は、エプロンもせず2人の周りをうろうろして、「2人ともすごいねー」って言っているだけだった。
こういうところは、瑠璃ってダメな子だった。
部屋についてすぐ、役立たずの俺と瑠璃は、近くのケーキ屋にクリスマスケーキの受け取りに行かされた。
なっちゃんと水野さんが、俺と瑠璃に気を使ってくれたのだろう。
「Dくんたちが来るって聞いてびっくりしたよ。」
2人になると、瑠璃は笑顔を見せた。笑うと目がなくなる瑠璃。
瑠璃は、色白で顔のパーツはすべて小さくて、細身でおとなしくて、ちょっとのんびりした子だった。
実は合コンに参加したとき、俺のいちばんお気に入りだったのは、瑠璃ではなかった。
俺のお気に入りは、目がぱっちりしたショートカットでボーイッシュな美人の弥生ちゃん。
しかし、次の週ボーリングに行ったときに、唯一欠席した弥生ちゃんが土日仕事の旅行代理店に勤めていることを知った俺は、「土日休めない女の子とつきあえるわけないし。」と、早々に方向転換をして、ボーリングに行った帰りの車の中で瑠璃の電話番号を聞き出すことに成功したというわけだ。
つまり瑠璃は、俺のベストチョイスではなかったわけだが、会社に入って2年目で、とにかく彼女が欲しかった俺は、そこそこカワイイ瑠璃とデートが出来て、満足していた。
「少し寄り道していこうよ。」
俺は、ケーキを受け取ると、瑠璃を公園に誘った。
公園のベンチに座って、2人で暮れていく冬の夕焼けを見ながら話をしていた。
瑠璃はおとなしいけど、気を許すとけっこうお喋りだった。
ただし・・・
「私が良くわからないって言ったら、同じ課の人が、話に加わってきたんだけど、けっきょく、その人も意味が分からなくて、分からないって言ったら、その人はまた最初から説明を始めたんだけど、やっぱりわからなくて・・・」
俺は、瑠璃の勤務先の出来事に関する着地点の見えない話の聞き役に回っていた。
すっかり日が落ちて星が一つ二つ輝きだした頃、瑠璃の長い話はオチがないまま終わり、無言でしばらく見つめあったあと、俺は瑠璃と、初めてのキスをした。
チキンな俺と、のんびりやの瑠璃らしい、唇が一瞬触れ合うだけのキスだった。
後から都合が悪くなれば、なかったことに出来そうな、そんな他愛もないキスでも、瑠璃は真っ赤になっていた。
そして、俺も照れくさくて、瑠璃の顔をまともに見れずに、「さぁ、戻ろう」と言って立ち上がった。
「お邪魔しまーす。」
本日2回目のなっちゃんの部屋、ご訪問。
パーティーの準備はすっかりできていた。
水野さんとなっちゃんがテーブルに料理を並べ、Cは隅の方で所在なさげに座っていた。
手伝おうとしたが邪魔だと追い払われたらしい。
「遅かったね~?」
なっちゃんが、瑠璃を冷かした。
「うん、少し迷った。」瑠璃が下手すぎる嘘をついた。
「へぇ、Dくんって、ひょっとして方向音痴?」 と、なっちゃん。
「うん、この前北海道に行こうと思って、着いたら沖縄だった。」
「ふーん、それで帰ってきたと思ったら、アメリカだったとか?」
「うん、アメリカだと思ったら、実はスペインだった。」
美人とは言えないが、愛嬌があるタヌキ顔のなっちゃんは、瑠璃とは対照的な、明るく話し上手な女の子だった。 確かにAとBが彼女が、なっちゃんと友達になりたいと思うことも良く理解できた。
水野さんと瑠璃は家が近所の幼馴染、なっちゃんを加えた3人が高校の同級生で、弥生ちゃんは水野さんの大学時代に出来た友人で、すぐ、なっちゃんとも仲良くなったらしい。
部屋の電気を消して、マライアキャリーの曲が流れた。
かんぱーい!と言った感じで女子3人と男子に2人のパーティは始まった。
女の子たちはもともとフレンドリーな性格で、男2人を温かく受け入れてくれて、パーティーはそれなりに盛り上がった。
Cの隣には水野さん。俺の隣には瑠璃。そして一番明るくて盛り上げ役だけど、少しさびしそうな、なっちゃん。
男子校から工学部と男ばかりの世界で育った俺は、男子より女子が多いと言う空間は人生初めてだった。
それを言うと女子たちにはめちゃめちゃ受けた。
「あ、でも幼稚園の時は、女の子3人と俺一人で遊んでたなぁ。」
「ハーレムじゃん。」
「でも、いつもいじめられていたけど。」と言うと更に受けた。
2時間ほどして、弥生ちゃんがやってきた。
「もうやだよ~明日も仕事なんて。」と、言いながら、弥生ちゃんは俺の横に座った。
「久しぶりだね。」
すぐ横の弥生ちゃんの笑顔に、俺はドキッとした。
弥生ちゃんは、4人の中では、いちばんさばけている。
地方のお嬢様風は他の3人とはちょいっと違う都会的な女の子。
落ち着いていて言葉遣いもはきはきしている。
逆に言うと男たちには、難攻不落的な印象を与えてしまうのかもしれない。
合コンの時、俺がいちばん話していたのは弥生ちゃんで、まぁまぁいい感じだった。
久しぶりに会う俺に嬉しそうに声をかけてくれる弥生ちゃん。
俺と瑠璃がデートしたことは知っているのか、いないのか。
左右に弥生ちゃんと瑠璃・・・ある意味、おいしいシチュエーション。
しかし、男子校育ちの俺にそんな幸せを享受できるメンタリティはない。
弥生ちゃんが普通に話しかけてくるだけでも、横に座る瑠璃に何か気づかれないか、ドキドキしてしまう。
逆に瑠璃に話しかけられると、俺と瑠璃のことを弥生ちゃんに気付かれるのではとドキドキしてしまう。
弥生ちゃんが、高校時代の親友同士だった3人の中に入ってきた経緯を聞くと、瑠璃と弥生ちゃんには微妙なよそよそしさがある。
俺は、嬉しくもあるが、落ち着かない気分だった。
「あっ」
離れたところの料理を取ろうとした俺の袖が手前の料理に触れそうになったのだろう。
俺の袖を弥生ちゃんがつまみあげてくれた。
「あ、ありがとう。」
そんな弥生ちゃんの女の子らしい気遣いに、俺はドキドキしてしまう。
瑠璃はそういう気が利くタイプじゃないからね。
そう、これだよ・・・合コンの時に弥生ちゃんに惹かれた理由は・・・
やっぱり弥生ちゃんにしとけばよかったのか・・・そう思ったとき。
「私、飲みすぎたかも。」
横で瑠璃が言った。
「瑠璃、お酒弱いからね~。大丈夫?」
水野さんが笑った。
「大丈夫?」僕も聞いた。
「うん。」
そう言いながら、瑠璃は少し俺に体重を預けてきた。
女の子の体の柔らかさと温もりが僕に伝わる。
「そこ、くっつきすぎ。」
なっちゃんの素早いツッコミ。
「違うよぉ。当たっただけ・・・」
照れたような顔の瑠璃の体が離れた。
左腕に残る、瑠璃の柔らかい感触。瑠璃の胸が腕に当たった気がする。
俺は瑠璃の小ぶりなふくらみをセーターの上からまじまじ見てしまった。
ふと、右側を見ると弥生ちゃんが少し驚いたような顔で俺たちを見ていたが、俺と目が合うと、にこっと笑った。
(事情は伺っております。ご心配なく)的な営業スマイル。
そうか・・・弥生ちゃんも、俺と瑠璃のことを知っていたんだ。
なんだ・・・俺・・・どうしてがっかりしてるんだろう?
落胆している自分に少し腹が立った。
とにかく、今は彼女を作るのが最優先。
それも、かなりいい感じになっている。
瑠璃と、ちゃんと付き合えるようにしないと。
俺は、自分に言い聞かせた。
7人でダラダラしゃべっているうちに、クリスマスイブの夜はどんどん更けていった。
Cはかなりの天然ボケのやつで、Cのすべての言葉が女性陣のツボに入りまくるらしく大爆笑だったし。
俺もCのボケにタイミングよく突っ込んどけば、それで女子も盛り上がってくれるし。
あ、そうそう、触れていなかったが、水野さんは、しっかりものの美人だった。
水野さんが、Cのどこがいいと思ったのかわからないが、まぁ、お似合いのカップルになりかけ・・・ではあった。
「瑠璃、うちら、そろそろ帰らんと。」
10時半ごろ、水野さんが言った。
「えっ・・・もう、そんな時間なの?」
と、のんびりした感じの瑠璃も少し慌てたようだった。
水野さんと瑠璃は実家暮らし。
なっちゃんのマンションから電車で1時間ぐらいかかる。
楽しくもドキドキのパーティーは終わりを告げた。
簡単に片づけをして、俺たちは、なっちゃんの部屋を出た。
駅までの道、6人で歩く。
駅まで送るという、なっちゃんと弥生ちゃんが先頭を歩き、水野さんとC。
いちばん後ろは俺と瑠璃。2人は黙っていたが、時々軽く手をつないだりした。
さっきのキスのせいか、瑠璃も少しだけ俺に対して積極的だった。
そして、僕は立ち止り、不審げに振り返った瑠璃にそっとキスをした。
瑠璃は一瞬、「えっ?」って顔をしたけど、素直に僕のキスを受け入れた。
夕方よりほんの少し長いキス・・・きっと誰にも気づかれなかったはず。
「もう・・・誰かに見られたらどうするの?」
頬を染めた瑠璃が、上目づかいで俺を睨んだ。
「見られても、全然いいけど・・・俺は」
そう言うと、瑠璃は、「私はやだ・・・恥ずかしいもん。」と言って、急ぎ足でなっちゃんたちの方に行った。
そんな、瑠璃の後姿を今まででいちばん可愛いと思ってしまった。
市電の駅についてしばらくすると、瑠璃と水野さんが乗る電車がやってきた。
ここから2駅市電に乗って、JRに乗り換え。
弥生ちゃんは逆方向だ。 俺とCは、ここから歩いて30分。
これで瑠璃たちとお別れ・・・少しさびしくなっていると、「Dさん、失礼します。」と市電に飛び乗ったC
よっぽど水野さんと一緒にいたいのだろう。
遠回りになるのにCは水野さんと一緒の電車で瑠璃とともに去って行った。
驚いたような顔の瑠璃は、俺を見て小さく手を振った。
(後から聞くと、瑠璃が驚いたのは、Cが同じ電車に乗ったからではなく、俺が電車に乗らなかったからだった。瑠璃って、やっぱりどこかズレている子だった。)
僕となっちゃんと弥生ちゃんも、手を振って3人を見送った。
「なっちゃん、私、片付け手伝うよ。」
3人の乗った電車が見えなくなった時、弥生ちゃんが言った。
「いいよぉ。もうほとんど、片付いてるし。」
「そう、でも、もう少し、なっちゃんと飲もうかな?」
「弥生、ついさっき来たばかりだもんね。」
2人が会話している。
俺は、2人の会話が途切れるのを待って、帰ろうと思っていたが、
「じゃ、Dくんも来て、少し飲み直す?」
なっちゃんが聞いてきた。俺に断る理由はなかった。
「そうしようかな・・・片付けの役には立たないと思うけど・・・」
正直言って、もう少し弥生ちゃんと話したいという下心もあった。
「おじゃましまーす。」
というわけで、弥生ちゃん、なっちゃんと一緒に、3たび、なっちゃんの部屋に。
弥生ちゃんとなっちゃんがキッチンで洗い物をしていて、俺は、ぼーっとテレビのクリスマス特番を見ていた。
そして洗い物が終わり、ワインで乾杯した。
さっきのはじけた感じとは違い、なんとなく大人なムードのしっとりした雰囲気。
「今頃、AくんとBくんは彼女と一緒かな?」
ぽつりと、なっちゃんが言った。
「え・・・いや・・・。」
僕はどう答えていいかわからず戸惑った。
「いいよ・・・なんとなく分かっていたから・・・。」
なっちゃんは、微笑んで、グラスを空けた。
「男の人ってずるいよね~。」
ワインを片手に体育座りをして壁によりかかるスラックス姿の弥生ちゃん。
「はい・・・すみません。」
俺は、彼らに代わって謝った。
「変なの。Dくんが悪いわけじゃないのに・・・。」
弥生ちゃんが笑った。
2人は就職してからの友達だから瑠璃たちと比べて、関係性が少し大人なのだろう。
会話も大人っぽい。
「でもね・・・最初の合コンの時、Dくんは弥生狙いだと思ったのになぁ・・・」
なっちゃんが、少し意地悪そうな視線を、僕に向けた。
「え・・・あ・・・」
僕は言葉に詰まった。
弥生ちゃんは黙ってワインを飲んでいる。
弥生ちゃんはお酒に強い。さっきからガンガン飲んでいるが、顔色もほとんど変わらない。
さて、俺は・・・ここは素直になった方がいいのだろう。
「うん・・・ほんとはそうなんだ。 でも、弥生ちゃんが土日も仕事って聞いて、じゃぁ会うのとか無理だよって思っちゃったし。まぁ・・・その・・・俺もやっぱりずるいのかも・・・。」
「Dくんって正直者だね。」
心変わりをあっさりと認めた俺に呆れたような、なっちゃん。
「はい、よく言われます。」
とりあえず冗談めかしてごまかそうとする俺。
「瑠璃には黙っといてあげるけど、あんまりそういうこと言っちゃだめだよ。弥生だって何をいまさら、って感じだろうし。」
なっちゃんが真面目な顔で言う。
「どーも、すいません。」
「いいよ、慣れているから・・・Dくんの気持ちもわかる。私だって、会えないのは、やだもん。」
弥生ちゃんが言う。
さっきは6人いたから、かなり距離が近かったが、今は3人等間隔だ。
「職場には、男の人もいるんじゃないの?」
「いるけど・・・男性は転勤も多いし・・・5年も勤めていると、私の方が古株になっちゃっているよ。新しい子がどんどん入ってくるしね。」
「うん、それにさ、職場恋愛をして別れると、周りが腫物をさわるような感じになるしね。」となっちゃん。
「なっちゃん、そんなことあったんだ。」
「私だって、Dくんが思っているよりモテるんですーっ。」
頬を膨らませるなっちゃん。
なっちゃんは、去年まで俺たちと同じ会社のまったく別の部署で働いていたらしい。
今回の合コンは、俺たちの会社の先輩(結婚済)と、なっちゃん(短大卒)が同期入社だったことが縁だった。
その先輩は、俺たちに合コンの様子を聞いてきたとき、
「俺は、とにかく、なっちゃんに幸せになってほしいんだ。」と言っていた。
なっちゃんの優しい性格だと、職場恋愛で傷ついて、周囲の視線にいたたまれず、会社を辞めてしまったという可能性も十分あり得る。真実は俺も知らない。
職場恋愛の件と言い、今回のAとBの件と言い、なっちゃんみたいな、性格も良い、真面目な明るい女の子が、どうしてそういう目に合うのだろう。
男たちもハードルが低いとか、遊ぶのには好都合とか、思ってしまうのだろうか。
悪く言えば、なっちゃんも、男のそういうずるいところに気づかない、夢見がちな部分があるのかもしれない。
比較的イケメンなAに優しくされて舞い上がっちゃうような・・・。
「なんかね・・・難しいよね。」
いろんなことを考えて、俺は言ったが、その真意は女子たちに伝わるわけもない。
「何が難しいの?」
「うーん・・・何が、だろう?」
「変なの。」となっちゃん。
「今が幸せMAXの人が言うことじゃないよね。」と弥生ちゃん。
「確かになっちゃんの部屋で、弥生ちゃんと3人で飲めるなんて、今が幸せMAXかな?」
沈んだ雰囲気を明るくしようと言ってみた。
「Dくん、嘘つくの下手だね。」となっちゃん。
うん・・・まぁ、わざと、そうしたってところもあるんだけど・・・。
「嘘じゃないって。」
「まぁ、そういうことにしとこうよ。」と、ニヤッと笑う弥生ちゃん。
なんか、なっちゃんと弥生ちゃんと話すと、瑠璃と話しているときより、しっくりきた。
なんていうか、ウマが合う3人なのだろうか。
でも、俺と弥生ちゃんの二人だけだったら、こううまく行くとは思えない。
なっちゃんと2人きりでもそうだろう。
お互い、恋愛感情がない3人だからだろうか?
もっとも俺はさっきまで弥生ちゃんに恋愛感情ありまくりだったが。
1時間ほどして、12時が近づき、僕と弥生ちゃんは、なっちゃんの家をお暇した。
明日は日曜日だが、弥生ちゃんは明日も仕事だ。
「言っとくけど、2人とも、浮気はダメだよ。」
部屋を出るとき、なっちゃんに釘を刺された。
「しないよ~。」弥生ちゃんは笑った。
「そんな、5寸くぎを刺さなくても。」と俺はおどけた。
「Dくんは藁人形なの? わかった、明日Dくんの藁人形を作ってあげる。」
「腹が立ったら、気が済むまで打ってください。あと、時間があればAとBの藁人形も。」
俺の言葉に、なっちゃんは笑った。
弥生ちゃんと俺、2人で夜の道を歩く。先ほどより更に夜道は暗く、通りには誰もいない。
2人とも無言だ・・・なっちゃんの言葉で意識してしまって、何を話していいかわからない。
「あ・・・星がきれいだね。」
俺はあほだ。顔と台詞が全く一致していない。
でも、弥生ちゃんは「そうだね。」と言って、そっと僕の手を握った。
冷たい感触。
瑠璃の手は子供みたいに小さくてやわらかかった。
指が長くてきれいな弥生ちゃんの手は、しっかり力強かった。
これって・・・俺が、瑠璃から弥生ちゃんに方向転換してもいいよっていうサインなのだろうか?
さっきから、弥生ちゃんが何を考えているかわからない。
「明日も、仕事大変だね。」
とりあえず、さりげない話から、俺は弥生ちゃんの真意を探ろうとした。
「うん、でも月曜日は休みだし、日曜日はわりあい早く終わるの。」
「じゃぁ、弥生ちゃんに会うなら日曜だね。」
誘っている・・・そう受け止められても構わない言い方をしてしまった。
「ねぇ・・・真面目そうな顔して、けっこう遊び人?」
弥生ちゃんが、少し俺を睨んで握っていた手を離した。
「遊び人とは対極的な人生だったと、自信を持って言えるけど・・・。」
僕は言い訳をした。
「そうなんだ・・・確かに、真面目だと思うけど、Dくんは、どっかで、衝動的に突っ走っちゃうとこあるような気がする。」
弥生ちゃんは言った。
そんなことを人から言われたことはなかった。
真面目で明るい感じだが、女性に対しては奥手で、自分から声をかけられないタイプ。
自分のことをそう思っていた俺には少々意外な、弥生ちゃんの指摘だった。
市電の駅に着いたが、最終の電車が来るまではまだ10分以上あった。
ベンチもあったが、2人で駅員もいない市電のホームに並んで立って電車を待った。
街は静まり返り闇に包まれているのに、誰もいない市電のホームは煌々と明るい。
この明るさと静けさの中で弥生ちゃんの顔を見るのは少々気恥ずかしい。
「もう寂しいのに慣れたって、言ったでしょ。」
弥生ちゃんが話題を変えた。
「土日も仕事で、休みの日は家で本を読んで、母親と出かけて、たまに仕事終わりのなっちゃんとかと晩御飯とかって、毎日、淡々と暮らしているんだけど・・・ふとしたダイミングで、火がついちゃうときがあるんだ・・・」
「へぇ・・・たとえば?」
「たとえば、新婚旅行の相談で同い年くらいのカップルが来たときとか。」
「あぁ、私だって・・・とかって思っちゃうんだ?」
「うんそういうこと・・・それから・・・さっきとか・・・」
「さっきって?」
「私が袖をつまんだとき。」
あぁ・・・俺の胸がときめき、心がぶれまくった瞬間だ。
「あの時、瑠璃ちゃんが、『酔っちゃったかも』って言って、すっとDくんに体をくっつけたでしょ・・・。」
「あぁ・・・俺も、ちょっとびっくりしたけど・・・偶然じゃない?」
「偶然じゃないよ。あんなおっとりした感じの瑠璃ちゃんが、あんなことするんだ・・・って、きっと、『Dくんは私のモノよ。』って、私に言いたかったんだろうなって・・・びっくりした。」
確かに、まったく予想が出来ない、瑠璃の行動だった。
でも・・・弥生ちゃんは何を言いたいんだろう。
確か火がついたとかそういう話をしていたような気が・・・
弥生ちゃんは、そんな自分から切り出した話は忘れたように、それきり口を噤んで、明るいホームの縁に立ち、暗闇の中のレールを見つめている。
俺は、弥生ちゃんの横顔を見つめた・・・俺の言葉を待っている・・・そんな気がした。
なんとなく、今、俺と弥生ちゃんが危ういバランスの中にいるような気がした。
「俺と瑠璃ちゃんを見て、弥生ちゃん、火がついたんだ・・・」
僕の声は乾いていた。
「うん。」
弥生ちゃんは俺の方を見ずに小さな声で頷く。
「今も?」
「うん。」
危うかったバランスが、どんどん崩れていく。
「俺も、あの時、火がついたよ。」
「えっ?」
弥生ちゃんが振り返った。俺は続ける。
「弥生ちゃんが俺の袖をつまんでくれた時・・・俺はすごい間違いをしてしまったかもって。」
「・・・」
「俺が本当に探していたのは、瑠璃ちゃんじゃなくて・・・」
言葉の続きは、弥生ちゃんの唇で塞がれた。
背伸びした弥生ちゃんの手は俺の背中に回され、俺も弥生ちゃんを抱きしめた。
今まで経験したことがない激しいキス。
俺の舌が弥生ちゃんの唇を割り、弥生ちゃんの舌が絡みつく
バランスは完全に崩壊し、俺と弥生ちゃんは明るいホームの上で、闇に落ちた。
俺の右手が、コートの下に潜り込み弥生ちゃんの胸に伸びる。
ボーイッシュな外見に似つかわしくないしっかりとしたバストの感触が手の中に広がった。
そしていつしか、弥生ちゃんの手が、俺の硬くなった股間をジーンズの上からそっと撫でていた。
そのまま、市電のライトが2人を包み込むまで、僕らは闇の世界に堕ち続けた。
「それじゃね・・・」
電車が着いても、名残惜しく見つめあっていた2人。
「もう少し一緒にいたい。」
そういいかけて手を伸ばした、電車の扉が閉まる直前。
弥生ちゃんは電車の中に滑り込んで、はにかんだ笑顔で手を振った。
「おやすみ・・・」
「うん・・・」
俺は小さく頷いた。扉が閉まり弥生ちゃんが遠くに去っていく。
電車が走り去ると俺の心の中にぽっかりと大きな穴が明いていた。
俺は、とぼとぼとホームを歩き、駅を出た。寒さが体を包む。
2分前の出来事が嘘のようだった。
今まで経験したことがない激しいキスだった。
俺と弥生ちゃんは、ものすごく近づいた気がした。
でも、実際のところ、俺は弥生ちゃんの連絡先さえ知らない。
次に会う約束もできない。
俺は明日どうするのだろう?
何もなかったように瑠璃に電話するのだろうか?
それとも、弥生ちゃんを探して街中の旅行代理店を回るのだろうか?
駅を出て踏切を渡り、誰もいない交差点を横切ろうとしたときだった。
「Dくーん!」
俺を呼ぶ声が聞こえた。
振り返ると、小さな自転車のライト、そしてぼんやりとなっちゃんの顔が見えた。
俺に追いついたなっちゃんは、よほど急いで追いかけてきたのだろう。
マンションの部屋から駅まで、自転車なら2、3分の距離なのに、はぁはぁしている。
さっきまで弥生ちゃんとしていたことを思い出すと、なっちゃんの顔を見るのは気恥ずかしい。
「どうしたの?」
「Cくんが財布忘れていったの。」
「えっ?」
「Dくんに会社で渡してもらおうと思って・・・。」
「あぁ・・・うん、わかった。」
「ごめんね。ひょっとしたら追いつくかもって思って、追いかけてきちゃった。」
よほど慌てたのだろう・・・なっちゃんはホッとしたような顔をしている。
だが、俺の中では大きな?マークが点滅している。
「それで・・・?」
「うん。」
「財布は?」
あっ!と、なっちゃんが小さな声を上げた。
「どうしよう・・・部屋に忘れてきた。」
こうして、俺は4たび、なっちゃんの部屋に行くことになった。
なっちゃんの自転車を押しながら歩く俺に、なっちゃんは、何度もごめんねって謝ってきた。
「いいよ。気にしないで・・・また、なっちゃんの部屋に行けるなんてラッキーだよ。」
俺は冗談っぽく言ったが、本音だった。
弥生ちゃんが俺の中につけた火が、心のどこかにくすぶっていたから。
このまま、なっちゃんの部屋に行けば、きっと何事もなく終わらない。
俺の中にもはやなっちゃんが瑠璃の親友だということとか、そんな前提は消え去り、なんなら瑠璃のことさえ頭になかった。
ただただ、次の何かを求めていた。
「またまたまたまた、お邪魔します。」
俺はそう言いながら、なっちゃんの部屋に上がった。
今日何時間過ごしたかわからないこの部屋で、ついに、なっちゃんと2人きりになってしまった。
「せっかく来たんだから、酔い覚ましに、コーヒーでも飲んでいってくださいな。」
なっちゃんの言葉に俺は腰を落ち着けた。テレビではクリスマス特番をやっている。
今日、この部屋の人数の推移は・・・1→3→5→3→5→6→3→1→2だなとか、俺はぼんやりと考えながら、テレビを見ていた。
なっちゃんが手際よくコーヒーを入れてくれ、当たり前のように俺の隣に座る。
なっちゃんが、Cの財布を出してくる気配はない。
俺も、なっちゃんの部屋にCの財布がないことは、気づいていた。
そして、俺がとっくに気づいていて、それでも部屋にやってきたことを、なっちゃんは知っている。
知っていて、なっちゃんは俺の隣に彼女のように座っている。
自分の親友の彼氏になりかけの男と、自分の彼女になりかけの女の親友。
俺の頭の中でわけのわからないフレーズが、映画の字幕のようにながれていた。
「ねぇ、Dくんは誤解しているかもしれないけど、私、AくんやBくんに振られたから落ち込んでいるわけじゃないよ。っていうか・・・今は全然、落ち込んでないし・・・クリパーすごく楽しかったし。」
なっちゃんがぽつりぽつりと話し始めた。
「そうなんだ・・・良かったよ・・・俺たち、邪魔じゃないかって思ってたんだ。」
「ううん・・・DくんとCくんがいてくれてよかった・・・だって・・・女の子ばっかりだったら、結局傷の舐めあいになっちゃうだけでしょ・・・男なんてさぁ・・・とか、やっぱり女の子どうしがいちばんだよねぇとか・・・」
「そうなっちゃうんだ・・・俺、今まで男同士がやっぱり一番だよねぇ・・・なんて思ったことないけど。だって、ずっと男同士だったから。」
くすっ・・・と、なっちゃんは笑った。
「DくんとCくんがいたから・・・やっぱり、女の子だって男の子がいるとドキドキするんだよ。 あの、おとなしい瑠璃だって、弥生に対して、ジャブを繰り出していたし・・・。」
「そうなんだ・・・俺、偶然だって思っていたけど・・・。」
「絶対、偶然じゃないよ・・・ほんとはね・・・最初は、私、ちょっと落ち込んでいたんだ・・・・だけど、瑠璃のおかげでファイティングスピリットを取り戻しちゃった。ふふっ・・・つまり、Dくんのおかげだよ。」
「俺のおかげ・・・かなぁ。」
「そうだよ・・・もう大丈夫、明日から、明るく元気な、なっちゃんに戻りますよ。」
なっちゃんは、笑顔を見せた。しかしその笑顔には陰があることに気づいてしまった。
女の子の気持ちには鈍感だったはずの俺だが、この夜だけはなぜか、意識が鋭敏に研ぎ澄まされていた。
それがなぜかと言えば、端的にいえば、プチハーレムなクリスマスパーティーで、オスの本能を、瑠璃や弥生ちゃん、なっちゃんに揺り起こされたからに違いない。
なっちゃんは、まだ何か言い足りなそうな感じだった。
「ねぇ、弥生の事なんだけど・・・」
なっちゃんが口を開いた。
「実は彼氏がいるんだ・・・。」
「えっ・・・あっ・・・そうなんだ。」
俺は平静を装ったが、それなりに衝撃を味わっていた。
彼氏がいるのに、どうして、俺とあんなことをしたんだろう?
「Dくんには、ごめんなさい。かな?」
「ううん・・・」
合コンの時、4人がかなりの粒ぞろいで、全員彼氏無なんて、なんかの間違いじゃないかとさえ思った。
なので、弥生ちゃんに彼氏がいたとしても、驚くことではなかった。
「合コンの時は、人数合わせみたいな感じで呼んじゃったけど・・・だから弥生は2回目のボーリングは参加しなかったし・・・ただ、今日はもともと女子4人でやるつもりだったから、弥生だけ来るなとは言えないし・・・事情は話してどうするか聞いたら、私も行くって・・・弥生もけっこうDくんに好印象だったみたいだよ・・・。」
「そうなんだ・・・。でも旅行代理店に勤めていて土日は仕事なのは本当なんでしょ?」
「それは本当だよ。でも彼氏は遠距離恋愛で、今日は会えなかったみたい。」
「そうなんだ・・・」
「これだけは、Dくんに話そうと思って・・・それで、追いかけたんだ・・・Cくんの財布の話は嘘・・・ごめんね。だから、BくんとAくんのことも、Dくんは気にしなくていいよ・・・女子も、お互いさまだから・・・」
そうか・・・このことを伝えるために、なっちゃんは、俺を部屋に呼んだのか。
別に、俺に何かを期待していたわけじゃなくて・・・。
何かを期待しまくっていた俺は落胆した。
「弥生ちゃんのことを伝えるために、俺を追いかけたんだ?」
俺の言葉に、なっちゃんは、うんと小さく頷いた。
「優しいんだね・・・なっちゃんは・・・」
そんなんじゃないよ・・・といいながら、つまり・・・・その・・・・と、なっちゃんは少し逡巡してから、言葉を継いだ。
「だから・・・Dくんは、瑠璃を大事にしてあげてね・・・あの子、気が利かないところがあるし・・・引っ込み思案なところもあるけど、でも、優しくて素直ないい子だし・・・Dくんに誘われたことも、私に報告してきたんだよ・・・嬉しそうに・・・だから・・・」
そう言いながら、俯いてマグカップに視線を落とすなっちゃんの横顔を見たとき、俺はさっきの弥生ちゃんの表情を思い出した。
ホームの下に広がる暗闇を見つめていた弥生ちゃんの表情が、マグカップの中のコーヒーに視線を落としているなっちゃんの表情に被った。
思い詰めているような、迷っているような、何かを待っているような・・・。
「あ、でも、こうやって、Dくんと2人でいること知られちゃったら、瑠璃に誤解されちゃうかな・・・Dくん、このことは、2人の秘密にしておこうね・・・。秘密にしなかったら、本当に藁人形を作っちゃうよ。」
なっちゃんが、顔をあげて、俺に笑顔を見せた。
俺は、なっちゃんが、なんとか踏みとどまろうとしていると感じた。
自分の親友の彼氏(になりかけの俺)に手を出しちゃいけない。
そういうモラルが、なっちゃんを、「優しくていい子」の檻の中に閉じ込めているんだ。
その檻を誰かが破らなければ、なっちゃんは、いつまでも「優しくていい子」のままだ。
いささか自己中心、我田引水的だが、俺は勝手に結論付けた。
「俺は・・・Cの財布をもらうために、なっちゃんの部屋に来たわけじゃないよ。」
俺はなっちゃんの肩に手を回した。なっちゃんがびくっとする。
「なっちゃんと2人きりになりたかったら、この部屋に来たんだ。」
えっ・・・という感じでなっちゃんが俺を見た。
「なっちゃんは、違うの?」
「そ・・・それは・・・」
言い淀んだなっちゃんの唇を奪う。
「あっ・・・」
なっちゃんが俺を押し返そうとしたが、俺は構わず、なっちゃんを抱きしめ、再びキスをして舌を絡める。
何度もキスを繰り返すうちに、なっちゃんは素直に俺に唇を許す。
俺が唇を離すと、なっちゃんは、じっと俺を見つめた。
「今日みたいな日に、ひとりぼっちは嫌だったから・・・私、いつもはこんなことしない・・・弥生とは違う・・・」
そうか・・・俺と弥生ちゃんのキスを見ていたんだ・・・。
それを誤魔化すために、俺と会ったとき、不自然なくらいはぁはぁしていたんだ。
「なっちゃん・・・今日は、いい子じゃなくていいんだよ・・・」
頷いたなっちゃんは自分から唇を重ねてきた。それを合図に俺はなっちゃんの胸に手を伸ばした。
瑠璃よりも、弥生ちゃんよりも、たわわなバストが俺の手を押し返す。
「なっちゃんの胸・・・すごい・・・」
俺の声に「やだ・・・」と、恥じらうなっちゃんがカワイイ。
ブラを外すと、色白な乳房に似合うピンクの乳輪と、大き目の乳首が現れ、夢中で俺は吸い付いた。
「あぁ・・・やだ・・・恥ずかしい・・・」
かわいく喘いでいるなっちゃんの、スカートを捲りショーツに手を当てると、なっちゃんのあそこは、ショーツの上からでもわかるくらい濡れていて、くにゅっと俺の指を包み込んだ。
「あぁ・・・どうしよう、Dくん、困る・・・」
なっちゃんの甘い声に、勇気を得た俺は、なっちゃんの手を、俺の勃起に導いてみた。
あわてて手を引っ込めるなっちゃん。積極的だった弥生ちゃんとは違う初心な反応に、俺は嬉しくなる。
そのまま、乳房を吸いながら、ショーツをずらすと、なっちゃんの蜜が溢れる性器に指を這わす。
いやらしく指に絡まるなっちゃんのヒダヒダ。はぁはぁというなっちゃんの甘い喘ぎ。
いつしか、なっちゃんの指がそっと優しく俺の勃起を撫でていた。
恥ずかしそうに勃起を撫でるなっちゃんの表情に俺の興奮はますます高まった。
「今日だけだから・・・二人だけの秘密だから・・・」
「うん・・・」
俺は、手早く服を脱ぎ、キスをしながらなっちゃんを裸にした。
「恥ずかしいよ・・・電気消して・・・」
「だめ・・・なっちゃんのカワイイ姿を見たいんだ。」
経験は少なかったが、出来るだけ優しく裸のなっちゃんを愛撫した。
そして、なっちゃんがもっと乱れる姿を見たかった。
なっちゃんのアソコは、すっかり濡れていた。
出来るだけ丹念に優しく、しつこくなっちゃんを責めた。
「あぁ・・・お願い・・・もう・・・」
なっちゃんの言葉・・・もっといやらしいことを言わせたかったが、それは後回しにしようと思った。
なっちゃんの中に入って行くと、なっちゃんは、俺の首筋に手を回し。俺を迎え入れた。
もう、俺にも余裕がなかった・・・なっちゃんの「あっ、あっ・・・」という甘美な喘ぎ声を聞きながら、激しくつきまくり、そして、「だめだ・・・気持ちいい・・・なっちゃん・・・」といいながら、なっちゃんの外に放出してしまった。
「ごめん・・・」
自分勝手にいってしまった俺がなっちゃんに謝ると・・・「そんなに気持ちよかったんだ?」と、微笑むなっちゃん。
遠慮がちだけど、自分から、俺のモノを舐めはじめた。
打って変った積極的な、なっちゃんの姿に、俺のものはたちまち勃起してしまった。
「Dくん・・・また、欲しいの・・・入れてもいい?」
優しくて明るい今までの姿からは想像つかない淫らな表情のなっちゃんは、自ら騎乗位で挿入した。
「すごい・・・すごいよ・・・Dくん・・・気持ちいい・・・」
誰にいうでもなく・・・うわ言のように言いながら腰を振るなっちゃん・・・。
なっちゃんの淫らな姿を見ながら、おっぱいを揉んで突き上げると、「あっ」と言いながらなっちゃんは絶頂に達した。
その後も、2人は何度となく、お互いを求めあい、空が明るくなるまで、何度も交わりあった。
こうして、信じられないクリスマスイブの一夜は過ぎて行った。
朝ご飯を頂いてから、なっちゃんの部屋を出た。
本当なら、その日は休みで、もう少し一緒にいてもよかったはずだが、昼前に目覚めたら、なっちゃんはてきぱきとご飯の支度をしていて、「Dくん、早く帰らなきゃね。」と、俺が知るなっちゃんに戻っていた。
日曜の昼、俺はフワフワした感じで、歩いて独身寮まで戻った。
そして、ベッドに倒れこみ、夜中までひたすらに眠った。
こうして、信じられないような俺のクリスマスイブは終わった。
当時の俺の感想は、ありきたりだが、「女性って怖い。」という一言に尽きる。
せっかくなので、それからのことも書いておきたい。
この後、年末年始のイベント、初詣やなんやらを経て、俺は瑠璃に告白してつき合うようになった。
半年ぐらいつきあったが、俺の仕事が超多忙になり、なかなか瑠璃と会えなくなった。
「無理して会ってくれなくてもいいよ。」
という瑠璃の言葉で、俺たちは別れた。
俺がもう少し努力すべきだったと反省したが後の祭りだった。
瑠璃と別れると、なっちゃん達とも疎遠になってしまった。
弥生ちゃんは、あれから暫くして旅行代理店を辞め、夏前に遠距離恋愛の彼氏と結婚したとCから聞いた。
あの時、すでに、弥生ちゃんは彼氏と結婚の約束をしていたのかもしれない。
あの時の大胆な弥生ちゃんは、彼氏と結婚する前に、ほんのひと時の危険な体験をしたかったんだろう。
俺とうまく行かなかったから彼氏と結婚した・・・なんて自惚れるほど俺はアホではない。
AとBは当時の彼女たちと、それぞれ1年後に結婚した。
そして、Aは、家業を継ぐために会社を辞めた。
Cは、1年後に転勤になったが、水野さんとの遠距離恋愛を成就させ、あのクリスマスイブから2年以上過ぎた3月に結婚した。
Cから連絡があり、水野さんの地元で開かれたお祝いのパーティーに招かれた。
27歳になっていて仕事だけの味気ない毎日を送っていた俺は久しぶりに瑠璃や、なっちゃんに再会した。
最初は、気まずくて瑠璃とは言葉を交わせなかった。
しかし、なっちゃんが俺のところにやってきて、「Dくん、瑠璃と話してあげて・・・」と、引き合わせてくれた。
「久しぶりだね。」
「うん・・・元気そうだね。」
「まぁね。」
「今、彼氏いるの?」
「ううん。」
「そっか・・・俺もいないよ。」
「そうなんだ。」
この再会がきっかけで俺と瑠璃は再びつきあうようになった。
お祝いのパーティーに俺を招待したのは、瑠璃が俺に未練があることを知った、なっちゃんや水野さんそしてCの心遣いだった。
そして、なっちゃんが唯一連絡先を知るBが、当時俺に彼女がいなかったことを、なっちゃんに伝えた。
いろんなことがあったが、俺と瑠璃を助けてくれたBとCには、ただただ感謝するしかない。
29歳になり、俺と瑠璃は結婚した。
地元で開いた結婚式の2次会で、Aを除く7人は、(つまりBも含めて)再会した。
いちばん最初に結婚した弥生ちゃんは、子供を産んだ後、離婚していて、地元の別の旅行代理店に勤めていた。
あの時と同じく、「もう、土曜日に仕事なんてやだよー」と言いながら、数年前と同じよう遅れて参加してきた弥生ちゃんは、ビールが入ったグラスを倒しそうになった俺の手の動きを察知して、素早くグラスをずらしてくれた。
「もう、ホントにあわてんぼさんなんだから。」と、呆れる瑠璃を、弥生ちゃんは微笑んで見ていた。
そして現在。
更に長い月日がたち、俺たちは40代になろうとしている。
俺は、瑠璃と、2人の娘に囲まれ、幸せにくらしている。
20代は、嵐の中だった会社生活も、30代半ばから年相応の役職と報酬、そして有り余る量の仕事を与えられている。
Cは、会社を辞めた。
水野さんの実家のある街で、新しい会社に勤め、娘さんと3人で幸せに暮らしている。
中学生の娘を持つシングルマザーの弥生ちゃんは、今でも旅行代理店に勤めている。
海外旅行に行くときは、いつも弥生ちゃんに切符の手配やホテルの予約をお願いしている。
旅行の相談の最後に、「いいなぁ、幸せそうで・・・私も火がついてきちゃった。」
と、弥生ちゃんはいつも口にして、その言葉の意味を知る俺は、ドキッとしてしまう。
旅行から戻ると、俺の携帯に弥生ちゃんから電話が入る。
「旅行はいかがでしたか?」
そういう時は、旅行のお礼を兼ねて、弥生ちゃんと食事をして、身の上話を聞く。
つくづく思うが、弥生ちゃんはお酒が強い。
なっちゃんは、職場の妻子ある男性と不倫関係になって泥沼化した。
しかし、瑠璃や俺のアドバイスもあり、男性との関係を清算して職場を辞めた。
俺も、未練がましい相手の男性に、なっちゃんと一緒に会いに行ったこともある。
なっちゃんは、俺が務める会社の別の部署で派遣社員として働きながら、独身を謳歌している。
「D課長 相談したいことがあって・・・」
ときおり夕方にガラス張りの会議室で、「社内の妻子持ちの男性に誘われた」とか、そういう相談を受ける。
なっちゃんは、今も昔も彼氏持ちや妻子持ちに狙われやすい。
しかし、Bが、なっちゃんに声をかけたと聞いた時は、さすが引いた。
まぁ、Bに他意はなかったことが後でわかって誤解は解けるのだが。
彼女たちは今でも親友同士だ。
時には女4人で休日にランチを楽しんでいる。
Cと俺は、水野さんや瑠璃の夫として、娘たちの父として、弥生ちゃん親子や、なっちゃんとキャンプに行ったりする。
「あのくりぱーみたいだね。」と瑠璃が言うと、「でも、女の子が増えて、もっとハーレムだよ。」と娘たちを見ながら、なっちゃんが笑う。
「〇〇ちゃんのパパって面白いよね~。」
Cの言うことは、なぜか女の子たちのツボに入るらしい。
俺がバーベキューの網を洗っていて、ふと気が付くと隣で弥生ちゃんが手伝っていたりする。
そんなときは必ず、「パパ、〇〇(娘たち)がバトミントンしてって。」と、瑠璃が呼びにやってくる。
俺たちは、ずっとそんな感じで付き合っていくのかもしれない。
瑠璃が、あのクリスマスパーティーの後のことをどれくらい知っているか、俺は知らない。
ただ、ある時、瑠璃に「あなたは、最後は道を踏み外さないから。」と、笑顔で言われて、ドキッとした。
日増しに女性らしく成長し、お小遣い欲しさに俺に甘えてくる娘。
何をどこまで知っているのか、まったく、わからない愛する妻。
つくづく、女の人って怖いと思う。
良かったら「いいね」してください。誰でも「いいね」出来ます!