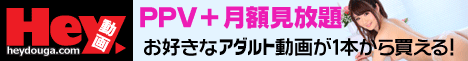もう50年以上も昔の話になりましたが、今でも当時のことは鮮明に記憶しています。
何しろ私の女性遍歴の中では初めての女性であり印象が鮮烈で今でも、ありありとおぼえているのです。当時、私は福井県の越前大野の町に住んでいました。そこは九頭竜川に沿って開けた越前松平氏と土井氏が治めた小さな城下町です。昔から絹織物が盛んで、私の生家はそこで代々、大きな機屋を営み、昔は大野藩の藩士の身分だったということです。私が生まれましたのは大正14年で昭和に切り替わる前年のことです。これからお話しするのは私が小学校から中学へ入るころのことで、ちょうど昭和の始め頃、日華事変が始まり世間がそろそろきな臭くなってくる頃のことです。とは言いましても田舎のことですから全くのんびりしたもので、私もまだまだ田舎の大きな機屋の倅として何不自由なく豊かに暮らしていたのでございます。
当時、父親はすでになく、家業及び家屋敷一切を母親が仕切っておりました。もともと女系家族で父は婿養子で母が気丈にすべてを仕切っていたという訳です。
そんな中で、私は女兄弟の中で唯一の男子として生まれ、それは大切に育てられたのです。とは言っても、母は大きな家と家業一切を仕切るのに忙しく子供を育てるのはもっぱら乳母と女中の仕事でした。私も大切に育てられたとは言ってもやはり母の手ではなく、すべて乳母と女中の手で育てられたのです。ですから母はあまり親しみは感じず、気丈で男勝りに下女や女工を追い使う怖い存在でした。
私はそこで中学を卒業するまで暮らし、高等学校と大学は京都の同志社に進みました。大学の途中で一時、戦争に取られて舞鶴の海軍予備士官学校へ行きました。幸い戦争は程なく終わり、私は無事大学を卒業して再び越前大野に戻って、家業の機屋を継いで生活しています。まあ、田舎ですが、それなりの資産がある生活で戦争の被害も無く、暮らしに困ることも無くまあまあ豊かに暮らしてまいりました。田舎ですが一応、名士のはしくれでもあり家業の関係で出入りの女性も多く、私も普通の男子として、いやそれ以上でしょうか、世間並みに女性関係もそれなりに経験しています。そんな私にとって、忘れられない初めての女性がこれからお話しする、福田久との関係です。
久は家の女中をしていており私の身の回りの世話をしてくれた女性でした。そして私の初体験の相手でも有り、半ば夫婦のように過ごした相手です。それは何と私がまだ小学6年生から中学を卒業するまでの年齢で言えば十二歳から17歳までの多感で性に目覚める頃の5年間の事です。久は確か私より二周りも年上で母と同じ位の年齢だったと思います。そんな女性と夫婦として暮らしたのですから、今から思えばやはり異常な経験です。しかし当時の私にとっては全く自然で楽しい生活でした。今ではもう久もこの世になく、当時のことを知る人も少なくなって、まあ、時効と申しますか洗いざらいを語っても良い頃だと思って筆を取った次第です。
その夜の夕食はひっそりした離れ屋敷での二人きりの夕餉だった。
久は私から離れて三畳間で後から取ると言うのを私が促して六畳間のちゃぶ台で私と差し向かいで食べるように命じたのだった。
下女が主人の家族と一緒に食事することなど有りえない時代だったから、それは格別の私からの計らいだった。何、私にしてみれば大人の女の久と差し向かいで一緒に食事をしたかっただけなのだが。
「そがいな事、あかんがいね・・・」
と久は躊躇ったが、主人の命令だったから、おずおずとちゃぶ台の前に座り、差し向かいで食事を取った。
十二歳の子供に大人の女を相手に世間話などできようはずも無く二人向かい合って黙々と箸を運ぶだけの食事だったが、それでも私は満足だった。久も嫌なそぶりではなかった。
夕食を終えると後はもう寝転んで本を読むか(ラジオなど母屋に一台あるきりで夜になれば早々に寝てしまうのが当時の常識だった)ごろ寝するくらいしかないのだった。
久は細々した片付けや繕いや何やかやと忙しく働いていたが、私が風呂に入るときは声をかけるまでも無く洗い場で背中を流してくれた。
洗い場で肌着一枚になりたすき掛けで背中を流してくれる久はまさに大人の女の色気に溢れていた。
背中を流してもらい再び湯船に浸かると、私は久に一緒に入って温まるように促した。福井の田舎は雪が多く、まだ三月の外は雪が残っており、薪をくべないと湯はすぐに冷えてしまうから、それは当然の流れだったし清にもそうしていたのである。
久は少し躊躇って見せたが、食事のときと同じように私の命令だと知ると、すぐに
「そんじゃあ、おおきにあても使わせていただきますがね。」
と嬉しそうに返して、すぐに肌着を脱いで裸になった。
私は心臓があぶつほどドキドキしてまぶしい久の裸の姿を見つめた。
薄暗い風呂場の中ではあったが久の裸は雪のように白く輝いていた。
清のまだ平坦な少年のように痩せて固い裸は知っていたが、大人の成熟した女の裸を間近でじっくりと見るのは初めてだった。それは何と豊かでふくよかな肉体だったろう。外見はやせて見えたが、流石に三十代半ばを過ぎた成熟した女の体は全身がゆったりと丸みを帯びて肉がつき、羽二重餅のような真っ白な柔らかな肉がたぽたぽと揺れるように全身を包んでいた。特に平坦な清の胸に比べてたっぷりした重みを感じさせる乳房は生唾を飲み込むほどの強烈な印象だった。そして腰周りには驚くほどゆったりとたっぷりの肉がつき、正に成熟した大人の女の艶かしい色気に包まれていた。
地味で粗末な紺の絣に覆われた凛とした気品を感じさせる久の姿からは想像も出来ない女体の艶かしさに、私は完全に我を忘れて見入っていた。
私は狭い五右衛門風呂の湯船から出ると入れ替わりに湯船に入る久をまじまじと見つめた。
「若さあ、そげに見たら恥ずかしいがいね・・・」
久は手ぬぐいで前を隠して恥ずかしそうに俯き体を屈めて湯船に入った。
私はもう完全に我を忘れ体も拭かずに立ち尽くしていた。
「あれ、はよう拭かんと風引くがいね。若さあ・・」
私は言われるままに慌てて体を拭いたが、その場を立ち去れなかった。
「いややがねえ、そんなに見られたら出られんがいね・・」
久はくくくっと、可笑しそうに笑いながらそう言って顔をうつむけた。
「お久はん、良かったらあても体を流してやろうがいね・・」
それは自分でも予期していなかった言葉だった。
「若さあ、あらまあ、これはたまげた。だけどもそげなことしたら罰があたろうがいねし・・・」
「うんや、おかえしだがねし。お清にも、たまに流してやったがいね。」
それは本当だった。清とはいつも一緒に風呂に入っていたし、背中を流し合うのは当然のことだった。但しそれは遊び半分の子供同士のふざけ合いのようなものに過ぎなかった。久を前に私が申し出たのは遊びの気分ではなくひたすら大人の女の体に触れたい、抱きつきたいという本能から出た言葉だった。それは清に対しては全く感じなかった感情だった。
「そがい本当かいねえ。こらあたまげた事。お清さんにもしてやっとたがいねし。そんだら、あても罰は当たらんかも知れんがねし・・・・・」
久は少し躊躇う風情だったが、私が再び促すと、今度は、
「そんじゃあ、あてもお清はんと同じように若さあの言葉に甘えるがねし。」
そう言って、ザバっと音を立てて湯船から立ち上がって洗い場に出た。
恥ずかしそうに前を隠して、背中を丸めると、片膝立ちにすのこにしゃがみこんだ。
真っ白く張りの有る女の色気を発散する大きな背中だった。
私は弾かれたようにぬか袋を拾い上げ、手桶に湯を汲んで久の女の背中に湯を流しぬか袋で擦りたてた。
「ひや~、若さあにそげなことをしてもらうなんど、ほんにありがたいことですがいね。」久は気持ちよさそうに目を閉じて黙って私の手にゆだねた。
私の興奮はすでに十分に限界を超えていた。
今、自分は大人の女の裸に触れている。
柔らかく、真っ白に輝く弾力に富んだ女の肌。
素裸の下腹部はむくむくと変化している。
頭の中がカッとなって私は夢中になってしゃがみこんだ久の背中に覆いかぶさって抱きついていた。全く我知らずの自然な勢いでそうなったのである。
夢中になって両手を前に回して胸をまさぐり、硬直した下腹部をごしごしと久の背中に押し付けた。
「ひやあ、あかんがねし、そげながいたらこと(乱暴な)こと・・・若さあ、なあ、あかんがねし・・・」
拒絶の言葉だったが案に相違して、久は体では強くは拒まなかった。
私は小柄なほうだったし、まだ十二歳の子供で大人の女である久より小さかった。
そんな子供に背後から抱きしめられても、本気で強く振りほどけば逃げ出せたはずだった。しかし久はじっと蹲って私のなすままに任せているのだった。
清ならきっと
「あかんて、若さあ、あほしたらあかんがや。」
と笑いながら、するりと身を翻して逃げてしまうに違いなかった。
しかし久は逃げなかったし、強い抗いの声も上げなかった。
長い時間そうして私は蹲る久の背中に圧し掛かるようにしてしがみついて、きつく抱きしめていた。静寂の中で裸の体を通してお互いの体温が暖かく伝わってきた。
抱きしめた腕の中に大人の女の体のすべてがあった。
女の髪の匂い。
柔らかい体のたぷたぷした弾力。
張りのある真っ白で艶のある肌。
ふにゃふにゃした氷嚢のような乳房のふくらみ。
豊かな腰まわり。
ゆったりした大きな尻。
それらすべてが私の腕の中に在った。
陶酔するような夢のような時間の流れだった・・・・・
やがて、
「若さあ、なあ、風引きますんで、もう出やんがいね。」
久の優しい声で私はようやっと我に帰って体を離したのだった。
「さあ、若さあ、着んがいね。」
寝巻きを着せ自分も手早く体を拭いて寝巻きを羽織った。
私はもう完全に理性を失っていた。
所詮十二歳の子供だった。
初めて触れた大人の女の体の感触に頭に血が上っていたのである。
寝巻きを着終えた久の体を私は夢中になって抱きしめていた。
久は今度も抗わなかった。
きつく抱きしめるといつの間にか久も両手を回して抱き返してきた。
押し黙ったまま、洗い場で暫く二人で抱き合っていた。
やがて、
「さあ、冷えるがいね・・・」
と促されて部屋に戻った。
同衾への誘い
興奮冷めやらぬままに風呂から上がった私は後はもう寝るばかりだった。
しかし、寝るどころの騒ぎではなかった。
心はもう久との同衾のことしかなかった。
久が布団を敷くのを待って早速に中に潜り込み私は息を凝らして待った。。
暫くして戸締りをして明かりを消した後、久が枕元にやってきて、
「お休みなさいませ。」
と両手を突いて丁寧に休む挨拶をした。
「なあ、寝床で温くうして・・」
私は子供が甘えるような振りを装って言った。
それは清にいつもねだっていた同じ言葉だった。
幼い時から母親代わりだった清は無論躊躇無く私の寝床に入って体を温め私が寝付くまで一緒に居てくれたのだった。
私は暗い中で久が頷いたのかどうか見もしなかった。
そして起き上がるとがむしゃらに久の体にしがみついていった。
「あれまあ、若さあ、子供みてえな事を・・・・・」
久は冗談でふざけていると受け取った様子で、くくくっと笑いながら、逃げる様子を見せた。私は体をかわした久の腰にしがみついて抱きついた。
「あかん、あかん、若さあ~、そがいな事~」
逃れようとする久としがみつく私は暫く布団の上で揉みあう形になった。
十二歳の私はまだまだ小柄で、大人の久の体より小さく、久がどうしても逃れたかったら容易に私の体を跳ね除けられたはずだった。
しかし久はそうしなかった。
だから、私も諦めなかったのである。
「なあ、いっつもお清は寝床に入いっとたがねし。」
実際、清は一緒に布団に入って抱き合うのを拒まなかった。
それは、寒い北陸の内陸部の夜寒に母親が我が子の寝床に入るのと同じだった。
「そんでも、若さあ、もう子供ではないがねし。」
「いんや、子供じゃあ、なあ、温くうなるまで一時だけ寝床に入ってえなあ」
私は子供であることを強調した。
「あかん、あかん、さっきよう分かったがねし。若さあ、もう立派な男子じゃ。」
先ほどの風呂場での事を指しているのだった。
私はドキンとした。
久の裸に背後から抱きつきながら、硬直した下腹部をその背中に押し付けたのである。
それは大人の印に違いなかった。
「なあ、ちょっとだけや、なあ、頼むがいね・・・」
私はひるまず、久の体を抱きしめたまま強引に布団の中に引き入れようとした。
「ひやあ、あかんがいね、そげなこと・・・若さあ、なあ、あかんがいね・・・」
久は拒んで逃れようとした。
しかし声は決して怒ってはおらず、どこか冗談ごとのように、可笑しそうに、
くくくと、ひそみ笑いを漏らしながらの抵抗だった。
今思えば、大人の女である久は、まだほんの子供である私の性的な要求を、半ば驚きながらも、からかい半分、本気半分で、軽くいなしながら楽しんでいたのだと思う。
しかし、私は本気だった。
私はもう頭に血が上って絶対に引き下がるつもりは無かった。
すでにたぎり立つものに押されていたのである。
最後は主(あるじ)として命令してでも久を寝床に引きずり込むつもりだった。
ほんの十二歳の子供に過ぎなかったが、私は自分が主であり、久はたとえ大人でも自分の命令に従うべき下女だと思っていた。実際、清は全く私の言いつけにすべてしたがっていたから、それが下女の当然の決まりなのだと思っていた。
久は半ばふざけながら、半ば本気で押し返し、逃れようとする。
しかし洗い場の時と同様に抗いは強くは無かった。
私は渾身の力で久に抱きつき離すまいとする。
久は逃れようとする。
二人は布団の上で揉みあい、抱きあ合った姿で転げまわった。
「あかんがね、あかんがね・・」
「な、なあ、何もせんて、一緒に寝床で温まるだけや。」
同じ言葉を繰り返して二人は揉みあった。
それは、半ばふざけ合いの様な遊びごとに近かった。
暫くすると二人とも息が荒くなり、汗ばむほどになっていた。
決して久が本気で嫌がっているのでは無いことは明白だった。
半ば楽しんでいる。
子供の私にもそれは伝わってきた。
だから諦めなかった。
「あ、あかんがいね、若さあ、そげんことはいかんがいね・・・」
荒い息を憑きながら久が口走る。
口ではそう言ってはいても抗いは強くは無かった。
子供心にも久がもう受け入れる気持ちであることを知っていた。
「なあ、お清はいっつもこうして一緒に寝ていたがね。なんでそれがいかんのや・・」
私は泣き出しそうな必死の思いで哀願するように言った。
久は流石にもう潮時と思った様子で応えた。
「そんでも、若さあ、お清はんとは寝ても何もせなんだでしょう?」
「ああ、そうや。たんだ一緒に寝床で温まるだけや。」
何もせなんだ、と言う言葉に内心どきりしていた。
図星を指されたのである。
確かにそのとおりだった。
清との事は同衾ではなかった。
夜寒を一緒に布団に入り温まるのが目的で抱きついてもそれだけだった。
いたずら半分で胸や股座を触ったことは幾度も有ったがそれは単なるいたずらで、性的な欲求とは違ったものだった。
しかし今の自分は違っている。
久はそれを言っているのだった。
流石に大人の女だから良く分かっている。
久が男と女の事を言っているのは明白だった。
その下心を見透かされている。
そう思うとたまらなく恥ずかしかった。
しかし、今更引くに引けなかった。
体には滾り立つものが支配している。
「当たり前や、何もせんがね、お清とおんなじだがね。」
全く口からでまかせだった。
「あれうまいこと言うて若さあ、ほんまがいね。」
「うん、きっとや、約束するがいね。絶対に何もせんて、温くうなるまでだけじゃ」
「本当やね、若さあ、だまくらかいたらいかんがね。」
「うん、きっとや、ただしな、一個だけ触るのはええやろがね。」
私は抜け目無く言い足した。
「触るてえ、どこをやの。」
「ちょこっと乳とそいから臍ん所じゃ。」
「あれまあ、乳と臍がいね・・」
たまげたと言った様子で久は見つめた。
それは明らかに温まると言う言葉とは関係ないことだった。
「何で?若さあ、あての乳と臍が好きなんかね?」
それはからかうような口調だった。
「何でもじゃあ、ちょこっと触るだけじゃあ・・・」
「ふ~ん、乳を触るのは赤子みてえやがいね?若さあ、赤子がいねし。」
今思えば久はほんの子供の性的な要求に内心ほくそえみながらからかっていたに違いなかった。
「うるさいがいね・・たんださわりたいだけじゃ。」
怒気を含んだ言葉に流石に久は引き下がった。
「ふ~ん、本当にちょこっと乳と臍だけ触るだけじゃねえ?」
「うん、きっとじゃあ。」
久は暫くじっと私の見つめていたがやがて、分かったと言う様に軽く頷いた。
「そんならええです。だけどもがいなら(乱暴)したらいかんよ。なあ、若さあ、がいならしいがねし。」
私はただ一人の男子で我がまま放題で育てられ、奥ではがいならしい(乱暴者)として通っていたのは自分でも心えていたから久の言葉は自然だった。
「うん、がいならはせんよ。約束する。」
続けて久が言った言葉は全く予想外だった。
「ほんだら、あての方も若さあの臍を触ってもええかね?」
私はどうして久がそんなところを触りたいのか全く分からなかったが、断ることは出来なかったから、すぐに承諾した。
「なあ、ええですか。若さあだけやよ、こげなことは・・・・・ほんだでね、絶対に他の人には言うたらあかんよ。な、約束やよ。」
久の真剣な声に私も真剣に応えた。
「うん、絶対に誰にも言わん、約束じゃ、違えたら針千本飲んだる。」
それで決まりだった。
男と女の間にはそうしたお互いの了解の嘘が必要なのだと私はその時学んだのだった。
私は久が二人の秘密だと仄めかした事がとても嬉しく、興奮を覚えた。
それは大人の女である久と自分だけの密かな秘め事の誘いのように感じられた。
それを許した久は自分を赤子だと言いながらも対等な大人として扱ってくれたような気もしたのである。
初めての精通
私は久の体を抱きしめながら布団の中に引きずり込んだ。
薄手の綿の寝巻きに包まれた久の体を横向きになってしっかりと抱き寄せた。
久も横向きになって私の小柄な体に手を回して抱き返した。
小さな布団の中で十二歳の子供と三十半ばを過ぎた大人の女がしっかりと抱き合う形になったのである。
それは傍から見れば単なる母子の添い寝のような感じだったが、私の気持ちは全くちがっていた。妻を抱く夫の気持ちのようなものだった。
真っ暗な部屋の中で私たちは完全に二人だけの世界に住んでいるようだった。
私は初めて自分のものとして抱いた大人の女の体に陶酔していた。
その温もり。
柔らかい体。
ふくよかでたっぷりした腰と丸く弾力の有る大きな尻。
そして久の吐く息。
大人の女の匂い。
その圧倒的な女としての存在感・・・
それらはすべてが清とは全く異なる本当の女だった。
私は夢中になって久の寝巻きを肌けてたっぷりした乳房に頬刷りし手で揉みしだいた。
「若さあ、な、きつうしたらいかんよ、なあ、がいたら(乱暴に)いかんよ・・」
夢中になっていた私は氷嚢のようにちゃぷちゃぷとした乳房を、繰り返し力任せに、ぎゅっと手で握り締めていた。
「うん・・」
片手で握りながらもう一方の乳房を頬すりし口を押しつけた。
「ああ、若さあ、そいだら事したらまるきし赤ちゃんやがね・・」
久は可笑しそうに言いながらも私の体を抱きしめていた。
私は久のたわわな両の乳房を代わる代わる口に含み頬張りチュウチュウと音立てて吸い続けた。
乳房の先端の大きな干し葡萄のような乳首を吸いたてると私の背中に回した久の手がぎゅっときつくなるのを不思議に感じていた。
大人の女が子供である自分の行為に反応するなどとは全く思っても見なったのである。
顔を離すと
「若さあ、ほんに赤ちゃんやがあ、上手におっぱいを吸うんじゃんねえ・・・清さんにもこんなんにしたんか?」
久が清の名を出したのが少し不愉快だった。
あれは、単なる子供だ・・・全く違っているのに比較になんかなるものか・・・・
「ううん、清はぺちゃんこじゃから、嫌いだがねし。」
それは本当だった。
いつも寝床の中で清の胸をまさぐったがまだ十七にしかならない少年のように青い体は全く堅く平板で色気の対象には程遠かった。
「ふうん、お清さんはぺちゃんこがいね・・」
久はくくくと、含み笑いを噛み殺すように言った。
「なあ、若さあ、そいたらあてのは、ええがねし?」
そう言うと、乳を揉む私の手に手を重ねてぎゅっと押し付けた。
もっと触ってくれと言っているようで驚いた。
手の中でふにゃふにゃと膨らみ揺れる大人の女の乳房は少しも飽きなかった。
久もそれを心地よく感じている様子だった。
乳房を散々弄んだ後はもう残る場所は一箇所しかなかった。
再び乳房を口に含みながら手を久の柔らかな腹に沿わせた。
そこも清とは全く違った大人の女の感触だった。
すべすべとしてなおかつ、たぷんたぷんとした柔らかさ。
私の興奮は最高潮に達しておりすぐに手を下に這わせた。
「あっ、あかん、そこ・・・・・」
久の手が押しとどめる。
しかしもう堰を切った興奮は止めようも無かった。
一気に手を下腹に這わせる。
「若さあ、そこはあかん、あかんがねし・・・」
私は全く聞いては居なかった。
柔らかなたっぷりした下腹の感触、ゆるくたるんだ下腹の肉は手の中で掴み取れるたっぷりした豊かさだった。
そこを手でぎゅっと握り更に進めると、意外にも、じょりっとした違和感の有る手触りが返ってきた。
それは風呂場で垣間見た真っ黒な三角の茂みに相違なかった。
それこそが大人の女の印だった。
清はかすかに僅かな毛がしょぼしょぼと生えていただけだった。
濃くて真っ黒な大きな三角の茂み。
母屋の風呂場で、他の下女のものも何度か盗み見た事があったがあれこそが大人の女の圧倒的な象徴だった。大人の女は皆例外なく下腹にべっとりと真っ黒な三角の茂みを生やしている。それが風呂場で下女を覗き見したときの強烈な印象だった。
それに今、自分は触れているのだった。
私はそれを確かめるために茂みを指先に何度も絡めては確かめた。
「若さあ、あかん、もうあかんて、な、もう堪忍して・・・」
久は今までとは違った、本気の様子で躊躇いを見せていた。
しかし私は辞められるはずは無かった。
「あかん、あかん、な、若さあ、やめて・・・」
無論聞く耳は無かった。
「若さあ、そんならあてもお返しに若さのここを触ったるから・・」
久は約束どおり、向き合った私の寝巻きをまくって下腹に手を伸ばしたのである。
あっと思ったがすぐに越中ふんどしの中に手を潜り込ませて来た。
痛いほどに堅く硬直した性器が柔らかな暖かい手に包まれた。
瞬間、ぞくっとする心地よさが全身を貫いた。
「ああっ・・」
私は思わず声を上げていた。
恥ずかしい硬直を久に知られて握り締められた狼狽で私は反射的に逃げようともがいた。しかし今度は久が逃がさなかった。
「若さあ、あかん、お返しやからねし・・」
体は抱きしめられているし、その上に硬直した性器をしっかりと握り締められ私は酷く狼狽した。
「さあ、若さあ、触ってもええよ、お互い様やからねし。」
そう言われたらもう狼狽などしていられなかった、背中を押される気分で焦って手を這わせた。
十二歳の子供はやはり大人の女の前では、仏の手のひらの上で良いように遊ばれている孫悟空同様だった。
結局私は急所を握られて久の下腹を探る許可を得たのだった。
私は再び手に触れている久の下腹に意識を奪われた。
そしてとうとう、茂みの奥の最後のところに手を潜り込ませていったのである。
清のもので知ってはいたが、やはり大人の女の急所は全く別物のような気がして、初めて触れる未知の神秘な世界そのものに思えた。
太ももに挟まれて窮屈な手の先に柔らかく「くちゃっ」とした肉片の重なりが有った。
清には無かった、柔らかな「くしゃっ」と重なり合う感触・・・・
どうなっているのだろう?
清のを思い出しながらいじったが、どこがどうなっているのか、良くは分からなかった。くしゃっと重なり合った肉片を指先でつまみいじる。
指先を重なり合った中心に探りを入れる。
すると暖かい濡れた感触があり、指先が更に中に入り込みそうになった。
「あぁ・・、あかん、あかん、なあ若さあ、きつうせんといて・・」
・・・
「若さあ、そこは、おなごの一番大切なところやさけえな、がいたらあかんよ絶対にな」私は恐る恐る見知らぬ地を探検するような手探りの慎重な行為だったから、久の言葉に戸惑いを覚えた。がいたら(乱暴に)しているつもりは全く無いのだった。
しかし、おなごの一番大切なところ、と言う言葉には酷く興奮を覚えた。
そうなのだ、自分は今、正に大人の女のもっとも大切な部分をまさぐっているのだ。
「若さあ、な、そっとさすってや、そっとやよ・・」
うんと、こっくりして私は指先に触れている「クシャ」とした柔らかな肉の重なりをそっとさすった。
ゆるりとさすると、そこはぬるっと何か濡れているらしかった。
おしっこ?
子供の私にはそれくらいしか思いつかなかった。
清はそうではなかった、と思う。
大人なのにおしっこを漏らしたのだろうか?
しかし汚いとは少しも感じなった。
かえって大人の女がその秘密の場所をおしっこで濡らしていると思うと、隠された秘密を知ったような卑猥な興奮を覚えた。
そこをさすっていると、ぬるぬるした感じが一層強くなってくるようだった。
そして「くちゃとした」中心部の奥に指先がするっと潜り込む深みを感じた。
少し周りを確かめて薄い肉片のようなものを摘み確かめる。
それから、思い切って肉片に囲まれた中心部にひとさし指を入れてみる。
ぬるっとした感触があり指は吸い付くような感触の中に嵌まり込んだ。
途端に、
「ああ、若さ、あかん、あかん・・」
久が小さな声を上げ、硬直した性器を包んでいた手にぎゅっと力が入った。
私は自分の行為が久にその反応を与えたのだと、幼いながらも直感して興奮を覚えた。
指先をぐっと奥まで進める。
ねばっとしたまとわり憑くような感触が人差し指を包み込む。
中を捏ねるようにゆっくりとまさぐる。
「はあ、・・」
それに反応してか、久が小さな嗚咽を漏らして性器を握った手にぎゅっと力が入る。
私はゆっくりと指を引き抜き再び奥まで突き入れる。
久はその都度、反応してぎゅっと手で握り返してきた。
今や自分の指の動きが久に何らかの痛み?か何かを与えて反応を引き起こしているのは間違いなかった。
私は夢中になって指を使った。
そして硬直した性器は都度、久の柔らかな手でぎゅっ、ぎゅっとしごかれて、興奮は一気に高まっていた。
「はあ~~」
久が感極まったように熱い息を漏らして私の体をきつく抱きしめ、手を激しくしごいたときだった。何かがぴかっと光って背筋から脳天にかけて、さ~~っと歓喜の電流が一気に突き抜けた。
何が起こったのかわからなかった。
ドクドクと私は生まれて初めての精液を久の暖かく柔らかな掌の中に放ち終えていた。
暫くの間、呆然として声も出せずただただ、必死に久にしがみついていた。
久は放ち終えた私の汚れた性器を自分の寝巻きの裾で包み込み掌の中でしっかりと握ってくれていた。
何が起こったのだろう?
何がチン○の先から漏れ出したのだろう?
あれは一体なんだったのだろう?
早熟で性的好奇心が旺盛な子供だったが、もとより性の知識が有るわけも無く、友達は晩生で何も教えてはくれなかったから精通についての知識は全く無かった。
私は呆然としていたが気だるい気分の中にも深い充足感と幸福感を覚えていた。
ただ、おしっこのようなものを久の手に漏らしてしまった、決まりの悪さは有ったがそれでも、久は少しも嫌な様子ではなく優しくしっかりと握り締めていてくれるのが嬉しかった。そう、久が確かに自分に起こった衝撃の一瞬をしっかりと受け止めてくれたのである。久を相手に男としての何事かを行ったのだと思った。それがあの男と女の間の性行為なのかはよく分からなかったが、それでも満足だった。
そんな私の気持ちを知ってか知らずか、久は私に優しく頬擦りししっかりと抱きしめてくれていた。私は久をこの上なく好もしく、親しく、今まで誰にも覚えなかった、いとおしいものに思えた。今や久は誰とも違った、清でさえ遠い存在に思えるほど親しい特別な存在に思えた。
どれほどそうしていたのだろう、やがて久が声をかけてきた。
「若さあ、やっぱし立派な大人の男子やがね・・・」
そう言って、優しく頬刷りをしてくれた。
硬直した性器の先端から何かの汁を放ったのが、大人の印らしかった。
「若さあ、知っとるがいね?大人の男子はねし、こがいにして、チン○の先から子種の汁を出しておなごを孕ませるんやよ。」
頬擦りしながら耳元で囁いた。
「子種の汁?」
「うん、子種の汁じゃがいねし。」
「これで赤ん坊が出来るんか?」
「はい、それをおなごのお腹の中に漏らすんだがいね。」
「どうやっておなごのお腹に漏らすんや?」
久は少し躊躇って、
「若さあ、お清はんは何にも言わんかったんがいね?」
「うん」
「そうかあ、ほしたらなあ、今度からあ、あてが先生になってあげます。ええですか、若さあ?」
「うん」
私は、もう単なる十二歳の幼い子供に戻っていた。
主(あるじ)だとか元服とかいっぱしになって気取っていた外の鎧は完全に脱げ落ちていた。今や久の手のひらの中で自分の急所はしっかりと握られており、完全に逸った気持ちは抜け落ち、十二歳の子供と三十七歳の大人の関係に戻っていた。
久は自分より経験豊富な大人であり性について先生になるのは当然のことだと素直に思った。従順に自分の言いつけに従うだけの幼い清とは全く違っていた。
久は下女では有ったが、それ以上に、私にとっては「妻」であり、その前に大人の女であり、そして自分の先導者だと素直に認めたのである。
「なあ、お久はん、どうやっておなごのお腹の中にその汁を漏らすんや?」
重要な疑問がまだ残っていた。しかし、久は
「それは、若さあ、また今度のお楽しみや・・・」
とくっくっくっと含み笑いをしてごまかしてしまった。
やがて、久は、つと寝床を出ると再び戻ってきて丁寧に汚れた下腹を手拭で拭き清めてくれたのだった。
それが50年の月日を経てもなお昨日のように鮮明に覚えている、私と久の「初夜」の一部始終の出来事だった。
手淫の誘い
「若さあ、起きんがいね。」
次の朝、私は久の声で目覚めた。
まだ寒さが残る、しかしよく晴れた明るい早春の朝だった。
昨夜のことが一瞬に蘇った。
あれから久は自分の寝床に戻り私もまた力尽きてすっと眠りに落ちてしまったのである。下腹に手をやるとかすかに何かの気配が残っている。
しかし、それだけで普段の朝と少しも違わなかった。
久はすぐに朝餉の支度をして、私たちは昨夜と同様に六畳のちゃぶ台で向かい合って差し向かいの朝食を摂った。
お互いに昨夜のことは一切口に出さなかった。
確かに自分は久の体を抱き、乳房を吸い、下腹をまさぐったはずだった。
しかし、それは本当だったのか?と思うほど久は全く何事も無かったそぶりだった。
ただ、一つだけ何となく違っていたのは、久と自分の間のぎこちない空気がなくなっている事だった。昨日はまだ一緒の部屋に二人きりでいるぎこちない空気があったが、それがすっかり無くなっている。言葉では言えないが、何か微妙な親密さが生まれているのだった。別に久は馴れ馴れしくするわけではなかったし、私も普通の下女を相手にするのと変わりなかった。しかし、何かが二人の間の空気に親密なものを生じさせていた。
子供なりにそれは感じていた。
その夜も当然のように私たちは一緒に風呂に入った。
そして同じように私は久の背中を流した。
違っていたのはそこからだった。
私は久を立たせて裸の久の体を正面から抱き寄せたのである。
久は抗わなかった。
二人は暗い洗い場で裸の姿でしっかりと抱き合った。
そして私は昨夜布団の中でしたように久の下腹を手でまさぐった。
久も当然のように硬直した私の性器を握り締めた。
二人はお互いの性器をまさぐりながら長い時間そこで抱き合っていた。
痺れを切らしたのは私のほうだった。
久の性器の中を指先でいじりまわし、久がそれに応えて硬直をしっかりと握り返すのを楽しんだ。
そして・・・・
私は精液を久の手の中に放った。
風呂場は後始末には好都合だった。
久は嬉しそうに微笑んで、
「若さあは、悪いお人じゃがねし・・」
そう言って丁寧に洗い清めてくれたのだった。
風呂から上がって布団に潜り込むと私は久を待った。
そうして「おやすみなさいませ」
と挨拶する久の手を握って布団に抱きいれた。
もう久は拒まなかった。
逆にそれを待っていたかのように、すっと自ら体を布団の中に滑り込ませてきたのだった。
昨夜とは全く違っていた。
私はすでに一回放ち終えてすっきりしており、落ち着いて久の体を抱いた。
逆に久のほうは風呂場での行為の続きになったから、酷く敏感になっている様子が分かった。
最初から私は久の寝巻きを肌だけさせて乳房を吸い下腹をまさぐった。
久もまた私の硬直を握り締めた。
私は落ち着いて久の反応を伺いながら久の性器をいじった。
そして久が酷く敏感に反応する部分が有ることを理解した。
偶然そこに触れたときだった、久は体をビクッと震わせて私の性器をぎゅっときつく握り返したのである。
私は夢中になってその秘密の箇所を探った。そしてここらしいと言う場所を探し当てていた。案の定、そこを攻めると久は立て続けに体を震わせて私の体にしがみつくのだった。そうして、思ってもいなっかたのだが、久の性器は熱く熱を帯びべっとりと濡れているのだった。おしっこ、だと思っていた私は、興奮して大人の女はおしっこを漏らすのだと思った。しかし、ぬるっとしているから、普通のおしっことは違う気もした。
多分、自分が漏らしたように何かの汁が久の性器からも漏れ出しているのだと思った。
でも自分のは子種の汁だと教えられたから、女の汁は一体なんだろう?
久の体を抱きながら、そんな事を考えるゆとりさえ有った。
今度は痺れを切らしたのは久の方だった。
繰り返し敏感なところを攻める私に久は焦れたように、
「若さあ、ね、あんましそこをいじったら嫌・・」
と拗ねたような鼻声を漏らした。
それは今まで一度も経験したことの無い女の甘えた物言いだった。
清が時々ふざけて甘えた声を出したがそれは全く子供の声に過ぎず、女の言葉ではなった。私は面白がってかえってそこを集中して責め続けた。
「いや、いや、イヤッ・・・」
久が勘に耐えたように小声で恥ずかしそうに呟いた。
しかし久は決して離れようとはせずにますますきつく私に抱きついてくるのだった。
久は、お返しにきつく私の性器をしごきにかかった。
そしてあっけなく、私は久の攻めに陥落した。
久は昨夜と同じように丁寧に私の汚れた性器を拭き清め、寝床から離れようとした。
「あかん、久、もう少し一緒に居てくれんがねし。」
久の体を抱き寄せて引きとめた。
「あんだ、若さあ、まんだするがいね?」
「ううん、違う。たんだ一緒にいるだけでええがねし。」
「はい、若さあの気の済むまで一緒にいますがねし。」
久は従順に頷いて私の体を抱き返してくれた。
黙って二人は抱き合っていた。
お互いの体の温もりで次第に眠気が襲ってきた。
深い満足と幸せに中で私は幸福な眠りに落ちていった。
久は口数が少なく、大人しい女だった。そして他の下女とは違って、背が高く、すっとした見栄えで、子供の目から見ても、凛とした雰囲気を持ったいかにも士族の出だと思わせる女だった。しかしそうした大人の女の近寄りがたさや冷たさは感じさせず、優しく柔らかでふくよかな温かみを感じさせる女でもあった。
私は久が本当に好きになっていた。
それは所謂大人の恋愛感情ではなかったが、自分ではそれに近い、ときめきの対象としてとらえていた。そんな大人の女が自分の下女として一緒に暮らすことに、私は嬉しく毎日がそれだけで楽しかった。
私たちは毎夜、一緒に風呂に入りそして布団を並べて一緒に寝た。無論、私は久を自分の布団に誘い久は私が寝付くまでの間必ず一緒に寝てくれた。そうしてお互いの体を抱き合い、手でお互いの性器をまさぐり合い、私は久の掌に精を漏らして寝につくのだった。それは私にとっては最も大切な毎夜の行事になっていた。
久は毎夜の寝床の中で少しずつ、私に性の手ほどきをしてくれた。
後に久から聞いたことだが、実は母が久に私への性の手ほどきを頼んでいたらしかった。私は離れで暮らすまで清に世話を見てもらっていたが、一緒に風呂へ入ったり、一つ布団に寝たりして、そろそろ性的に目覚める年頃の私を心配したらしかった。もし若い下女の清と間違いが有って、赤ん坊でも出来ればやはり困ったことになる。そして、母は私が父親譲りの女好きの性癖を持っていることを見抜いていたらしかった。
清を遠ざけるのは良いが、放って置けば私は他の下女に手を出していただろう。実際、下女の入浴を盗み見たり、厠を覗いたり女中部屋に忍び込んで着替えを盗み見たりしており、母はそんな私を心配していたのである。そして、思い切ってきちんと「嫁」を持たせて大きな間違いが起きないように監視させ、かつ性の手ほどきをさせてしまおうと考えたようだった。
久は従順で性格も良く士族の出で育ちも悪くない。それに二度も離縁された身を拾われた恩も有ったから無理を頼みやすかったのだろう。もっと大切なことは、久が夫婦生活の経験のある年増の女であり、なおかつ子を産めない体だったことだと思う。要はまかり間違って何か有っても子は出来ず、大切な嫡男の性の手ほどきをさせるにはまたとない存在だったのだろう。今、振り返ってみれば、その母親の作戦は見事に成功したと言ってよかった。
私は初めて接する大人の女に夢中になった。そして母の狙い通り、私は女というものを学んだのだった。ただし、他の女に手を出して問題を起こさせないと言う点に関しては残念ながらあてが外れたと言って良かった。かえって私は自信をつけて他の女にも手を出すようになったのである。だから、中学でも勉強は下から数えたほうが早いほどの成績で、当時入学試験が簡単だった同志社の予科にもぐりこんだのだった。しかし私は今でも久に感謝しているのは性のあれこれの知識を実地に教えてもらったことだった。もとより性教育など有り得ようも無い時代で、普通なら若集宿で知ることも私は無縁で、正しい性の知識を得る機会は全く無かった。男子にとって女子を良く知ることは大切なことであり、それも年上の経験のある女性から手ほどきを受けるのが最良の方法だと私は思っているが、まさに私はそれを受けたのである。久を通して私は女というものを学び、その後の人生で女を相手にするのに本当に役に立ったと思っている。
男女の営みの秘密
その夜も私は久と一緒に寝床に入って裸になって抱き合い、お互いの下腹を手でまさぐり合った後、いつものように久の手でしごかれて射精を終えていた。
久が枕元に用意してあった濡れ手拭で丁寧に拭き清めてくれて、再び私たちは抱き合って下腹をまさぐり合った。一度射精した後は余裕を持って久の性器をじっくりと弄り回し、今度は久を喜ばせるのが慣わしになっていた。
わずか一ヶ月だったが、毎夜の儀式ですっかり久の反応を学び、喜ばせる技巧を覚えていた。たかだか十二歳の子供にしては上出来で私が性的にませていた証拠だろう。
私は二本指を久の膣に深く挿入してその中を巧みに掻き回し、同時に親指の先で膣の上に有る小指の先ほどの豆を刺激すると久が酷く反応することを知っていた。私はその技巧で久を喜ばせ、久の喜悦の表情を見ながら私もまた二回目の射精を久の手に放ち終えるのだった。その後、お互いに満足してまた私たちは抱き合った。
今度は大人しく、私が寝るまで一緒に添い寝してくれるのである。
その間が私と久の寝物語の時間だった。
今でも良く覚えているが、毎夜、そうして真っ暗な闇の中でお互いに満足して心地よさの余韻を噛み締めながら、ひしと抱き合い様々な話しをするのだった。それは本当に仲睦ましい新婚夫婦のようだった。
久は自分の生い立ちや、毎日の家事や、機織の仕事やその他、同輩の下女や出入りの職人たちの噂話を話して聞かせた。普段は大人しく無口だと思っていた久が饒舌に話すのは私に心から気を許している証拠で嬉しかった。私もまた学校のことなどを話したが、やはり大人の久の話が中心でもっぱら私は聞き役だった。そんな寝物語の中で私は最も関心のある性の話を久に求めた。
それは、男や女の体のことや、男女の関係の様々な話だった。
その中で、やはり最も大きな驚きだったのは男女の性行為の秘密だっただろう。
私は男女の行為や子供がどうしたら出来るるかなどについては、全く知識が無く、久から手淫をしてもらって射精するようになった後も相変わらず子供が出来る具体的な方法は知らないままだった。何度か久に、チン○の先から出るのがおしっこではなく、子種の汁だと教えられたが、その先の具体的な性行為については流石にうまくはぐらかされたままで教えてくれなかった。久がそれをようやく教えてくれたのは、一緒に暮らし始めてもう一月近く経ったある晩のことだった。
「若さあ、本とはなあ、何でもない、いっち簡単な事ですがね。男しの硬うなったち○ち○をば、おなごしのおそ○に嵌めるんやがね。」
「嵌める?どうやって?」
「ほらあ、今、若さあがいじっとるところへ、チンチ○を重ねて、ずんと突き刺すんだけだがねぇ。」
私は内心、あぁそうなのか、と思った。
それは半ば予想していたとおりの答えだったが、そうして改めて言われると、やはり半信半疑だった。
一体チンチ○をそんなところへどうやって挿すのだろうか?
本当に挿せるのだろうか?
それに挿したら自然に汁が出るのだろうか?
手でしごかずに汁が出るとは思えなかった。
再び広がった疑問をそのまま久にぶつけてみた。
「若さあ、硬いち○ち○は簡単に濡れて湿ったおそ○に突き刺せるんだがね。
なあ、指が二本も入るんやから、硬いち○ち○ならすっと根元まで入りよるんよ。」
言われてみればそのとおりだった。
指で弄っているからそこが柔らかく、意外に奥が深い事は良く知っていた。
だから、チン○が全部入るのは容易に想像できたし硬い棒のようになったチン○なら突き刺すのは容易だろう。
「そんでもぉ、ち○ち○をおそ○の中に入れたら、手でこすれんがやぁ?こすらんかったら、汁が出やんがね。」
「あれまあ、若さあ、ほんま何も知らんがねぇ。入れたらおそ○で擦るんだがね。せっせと擦ったら、すぐにち○ち○が気持ち良うなって、勢いよお、汁を飛ばしますがね。」
「ふ~ん、おそ○の中で擦るんかいなあ?そんで、ほんとに気持ち良おなるんかいなあ?」まだ半信半疑だった。
何しろ、今までずっと久の手でしごかれて射精していたから、手で擦るのが最も気持ちがよいのだと信じ込んでいた。
ただ、ち○ち○をおそ○の中に入れると言うのは本能的に良く分かったし、想像するだけで、ぞくっとするような興奮が有った。
自分の硬く強張ったチン○を、今、手で弄っている久のおそ○の中に入れる?
そこは、ぬるぬると粘って膣道の中は熱く、ぐちゃぐちゃとした柔らかな海綿のようだった。ここに、チンチ○を入れる?
女の大切な所にこのチンチ○を入れる?
思っただけでも興奮でぞくぞくしてくるようだった。
そう思うと、もう二回も射精し終えていたがまたち○ち○が棒のように硬く反り返ってきた。
「あれまあ、また若さあ、こんなに・・」
久が感に堪えたように言った。
私はもう妄想の虜で頭に血が上っていた。
「ああ、わしぁ今から久のおそ○に突き刺しとうなった、なあええがやぁ?」
私は身を乗り出して久の上に圧し掛かろうとした。
「あかん、あかん、若さあ、そがいなことはあかんです。」
久はきつい口調でぴしゃっと言い、圧し掛かろうとする私の体を押しのけた。
「なあ、そんだけは堪忍してやってくれんがね。若さぁの汁をあてのおそ○の中に出したら、やや子が出来ますがいね。なあ、若さあ、そいでもええんかいなぁ?」
私は一瞬、ドキンとした。
流石に赤ん坊が出来ると言われて私はその意味を改めて理解したのだった。
妄想の虜
その夜から私の頭から久のおそ○にチン○を突き刺す妄想が離れなくなった。学校にいるときも放課後もいつもそのことが頭から離れなかった。もう勉強どころではなかった。相変わらず、毎夜、一緒に風呂に入っていたし寝床の中で裸で抱き合い、手でお互いの性器をいじり合い久の手で精を放っていた。それでも私はもう満足できなくなっていた。所詮、手の中でするのは本物ではないのだと思うといっそう腹立たしかった。
私は久に邪険に当たるようになっていた。執拗に拒む久が憎らしかった。
私は気に入らないことがあると大声でわめき散らして、久に手を上げることさえあった。一人息子で我がまま放題で育った弱さで、自制心が弱く思い通りにならないことに腹が立って仕方が無かったのである。
久は本当に申し訳なさそうに、
「堪忍してやってくれんがねぇ、あてが悪うございます・・・」
とひたすら謝るのだった。
そして、ある夜のことだった。
いつものように私は風呂場のすのこの上で裸の久を抱き寄せて、ぐいぐいと体を押し付けていた。大抵そこでお互いの性器を弄りあい、一回手の中に放ち終える慣わしになっていた。私は乱暴に久のおそ○を弄り、そのまま硬直したち○ち○を重ねた。そうして本能に背中を押されるまま、久の腰を抱えて風呂桶に押し付けた。そのまま立ったままの姿で股を広げさ無理やりにでも、チン○を入れてしまおうと頭に血が上っていたのである。
「あかん、あかん、若さあ、なあ堪忍して・・・」
久は本気で抗った。
流石に女でも大人の体で私よりうわ背があり本気で跳ね返されれば勝てなかった。
私は押し返されて、腹立ち紛れに久の下腹をコブシで殴った。
うっと、久はその場に痛そうにしゃがみ込んだ。
そして、「堪忍して、堪忍して・・」と肩を震わせて嗚咽するのだった。
流石に気がとがめた。
拒絶される理由は分かっている。
しかし頭ではわかっても体は別だった。
やり場の無い激しい性欲に私は捉えられ、その久の頭を手で殴った。
すると、久が堪忍してと泣きじゃくりながら、しゃがみ込んだ姿勢で私のち○ち○を手にとった。
そして何とそれを口に含んだのである。
それは思っても見なかった行為だった。
あっと思ったが私は久のなすままに任せていた。
ち○ち○が生暖かい口の中にすっぽりと根元まで咥え込まれていた。
そして、暖かな口中で、ねばっとした舌が絡みつき硬直したものに絡みついた。
それは、何とも言えない、ぞくぞくするような心地よさだった。
堪らない快感が背筋を伝って来る。
そんなものを口に含むなど汚い・・・と言う思いは有ったが心地よさで拒絶できなかった。久は口に含んだものを舌を絡ませて音を立てて吸った。
それは手でする行為とは全く異なるぞくぞくする快感だった。
たちどころに興奮の頂点を迎えて、いけない、と思ったときはもう遅かった。
一気に久の口の中に精を勢い良く放ってしまった。
久はそれをしっかりと口で受け止めてくれたのである。
荒い息遣いでがっくりして、蹲ったままの久の肩に手を載せて呆然としていた。
久が口の中で丁寧にそれを清め終えると、ゆっくりと口を離した。
「なあ、若さあ堪忍してやってくれんかね、いつでもあてがこうしてあげますがねぇ。」私は心地よさでもうおそ○へ入れることをすっかり忘れていた。
それからは、もう決して手では満足できずいつも私は久に口でするようにせがむようになった。
女の体
久との生活は夢のように過ぎていった。
毎夜、私は風呂場と寝床で必ず二回、久の口に射精して思春期になったばかりの旺盛な性欲を満たしていた。
そうした直接的な性欲の処理以外でも久からは女と言う物を実地で教えられた。
たとえば、女の体、女特有の生理、そして女の感情などなどだった。
私は一人息子で兄弟も無くまた女姉妹も無く女については清から学んだことがすべただった。しかしそれは幼い子供の時代で、清を女として意識していたわけではなく、今、改めて久から大人の女と言うものを学び直すことになったのである。
女の体といえば真っ先に思いつくのが生理である。
毎夜欠かさず久の体を抱いていたから、月のものについて否応無く知ることになった。
好奇心旺盛でませていた子供だったから、女の体には興味深深で久に詳しく説明させてあげくには実際に出血するおそ○を見せるように頼んだ。流石に久は恥ずかしがってそれを見せてはくれなかったが、女の体は月に一度、血を漏らすのだと言われたときには全く信じられなかった。どこからどうやって出血するのか、怪我もしていないのに何故血が出るのか?どこか悪いのではないか、血が出たら死んでしまうなどなど、子供らしい興味が山ほどあった。それに久の体が心配でもあった。久の月のさわりは子を産んでいないせいか、あるいは、四十を目の前にした年齢の関係か、傍で見ていてもつらそうだったのである。月のものが始まると久は腰巻の下に紺色の越中ふんどしのような形の晒し布を締め、小さく畳んだ手拭を股に挟んでいた。所謂丁字帯で、当時それが普通だったのかどうか知らないが今のように生理帯や脱脂綿が手軽に入手できる時代ではなかったから、そうするのが普通の過ごし方だったのだと思う。
私は久のすべてを知りたくて無理やりに嫌がるのを着物の裾をまくって見せさせたのである。そして風呂は背中を流してくれたが湯船には一緒に入らなかったし裸で抱き合うことは許さなかった。無論口で吸うのはきちんとしてくれた。寝床は一緒に入ったがふんどしを外さず、同じように口で楽しませてくれたから私としては満足だった。
月のものが始まると久の体から少し酸っぱいような体臭がしていたのを覚えている。
普段体臭が濃い女ではなかったが、どちらと言えば毛深く今と違って化粧を毎日するわけでもなく冬場などは毎夜風呂に入ることも無く誰でも体臭は漂わせていた。生理の出血はやはり独特の匂いで敏感な私はそれを感じ取っていたのだ。
ついでに言えば、腋毛は今でこそ皆剃りあげているが当時はふさふさと生やしているのが普通で久も濃い腋毛をいつも生やしており、冬場など風呂に入らない日はつんとした腋臭が匂っていた。
暫らく前から、私は久の口を吸うことを好むようになっていた。
他人の息や唾液は汚いものだという気持ちが強く、それまでは考えたことも無い行為だったが、久に教えられ私はそれを好むようになっていた。そうすることが、酷く卑猥で親密な男女の間の密かな行為のように思えた。単に体を弄り回すだけでなく、もっと何か別の精神的な繋がりさえ感じさせる親密な行為に思えたのである。
私は心底から、久ともっと親密になりたいと思っていた。
今や久は私にとっては絶対的な存在だった。
それを深く確かなものにするのに口吸いは必要な行為だと思った。
舌を絡め合い、唾液が混ざり合う。
混ざり合った唾液が溢れそうになるのを私は音立てて飲み下した。
少しも汚いとは思わなかった。
大好きな久の唾液ならいくらでも飲むことが出来た。
その気持ちは久にも伝わったのだと思う。
久もまた混ざり合った唾液を飲み下した。
唾液は飲んでも飲んでもいくらでも溜まって口から溢れそうになった。
私たちは競うようにして相手の唾液を飲み込み、二人で互いの口の周りがべたべたになるのを面白がった。それはまさにじゃれあうような行為で、性器を弄り精液を放つこととは違った特別な楽しみだった。
そうしていると互いの気分が高まってきてそのまま下腹に手を這わせて互いの欲しい物をまさぐりあうこともしばしばだった。
その日の私は何時に無く欲情しており当然のように久の着物の裾をまくって手を忍ばせた。そして散々弄った後で私は久の股の間に体を割り込ませて硬直した性器を久の下腹に押し付けていた。
「あかん、あかんがねぇ、若さあ、そがいな事はあかんですがねぇ、なあ、はようあてが吸ってあげますがねぇ」
いつもならそれで私は久の口で吸われて射精して終わるのだった。
しかしその日は何故か酷く昂ぶりそれだけでは満足できない気分だった。
「なあ、久、ええがや、なあ、いっぺんだけ、どうしてもさせて欲しいんやがぁ」
私は本気で哀願した。
しかし、久は、
「あかん、あかんがねぇ、そんだけは堪忍してぇなあ」
といつもの言葉を繰り返すだけだった。
その日の私は何時に無く欲情しており当然のように久の着物の裾をまくって手を忍ばせた。そして散々弄った後で私は久の股の間に体を割り込ませて硬直した性器を久の下腹に押し付けていた。
「あかん、あかんがねぇ、若さあ、そがいな事はあかんですがねぇ、なあ、はようあてが吸ってあげますがねぇ」
いつもならそれで私は久の口で吸われて射精して終わるのだった。
しかしその日は何故か酷く昂ぶりそれだけでは満足できない気分だった。
「なあ、久、ええがや、なあ、いっぺんだけ、どうしてもさせて欲しいんやがぁ」
私は本気で哀願した。
しかし、久は、
「あかん、あかんがねぇ、そんだけは堪忍してぇなあ」
といつもの言葉を繰り返すだけだった。
「なあ、どうしてもあかんがかぁ?なあ、わし、やや子が出来てもええと思うとるんじゃぁ、なあ、本当にわしはええんだがぁ」
それは本音だった。
幼い私は一途に、もう久のためなら何物も代え難いと思うようになっていた。
「あんれえ、若さあ、そんだらぁ、あてはここにおれん様になりますがいねぇ、そんでもええんですがいねぇ?」
「いいや、久は置いてやる、わしがおっかあに掛け合ってやる、なあ、久、わしの嫁になったらええんだがぁ、なあ、そしたら、ずっとずっと一緒におれるがねぇ」
それは思いつきでは無かった。
暫らく前から私はそれを子供なりに真剣に考えていたのである。
大好きな久とずっと一緒にいられるためには祝言して本当に夫婦になってしまえば良いのだ。幼い私は大人の世界を知らなかったから単純にそう思ったのである。無論、怖い母の承諾が絶対に必要だったが、何としても押し通すつもりだった。
「なあ、久、わしのことが好きか?なあ、わしは死ぬほど久が好きじゃぁ、そんだで、わしはおっかあに頼んでやる、わしは久と一緒になりたいんじゃあ、そんで、やや子を作るんじゃ、なあ、ええじゃろうがぁ?」
久は、あっけに取られている様子で暫らく何も応えなかった。
代わりに、
「ああ、若さあ、そがいな事言うてくれたら、あてはなんぼうかうれしゅうて、涙が出ますがねぇ。」
実際にその声は鼻声になっていた。
「そんでもぉ、こがいな婆さまあだでねぇ、若さあぁの嫁にはなれませんがぁ、なあ、若さあ、堪忍やがねぇ・・」
悲しそうな答えだった。
「あほらし、わしは久が好きじゃと言うとるんだがねえ、久はわしを嫌いなんかぁ?」
「ううん、そがいな事はあれせんだがぁ、あても若さあのことがいっち、好きだがねぇ」「そんだら、ええがねぇ、嫁さんになってくれぇ、なあ、久、ええがねぇ?」
暫らく久は何も言わなかった、そして久は小さく肩を揺すってしゃくりあげていた。
本気で泣いているのが伝わってくる。
何が悲しいのか?
幼い子供には理解できない事だった。
・・・・・・・・・・・
久はいきなり畳みに正座した。
慌てて私も正座して向かい合った。
久はそんな私の顔をじっと見つめてから頭を畳みに擦りつけた。
「若さあ、あてのような出戻りの婆さんに、そがいな事を言ってくれるがいなぁ、ホンにうれしゅうごぜえます。何かぁもう身が縮むような気持ちですがいねぇ。」
久の言葉は実のこもったしみじみしたものだった。
そして、改めて頭を下げると、
「若さあ、そがいなまでぇ言うてくんさるんだらぁ、あても覚悟をば決めましたがぁ。
あてもぉ、若さあのことはいっち好きだがねぇ。そやからぁ一緒に風呂へ入ったり寝床に入ったりしておりますがね。あてみたいなもん、若さあの嫁にはなれんです。そんでもぉ、好きやからぁ、もし若さあがしたいんならぁ、好きにしてもろうてもええです。」
そして、こう続けた。
「だけんどもぉ、少し待ってくだされ、こんなぁ、まっ昼間じゃあ、誰かにい見られるかも知れんし、やっぱしぃいかんがいねぇ。なあ、今晩、寝床できちんと致しましょうがいねぇ。」
流石に私はそう言われてはもうそれ以上無理押しは出来なかった。
「うん、久、きっとやがね、今晩、寝床でするんだがねぇ?」
久は答える代わりに私の体を抱きしめ、口を吸ってきた。
私もそれに必死に答えた。
その口吸いは今までにない親密で情のこもった長くて濃厚なものになった。
久はいっこうに寝床へやってこなかった。
じれて何度か呼んだが、
「若さあ、ちっとぉ待って下さえまし。」
そう言って中々姿を見せなかった。
いい加減待ちきれなくなってから、久は六畳間の私の寝床にやってきた。
その久の姿に私は心臓があぶつような激しいトキメキを覚えた。
久は今までの粗末な綿の寝巻きではなく、エリだけが白い、全身真っ赤な緋色の襦袢に身を包み、明らかにそれと分かる白粉を塗り口に紅を差していたのである。
体からは桃の香りのような甘酸っぱい香りがかすかに漂っていた。
そんな姿の久を見るのは初めてのことだった。
普段は粗末な麻や綿の仕事着やうわっぱり姿で、無論、化粧などしたことも無く髪も無造作に後ろで束ねているだけだったから、正直、その姿に私は言葉にならない感動を覚えていた。
久は年をくってはいたが、姿勢が良く上背が有り姿は良かった。
そして色が白く凛とした整った顔立ちで昔は別嬪さんだったと噂されていた器量だったから、そうして妖艶に装うと別人のような見栄えだった。
今でも思うのだが三十七と言うのは女が最後に輝く熟しきった色気の迸る年齢なのだろう。だから子を産んでいない久はその最後の輝きを一層強く放つような色気と美しさに満ちていたのだと思う。わずか十二歳の子供には全く過ぎた相手だった。今の私でもその年齢の女には食指が動くのだから思春期を迎えたばかりの子供にはもったいない相手だった。とにかく私は久に性の手ほどきを受けたことを今更ながら人生の最大の幸福だったと思っている。
薄暗い30燭光の電球に照らされた部屋の中で、久の艶かしい姿は、幼い私さえゾクゾク震わせるほどの艶やかな大人の色気に包まれていた。
髪の毛もいつもと違って後ろで束ねずばらりと肩から流して艶やかに黒く光っている。
髪をそうして流すと、酷く若い様子でとても三十七には思えなかった。
私は子供心にも久が本気で私に女の姿で臨んでいるのだと思った。
久は寝床の前にきちんと正座すると、三つ指を突いて私に深々と頭を下げた。
私はあっけにとられて、反射的に起き上がって正座して久に向かった。
「若さあ、ほんに昼間はうれしゅうござんした。こうしてぇ、御礼致しますがいねぇ。あてみたいなぁ出戻りの婆さんに、あげな事を言って下さるのはぁ、若さあだけでござんす。ほんにうれしょうござんした。」
頭を畳みに擦りつけながら言う久に私は返す言葉が無かった。
「若さあ、昼間もぉ申し上げんしたがぁ、あてみたいなもんは、決して若さあの嫁さんにはなれんです。だけんどもぉ、こうして二人きりで、誰にも知られんとこだけならぁ、ひっそりとぉ二人だけの秘密でぇ、若さあの嫁にしてやってくださらんがねぇ。」
私はまだ子供だったが多くの下女や職工たちの大人の世界を垣間見て育ち、そうした大人の言葉の機微は何とはなしに理解できるのだった。だから久の言っている意味は良く分かった。
本当の嫁にはなれないのだ、それは恐ろしい母が絶対に許すはずが無かった。
しかし、こうして二人きりなら誰にも知られずに嫁さんに出来るのだ。
久はそう言っているのだった。
久はつと立ち上がると天井の電灯を消して、私の寝床にそっと潜り込んだ。
二人は互いに相手の体を抱きしめ合い、口を重ねあった。
そして今までに無い親密な情愛のこもった口吸いが交わされた。
それは今までに無い本気の口吸いだった。
お互いの唾液を貪るように吸い、飲み下し、また求め続けた。
抱いている久の体からは甘酸っぱい香りと女の匂いが強く立ちこめ、いつもとは違った女を感じさせ私は異常に興奮していた。
自然にお互いに着ている物を脱がせ合い、素裸になった。
肌をきつく重ねあい、痛いほどにきつくしっかりと抱き合った。
私はたわわな久の乳房をまさぐり口で吸い、豊かな尻を抱きかかえて、大人の女の豊かな体を心行くまで堪能した。
抱き合いながら、馴染んだ互いの下腹をまさぐり合った。
久はいつもと違ってすでに激しく濡れ、そこは湯のように熱く潤っていた。
そして久の手が硬直した私のチン○を優しく握り締めた。
互いに愛しい相手の性器を手でまさぐり愛撫しあった。
久はすでに息が上がってハアハアと喘ぎ声を漏らしていた。
やがて我慢できずに私が声をかけた。
「ええかぁ?」
問いかける私に久は
「はい」
と小さく恥じらいを見せて頷いて見せた。
後はもう経験豊富な年上の久のリードだった。
私の体を両手で抱きしめながら上に乗るように促した。
促されるままに体を起こして久の腹の上に圧し掛かった。
久が圧し掛かった私の体を下から両手で抱きかかえ、足を開いて私の体をはさみつけた。それで小柄な私は大人の女の腹の上に乗せられて両手両足ですっぽりと包まれるような形になった。
女の体で包み込まれて抱かれることの安堵感、幸福感。
今でもはっきりと覚えているがそれは天国にいるような心地よさだった。
そうしていると、硬直したものが久の下腹に押し重なる。
どうしたものか、と思っていると、つと久の手がそれに触れて誘ってくれた。
私は両手で体を支え両足を踏ん張って姿勢を整えた。
そうして促されるままに腰をゆっくりと進めていった。
先端が熱い湯の中に重なってずるっと少し埋まった。
後は一気呵成に、と逸る気持ちを裏切るように、意外にも、その先は固い壁に阻まれるような感じで、するするとは入らなかった。
いつも指で中を掻き回していたがどうも感覚が違うことに戸惑った。
子を産んでいない久の体は、やはり狭く硬さが残っており、子供の細い指で攻めるのとは勝手が違うようだった。
今思えば、久は三十七と言う年齢にも関わらず、子を産んでおらず、また離縁されてから長い間、空閨を守って来たはずで、いきなりの性行為にすぐには応接が出来なかったのだと思う。それに小柄ながら十二歳になっていた私は、すでに陰毛も生え、一人前に近い一物だったから準備の出来ていない久の体にはきつかったのかもしれない。
私はそんなことは全く思い至らず、ただただ、闇雲に腰を進めたから多少の無理があったのだと思う。無理に押すと流石に久が痛そうな表情で、眉に皺を寄せた。
一瞬どうしたものかと躊躇する私に、
「ええんですよそのまんまでぇ、たんだ、そっとやよぉ、なあ、若さあ・・」
久が小声でそう励まし、背中に回した手で優しく引き寄せ促してくれた。
促されて、再び腰を進めようとすると、久も腰を浮かせて迎え撃つ姿勢を見せた。
女のほうがそうして積極的に動くのが新鮮な驚きだった。
なるほど夫婦の性愛は互いの協同作業なのだと久が言っていたのを思い出した。
お陰で挿入は随分とスムーズなものになった。
きつく押すと久は腰を引いた。
逆に押しが弱いと自ら腰を迫り上げて重ねてくる。
まるで互いの性器の先端同士が意思を持っているように重なり合い、押し付け合い、一つになる作業を進めているようだった。
一進一退を繰り返して、やがて私の性器はしっかりと久の性器の中に挿し込まれていた。そのまま動かず、久の両手が私の尻を抱え込んで引き寄せる。
否応無く私の性器は根元までしっかりと久の性器に埋まり、付け根の部分が痛いほどきつく重なり、ぐいぐいと押し合わさった。
そうしていると、完全に互いの性器が繋がりあったことを実感させた。
久が下から私の顔を挟んで口を求めてきた。
私も腹の下にある柔らかな久の体を力の限りにきつく抱きしめ口付けに答えた。
激しく口を吸い合いながら、二人はきつく重ねた体を擦り合わせた。
下の久のお腹が柔らかく動くたびにちゃぷんちゃぷんと波打つようだった。
決して肥えてはいないが、久のお腹は柔らかく暖かい湯を入れたゴムの袋のようだと思った。
体重を乗せて体を上下に激しく動かす。
そしてきつくきつくあそこをこすり付ける。
私は夢中になって腰を使い、本能の行為に没頭していった。
久はそんな私にしっかりと合わせて従順に従った。
久はもう先ほどから打って変わって、年上の経験豊富なリード役から、素直な可愛い嫁に変わっていた。久は年上でも決して私を蔑ろにすることは無く、常に目下の立場で私を主人として立ててくれていたし、閨の中の性愛の行為でもでしゃばることなく、控えめに私に従ってくれるのだった。
私はリード役を引き受け、腰を使った。
久もそれに合わせて腰を使い二人の体は一体となってリズミカルに上下し前後に揺れ動いた。
私はたちどころに終焉を迎えた。
当然だったろう。
久の中に入れた初っ端から爆発しそうだったのである。
経験の無い初めての行為に、子供の私は我慢など出来ようはずも無く、一気に興奮の頂点に駆け上がっていった。
さ~っと激しい電流が背筋から脳天まで走りぬけ、思う存分の精を久の腹の中に放ち終えていた。
久も同時に、私の背中に爪を立て、うううううんっと嗚咽を漏らして、体をのけぞらせていた。
夫婦の契り その三
生まれてはじめての本物の性行為はあっけなく終焉を迎えた。
私は興奮に包まれたまま呆然として体の力を抜いて久の腹の上に圧し掛かっていた。
チン○は湯のように熱く海綿のように柔らかな久の膣に埋めたままだった。
久はそんな私の体を優しく慈しむ様に抱きしめてくれていた。
暫らく私は何も言えず身動きも出来なかった。
まさに陶然として、ぼんやりとたゆとうような夢心地だった。
久も同じだったのか心地よさそうに目を閉じてじっと動かなかった。
暗い中でそんな久の表情を確かめるようにじっと見つめた。
それに気づいたのか、久が恥ずかしそうに、イヤッと言う仕草をした。
それは心底からいとおしさを感じさせる仕草だった。
久が自分より二十五も年上の女だとは全く思わなかった。
ただただいとおしい、可愛い嫁だった。
私は久の頭を腕に抱えて口を重ねた。
久もすぐにそれに答えてくれた。
満ち足りた幸福感の中で私たちは愛に満ちた口付けを交わした。
しっかりと体を繋げあったまま舌を絡め合い唾液を吸い合うのは、とてつもなく深く互いの体が一つになっている感じがした。
そうして口付けを交わしているとまた腹の底からの欲情が込み上げてくるのだった。
私は久の口を吸ったまま、ゆっくりと腰を動かした。
久は、口を塞がれたまま鼻から、ふっふっと熱い息を吐きながら、きつく私にしがみつき両足を巻きつけて抱きついてそれに応えた。
私は久の体に包まれたまま口を吸いながらゆっさゆっさと体を揺すり立てこすり付けた。初回とは違って流石に少しはゆとりがあって動きは性急ではなく、ゆっくりしたものになっていた。
そのときだったと思う、確かに久の体がきゅっと私の性器を締め付ける感覚が有った。何となく手で握られたときのような感じで、あっと不思議に思った。
今まで柔らかな海綿のようだと思っていた久の性器の中が、急にきつく狭くなってチン○に絡みついてくるようだった。抜き差しすると粘っとした感じがして、まるで口の中で舌を絡めて吸われている時の様な感触だった。
しかしもうじっくりとそれを楽しんでいるゆとりは無かった。
私は二度目の終焉を向かえ、激しい快感の中で一気に精を放っていたのである。
流石に二度立て続けでの行為の後は全身から力が抜けるような脱力感だった。
私は久の腹の上に圧し掛かったまま再び呆然としていた。
久も全く同じ様子で、何も言わずただただ、優しく私の体を抱きしめて、子供をあやすように背中をさするのだった。
私は下敷きになった久が重いだろうと早く体をどけようとした。
しかし久が、「イヤッ」と小さく呟き私の体をきつく抱きしめた。
それで私は性器をしっかりと埋めたまま動かなかった。
どれほどそうしていたのか、私には分からなかった。
あまりの心地よさと脱力感で少しの間、うとうとしたのかも知れなかった。
やがて、久が私の口を吸ってきたので我に帰った。
それはもう激しい口付けではなかった。
幼い子供のように、互いの唾液を吸い合い、舌を絡ませ合って遊んだ。
舌は口中に潜む小さな小動物のように、相手を求めて追いかけあるいは逃げ回り、まるで鬼ごっこのように動き回った。
私はチン○を久の性器に突き刺しているのと同じように舌で久の口の中を突き刺しているのだと感じていた。性器が単に硬いだけで自在に動かないのに比べて舌は自在に動かせるのでより、激しく攻めているような気がした。
そして時折下腹に突き上げてくる欲情に任せて、繋げあっている性器を激しく突き動かした。私は、硬く尖らせた舌先とチン○で同時に久の体を犯しているのだと思った。
「不思議なことだがぁ、何や知らん、若さあとは何とのう体がしっくりと合う様な気がぁしますんがいねぇ・・・」
初めての経験で良くは分からなかったが、確かに久の言うように繋げ合わせた自分の性器と久の性器は、しっくりと馴染んだように絡み合い一つになっている様な気がした。
ただ、久の体は成熟した大人の女の体だから、自分のような子供のチン○をしっかりと包み込んで気持ちよくさせたのだろうと思った。
体を重ねながらそんな普通の会話を交わしているのが不思議な気がした。
何しろ今も自分の体は温かく柔らかな久の腹の上に乗っておりチン○は根元まですっぽりと久のおそ○に包み込まれているのだった。
「ああ、気持ちええがやぁ、久のおそ○の中はぁ・・・」
「ふふふ・・・若さあ、そがいに気持ちええですかねぇ?」
「うん、口の中より遥かにぃええ気持ちで、天国みたいな感じじゃあ・・」
「あれえ、若さあ、ほんに、うまいこと言わせるがねぇ。あてもぉ、若さあのが硬とうてぇ、まるきし鰹節見てぇにこちこちで、ええ気持ちですがね。」
鰹節みたいだと言われて、ああ、確かにそうだと思った。
十二歳の性欲の塊だった私のチン○は、硬直するとかちかちの棒のようだった。
大きさも形も硬さも確かに鰹節に似ていると思った。
「ああ、本当にぃ、こんだら気持ちは初めてじゃがぁ、天国に上るような気持ちよさじゃったぁ・・・・」
「あてもぉおんなじだがいねぇ・・何とのうあんまし気持ちがようてぇ、このまんま死んでもええ、思うほどじゃたですがねぇ」
それは、まさに性愛に満ち足りた後の親密な夫婦の閨の会話だった。
「なあ、若さあ、もしも、こがいな事をしてぇ、あてにやや子が出来たらばあ、若さあ、どがいされますかいねぇ?」
久が少し遠慮がちに、ためらう口調でたずねた。
しかし真剣な気持ちが伝わってきた。
自分が試されているのだと、幼いながらも私は理解した。
それは以前に久から問いかけられた大きな問題だった。
自分が父親になると言う問いかけだった。
私はもう躊躇しなかった。
「ああ、ええよう、わしはやや子のてて親になったる。そんでぇオッカサンに許してもらうだがね。」
それは必ずしも閨の興奮した口から出任せの言葉でも無かった。
子供なりに久を可愛がり大切にしなければと思ったし責任を取ることすら考えたのである。その思いが久に伝わったらしかった。
「うれしいがねぇ、若さあが、そがいな事を言うて下さりますとは・・・・・
ほんに嬉しい事ですがねぇ・・・・・・・・・・・」
最後は聞こえないような涙声だった。
そして久は再びきつくしがみついてきたのだった。
体を繋げあったままでの睦み事は長く続いた。
性欲に溢れた少年のチン○は、その間も少しも緩まずずっと硬いまま年上の大人の性器の中で息づいていた。
ときおり、どちらからとも無く腰を揺すって繋ぎあった性器を擦り合わせた。
流石にもう二度も放っているから、こんどはもう容易には果てなかった。
何度か勢い良く突き上げると久は眉に皺を寄せて苦しそうにするのだった。
私は本気で心配になり、
「久、どがいした、ええか大丈夫か?」
と声をかけた。
「ああ、ええです、若さあ止めたらあかんがぁ、なあずっとずっとそがいに突いてやってくれんがねし。」
久は恥ずかしそうにそう答えた。
ただ、私はあっけなく終焉を迎えるよりもそのまま長く久の中に入れておきたかった。
そうしてずっと睦事を交わして居たかったから、果てる前に動きを止めるのだった。
結局、私は朝までずっとそうして久と交わって一夜を過ごしたのだった。
覚えているだけで、七回は精を放ったと思う。
今思っても十二歳の自分は性欲の絶頂期だったのかも知れない。
何しろ嵌めたまま七回まで精を放ったのだから。
新婚の朝
翌朝、私は久に起こされて、目を覚ました。
明け方まで繰り返し繰り返し情を交わした。
そうして、ようやく鶏鳴の中で、うとうとと寝についたのだった。
しかし久はいつもと変わらず、すでに起き出して朝餉の支度を終え、洗濯に取り掛かっていた。久は細いけれども働き者で、若い清に比べても遜色ないほど身のこなしが軽く、きびきびとした女だった。
眠い目を擦りながら、外の井戸に出ると、
「若さあ、おはようございます。」
と久が洗濯の手を止めて明るい声で丁寧に挨拶した。
浅黄色の櫓の着物にタスキ掛けをした、いつもの姿である。
見慣れているはずの久の姿だったが、明るい五月晴れの光の中で見ると、はっとするほどに美しかった。久は年よりも若く見える性質だったが、その日は特に若々しく輝いて見えた。朝から五月晴れの良い天気で夏を思わせるような陽気だった。
朝食は珍しく卵が添えられていた。
豊かな暮らしでは有ったが、田舎の質素な生活では卵を食べることは滅多に無く、病人が滋養をつける手段として食べる程度だったから、私は驚いて声に出した。
すると久は
「若さあには、うんと精をつけてもらわねばなりませんがねぇ。」
そう言って、可笑しそうに、クククと含み笑いをするのだった。
久はいつもの味噌汁とたくあんだけだった。
精をつけると言う言葉には含みがあった。
何しろ七回も精を放っていたから滋養をつけることが必要だった。
それに、今夜のためにもご利益があるだろう。
久がそれを暗に仄めかしていると思うと、股間がゾクッとした。
明るい日差しの中で久と差し向かいで食べる朝食は昨日までのそれとはどこと無く違って感じられた。別段、会話が弾んだわけではなく却って二人とも無口になっていた。
私は目の前の久を見ながら頭の中は昨夜の事で一杯だった。
久の熱く柔らかな体の感触。
ずっと差し込んでいたあの中の湯のような熱さと海綿のような柔らかさ。
そしてきゅっと締め付けられた感触。
そして何度も何度も放ったときのゾクゾクする興奮。
それらすべてが生々しく体の感触として残り今もまだ目の前の久の体を抱いているような錯覚がするのだった。
「若さあ、そがいにぃ見たらぁ恥ずかしいですがねぇ・・・・」
久が顔を俯けて、ぼそっと言った。
自分が考えている事を久に見透かされているようで酷くばつが悪く、何か言わねばと思って口を開いた。
「好きや、久がぁ・・・」
何も考えずに思わず口から出た言葉だった。
久が顔を上げ、知らず二人の目が合った。
「あ、あてもです・・・」
久が聞こえないような小さな声でボソッと答えた。
久の頬は小娘のように恥じらいで赤くなり慌てて顔を俯けた。
そして二人とももう何も言わなかった。
http://yukemuritarou.sakura.ne.jp/mousou20080101/12sainofudeorosi.html
良かったら「いいね」してください。誰でも「いいね」出来ます!