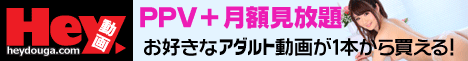あれは高校2年の時…。
どうしても告白したい、好きな子がいた。勿論それまで付き合った事も、女と喋るのも苦手だった。
周りの友達からは
「やめとけ、お前じゃ無理だ」
「あの子レベル高いぞ?釣り合ってねーよ」
「あいつはライバル多いぜ?バスケ部のエースも惚れてるらしい」
「つか、うちの学校で一番人気じゃね?」
などなど、今にして思えば彼らの中にも彼女に惚れている奴がいたかもしれない。
名前は仮に美樹さんとしておこう。
男友達はいたが、女が苦手な俺は当然、モテなくて、奥手で、冴えない奴だった。
放課後、茜色の空の中、手をつないで帰る同級生のカップルを、眩しく見つめる事もあった。
俺は、帰宅部、成績中の中、顔は中の下。スポーツも大して得意じゃない。
球技は苦手だ。確かに釣り合っていない。自覚はしていた。
だが、それでも俺は告白したかった。告白したくなる理由があった。
当時美樹さんは体操部に入っていて、毎日必死に練習していた。
その美貌故、ファンも多く見学者という名の覗きは後を絶たず、
異例な事だが男子は体操部の練習は見てはいけないという決まりが出来た。
男子の不埒な視線が集中力を妨げると。
それでも悪ガキというのは懲りないものだ。ダメだと解かると益々見たくなる。
禁止された事によって、その行為の価値は尊くなったのだ。
案の定、「おい毒男、見つけたぞ!秘密の覗き穴!来いよ!」悪友の一人が誘う。
「ええ?ちょ、ちょっと待てよ!引っ張るなって…」
「これのどこが覗き穴なんだ?…くっ…」
「(小声で)バカ!動くなっ!落ちるだろ!?」
何のことはない、校舎と校舎の狭い隙間に入り込み、俺に肩車された悪友がギリギリの高さで
小窓の淵から覗いている。俺が彼の土台に選ばれたのは単に背が高かったからだ。
「…おお、スゲー…見える…!」彼は興奮気味に言う。俺は膝が震えだし、肩も軋み、それどころではない。
「…おい…まだか? ボチボチ限界だ…。」
「変わるか?毒男」
「いや、俺は…いいよ」
「そうなのか?欲のないやつだな。…じゃあ、もうちょっとだけ…ってヤバイ!」
「え?どうした?」
「誰か向かって来る…!!って、動くな!」
「うわあ…」
バランスを崩した俺達は倒れた。大きな落下音と悲鳴が木霊した。
「ヤバイ、逃げろ!」
悪友は運が良かった。俺の上に倒れ、俺がクッションとなり、倒れたながらも着地の体制が良かった。
そのまま脱兎のごとく駆け出した。俺を見捨てて。
俺は背中から倒れた上、足を少しひねった様だ。痛い。すぐには動けない。
見上げたさっきの小窓から顔が見えた。
———美樹だった。名前くらいは俺でも知ってる。学校の男の誰もが知っている。片瀬美樹。
学校のマドンナ。
…目が合う。動悸が高鳴る。顔が熱い。
「美樹ー!誰かいたのー?」体育館の中から他の部員の声がする。
俺は我が身の不運を嘆いた。俺は覗きなんてするつもりはなかったのに。
でも、そんな言い訳は通じるわけがない。
悪友の誘いを断らなかった事を今更ながらに自分を悔いた。
…これまでか。親は泣くかな。女子には変態呼ばわりされるかな…。
観念にも似た諦めの気持ちでいると、片瀬は口を開いた。
「何をしてるの?そんなところで倒れて」抑揚のない、落ち着いた声、怒気は感じられない事務的な声。
「いや…足を捻っちゃって…」俺はそんな事しか言えない。彼女が聞きたかったのはそんな事ではなかったろう。
片瀬は俺の顔から俺の足に視線を移す。
「美樹ー? どうしたのー?」
ヤバい、もうダメだ…。俺は目を閉じ、天を仰いだ。
「んーなんでもなーい!」
「え?」
「…早く行きな?」
「う、うん」
俺は釈然としないまま、足を引きずりながらその場を離れた。
どうして片瀬は俺の事を逃がしたのだろう…。
しばらくして、花壇の淵に腰掛け、足の様子を見る。
すると、片瀬が向こうからやってくる。まだ体操服を着ている。練習の休み時間だろうか。抜け出してきたのか。
俺に用があるのか。さっきの事だろうか。逃げられる雰囲気じゃない。俺は身構えた。
「足は?痛い?」
「あ、う、うん…」
「見せて、捻挫?」言って俺の前にしゃがみこむ。
「いいよ。大丈夫」
「いいから」有無を言わさない強さを言葉の中に感じる。負い目がある手前、逆らえない。
靴と靴下を脱ぎ、素足を晒す。たったそれだけの事なのに、どうしようもなく恥ずかしい。俺は彼女から目を背けた。
大きな瞳と、白い肌、艶のある綺麗な黒髪を束ねたうなじはもう少し見ていたかったけれど。
「腫れてはないね、本当に捻っただけみたい。これなら大丈夫だよ」
「わかるの?」
「体操は意外と怪我が多いの。特に足はね」
「そうか…」
「無理しないで、帰ったら冷やしておけば良くなるよ」
「あ、ありがとう…」
「覗きはダメだけどね」
「あ、いや…あれは…」
「ふふっ…お大事に!」小さく患部を叩く。彼女なりの断罪の方法だったのだろうか。
「いて…」大した痛みではなかったが、俺は小さく呻いた。片瀬は悪戯っぽく微笑む。
彼女は少し早歩きで体育館に戻って行った。俺は彼女の背中が見えなくなるまで見つめていた。
その間、足の痛みは全く気にならなかった。その代わり、胸の奥に僅かに痛みを感じた。
この日のこの出来事が、全ての始まりだった。
翌日、痛みはもうなかった。足には。
俺は悪友を責める。見捨てて逃げた事を。
「いや、ゴメンな…。何も考えられなくなっちゃってさ…」
この男の行動には悪気はない。それはいつもの事で、皆知っていた。俺はとりあえず文句を言った事で満足した。
それから少したったある日。
その日は放課後は教室で遅くまで友達と喋っていた。
もう暗くなり、みんなと帰ろうと校門まで来たが、忘れ物をした俺は皆を先に返し、教室に戻った。
「一人で帰るか…」つぶやきながら教室を出る。
玄関から校門に向かって歩く時、大きな声がした。
「おーい。ちょっと待ってー!」
「?」
「あ、いたいた。探したのよ、貴方の事」片瀬だった。練習が終わって今帰りだろうか。
「片瀬…さん?」 「あ、私のこと知ってるんだ。そう、2-Bの片瀬美樹。でも私も君の事探してたんだよ?」
「え?どうして?」胸の中に警戒の鐘がなる。どうしても後ろめたい気持ちをぬぐえない。
「いや、ちょっと話があって。…でも名前も知らないし、まさか、覗いてた人っていうわけにも行かないし」
彼女はそういって笑った。とりあえず怒っている感じではない。気後れの、人見知りのしない朗らかな人だった。
「話?こないだの事?」
「そうそう。ねぇ、どうして覗いてたの?」
「どうしてって…いや、実は友達が…」
俺は簡単に顛末を説明する。
「ふーん、でその友達は?」
「い、いや、それはちょっと…名前は言えない…」
「なるほど、俺は連れてこられただけ。手伝いはしたけど覗いてはいない。
だけど、その主犯の名前は言えない。って事ね?」
「あ…」言われてみれば虫のいい話だ。それでは自分が覗いていたと言ってるようなものだ。
「そんな話、通じるかなぁ…?」
「う…」俺は言葉に窮した。が、
「ごめん。俺が覗いてたんだ…。友達の話は嘘だ。」
「ふーん、で、どうだった?練習風景は」
「えーと、レオタードを着てた人がいて…踊ってた…」
「ぷっ!あはははは」
「え?どうしたの?」俺は何故彼女が笑うのかわからない。
「だって…くくっ、練習でレオタード着てる人なんていないよ…本番を想定した演技の練習ならともかく、
普段は体操着とかジャージだよー。あははっ」
「え?あ、そう言えば、片瀬もあの時体操着だった…」
「あはは、わかったわかった。君は本当に見てない、覗いてないのね。信じましょう!
実際あの時、二人の人間の悲鳴が聞こえたし、確かに一人ではあの窓まで届かないしね。台になるようなものもなかったし」
「あ、ありがとう…」
「いいの、いいの。私もちょっと意地悪だったね。ゴメンね?
でも、なんで友達を庇うの?あなたの事置き去りにしたんでしょ?」
「え…あー、そう言えばなんでだろう。…ごめん、よくわからない。なんとなく、言っちゃいけないような気がして…」
「それで、自分が罪を被ってもいいって?」
「…うん。なんかそんな綺麗な感じじゃないけど…」
「真面目なんだね。君って。」片瀬は感心したように言う。なんだかこそばゆい。
「そんな事ないよ…。」
「いや、偉い偉い。」そういって彼女は俺の肩を叩く。
「そう言えばまだ、名前も知らなかった。クラスも。あ、学年もだ」彼女はまた笑った。よく笑う人だ。
「えと、2-Aの西野尚(仮名)」
「にしのひさし君。部活は?」
「…帰宅部」
「そう、…だと思った」また笑顔。
この日、初めて彼女とちゃんと話した。正確には、こんなに長い時間女の子と話したのも初めてだった。
「でもどうして、ウチの学校の男の子はすぐ覗くんだろうね。ちゃんと体操って物を見れないのかな」
彼女は少し、悲しげに呟いた。
「そんな事はないと思うけど…」
「本当?君はそう言えるの?」大きな瞳が俺を真正面から見つめる。
「いや、実際に見たことないからわからないけど…」自信なさげに俺は答えた。
「そう…。…じゃあ、今度ちゃんと見てみる?練習。覗きじゃなくて、ちゃんと。近くから」
「…え?」
覗きの片割れ、フリーパスをゲット。
「そんなこと出来るの?だって男子の見学は禁止じゃ?」
「ううん、男子の見学が禁止なんじゃなくて、ニヤニヤしながら笑ったり、ふざけたりするのがダメなの。
そういうのは私も迷惑だし、気も散るわ。かといって、じーっと真面目に覗いてるのも嫌だけど」彼女は笑う。
「だって本来体操は人に見てもらう為の競技でしょ?見学ならいいのよ。
ただ、そういう理由があるから、男子が正式に見学する場合には部員の推薦が要るの。
だから私が前もって伝えておけば大丈夫なの。それとも、迷惑?別に見たくないかな?」
「いや、そんなことは…。見てみたいよ。見たことないし。あ、変な意味じゃなくて」
「ふふっ。わかってるって」
「…でもさ、聞きたいことがあるんだ」
「何?」
「どうして俺を招待してくれるの?あとさ、どうしてあの時、俺を助けてくれたの?
片瀬さんにとっても、覗きは迷惑なんだろう?気が散るし」
「…それは…うーん。別に言ってもいいんだけど、練習見てくれたら教えてあげる」彼女は少し逡巡したあと、そう言った。
「わかった。見学させてもらうよ。」
「そう。じゃあ、明日は?」
「うん。問題ない」
「帰宅部だもんね」彼女はからかうように笑う。でも嫌味な感じは少しもしない。この明るい性格の成せる業なのだろう。
次の日。
「おーい、尚ー。どっか寄ってかねー?この後」HRが終わり友人が声を掛ける。
「いや、今日はちょっと」なんとなく、体操部の練習を見に行くとは言いづらかった。囃し立てられるのがオチだったから。
一緒に行きたいと言い出す奴もいただろう。
俺は体育館に入る。体操部のコーチが寄って来る。
「西野か?」
「はい」
「そうか、邪魔にならないようにな」
「はい」
俺は体育館の隅の目立たないところに座る。なるべく部員達から気付かれないような場所で。
他には数人の女子生徒がいた。男の見学者は今日は俺だけ。なんだか恥ずかしい。
「あ、西野君。来てくれんだ?」練習の休み時間、片瀬が寄って来る。
汗をかいていて、髪が首筋に少し絡んでいる。ほのかに頬が上気していて色っぽい。が、そんな事は言えない。
「うん」
「なんでそんなところにいるの?」
「いや、邪魔にならないようにと…」
「西野君らしいね」小さく笑う。
「どう?」片瀬は俺の隣に腰掛けて水を飲んでいる。白い喉が鳴る。なるべく見ないようにした。
「そうだね…凄いと思った」
「凄い?」
「なんていうか…細くて小さいのに…力強い。しなやかで、柔らかいんだけど、たくましさも感じる。
俺はオリンピックとかでしか見たことないから、専門的なことは解からないんだけど、
入念にストレッチとか準備運動、反復練習をしてたよね?」
「うん」
「そういう、地味な、目立たないけど苦しい基礎訓練をしているから、ああいう凄い動きが出来るんだな、と思った。
実際は、普段の練習はとても地味で、辛そうだ。でも、それを我慢して、本番で披露するから美しく、
綺麗に見えるのかなって思った。
白鳥が、地上からは優雅に泳いでる様に見えるけど水面では一生懸命に水を掻いているような」
俺は始めて演技を見た事で、少し興奮気味に話した。
「……。」片瀬はビックリして俺を見てる。
「? どうかした?」
「なんか意外…」
「何が?」
「あ、ごめん、休憩終わりだ。行かなきゃ。あ〜最後まで見てく?」
「うん」
「じゃあ、終わったら、体育館の外で待ってて」
「あ、う、うん」
(体育館の外で待ってて…。「待ってて…」か。)
なんだか俺達が付き合ってるような言葉だな。…少し照れて、しばらく頭の中で反芻していた。
練習が殆ど終わり、クールダウンのストレッチに入った頃、俺はそっと体育館を出た。外は暗くなり始めていた。
体育館の向かいの花壇に腰掛けて、俺は片瀬を待った。
なんだか無性にドキドキする。少し不思議だ。考えてみれば、どうして俺は片瀬と待ち合わせをしてるのだろう?
覗きの幇助をして、本来弾劾され、学校から厳重注意を頂いてもおかしくない立場なのに。
本来、体育館で体操部の練習を堂々と見ていられる立場の人間ではない。近づくのを禁止されても文句は言えないのに。
何より、片瀬本人にも嫌われて、軽蔑されて当然の事をしてしまっているのに。
それが、どうしても知りたかった。聞きたかった。
他の部員が少しずつ帰っていく。校門の方へ。やがて、体育館の照明が落ちた。
———片瀬だ。俺の胸は何故か騒ぐ。覗きをやっていた時とは違うリズムで心臓が鳴る。
「ごめん、遅くなって。待った?」
「いや、大丈夫」
(ごめん、遅くなって。待った?)くどいようだが、いちいちデートのような言葉に当惑する。心がかき乱される。
「えへへ、シャワーが混んでてさ」
「ああ、そうなんだ」またしても俺はシャワーという言葉にかき乱される。一体どうしてしまったのだろう。
片瀬の身体が側に来るとシャンプーのいい匂いが風に運ばれてくる。眩暈を起こしそうになる。
「じゃあ、いこっか?」
「…え? どこに?」
「あ〜言ってなかった。時間ある?」
「うん。大丈夫だよ」
「帰宅部だから」
「帰宅部だから」
今度は言われる前に言った。結果、ハモった。二人で笑う。…楽しい。俺は照れていたけど、この時間を離したくないと思った。
やがて二人でファーストフードの店に入った。考えてみれば女の子と二人でこんなところに来たのは初めてだ。
というか、これはデート? デートと呼べる代物なのだろうか?いや待て、こんなのはただ、たまたま偶然…
—————取りとめもない思考が頭を交錯する。
「ようやくゆっくり話せるね」片瀬がレモンティーを飲んで言う。
「そうだね」俺は答える。
少し、二人の間に柔らかな空気が流れているのは多分、錯覚ではない。片瀬は少し楽しそうだ。きっと俺はそれ以上に。
改めて彼女を真正面から冷静に見る。照明の充分な室内で。
考えてみれば、面と向かって、二人腰を据えて話し合うのは初めてだ。
俺は常に彼女から目を背けて話していた気がする。愚行のせいで。それのお陰で今こうしているのだが。
今更ながらその美しさに我を忘れそうになる。黒く繊細な、流れるような髪。
普通の女性より鍛えられているのだろうが、
細く華奢な身体。白魚のような指先。
小さな顔、雪のように白い肌。細く整った眉、切れ長で大きな瞳は少しだけ勝気な印象を与える。今は穏やかだが。
細く涼しげで整った鼻梁、小さく形のいい唇は笑うと笑窪ができる。
まだ幼さを多分に残してはいたが、それでも彼女の美しさは際立っていた。
事実、ここに来るまでも、彼女にすれ違う度、振り返る人が何人かいた。
年頃の男子が、禁忌を犯してでも覗きたくなる気持ちもわかる。俺は覗いたんだけれども。
「? どうしたの?」
「ああ、いやなんでもない」…君に見とれていた…なんて思っていても言えない。
「で、さっきの話だけど…」
「あ、その前に、私が話してもいい?」
「え?ああ、うん」
「さっきの西野君の感想ね。ほら、休憩中に聞いたやつ」
「うん…意外だったって…ビックリしてた」
「そう。ビックリした。何ていうか…あんまりお話は上手じゃないのに…言葉が…何て言ったらいいんだろう…
詩的な表現だったって言えばいいのかな? それと、競技の本質を突いていたと思う。初めて見たのに」
彼女は少し身を乗り出していった。
「ね、勉強できる?」
「いや、大して…真ん中くらいだよ」
「じゃあ、得意な教科は?」
「国語…かな。論文とか作文とか…」
「やっぱり!だと思った!」
「え?」
「さっきそう思ったの。ね、いつだったか、賞を貰った事がなかったっけ?全校集会で」
「あ〜こないだのやつだね、確か感想文だった。いや、でも、他にも貰ってた奴いたし、別に…」
「違うの。私文芸部の会報で見たの。ねえ、何について書いたの?」
「えーと、森鴎外だった」
「それ!それよ!私凄く共感したの!」
「そうなの?」
「うん!いや、信じられない!あなたを見た時には気付かなかったんだけど、そうじゃなんじゃいかって昨日思ったの!
ほら、授与式の時に簡単な説明があったじゃない?それで多分あなたの事を記憶してたの」
片瀬は完全に身を乗り出し、顔が俺の顔のすぐそこだ。
こんなに驚いた彼女の顔を見たのは初めてだ。といっても、あとは笑顔と、競技に打ち込む顔しか知らないが。
「よく覚えてたね…」俺はなんだか居たたまれない。面映い。自分のした事をこんなに認めてもらった事はなかった。
勿論、嬉しいんだけど。
「…それで、覗いてた時、助けてくれたの?」
「うーん。それは半分。」
「どういう事?」
「もしかしたら、あの人なのかなっていうのも助けた理由。もうひとつは、なんか違ってた」
「違ってた?」
「うん。覗きは珍しくないの。よく来るし。勿論歓迎はしてないわ。」
「…うん」俺は途端に小さくなる。
「あ、西野君はもういいの。怒ってないし、あなたは悪くないから。友達は…ちょっと酷いけど…」彼女は笑う。
「何て言ったらいいか…覗きってね、悪いと思ってないのよ」
「どういう事?」
「うーん。私も良く見つけて、怒るんだけど、大概が、ヘラヘラして悪びれもなく帰るの。
この人達は本当に自分が悪い事をしている自覚があるの?って思う。あとは…ちょっとオタクっぽい人。
この人達は…なんか怖い。怒ると、なんだか不気味に笑うの。何を考えているのか解からないl怖さがあるの」
「ふーん。で、俺は、どうだったの?」
「どっちでもない感じがした。開き直って悪びれるでもなく、かといって何考えてるのか解からないでもなく。
なんていうかね、本当にバツの悪そうな、申し訳なさそうな顔してた。ふふっ、それに怪我なんてしちゃったドジな人は初めて。
それで、ちょっと同情しちゃったのかもね。ははっ。」
そう言って片瀬は無邪気に笑った。ちょっと馬鹿にされているわけだが、少し照れはしたが、嫌な気持ちはしなかった。
むしろ、俺の行動が元々悪い行為だったとは言え、彼女の笑顔を引き出せたことが少し嬉しかった。
「それはどうも。見逃していただいて…」
「うん。私も逃がしてよかったと思うよ。今こうしているとね」静かに微笑む。彼女も今この時を、楽しいと思ってくれているのか。
「ね、西野君は小説家になるの?」
「え、なんで?」
「だって、文章得意じゃない?国語の成績もいいし、洞察力…っていうか観察力もあると思う」
「買いかぶりすぎだよ。そんな大したものじゃない。ちょっと人より本が好きなだけでさ」
「そうかなぁ…」
「それより、片瀬さんは?体操ずっとやってくの?」
「うーん、多分高校まで…かなぁ…?」
「どうして?それこそ、俺の文章なんかよりずっといけるのに」
「それこそ買い被りだよー。大体ウチはそんなに強い、レベルの高い学校じゃないし…。でも好きだからやってるけどね」
「そうなんだ…でも実力はかなりあるように思えたけど、正直、一番上手かったと思う。見栄えが一番良かった」
「どうして?」
「まず…手足が長いから、同じ技でも他の人よりも凄く見える。大きく見える。例えば、
足を上げるの一つにしても、片瀬さんと他の部員じゃ高さが違う。
何ていったらいいかな。同じ模様でも、孔雀の羽も大きい方が見栄えがいい。迫力がある。…みたいな感じ」
「…ありがとう。ちょっと照れちゃうね」彼女は頬をほのかに染めた。照れた顔も初めて見た。
「でもね、体操ってあんまり大きいとダメなの」
「そうなの?どうして?」
「小さい方が回転とか…バック転とかする時、小回りが効くでしょう?」
「え?」
「…極端な話だけど、2メートルの人が1回転するのと、
1.5メートルの人が回転するの、どっちが早くて、沢山回転できると思う?」
「…あ…」
「確かに大きい人が見栄えするって言うのは解かる。体操以外の、ダンスなんかではそうね。
でもポイント制の体操では、どれだけ何度の高い技を出来るかが問題なの
世界的なトップレベルの女子選手の平均身長は150cm前後。ウチは大して強い部じゃないから色んな背丈の人がいるけど」
「片瀬さんの身長は?」
「166cm。ちょっと大き過ぎるね」
「ああ…ごめん。無責任な事言っちゃったね、俺」
「ううん。あくまで、トップレベルの話だから。仮に私が小さくても、そんなところまではいけないよ」彼女は屈託なく言う。
「でも」
「ん?」
「嬉しかったな、西野君の批評。大きいのは、体操やってる人間としてはあまり嬉しくないんだけど、
そういわれると、嬉しい。本当に」俯きながら言った。さっきとは打って変わって消極的で、声も小さい。
俺は少しでも、彼女を喜ばせる事が出来て嬉しかった。
喜ばそうとしていったつもりではなく、本心から言った事が彼女を喜ばせた事に二重の喜びを感じていた。
「…じゃあ、また明日」
「うん、また明日」
ファーストフード店から出てしばらく歩いた俺達は、別れ道に差し掛かった。名残惜しいが、楽しい時間だった。
「ありがとう、色んな話してくれて。楽しかったよ」微笑みながら、片瀬は言う。
「いや、こっちこそ。嬉しかった。褒めてもらえて」俺はどうにか言葉を繋ぐ。
「じゃあね。気をつけて。お休み」別れの挨拶は俺の口から彼女の耳に。
「…うん。お休みなさい」その答えは彼女の口から俺の耳に。
空を見上げた。気が付けばもう、大分前に夜が始まっていた事を空は俺に伝える。
俺は一人、帰り道、この胸の暖かさについて考え…る前に理解した。脳より先に身体で。
俺の考えは解かった。すべき事も同時に。
(…伝えるんだ…! この気持ちを彼女に。俺が恋した、好きな人に。)
…俺は溜息を風に乗せ、呟いた。
その時は不思議と怖さや不安はなかった。
暗い闇夜の中を、静かに微笑むように照らす今夜の満月の様に、俺の心は満ち、透き通り輝いていた。
翌日。
気持ちは固まったが、きっかけが掴めない。そもそも俺は片瀬といつでも会える訳じゃなかった。
クラスは違うし、彼女には部活動もある。
俺とは帰る時間も違うし、学校で見つけても大概二人とも周りに友達がいる。
友達の中で俺と最も仲がいい秋田という男がいる。明るく、冗談好きで、面倒見のいい、まとめ役のような男だ。
「ああ〜もうじきマラソン大会か〜。嫌だなぁ…」
「そうだな」俺の返事は素っ気無い。
「8㌔だぜ?8㌔。俺達ゃメロスかっつーの。友達人質に取られてんのかっつーの。
俺はかーちゃんの奴隷じゃないっつーの」
「なんで最後だけタケシ?」俺は彼の冗談に笑う。彼は抜群にモテるような美男子ではないが、
生来の明るさと面倒見のよさで友人が多かった。男子にも女子にも。必然、女子の話題にも詳しい。
「そういやさ、お前、昨日片瀬と一緒だったんだって?」
「え?なんで?」———瞬間、胸の奥が冷却した。悪い事したわけでもないのに。
「昨日、体操部の子が見たって。お前らが並んで歩いてるのを。今朝聞いた」
「そ、そうか…」俺は動揺を隠せない。
「でもなんで?お前ら仲良かったの?」秋田は興味を持ったようだ。俺は言葉に困った。
なんでもなければ、他愛のない世間話だと言えた。が、もう今の俺は彼女に惹かれている。
その場をごまかすほどの機転は効かなかった。
「ちょっと、こっちへ…」俺は意を決し、有無を言わさず彼を引っ張った。
「…ちょ、なんだよ。いきなり拉致監禁?まだ心の準備がアタシにだって…」
「やかましい!いいから来い!」男には強引な俺だった。
やがて屋上。授業はサボった。空は青く、日は高かった。少し強めの風が快く頬を撫でては去り、舞い戻ってきた。
俺達は柵に寄りかかり、座りながら話し始めた。
秋田には片瀬との事を黙っていて欲しかった。他の男子や友人に喧伝されたらたまったものではなかった。
話好きな男だが、大事な事には口が堅かった。
約束や頼み事を無下にする様な人物ではなかった。この辺りが、彼の人気の理由でもあった。
「言わないでくれ。頼む」俺は深々と頭を下げた。
「話が見えねぇよ。なんだか困ってて、必死なのはわかるけどさ。とりあえず落ち着いて話してみろ」
「実は…」俺は喋った。包み隠さず喋った。秋田を心底、信頼できる親友だと思っていたから。
「そう…か…」秋田は腕を組んで目を閉じ、時折唸りながら聞いている。
「だからな、彼女に告白する前に、俺の気持ちを彼女に知られてしまうと困るんだよ」
「お前も一応落ちぶれたとは言え、もののふの端くれだから、告白するなら知られるのではなく、自分で言いたいと」
「落ちぶれたもののふの端くれではないが、まぁそうだ」
「でも片瀬は難しいんじゃねー?いやいや、やる気を削ぐ訳じゃないけどさ」
「釣り合ってないのは自覚してる。それを差し置いても…」俺は言葉に詰まる。まだ人に言うのは恥ずかしい。
「惚れていると。好きだと」秋田は補完してくれた。
「…うん」小さく頷く。
「あいつは学校のアイドルみたいなもんだからな。おまけに体操部で容姿端麗、成績も上々で、性格もいいと来た。
南ちゃんみたいなもんだよ」
「そう…だな」
「方や君は、まぁ、見た目はそれほど悪くない。背も高く痩せてるし。
が、特別美男子でもなく、オシャレでもなく、垢抜けない。面白いわけでもなく、人見知りだ。
成績は真ん中くらい。出来るのは国語だけ。スポーツはダメじゃないが、得意でもない。
球技はセンスがない。楽器が出来るわけでもない。蛇足だがケツに大きな痣がある」
「…蛇足はともかく良く知ってるな」彼の指摘は全て的を得ていた。人物評は得意な秋田だった。
「まぁでも、恋愛なんてどう転ぶかわからないよ。世の中の美男美女が皆釣り合った相手と付き合ってるわけじゃないし」
「…詳しいんだな」大人びた彼の発言に感心した。
「いや、昨日テレビで言ってたの」彼は照れくさそうに言った。
「片瀬か…あいつ去年転校してきたんだよな。なんか親の仕事の都合とかで。まだ1年かそこらなのにもう有名人だもんな」
「そうなんだ。全然知らなかった」
「そこなんだよ。お前は何も彼女の事を知らない。俺の方が知ってるんじゃないかってくらい。
片瀬の家、電話番号、家族構成、親の仕事、あいつの趣味、食べ物の好き嫌い、
あいつの友達、彼氏や好きな人のいるいない。どれか一つでも知ってんのか?」
「…顔と名前と部活くらいしか…」改めて彼女の事について、何も知らないことを知る。
「ぶっちゃけると、今彼氏がいるのかどうか」
「ああ〜」俺は全くその事を考えていなかった。
「もしくは、付き合ってなくても、好きな人がいるのか」
「あああ〜」それも考えてなかった。
「もしくはレズなのか」
「ああああ〜!」思いもよらなかった。俺は目の前が暗くなった。
「…最後のはボケだったんだけど。むしろ怒られると思ったんだけどな」
「へ?…あ。」
「…疲弊してますね、西野君」
「…どうもそうみたい…」片瀬の事となると、まともに頭が働かない。
「ともかく、まだ早えー。告白するのは。まず、あいつとの関わりを日常的に持たないと。
舞い上がって突っ走って転ぶ前に、必要な事を知るのが先だ。
彼氏がいるのに告白して、「ごめんなさい」なんてカッコ悪いだろ。
母さんはそんな風にお前を育てたつもりも、育てられたつもりもない」
「最後は意味わかんないけど、そうだな」
始終、冗談を交えながらも、秋田の言うことはもっともだった。
俺は先走るところだった。まずは彼女に接近しなくては。彼女の事をもっと知らなくては。
まずどうにかして彼女と会わなければならない。
それにはやはり、今ある接点を使うのが一番だとは秋田のアドバイス。俺は休み時間、どうにか片瀬をつかまえた。
「あ、西野君、おはよう」片瀬は俺に気付き微笑む。なんだか意識してしまう。
「おはよう。今日も練習?」俺は努めて冷静を装う。
「ん、今日はお休み。軽い自主トレだけするつもりなの」
「あ、そうなんだ」
「どうしたの?」
「いや、また見学させて貰おうと思ったんだ」
「ああ、そうなんだ?そんなに面白かった?」
「うん、面白かったよ」
「そっかー。興味持ってくれたんだね。体操。なんか嬉しいな。ふふっ」笑顔。ずっと見ていたい笑顔。
少し後ろめたい。体操に特別興味を持った訳じゃない。目の前の人に強く惹かれているんだ。
しかし、計画に早くも綻びが見え始めた。見学して一緒に帰り、話をする予定だったのに。
「じゃあ、今日は授業終わったらすぐ帰る?」
「そのつもり。今日は私も帰宅部。一緒だね?」少し嬉しそうに笑う。俺もつられて一緒に笑う。
「あ、そうそう私西野君に聞きたいことあったんだ」
「何?」
「うーん、今はちょっと時間ないから昼休みでいい?」
「うん、いいよ」
「じゃあ、後でね」
「うん。あとで」話とやらも気になったが、彼女と昼休みを過ごせることに小躍りしたい気持ちだった。
誰もいなくなってから俺は小さくこぶしを握り締め、ガッツポーズ。
やがて昼休み。俺は彼女と待ち合わせして合流した。校庭のベンチに二人、腰掛けた。
彼女は小ぶりな弁当箱を空ける。少し子供っぽい、可愛らしいデザインだった。
「あ、昼いつも弁当なんだ?」
「うん。大体そう」
「親が作るの?」
「うーん、自分で作る時と作ってもらう時と半々くらい」
「西野君はいつもパン?」
「うん、昼はあまり食べないんだ」
「いいなぁ、細くて」片瀬が羨ましそうに言う。
「片瀬だって細いじゃん」実際彼女はかなり華奢な方だった。ダイエットが必要な様にはとても見えない。
「そうかなぁ…」そういって彼女は自分の腕や足を見る。俺も彼女の視線につられる。
「…どこ見てるの?」彼女はちょっと照れて言った。
「あ、いや、つい。片瀬の視線につられちゃって…。ごめん」顔が赤くなる。
「…もう、真面目だと思ってたのにエッチなんだね」
「い、いや…そんな事は…たまたま…」
「たまたま見ちゃった?」顔は怒っていない。むしろ少し楽しんでいるかのようだ。
「う、うん」
「あの時も、たまたま覗いちゃった?」
「あ、それは…厳密には…覗いてないんだけど…」しどろもどろになる。
「ふふっ、冗談。面白いなぁ。真面目なんだから」この人は少し、小悪魔的な所がある様だ。
「……それより、話って?」俺は嬲られるのに耐えられず、話を切り替えた。
「ああ、そうそう」切り替えの早い彼女だった
「…ええとね、西野君の文章が見たいの」
「? どういう事?」
「感想文とか、論文とか…日記とか…そういうのでもいいから。自分で書いた小説とかでもいいから」
「小説なんて書いたことないよ…日記はたまに書いてるけど、人に見せるものじゃないし…」
「うーん、じゃあ感想文とかは?」
「見せてもいいけど、感想文はその本を知らないといけないし、知らなかったら読まないといけないし」
「ああそうか〜」彼女はしまったというような顔をした。
「本はよく読むの?」
「ううん、あんまり」彼女は残念そうに呟く。何か、考え事をしているようだ。
「ねえ、聞いてもいい?」
「なに?」
「どうして俺の文章なんて読みたいと思ったの?俺だって別に読書家って程じゃないし、
文学なんて殆ど読まないし、俺よりもっと上手い奴なんて文学部とかに一杯いるよ。
実際文学部に、同い年なのに凄い文章書く人もいるし」
「…でもね、私は西野君の文章を読んでみたいと思ったの。それじゃダメ?」
彼女は少しだけ縋る様な瞳で俺に言った。
彼女との接点を模索していた俺にとってはまたとない話。
大体好きな人にこんな瞳で頼まれて断れるわけがなかった。
しかし、どうすればいいのか。
「いや…俺だって、片瀬に褒めてもらえて嬉しかったし、望むなら見せてあげたい。本当に。
だけど小説なんて書いたこともないし、書いても短編にしてもすぐに出来上がるわけじゃないし。
どうしたらいいかな…。何か方法は…」
俺は考え込む。が、気持ちばかり焦って何も浮かばない。
「そう…。うーん、何かないかなぁ?」片瀬も考える。やがて彼女は、
「そうよ!これがあった!うん、いい事思いついた!凄い!」
まるで世紀の大発見をしたかの様に、飛び上がって喜んだ。興奮している。
大きな瞳がキラキラと輝いて俺を見つめる。
「え?な、何…?」
俺は驚いて少しのけぞる。が、お構いなしに彼女は距離を縮めて言った。
「————交換日記!!!」
「…は?」
…俺の脳は停止した。
「交換日記?」俺は突拍子もない提案に戸惑う。
「そう!ちょっとアイデアが古いけどね」片瀬は笑顔で言う。
「でもそれって…」恋人同士がするものなんじゃ…と言おうとしたけど言えなかった。
「そんな気を遣わなくていいって。昔は友達同士でもやってたみたいだし」
友達と認めてくれるのか。ここで俺は初めて、攻勢に出てみようと思った。
「でもさ、俺と交換日記なんてしてたらさ。怒られないかな?」
「? 誰に?」
「い、いや…片瀬の彼氏…に」俺は勝負に出た。喉の奥で生唾を飲んで彼女の言葉に備えた。
生か死か。極刑か、自由か。大袈裟でなく、判決を待つ罪人のような気持ちだった。
「……」彼女は少し驚いていたが、やがて少し意地悪な顔になって、
「…嫌味ですか?」
「え?」
「怒る人なんていないよ。彼氏なんていないもん。…今まで17年間」彼女は少し寂しそうに、怒ったように言う。
俺は天の采配に感謝した。幸運に涙がこぼれそうになった。
かと言ってまだ、スタート地点にすら立っていないのだが、そんな事はどうでも良かった。
望みが断たれることに比べれば微々たる問題だった。
「え?そ、そうなの?…なんか意外だ」努めて冷静に言った。本心ではあったけど。
「何で?」
「だって…モテそうだ…片瀬は」
「うー」片瀬は何だか迷っている。おそらく、これから言おうとしてることに対してだろう。
「どうしたの?」
「…自分で言うと、ちょっと自慢みたいで嫌なんだけど、あ、これは誰にも言わないでね?」
「うん。約束する」心から。は、思ったが言わなかった。
「その、まぁ何度かそういう事を、言われた事は…あるの」恥ずかしそうに言う。少しも自慢げには言わなかった。
「…告白?」
「…うん。」そりゃあ、そうだろう。それに関しては全く驚かなかった。実に理に適った話だった。
「でも、断ってきたわけだ? 今まで」
「…うん。全部」
「なんで? 皆気に入らなかったの?」
「…そんな事は…ないんだけど…。
カッコいい人も、面白い人も、頭の良い人も、スポーツできる人も、いた。…と思う」
「凄いなぁ」改めて彼女のレベルの高さを知らされる話だ。かぐや姫みたいだ。
「でも…」
「でも?」
「私が…いけないのかもしれない」
「? 理想が高いとか?」
「ちょっと違うと思う。臆病…なのかな…? 私、身体は大きいのに。なんか、怖かった…」
「怖い?」
「ちょっとね、嫌な事があって…。自分と相手に対して自信が持てないんだと思う…」
「嫌な事?」
「それは…ちょっと…」
「?」
「あ、うーん。楽しい話じゃないから、あんまり言いたくないな…」申し訳なさそうに言う。
「あ、いやいいんだ。充分良く話してくれたし」
「そう? あ、西野君は? 彼女」
「いない。いたことない」悲しいかな、即答。
「ごめん、そうじゃないかと思った。奥手っぽい」彼女ははにかんで言う。
「よく言われます…」自嘲気味に答える。
「あ、違うよ。悪い意味じゃないよ。真面目そうって事。それに同じだね。私達。
ふふっ、ちょっと寂しい同士だけど」
「そうだね。でも、無理に付き合わなきゃいけないわけじゃないしね。
あ、俺の方はそんな贅沢いえるような立場じゃないけど」
「ふふっ。でも、真面目なのはいい事だよ」
「ありがとう…でもさ…」
「何?」
「こういう話こそ交換日記ですれば良かったんじゃない?」
「あ、そうか…」
二人で笑う。近く、予鈴の音。
昼休みは終わりを告げたが、俺達の関係は今これから始まろうとしていた。
ともかく俺達は交換日記をする事になった。俺の頼みで、俺達意外に言わないでくれと頼んだ。
片瀬は了承してくれた。私も他の誰かに見せるつもりはなかったと。
二人の秘密。その言葉に俺は喜びを感じていた。
日記は不定期だったのだが、早い時は1日、遅くても3日と空けずに交換していた。
片瀬は部活や家の事、友達の事などごく日常的な話題を、
俺は主に映画や本、たまに友達とのやり取りなどを記した。
あとは二人で学校行事や、共通の知り合い、教師の話などを話題にした。
結果は概ね好評で、片瀬は喜んでくれ、楽しみにしてくれていた。
俺も少なくとも日記の中だけは、彼女の考えや意見を俺だけが知れることが嬉しかった。
何より、彼女が俺だけのために手書きで文章を書いていてくれることが嬉しかった。
彼女の字は外見同様美しく、同年代の女子が書くような女子高生の文字ではなく、綺麗で丁寧な文字だった。
俺は彼女の文字すらも愛しく、その筆跡を指で愛撫するかのように優しくなぞった。
互いの事を知るようになると必然仲も良くなる。俺達はよく二人でいることが多くなった。
俺はそれを人に知られるのは恥ずかしいのだが、彼女は気にしていない。
それは二人の間に横たわる疎隔だった。彼女は俺を友達だと思ってるから、誰に見られても構わない。
俺は彼女を激しく意識しているからそうはいかない。そういう意識のズレはあった。
でも、俺達は友人としては極めて良好な関係を築きつつあった。日記は日増しに文字数が増えていた。
同じ様に日常での会話も増え、砕けた感じになっていった。
「ねぇ、昨日のドラマ見た?」
「あ〜途中までしか。どうなったの?」
「ふふっ、知りたい?」もったいぶって片瀬は言う。いつもの手だ。
「意地悪するなよ〜」
「ああ、喉が渇いたなぁ」わざとらしく芝居がかって言う。
「水道ならそこだよ」
「ジュースが飲みたいなぁ」
「自販機なら下の階だ」
「知りたくないの?」
「友達に教えてもらう。無償の友情を捧げてくれる友に。タダで」
「タダより高い物はないんだよ?」負けじと食い下がる片瀬。彼女は負けず嫌いだった。
「少なくともジュースよりは安い」俺は勝ち誇ったかのように言う。
俺達は良くこんなやり取りをしていた。
…そろそろかな。交換日記を続けて2週間くらい。俺は告白してもいい頃だと思った。
告白しないで、関係を壊さずこのまま友達でいるべきかとも考えたが、
どう考えても片瀬は俺にとっては友達ではなかった。友達の範疇を越えた感情を抱いていたし、
それを伝えずにいることは辛かった。失う可能性があっても、もう一段上に上がりたかった。
なにより、彼女に本心を隠していることが嫌だった。
朝、俺は秋田と二人で登校していた。その途中、俺は意を決して言った。
「俺さ、そろそろ言おうかと思うんだよ」
「告白…か?」
「うん」
「そうか、うん、いいんじゃないか? お前ら最近仲いいし。
まぁ、絶対大丈夫だとは言えないけど、しないで後悔するよりは良いよ」
「うん、そうする」
「当たって砕けて来い。骨は拾ってやる」
「…うん。悪いな。色々助けて貰って」
「…青春だねぇ」秋田は空を見上げて唸る様に言う。
「ホントだな」俺は笑う。
「…頑張れよ」彼は真面目な顔でそう言った。
「ああ」俺は少し笑って答えた。
その日の放課後、俺は片瀬に今日の分の交換日記を渡した。彼女はこれから部活だった。
誰かに見られない様に手渡すのは毎回苦労したが、その苦労も俺には楽しかった。
俺は一人、図書室で時間を潰し、体操部の練習が終わるのを待っていた。
やがて、頃合を見計らって俺は図書室を出て、体育館の近くで彼女の姿を探した。
日が暗くなっていくにつれ、じわじわと緊張の波が訪れた。
「あれ?西野君?どうしたの?」
「待ってた。片瀬の事を」緊張していた俺は掠れた声で言った。
「…どうしたの?なんか変」彼女はおかしそうに言う。
「ちょっといいかな、話があるんだ」
「いいよ、ここでいいの?」
「うーん、ちょっと場所変えようか」そう言って俺は彼女を誘って歩き出す。
途中、片瀬は今日も色々と話してくれた。朗らかな調子で。でも俺は殆ど覚えていない。
曖昧に相槌を打つ事に終始していた。
やがて、川の土手にやってきた。すでに空は暗く、人影もなかった。
いつもそこで草野球や草サッカーをする人達の姿ももうなかった。
「この辺でいいかな」川の土手から舗装されたジョギングコースの方に降りて俺は言った。
「? …うん…」彼女は不思議そうに俺を見る。
見渡すと空が広い。川の周りは景色が開けていて、一面に星空が広がっていた。
俺が空を見上げると彼女もつられて空を見た。
「うわぁ、今日は星が綺麗だねぇ…」彼女は惚けた様に空の美しさに酔う。
「そうだね。でも今、俺は目の前の星だけを見ていたい」
…などと、思ったがこれは流石に言えなかった。
いくらなんでも気障過ぎる。俺なんかが言ったら寒すぎる。
こんな事を思いついてしまう己の思考回路を呪った。
星空を見上げる片瀬がこちらを見ていないのを確認して、俺は自分の頭を軽く小突いた。
俺の脳は多少、混乱していた。これも経験の無さと極度の緊張から来る混乱だった。
こういうセリフはハンフリー・ボガードにでも任せてばいい。俺は俺らしく、伝えればいい。
俺は少し深呼吸をして己を戒めた。落ち着け。逸るな。慌てるな。余計な事は考えるな。
空を見上げる片瀬を呼ぶ。彼女はこっちに視線を移す。
「? どうしたの?」
「あのさ…話があるんだ」上ずる声。震えそうだったが堪えた。
「なに?」
俺は彼女をまっすぐに見据える。片瀬は少し、きょとんとして俺を見ている。
頭の中は空っぽだった。もうこの言葉しか言う必要はなかった。意を決し、口を開いた。
「…好きだ、君の事が」
「……え……」
賽は投げられた。
それはたった今俺の手元を離れ、これから彼女の采配に委ねられる事になった。
どんな目かはまだ解からなかったが確実に、今。賽は投げられた。
「俺と、付き合って欲しい」
「………」
片瀬は驚いた顔のまま、固まっている。俺は少し違和感を感じた。
彼女ほど告白されるのに慣れた人にしては、随分驚いている事に。
もっと冷静な反応が返ってくると思っていたが。
「西野君…、私の事を…好き…なの?」
「うん」即答。きっぱりと。はっきりと。しっかりと。
「本当に? …本気なの?」
「そうだ。本気だ」もう一度即答。
「…あ…」
彼女はまだ固まっている。
「返事を…聞かせて欲しい」ゆっくりと、言った。
「…え? で、でも…私…」
うろたえた彼女も初めて見たな…この期に及んでも俺はそんな事を思った。
「い、いつから、そう思ったの?」
「…あの日、練習を見学して、一緒に帰った日。
片瀬と話して、別れた帰り道で、気付いた。俺は君の事が好きなんだって」
「え? あ、あの時に?」
「そう。それからずっといつ言おうかと思ってた…それが、今日、今だった」
「…そう…なんだ…」
「………」
無限に思えるような、長い沈黙。俯いた彼女の顔が僅かに歪む。なんだか苦しそうだ。
どうしてだろう。なんで彼女は苦しそうなんだろう。
俺のせいなのか。どうして俺は彼女を苦しませなくてはいけないのか。
しかし、苦しいのは俺も同じだった。体中を冷や汗が伝う。かすかに身体は震えていた。
気を抜いたら倒れてしまいそうだった。平衡感覚を失い、大地に立っているという実感がなかった。
ぐっと拳を握り締め、身体に力を入れた。
「私は…私も西野君の事、…良く思ってるよ…」長い沈黙を破ったのは片瀬の方だった。
「…え」
「一緒にいて、楽しいし、優しいし、真面目だし…。…交換日記も、…面白いし…」
一つ一つ区切るように、彼女は言う。
「じゃ、じゃあ…」俺は少し身を乗り出し、先を急いだ。希望が見えた気がする。もしかして…?
また少しの沈黙。…それから。
「———……」彼女は小さな声で、俺から目を逸らしたまま何か呟いた。
「…え?」しかし、その時、強い風が音を立てて俺達や川原の草花を揺らした。
片瀬の声はその風と草木がざわめく音に掻き消され、俺の耳には届かなかった。
俺はそれが告白に対する答えだと本能で理解した。
「…ごめん、聞こえなかった。もう一度言ってくれる?」
彼女は静かに伏せた顔を上げ、逸らしていた視線を俺の瞳に合わせた。
僅かに、その大きな瞳は濡れていた。酷く真剣で、悲愴な表情をしていた。
俺は全く微動だにせず、真正面から彼女の言葉を待った。
そして、もう一度、さっきと同じであろう言葉を俺に告げた。
「———……」
…今度は風も邪魔をしなかった。
小さく、消え入りそうな、その言葉。
しかし、確かにそれは俺に届き、伝わり、聞こえた。彼女の意思を宿す音の波を。
————瞬間。夜空の星も、街の灯りも、時折通り過ぎる車のライトも、
この場に存在するあらゆる光は潰えたのではないかと思った。
ほんのさっきまで、俺は胸の中にあった小さな光さえも。
彼女は確かにこう言った。
—————「ごめんなさい」と。
「……そう、か…」
「………」
重苦しい空気。逃げ出したい衝動に駆られたが、足が動きそうもなかった。
俺は気力だけで立っているような有様だった。
片瀬は俺に背を向け、しゃがみ込んだ。肩を震わせている。嗚咽しているのは容易に理解できた。
「…うん、…わかった」俺は溜息の様に呟いた。
…まぁ…仕方ない。勿論まだ好きではあったが、振られた事で徐々に冷静さを取り戻していた。
「…ごめんね? …ごめんなさい…」
「いや、いいんだ。…片瀬は何も悪くない」
「…う、うぅ…、ごめん…なさい…」
「泣くなよ…。…どっちかというと俺の方が泣きたいんだからさ?」
冗談のつもりで和まそうとしていったのだが、逆効果だった。
「そうだよね? 私が泣くなんておかしいよね…」
しばらく宥めるのに必死だった。
どうして振られた男が振った女を慰めているのか。シュールな構図だった。
「もう…大丈夫?」
「うん…うん」
しばらくなだめ、彼女はやがて落ち着きを取り戻しつつあった。
「でさ、どうしようか?」
「…え?」
「これからの…俺達。…関係っていうか、接し方…って言えばいいのかな」
「あ…」
「片瀬はどうしたい?」限りなく優しい声で聞いた。
「……」彼女は困惑していた。どうしたらいいかわからないといった感じだった。
「俺とはもう、一切関わりたくない?」危惧していた事を聞いてみる。
「……」
片瀬は小さく首を振る。…未練がましいが嬉しかった。
いなくなっても構わないわけではない。その程度には思ってくれていた事が。
「じゃあ、今まで通り…友達でいる?」
「……うん」
「それでいいの? 本当に。きまずくない?」
「…今は…ちょっと、難しいけど…多分大丈夫…と思う」
「そうか。…良かった。そう言って貰えて」俺は安堵した。
「に、西野君は…それで大丈夫なの?」
「ん〜そりゃあ、思う所はあるよ。でも、片瀬が俺の中からいなくなることに比べれば全然いいよ」
「…辛くないの? 私の事…す、好きなのに、友達のままで」
「友達でもいい。それ以上の関係じゃなくても。とりあえず、失う事にならなくてすんで、
どこかホッとしている」
「…うん」
「じゃあ、帰ろうか? もう遅いから」
「うん…」
やがて、わかれ道に差し掛かる。俺達はそれまで一言も会話をしなかった。
流石に語るべき言葉を持たなかった。片瀬の目はまだ赤く腫れていて、
俺が泣かしたのは誰の目にも明白だった。
途中、振り返る人もいたが、なるべく気にしないように努めた。
「じゃあ、また明日」俺は努めていつもの様子で言う。我ながら良く頑張っている。
本当は泣きたかったが、泣き顔の片瀬を見ると、俺まで泣くわけにはいかないような気がしていた。
「…うん、また明日…」
「ちゃんと学校来いよ? あ、それを言われるのは本来俺か」俺は少しおどけていった。
「…うん…ふふっ…」ここで彼女は初めて少し微笑んだ。
今や俺は完全なピエロだったが、そんな事はどうでも良かった。
愛する人の泣き顔を終わらせる為にはなんら惜しまなかった。
「…お休み」
「…うん、…おやすみ…」
片瀬は別れを告げると夜の道に消えた。
俺は心細そうな彼女の背中を見えなくなるまで見つめていた。
(家まで送るって言った方が良かったかな…)
しかし、振られたばかりでそんな提案を申し込めるほど、俺は図太くはなかった。強くはなかった。
そして、一人の帰り道。
さっきまで空元気を張っていた代償だろうか、歩みは重かった。
空を見上げる。何の役にも立たなかった星空の美しさがなんだかとても残酷な物に感じた。
(ロケーションは良かったと思ったんだけどなぁ…。やっぱ、釣り合わないのかな…)
一人反省会をしながら俯いて歩く。家はもう、すぐそこだった。
自分の部屋に入り、何気なく机の上を見る。
交換日記が机の棚にあった。俺は手に取り、何気なく開いてみる。
片瀬の綺麗な文字が目に映る。切なかった。とてつもなく切ない気持ちになった。
自分の腕に水滴が穿たれる。
「……あ…」
そこでで初めて泣いている事に気付いた。自覚してしまうともう止まらなかった。
俺は膝を付き、崩れるように机に寄りかかり、泣いた。みっともない姿だったが関係なかった。
…さっきまで必死で我慢していたんだ。
一番見せたくない人には涙を見せずに済んだんだ。
泣いていた彼女を、最後には笑わせることも出来たんだ。
もういいじゃないか。許してくれ。
誰に言い聞かせるわけでもなく。いや、きっと自分の弱さに言っていたのだろう。
俺はしばらく声を殺して泣いていた。床に涙の染みが出来る。
好きな人に告白して、拒絶される事の辛さ、苦しさ、悲しさを俺はこの日初めて知った。
予想もしない程の痛苦に心は千切れそうになる。
こんな苦しみを抱えてこれから生きていけるのか心配になる。
「…片瀬…」
愛する人の名前を呟いてみる。
…失敗だった。涙の勢いが増すだけだった。
俺はベッドに仰向けに倒れた。
窓から映る空は今はもう、雲に覆われていた。
もう星は見えず、少しの雨が降り始めようとしていた。心模様を代弁しているかのようだった。
(そうだ…それでいい…)
さっきはまるで役に立たなかった空の神様に少しだけ感謝して、俺は濡れた目を閉じた。
翌朝、目は少し腫れていたが目立つほどではなかった。
正直、気は重かったが学校には行かなくては。片瀬にああ言った事だし。
俺は支度を済まし、家を出た。
出来れば今日は誰とも関わらず、穏やかに静かに過ごしたかった。
傷はまだ塞がるどころか、いたずらに刺激を受ければ再び血を流してしまいそうだった。
片瀬にあったらどうしようか。知り合ってから初めて、彼女に会いたくないと思った。
しかし、運命は中途半端に俺たちを引き寄せる。
「……あ…」
通学路、今日は片瀬は一人で登校していた。
「…あ、片瀬…お、おはよう」
「お、おはよう…」
彼女も少し目が赤かった。夕べ、あれだけ泣けば無理もないか。
流した涙の量は俺も負けていないとは思うけれど。
「目が赤いね。寝不足?」俺は解かりきったことを聞く。
「…うん…。夕べ、ちょっと泣いちゃって」
「片瀬を泣かすなんて酷い人がいるもんだね」少しおどけて言う。
「ふふっ…。…ありがとう…」少しは元気になっていたようだ。俺は安堵した。
この調子なら、近い内に元の関係に戻れそうだ。例えそこから進まない関係であったとしても。
とりあえず、今の俺はそれで満足だった。
とりあえずその日は何事もなく無事授業は終わった。が、俺は帰りに秋田につかまった。
「……」彼は黙っているが、誰よりも沈黙の似合わない男だった。
「何か言いたそうだな」
「いや、…聞きたいことはあるけど、今は止めとく」
「どうせ、大体気付いてるんだろう? いいよ。お前の思っている通りだよ」
「そうか…いやすまなかったな」
「いいんだ。お前には世話になったし」
「ゴメンな。お前のお気に入りのボールペン、、踏んづけて壊しちゃって」
「…その事じゃない。それはちゃんと弁償しろ」
相変わらず、秋田は秋田だった。俺は笑った。この明るさが今はありがたい。
彼は全てわかった上で、バカをやってくれているのだ。
ともかく俺は人には比較的恵まれていた。傷心の時、癒してくれる友の存在に感謝した。
きっとすぐに、いつもの日常に帰ることが出来るだろう。俺の胸は少し軽くなった。
しばらくすると、片瀬とも元通りになりつつあった。それでも彼女は時に以前にはない、
微妙な表情をすることはあったが、告白し、胸の内を伝えてしまっている以上、
以前と全く同じ姿でいるのは難しい。それはある程度は仕方のない事と言えた。
しかし、告白を拒絶されても尚、俺の彼女への気持ちは変わらなかった。
徐々に友達の関係が自然な姿に戻って来ても、彼女の事は好きだった。
少しも気持ちが薄れる事はなかった。
「再来週のマラソン大会出るんでしょ?」ある日の昼休み。片瀬は唐突に言った。
「出たくないけど、単位のために…。はぁ、嫌だなぁ。まぁ、適当にダラダラ歩いて」
「ダメだよそんな。出るからには頑張らなきゃ」
「熱血だねぇ。何分、俺文科系だしさ。あくせく身体張る体力部門は片瀬さんに任せるよ」
「ふ〜ん。そお〜。あれ? でも私の方が成績良かったような…?」
「う…」
「ふふっ。頑張るよね? マラソン」
「…なぜそうなる…」
「私は全力で走るよ? 西野君も全力で走るよね? 1位…はあれだけど、入賞目指して」
「人は人。俺は俺。片瀬は片瀬」
「もう! せっかく人が鼓舞してあげてるのに!」
「だって、別に賞金や褒章があるわけじゃないしさ…」
「うー…。じゃあ、どうしたら本気出すの?」
「そうだなぁ。う〜ん…。……デ、やっぱいい」俺は思い付きを言うのを途中で止めた。
「デ? 何? 言って!」こうなると彼女は強い。
「で、……でーと……」尻すぼみな俺の声。
「………」片瀬は少し驚いた顔をした。
「あいや、いいんだ。つい。調子に乗った。悪い」俺は照れくささに目を逸らして言った。
「…いいよ?」
「……え…」
「デートすればいいんでしょ? いいわよ。それで本気出して、あなたが一生懸命走るのなら」
「…マジで?」
「大マジ」
「……やる。断固走る。絶対走る。俄然走る。よーし、燃えて来たーー!!!」
俺は立ち上がって叫んだ。
「……凄いやる気…」彼女は驚いて俺を見た。
「早速特訓する。今日から」淀みなく言う。
「え? で、でも」戸惑う片瀬。
「問答無用。俺は毎日、夕方から川原の土手で走る」
「ほ、ホントにやるの?」
「男に二言はない。俺に火をつけたのは君だ」
「…う、うん…で、どうするの?」
「とりあえず、入賞は確か10位以内か。それを目指す」
「わ、わかった…」
こうして非常に単純かつ、不純なモチベーションを得た俺は夕方一人、川原の土手を走る事になった。
一旦、家に帰り、支度をして夕暮れの空の下を走り、日が暮れる頃に練習は終わる。
片瀬が部活を終え、帰る時間に合わせていたあたり、少なくない打算が存在していた。
事実、彼女は良く帰りがけに姿を現した。
「どう? 調子は」彼女はスポーツドリンクを俺にくれた。
「サンキュー。悪くない。思ったよりもやれそうだ。意外にスタミナはあるほうみたい。
結構イケると思うよ」
俺はドリンクを飲みながら汗を拭く。川辺の風が気持ちよく、身体を冷やす。
「そう。ふふっ、なんかいいね」片瀬は楽しそうに笑う。
「何が?」荒い息を整えながら俺は尋ねる。
「いや、私西野君がこんなに頑張ってる所、初めて見た。結構熱い人なんだね」
「約束があるからな。ニンジンぶら下がってれば、やる気も出るよ」
「じゃあ、楽しみにしてるね。明日の本番」
「ああ。片瀬も。って、そう言えば片瀬はどのくらいを目指してるの?」
「勿論、優勝。女子は5㌔だし」あっさりと野望を口にする。
「陸上部の奴も出るのに?」俺は驚いて聞く。
「だからいいんじゃない」そう言えば片瀬は体育の成績もトップクラスだった。
「勝った方が気持ちいいもん」
「そりゃそうか…。ま、俺は俺なりに頑張るよ。
10位以内でも、学年全体の10%に入らなきゃいけないわけだし」
「でも、陸上部の人も出るでしょ?」
「長距離…って言っても8㌔だけど、大体短距離、中距離の奴が多いからね、ウチの陸上部は。
そんなに強い部じゃないし。
それに去年もそうだけど、必死に走ってる奴なんて運動部でも結構少ないからね。
基本的にウチの学校はのんびりしてるっていうか、あんまやる気のある、熱い人がいないから。
俺でも充分、付け込む隙はあるんじゃないかと。特訓の成果も上々だし」
「頑張ればあながち無茶でもないか、入賞も。厳しい事には変わりないけど」
「そういう事。まぁ見ててよ」俺は少し偉そうに言った。
「じゃ、明日」
「うん、頑張ってね。入賞」
「片瀬も、…優勝目指して」目標が女の子よりも低い俺は少し情けなかったが、彼女は気にも留めないで、
「うん。お互い頑張りましょう」
俺達は握手を交わした。彼女の手は細く、柔らかだった。
しばらく彼女の手の感触を残したまま、夕暮れの中、俺は家に向かった。
…走って。
秋の空は晴天、風もなし。絶好のマラソン日和だった。
しかし、俺の方はコンディションは良くなかった。
夕べ、最後の練習を頑張りすぎたのが良くなかったのだろうか、身体は重かった。
しかし、走れないほどじゃない。なんにせよ、やるしかない。
俺は気合を入れて、家を出た。
今日は朝から、川原に集合だった。教師や役員の生徒が慌しく、準備をしていた。
「あ、おはよう。いよいよだね」しばらくして片瀬がやってきた。体操服から覗く長く白い手足が眩しい。
「おう、任しといて。…って、女子が先だったよね?」
「そう、女子が午前。男子は午後」
「一緒にやればいいのに」
「人が多くなっちゃうからでしょ? 多分。あ、それはそうと、ちゃんと応援してくれる?」
「するよ。優勝目指してるんだろ?」
「まーね。そんなに長距離は得意じゃないけど、やるからには全力でね」
「…そういうとこ、尊敬する。俺には全くないメンタリティーだ」
「褒められてるのか貶されてるのか…」
「いや、褒めてる。がんばれ。応援するから」
「うん!」力強くうなずいて、笑った。
やがて、女子のスタート時刻が近づく。
ぞろぞろと、100人近い女子達がグラウンドのトラックの開始線に並び始める。
400メートルトラックを一周して、土手のランニングコースを2kmと少しを往復し、
最後にもう一度トラックを一周するコースらしい。計5km。
俺は秋田と様子を見ていた。
「片瀬なんだって?」秋田が聞く。
「優勝目指してるらしい」
「え? 嘘だろ? そりゃ無理だよ。いくらあいつでも」
「そうなのか?」
「だって、陸上部の長距離エースの奴もいるんだぞ。
いくら片瀬が運動神経良くても、毎日何kmも走ってる奴には勝てないよ。絶対」
「そう言われて見ればそうだな。なんでそんな大きい事言ったんだろう。片瀬」
俺達の会話をよそに、号砲が青空の下鳴り響く。
一気に駆け出すグループ。静かにその後を追うグループ。
早くも固まって談笑しながらダラダラと走り出すグループ。
片瀬は最初のグループだった。先頭グループに食らいついたまま、
トラックを出、ジョギングコースに向かって行った。
「すごいな。俺なんてあの時点でもうバテてるよ」秋田が驚いた顔で言う。
「うん。速いな…」改めて彼女の凄さの片鱗を見た気がした。
「でも、今からあのペースじゃ後半持たないんじゃないか? 見ろ、先頭グループは…8人か。
片瀬以外は陸上部と、バスケ部しかいないよ。普段から死ぬほど走ってる奴等だ」
「そう…なのか…」俺は片瀬に感心する反面、不安だった。
「な、西野。見に行かないか? 応援しようよ。片瀬を」
「俺もそう思ってた。行こう」
俺達はジョギングコースの方へ駆け出した。
先頭グループは折り返し地点から、トラックの方へ戻ってきた。残り、1kmくらいだろうか。
先頭グループがこっちに向かって走ってくる。ジョギングコースの沿道には他にも男子の姿があった。
皆、仲のいい子、彼女、好きな子、同じクラスの子などを応援しているようだ。
「片瀬は…いた! まだ食らい付いてる。…けど、ちょっと離されてる。辛そうだ…。大丈夫か?」
秋田が焦り気味に言う。現在1位の生徒が他を20メートルほど離し、その後が第二集団。
第二集団は現在4人。片瀬はその集団の最後だった。いや、今はもうグループからやや遅れている。
大健闘と言えるが、顔は辛そうで足の運びも重そうだった。このままではさらに脱落していきそうだ。
一位の生徒が俺達の前を走り過ぎた。数秒後、第2集団も目の前を走る。残りは約700〜800メートル。
一番きつい時間帯かもしれない。
片瀬が俺たちに近づいてきた。
「がんばれ片瀬! ここを踏ん張るんだ!」
俺は気付いたら叫んでいた。片瀬が俺の方を見る。目の前を通り過ぎる。
その瞬間、俺は片瀬と併走した。沿道から。
「いいか、フォームが乱れてる。もっとコンパクトに走るんだ。フォームが乱れるともっと辛くなる。
頑張れ。優勝するんだろ!?」
俺は片瀬と2メートルほど離れて走りながら言った。
片瀬は俺の話を聞いて、力強くうなずいた。言葉で返事できないくらい、息が苦しいのだろう。
やがて、乱れ気味だったフォームも綺麗になっていく。
「そうだ、その調子! そのまま食らいつけ。お前以上にあいつらも苦しいんだ。
ここでちゃんと走ってれば、必ず追いつける。
見ろ。あいつらも顎が上がってきてるし、走り方も雑になってる。
そのまま行ければ勝てるぞ!! 頑張れ!!」俺は走りながら必死に彼女に言った。
やがて、彼女はもう一度強く頷いた後、速度を速めた。その時、片瀬は少し笑った。
そのまま彼女は走った。俺は立ち止まり、その背中を見送った。第二集団との差が縮まる。
————抜いた。信じられなかった。が、第二集団の生徒達は明らかに失速していた。
「…おおお? いけるんじゃない?」秋田がこっちにやって来て言った。
「応援とアドバイスが効いたみたいだ」
「しかし、お前…。熱かったな」
「…しょうがないだろ。お互い健闘を誓ったしな。って、俺ちょっとゴールの方行って来る」
「え? あ、おい…」
俺は秋田を残し、トラックの方まで走った。コース通りに走る選手達と違い、
土手を降りて直線距離を走ればこっちの方が速かった。
片瀬は必死にトップの選手を追い上げた。トラック勝負になった。
割れるような歓声。片瀬の人気もさる事ながら、デッドヒートの行方に皆釘付けだった。
やがて、1位のランナーは勝利の歓声に包まれた。
ゴールして、座り込む片瀬。激しい息をして苦しそうだ。
何人かの人が彼女に駆け寄ったが、片瀬は大丈夫だと言って、その人達から離れ、俺の方に歩いてきた。
まだ息は荒く、心底消耗した表情をしていた。
「…お疲れ。凄かったよ」
「…ありがとう。でも、負けちゃった。最後、追いつけなかった…」彼女は寂しそうに笑う。
「でも2位じゃないか。凄いよ。信じられない。1位は陸上部の子だもん」
「うん。確かに、良くやったとは思う。優勝するなんて言ってたけど、本当は無理じゃないかって思ってた。
でも、自分を奮い立たせたかったし」
「うん。よくやったよ」
「んん〜でも悔しい〜!!! あとちょっとだったんだよ? 20メートルなかったのに!
ああもう〜〜!!」彼女は拳を握り締めて言う。だけど、表情は明るかった。
「本当に負けず嫌いだね…」俺は心から感心する。
「でも、楽しかった。苦しかったけど、自分の力以上のものを出せた。
普段の私だったら、もっと順位は下だった」
「そうか?」
「うん。第二集団から離されそうになった時、ああ、もうダメだってちょっと思った。
でも、その時西野君が…」
「…あ〜」俺は少し恥ずかしくなる。
「一生懸命、応援してくれて、励ましてくれて、
ちゃんと私と前の人の走りを見てて、アドバイスしてくれたから。だから頑張れた」
「いや、どうも…」
「うん。凄く力強くて、嬉しかったよ」
彼女は心底嬉しそうに笑った。輝くような笑み。
俺が今まで見た彼女の表情の中で一番美しく見えた顔だった。
「ありがとう」彼女は丁寧に言って、頭を下げた。
「いや、いいって。…でもこれで、俺も頑張らなくちゃいけなくなったね。益々。
片瀬は限界を超えたんだから」
「うん。頑張って。応援する」
「うん。ありがとう。頑張るよ」俺達は握手をした。
昼休み。これから始まるレースに備え、俺は軽く炭水化物を採っただけで昼は殆ど食べなかった。
事前に教師からあまり食べるなと説明があったが、やる気のない生徒達はいつも通り、
旺盛な食欲を発揮していた。俺の隣にも、弁当をがっつく男が一人。
「よくそんな食えるな。これから8kmも走るってのに」俺は呆れたように秋田に言った。
「へ? 何言ってんの? 俺走んねーよ」
「はぁ?」
「これ食ったら食後の運動。優雅に秋の川原をウォーキング」
「…やっぱりか…」
「お前なんで食べないの? もしかして真面目に走んの?」
「ああ」
「嘘だろ?」
「ホント」
「…マジ?」
「大マジ」
「…どういう風の吹き回しだ? 去年は俺とダラダラ歩いてたじゃんか。それにお前、今日調子悪そうじゃん」
「調子悪くても本気で走る。去年と今年では事情が違うんだ」
「ははぁ…」…気付かれたか。この男は勘が鋭い。
「言わなくていいぞ」俺は会話を拒絶した。
「応援した片瀬美樹ちゃんの頑張りに触発されちゃったりしてるわけだ。もしかして」
意地悪そうな顔で言う。わざわざフルネームとちゃん付けで言う辺りに悪意が感じられる。
「ノーコメント」俺はなおも拒絶。
「愛の力で走るわけだ。愛で地球を救っちゃうわけだ。
生放送中に間に合うように、武道館目指して走っちゃうんだ。黄色いTシャツ着て」
「サライがカラオケで十八番のやつに言われたかないけどな」
「バカ、あれは、名曲中の名曲だぞ!? よし、聞かせてやる。あーあー。ゴホン」
「空き地のリサイタルはいい。そろそろ俺行くから。昼も終わりだ」俺は歩き始めた。
「ちょ、あそこまでヘタじゃねーよ。…って、おーい…」
俺は秋田を置き去りにした。今だけは彼と同じペースでいるわけにはいかない。
そろそろ身体を動かしていた方がいいか。俺は準備運動をする。秋田は友達と喋ってる。
「おーおー。気合入ってますねー」片瀬がやって来て言った。楽しそうだ。
「うん。俺はやる。片瀬もあんなに頑張ったし、俺はやる」
「すごーい。ホントにやる気になってる…」片瀬は呆けた顔で俺を見る。
「前も行ったが、俺に火を付けたのは君だ。ニンジン目指して頑張る」
「ライトマイファイヤーだね」
「随分渋い曲知ってるんだな…。俺もだけど」
俺達は笑った。
いよいよ、スタートの時が迫る。俺は少し興奮していた。アドレナリンが脳に広まっていくのを感じる。
武者震いがしてきた。スポーツにこんなに真剣に取り組もうとしているのは初めてだった。
元来、争い事、勝負事は好まない性質だったが、この時だけは違っていた。
————やってやる。
やがて渇いた号砲。俺達は走り出した。
まずは飛び出さず、様子を見る。無理に先頭集団に合わせる事はない。
俺は例年の10位以内の人間のタイムを事前に調べ、大体把握していた。
全くその通りには行かないだろうが、かといって大きな差があるわけでもない。
人よりもタイム。それを気にして走れ。自分に言い聞かせた。
2km地点、調子は悪くなかった。
体調は優れなかったが特訓の成果だろうか、秋田が茶化す愛とやらの力か。俺は快調なペースだった。
現在は30位前後だろうか、まだ、上位は先にいたが慌てなかった。
今は速くても、どうせ脱落してくる人間がいる。女子のレースでもそうだった。
4km地点、折り返し。流石に疲れてくる。が、まだ特別ペースは落ちていない。
俺は腕時計で確認していた。案の定、勢いに任せて前半飛ばした人達が苦しそうに立ち止まったりしていた。
俺はそんな彼らを追い抜いていった。
今は多分、20位前後。最後の1kmまで、どれだけ縮められるか。俺は自分を引き締めた。
5km地点、足が重い。まだ後3kmもあるというのに。しかし、なんとか頑張ってはいる。
先頭を行くランナーは、まだ肉眼で確認できる。そこから数えて、数え方が間違っていなければ16位か。
しかし、俺も少し失速していた。
俺が追い上げているというより、上位が俺以上に失速し始めているという状況だった。
6km地点、上位に変動はない。
…苦しい。練習でも8kmは走っていたが、こんなには苦しくなかった。
やはりこれが本番の厳しさ、人と競う事の難しさなのか。
———熱い。身体は汗でぐっしょりだった。バケツの水を頭からかぶったかのようだ。
秋とは言え、まだ初秋。残暑の季節の午後の日差しは強く、午前中よりも気温が上がっている。
ジョギングコースの反対側から、向かって歩いている生徒達の姿が見える。談笑しながら笑っている。
——くそ。ヘラヘラしやがって。こっちはこんなに辛い思いして走ってるのに。
八つ当たり。去年の俺も同じだったのに。
「お? 西野か! 頑張れー!」向こうから来る秋田だった。
彼も他の友達とふざけていたが俺を見ると励ました。少なくともその応援は真剣だった。
俺は小さくうなずく。…そうだ。人は人、俺は俺だ。秋田が歩いていても、俺が怒る道理はない。
秋田だって俺みたいな理由があれば真面目に走っていたかもしれない。
俺は他の事に気をとられるのを止め、集中を心がけた。
やがて、10位から15位の俺までの間に変化がおきた。1位から5、6位くらいまでは陸上部をはじめ、
各運動部のエース級の選手達。それには到底適わないし、彼らのタイムやペースも大きく崩れる事はないだろう。
所詮、俺のような付け焼刃とは基礎体力が違う。それは解かっていた。しかも彼らはトップを目指し走っている。
必然、競争も厳しく、勝利への執着心も高い。
しかし、それ以降の10位前後となると話は変わってくる。
彼等も優れた体力を持っているだろうが、トップの選手達には適わない。それは理解している。
しかし、理解しているからこそ、トップを望めない事をわかってくると、モチベーションが下がる。
こんなに苦しい思いをして、本気で走っても俺は10位前後かと。
俺が狙うのはまさにそこ。彼らの心の綻びだった。
他力本願だったが、運動部でもない俺が食い込むにはそれしかなかった。
俺は10位でいい。10位が最大、最高、最良の望みで、10位は俺にとって1位に等しかった。
しかし、今走っている10位前後の彼らはどうか。きっとそうではないだろう。
事実、彼らは先頭集団からかなり遅れ始めた。
苦しい。意識が朦朧とする。しかし、一人つかまえた。…抜き去る。
15位。
辛い。早く終わりたい。でも勝って終わらなきゃいけない。
また一人交わす。
14位。
顎が上がってくる。フォームに綻びが見え始める。くそ。しっかりしろ。ここで負けてどうする。
更に一人を追い越す。俺に抜かされたその彼は、走るのをやめた。
……よし、この辺のランナー達は厭戦気分に蝕まれ始めている。
13位。
あと1.5kmか。ここが苦しい所だ。耐えろ。堪えろ。我慢しろ。
俺の目の前に二人の背中が見える。あと三人。こいつらを抜かせばあと一人だ。
ペースはもう、上げられなかったが、落とす事だけはしないように努めた。
じりじりとその二人に迫る。焦るな。彼らのフォームはバラバラだ。自滅を待て。
…並ぶ。しかし、彼らにペースを上げる余力はなかった。俺以上に疲弊している。…並び、抜いた。
11位。
…あと一人! 現在7km。俺に10位を明け渡す予定の男は30メートルほど前。
もうゴールのトラックが見えている。ここで縮まらなかったら勝てない。
————しかし、差は縮まらない。
彼も疲れていたようだが、俺も限界だった。もう走っているのがやっとだった。
この30メートルの差が永遠に埋まらない溝のように、重たく俺の心にのしかかり、
気持ちを弱気が汚染していった。闘争心は潰えつつあった。
…ダメか…。考えてみれば、この辺りを走っている選手は皆運動部だった。
そういえば、俺の前を行く男はサッカー部のレギュラーだった。名前は知らないが、顔くらいは知っていた。
帰宅部の俺が学校から帰る頃、グラウンドで練習をしている彼の姿を何度か見たことがある。
勝てるわけないじゃないか。毎日走り回ったり、トレーニングをしているような人間に。俺なんかが。
土台、勝てるレースではなかったのだ。むしろここまでですら奇跡的な僥倖と言えるのかも知れない。
大体なんで俺はこんなに苦痛を抱え、必死に走っているのか。走らなくていけないのか。
なんでこんな思いをしなくちゃいけないんだ。そもそも勝負事は好きじゃないのに。
————馬鹿馬鹿しい。
俺は走りながら、俯いた。その直後。
「西野君! 頑張って!下見ちゃダメだよ、顔上げて!!」
「…え…」
「ほら、走って! 入賞するんでしょ!約束でしょ!」
…か…たせ…?
走る俺の斜め前から必死に叫ぶ彼女の姿が見える。
彼女は沿道から声を掛けた。さっき俺がしたのと同じように。
「前の人だって苦しいんだよ!? 諦めちゃダメ!!」
…簡単に言うなよ…。大体俺がどれだけ辛いか、片瀬にはわかって…
————そうか。わかってるんだ。さっきまで走ってたんだから。彼女も。
しかも彼女は俺よりもっと前を走ってたんだ。優勝を狙っていたんだから。もっと辛かったかもしれない。
あの時の俺は必死に彼女を応援した。心から。今の彼女も同じ気持ちだろうか。
「フォーム崩れてるよ? しっかりして!ここで挫けちゃダメ! あと一人だよ!?」
片瀬は叫ぶ。悲痛な表情。今の俺ほどじゃないだろうが。
片瀬が見ている。応援している。支えてくれる。
それは何よりも心強い事だった。彼女の前で、だらしない姿は見せたくない。
しかも、自分がやると豪語したのだ。その目の前で諦めるわけにはいかない。
俺は必死に自分を奮い立たせた。もう少しだけもってくれ。自分の身体に念じた。
30メートルの差は未だ縮まらない。
…なら詰めるしかない。俺は限界に挑んだ。ここでペースを上げるのは不可能に思えた。
片瀬が見ていなければ。
前を走るサッカー部の彼は俺の存在に気付いている。何度か後ろを振り返っていた。
現在10位の彼は入賞を意識しているだろう。今までとは違う、表彰の掛かった戦い。
彼は名誉を、俺はデートを賭けて走っている。
何だかわからないが、俺の方がいい物を賭けて走っているという根拠のない自信があった。
徐々に差が詰まっていく。この場合は追う方が有利だ。
逃げる者と追う者、王者と挑戦者、ライオンとシマウマ、警察と泥棒の心理。
——捕まえてやる。
彼我の距離は20メートル。彼の走りに明らかな焦燥が窺える。
(そうだ、焦るんだ)彼は何度も振り返るようになり、俺は駆け引きに出た。
本当は口から心臓が飛び出そうなほど疲弊しきっていたが、敢えて涼しい顔をして淡々と走った。
そしてそのまま距離を詰めていく。更にペースを上げた。
10メートルまで詰めた。そこで一旦ペースを落とし、その距離のまま走る。
彼は詰められるのを嫌ってペースを上げる。
…かかった。また20メートル程距離は開くが、予想通りの展開だった。
そのまま開いた距離を詰めずに平然と走る。
やがて彼の走りに変調が訪れる。ペースが乱れる。失速と加速を繰り返すようになる。
…限界だな。俺は距離を詰める。…並んだ。彼の顔に恐れの表情が浮かぶ。
俺は一瞥しただけで、気にしない振りをする。
賭けだった。普通にやっていては勝てなかった。駆け引きは裏目に出れば自分が疲労するだけだった。
彼に余力があったら成功しなっただろう。一か八の綱渡りだった。彼は限界だったようだ。
並んだ。もうそれでいい。彼に更にペースを上げる力はない。
事実、彼は失速し始めた。俺は遂に目標の順位に到達した。残りは僅かな距離とトラックを一周するだけ。
後ろを振り返る。が、後続のランナーが気になったわけじゃない。
沿道の彼女を探した。何か叫んでいる。大袈裟に飛び上がって喜んで手を振っている。
俺がサッカー部の彼を抜かした瞬間も見ていたようだ。
(子供っぽい所があるんだな…)
うれしかったけれど、少し可笑しかった。誇らしい気持ちだった。かっこいい所を見せられたかな。
再び前を見据え走る。さっきまで争っていた彼はもうかなり離されていた。まず追いつかれる事はないだろう。
俺は勝利を確信した。
———刹那。身体が重くなる。忘れていた疲労が鉛のように圧し掛かる。
思い出したように初秋の太陽と汗に不快感を覚える。
どうした、俺の身体? あと少しなんだ、もってくれ。…頼む!
しかし、歩は進まない。ペースが落ち、フォームが乱れる。
さっきの無理がたたったのか、駆け引きの時に無理にペースを上げたのが。
これじゃ本末転倒じゃないか、ミイラ取りがミイラになるなんて…!
視界がぼやける。動悸が激しい。体中の細胞と組織が休息を求めているかのようだった。
「…う」
俺は口に手を当てた。おかしい、気分が悪い。走っている時に感じる苦しさとは種類が違っていた。
俺の走りはよろけ始めた。アスファルトのコースから逸れ、雑草の茂る芝生の方にずれていった。
やがて、走れなくなった。腹痛がする。横っ腹が痛い。俺は膝を付き、芝生の上に力なく崩れるように倒れた。
さっきまで競っていたサッカー部の彼が、俺の事を見下ろしながら走り去っていった。
「…あ…待て…」
俺は呻くように彼の後ろ姿に手を伸ばす。
が、腕は望む高さまで上がらず、力なく地面の雑草を掻くだけだった。
彼の姿が遠くなる。続いて後続のランナー達が俺の横を走り去る。
皆、一様に俺の姿を見下ろしていた。憐憫と同情の入り混じるような複雑な表情。
しかし、誰も手を差し伸べる事はない。当たり前だが。
———絶望。奈落の底に叩き落された咎人の様に。
もう二度と這い上がる事は出来ない所まで堕ちたと知った時、人はこんな気持ちになるのだろうか。
時は、俺だけを置き去りにして無情に流れていった。
目の前が暗い。青臭い草と土の匂いがする。
「はっ、…はっ…うぅ…」呼吸が不規則になる。酸素を体中が求めているが足りない。
意識が遠のく。大地がぐにゃりと歪んでいる。
遠くから足音が聞こえる。何故かランナーの足音とは違って俺に駆け寄るような足音。
「西野君!? ど、どうしたの!? 大丈夫!?」
(ああ、片瀬か…。倒れてた所も見てたのか…。…くそ。情けない。
見ないでくれ、こんな無様で惨めな姿を…。…お願いだ…!)
俺は心の中で念じた。
悔しさに歯を食いしばる。が、口に力が入らない。口の中はカラカラに渇いていた。
目を開けていられなくなってきた。暗い闇が優しく俺を手招きして誘っているようだった。
音と色と匂いの感覚が遠く、薄くなる。何も聞こえない、何も見えない。
どこかに堕ちていくようでもあり、昇っていくようでもある不思議な感じ。
目の前は黒く、頭の中は白かった。
(片瀬…応援してくれたのに…ごめん…)
最後に意識したのはそれだった。
…やがて、俺は気を失った
「…ぅ…う…?」
天井が見える。見たことのない、茜色の天井。蛍光灯は消えていた。夕方である事は理解できた。
「…気が付いた?」
「…あ、れ…?」白衣を着た女性がそこにいた。中年の、物腰の穏やかな人だった。
「…えーと…」俺は状況がよく理解出来てない。
「落ち着いて。そのままでいいから聞いて」優しく諭すように言う。
「…はい」俺は従った。
「気分はどう? 気持ち悪いとか、苦しいとか」
「…特には…ないです」
「そう? じゃあ、私の手を握ってみて」
「…はい」俺は出された手を握る。
「少し力を入れてみて」
「はい」その手は暖かかった。言われた通り、少し力を入れてみる。
「…うん。じゃ、起き上がれる?」
「…はい、…よっ…と」俺は上半身を起こす。
「どうやら大丈夫そうね。ああ、順序が逆になっちゃったわね。
あなた、倒れたのよ。マラソン大会の途中に気を失って」
「ああ…そう…だ…」思い出した。
「で、学校の先生の車でこの病院に連れて来たんだけど、今は夕方。ずっと寝てたの」
「…病院…」ようやく事態が飲み込めた。
「じゃあ、ついでに2、3質問するわね?」
「はい」
名前や住所、生年月日などを聞かれ、答えた。医師の先生は書類に目を通し、確認している。
「ちょっと前から練習してたみたいだけど、昨日も走ったの?」
「はい」
「どのくらい?」
「10km…くらい」
「普段運動は? 部活とか」
「いえ…やってないです」
「昨日の夜は良く眠れた?」
「あまり…」
「今日、走る前の体調は?」
「あまり、良くなかったです」自分で答えていて恥ずかしくなってきた。
こんな状態で無理すれば倒れるのも無理ないか。
「私や、他の人達が何が言いたいか解かる?」
「…はい。すいません…」
「…まぁ、どうやら大丈夫そうね。疲労と酸欠と軽い脱水症状で倒れたのよ。
調子の悪い所に無理が重なって。でも、もう大丈夫だから安心して。
病気とかじゃないから。まぁ、今は大人しくしてなきゃダメだけど」
「はい」
それから簡単な検診を受けた。血圧や脈も測った。いずれも正常だった。
「じゃあ、今日は大事をとってここに泊まっていく? どうする? どちらでもいいわよ」
「あ…、か、帰ります」
「そう? まぁその辺は親御さんとも相談しなさい。
あと、友達も来てるみたいだけど、さわいじゃダメよ?」
「はい…」友達…。誰だろう。
「じゃあ、私は行くけど、もう友達や親御さんに会っても大丈夫?」
「はい」
「じゃあ、呼んで来るわね」そう言って先生は病室を出て行った。
一人になり、がらんとした病室を見つめる。一人部屋のようだ。なんだか湿っぽいところだった。
やがてその後、母親と、担任、校長が部屋に入ってきて、俺を気遣った。
俺はなんともない、帰ると言ったが、皆今日は泊まれと言う。仕方ないので言う通りにした。
明日は学校に行くと言った。身体は少し痛かったが、怪我もなかった。
とりあえず、俺は全員に迷惑かけたことを詫びた。
3人はとりあえず俺が大丈夫な事に安堵し、俺の謝罪に納得し、部屋を出た。
母親は俺の着替えやら制服や鞄を取りに戻った。思ったよりも大事になってしまっていたようだ。
やがて、ドアをノックする音。
「はい、どうぞ」
「ああ! 手術は成功だったんだね、一郎兄さん! 僕の事、思い出した!?」
「…そんな弟がいた覚えは一切ない。大体笑えないぞ、事と次第によっちゃ」
秋田だった。まったくこいつは。俺は笑った。
「まぁまぁ、でもビックリしたぞー? いきなり倒れるんだもん」
「……」
「なんかさ、人が何人かいてさ、その後教師が来て、お前を車に乗せてった」
「そうなのか…」
「そういや片瀬もいたな。俺が駆け寄った時はもう何人かいたけど、片瀬が最初に駆け寄ってたみたいだよ。
「なんつーか、初めて見たな、あんな片瀬。凄いうろたえてた」
「そう…か…」何だか申し訳ない。自分で走るって言っといて、心配させてしまって。
「あ、忘れてた。ちょっと待ってろ」
「?」
「へへっ…いいから待ってろって。すぐ戻ってくるから」ニヤついて部屋を出て行った。
しばらくしてドアが開く。ノックもしないで開けるあたり、秋田が帰ってきたのだろう。
が、その後ろ。
「片瀬?」秋田の後に、俯いておずおずと彼女が入ってくる。
「へへ、俺達一旦家に帰ってから病院で待ってたんだよ。お前の目覚めを」
「あ、そうか…」言われてみれば二人とも私服だった。俺は体操着だったけど。
「……」片瀬は俯いて立っている。目を逸らし、どうしていいか解からないといった様子だった。
「……」俺も何を何て言ったらいいのか解からない。沈黙。
「あ〜、じゃあ、俺行くから」秋田が言う。
「え? もう帰るのか?」
「いや、用を思い出して」
「用?」
「そろばんのお稽古行かなきゃ」
「やってねーじゃん」
「あ、間違えた。バレエのレッスンだ」
「嘘にも程がある」
「プリマドンナ目指す事になったんだよ。家の都合で今日から」
「どんな家だ。それにお前んちスーパーじゃん」
「世を忍ぶための、表の顔はな」
「…もういい。好きにしろ」おそらく俺と片瀬の間にある事情を察して気を利かせているのだろう。
「悪いな。まぁ、二人で仲良くな。じゃあね、片瀬」
「…あ、う、うん」彼女は名前を呼ばれてようやく喋った。
「じゃあな。明日は俺学校行くから」
俺は秋田に言った。暗に、健康だから心配するなと言う意味を含ませたつもりだった。
「ああ。…おっと、お大事に」どうやら伝わったようだ。
「どーも」秋田は出て行った。
そして静寂。片瀬はまだ俯いて立ちつくしている。
「と、とりあえず座りなよ」俺はベッドの脇にある椅子を勧める。
「あ…うん」片瀬はそれに座った。
俺はベッドに座って彼女を見詰めた。いつもの覇気が全くない。
萎れた花のように身体に芯が通っていなかった。
やがて。
「…ゴメン…ね…」
「…え?」何故謝るのか解からない。
「私のせいで、西野君、倒れちゃって…。さっき秋田君から聞いた。今日、調子悪かったって…」
「あのバカ、余計な事を…。いや、それは…」否定しようとしたが、
「ううん。私が、無理に走らせた。元々、興味なかったのに全力でやらなきゃダメだよなんて。
デート…するなんて言って無理やりやる気出させて。
自分がちょっと頑張れたからって西野君にまで全力出させて。今日、本当は調子悪かったのに…」
今にも泣き出しそうな彼女。
「私、自分の事しか考えてなかった。西野君が頑張って、走って、全力出して…。
そんなの、人に言われて頑張ることじゃなかったのに…!
それで、こんなことになっちゃって、失神までさせちゃって」
遂に涙が零れ落ちた。嗚咽する。どうして俺は彼女を泣かせてしまうんだろう。
そんなつもりはさらさらないし、いつも幸せでいて欲しいと、心から望んでいるのに。胸が痛んだ。
「…違うよ。片瀬は悪くない」
「でも…!」
「いいから、ちょっと話を聞いてくれないか?」優しく問いかける。
「……」無言でうなづく。俺は続けた。
「まぁ、きっかけを作ったのは片瀬だよ。俺に本気で走って、って言ったのも片瀬。
それは間違いない」
「…うん…」彼女はすまなさそうに頷く。見てるこっちの方が悲しくなるくらい痛々しい。
「でもさ、走ったのは俺じゃん」
「……」
「片瀬の話に乗って、デートを見返りにして、特訓して、本番に臨んで、本気で走って倒れたのも俺」
「でも、それでも、私があの時応援しなければ、倒れるまで無理する事はなかったかもしれないし…」
「違うよ」
「え…?」
「俺な、あの時凄く嬉しかった」
「……」
「結果的に倒れて、まぁ、リタイアっていうかっこ悪い結果だったけど、
多分、本調子の時だったらあのまま10位でゴールできてた。
あの応援のお陰で、一時的にでもあのサッカー部の奴を抜けたんだよ。
片瀬の励ましがなかったら、無事ゴールしてたかもしれないけど、10位は無理だった。
彼は抜けなかった。絶対に。
今日は、俺の失敗。敗因は体調悪いのに無理したから。でも、片瀬の応援は間違ってなかった。
だって、限界だと思ったもん、あの時。でもそこから更に一歩、前に進めた。
結果だけ見れば俺は失格だけど、無意味じゃなかった。自分でも驚いたよ。
応援がこんなに心強い物なのかって」
「……」
「な? わかったらもう自分を責めるなよ。それに、俺はもうなんともないんだからさ」
「……」
「どうしたの?」俺は黙り込んでいる片瀬に聞いた。
「…かっこ悪くなんかないよ…」
「…え…」
「凄く、かっこ良かった。実際、厳しいんじゃないかって思ったけど、
サッカー部の人を抜いた時は信じられなかった。本当に興奮したし、嬉しかった。飛び跳ねて喜んじゃった」
「ああ、あれ。…ふふ、見てたよ」俺は笑って言った。
「でもね、誰の応援でも良かったわけじゃない」
「え?」
「片瀬の応援だったから。絶対抜いてやろうって思ったよ。あの時。
片瀬もさ、俺の応援でスパートしたじゃない? それで勇気付けられたって言ってたし、
それに応えなきゃってのもあったけど、それ以上に…」
「それ以上に? 何?」
「あー…その…片瀬だったから、かっこいい所を見せたいとか、見てる前では諦められないとか、
思ったわけですよ…。僕は」照れながら言った。
「あ…」赤くなる彼女。
「ああ、ごめん、変な事言って…また困らせちゃうよな、こんな話」
彼女は沈黙して顔を伏せた。何かを思案しているようだったが、やがて意を決したように、
「あ、…西野君…?」
「何?」
「あのね、…聞いて欲しい事があるの」
「? いいよ?」
「…前に、その、何人かの人が私に告白してきたけど、全部断ったっていう話、覚えてる?」
「ああ、覚えてるよ」俺も断られたけど。とは言えなかった。
「前にも言ったけど、断った人の中には良さそうな人もいたの。真面目そうな」
「…うん」
でもね、何人かの人は、私に断られてからすぐ他の人にも告白して、付き合ってたの」
「ああ。そうなんだ…」
「私、思ったの。あの人達は、本当に私の事を好きだったのかって。
どうして、そんなすぐに他の人を好きになって、付き合えるんだろうって。
そんなに簡単に好きって気持ちは変わっちゃうのかなって、思うの」
「…うん」
「それで、怖くなったの。真面目そうな人もいたけど、この人もそうなんじゃないかって。
ここでOKして付き合っても、この人もすぐ心変わりしてしまうんじゃないかって。
それで、私は断るようにしたの。全部。…怖かったから。気持ちが変わってしまうのが。
本当に、本当にね? 本当に好きなんだったら、そんなに簡単に気持ちは変わらないんだよ。
減ったり、薄れたりする事はあるかもしれないけれど、
すぐにパッと点いたり消えたりするものじゃないんだよ。本当に…愛しているなら。真剣なら。
家族の愛情や、友情だってそうでしょ? ちょっと嫌な事があったり、喧嘩したりしても、
仲直りしようと努力したりするし、いきなり絶交や、勘当したり、家出したりしないでしょう?」
「…うん。そうだね」
「なのに、相手に拒絶されたからって、告白したその舌の根も乾かない内に、
すぐに他の人の所へ行っちゃうなんておかしいよ。私は好きな人に断られてもそんなにすぐに忘れられない。
それは性格の違いかもしれないけど、好きな人に拒絶されたら普通は落ち込むよ。しばらくは」
「…ちょっと、いい?」
「何?」
「その、片瀬に告白した人って、すぐに他の人と付き合ってたんでしょ?」
「うん」
「告白してからどのくらいで、他の人と付き合ってたの?」
「…3日、経つかたたないか…くらいだったと思う」
「そりゃ…凄い」フットワークのいい奴もいるもんだ、世の中には。
「その人を見て、他の人のも断るようになった?」
「…うん。ちょうど、1年前くらいかな。私がこの学校に転校してきてすぐくらい」
「なるほど。大体解かった」
「え?」
「多分、そいつは外見に惚れたんだな。片瀬の。いや、惚れたというか、気に入っただけというか」
「どういう事?」
「そいつと面識あった? クラスが一緒だったとか」
「ううん。知らない人だった」
「やっぱりか…。いや、多分、推測だけど、
可愛い子がいたからとりあえずモノにしてみたかったんじゃないかな。
だって、転校してきてすぐで、しかも片瀬とろくに面識もないのにいきなり好きだって、
そりゃ外見しか見てないよ。きっと」
「やっぱり、そう思う? あ、いや、私が可愛いとかじゃなくて…」
「ははっ、謙遜するなって。実際可愛いんだから」
「うう…あ、ありがとう…」泣きながら照れてお礼を言う彼女。可愛い人だと思った。改めて。
「どうも。でだ、それでそいつの事は断ったのはどうして?」
「え…だって、良く知らないし。いきなり言われても困るし、
とりあえず付き合ってみればいいじゃん、って言ってたけど、そんなに簡単な事には思えなかったから…」
「…聞けば聞くほどどうしようもない奴だな。…だんだん腹立ってきた」
「そ、そう?」
「そうだよ。だってさ、さっきの片瀬の話の続きだけどさ、君の言うとおりだよ。
そんなに簡単に点いたり消えたりしないんだよ。気持ちは電球じゃないんだから。
本当に真剣なら。俺だって、片瀬に断られたけど、しばらく辛かったもん。立ち直るの結構時間掛かったし」
「…ごめんなさい…」
「あーいや、謝らなくていい。だってそれはしょうがないじゃん」
「……」
「でもね、断られたからってさ、いきなりなくなったりしないよ。現に今だって…あ…」
「今だって?」
「…あ、いや、いい」照れくさくなった。
「言って?」
「だって、今更言った所で…さ…」
「それでもいいから。…お願い…」
「う。わ、わかったよ…」俺は逸らしていた視線を彼女に合わせ、
「…今だって…す、好きだしさ…」
「……本当に?」
「ああ、当たり前だ。大体デートして欲しかったからあんなに走ったんじゃないか。特訓までして」
「…あ…、そ、そうだよね」
「おいおい、忘れてもらっちゃ困るぞ? あれがなきゃ、こんなに頑張らなかった。
たとえば、他の人が頑張ればデートしてくれるって言われてもやる気にはならなかったよ」
「そう?」
「そう。まぁ、最後の方はデートがどうだとか、そんな事忘れてたけどね。片瀬との約束を果たしたい。
片瀬が頑張ったから俺も頑張りたい。なんとか片瀬の前でかっこいい所を見せたい。
情けない所は見せたくない。それだけしか考えてなかったよ。
まぁ…結果は非常に無様でしたが…」俺は自虐気味に笑って言った。
「…そんな事ない…」
「え?」
「そんな事ないよ! かっこよかったもん。倒れてまで真剣に、倒れるくらい必死にに頑張ったんだもん。
私なんかのために、無理してまで…」
「……」
「今までだって、西野君の気持ちを嘘だと思っていたわけじゃないよ?
でもね、私、怖かった。この人も、真面目な人だけど、
結局あの人達みたいにすぐ変わってしまうんじゃないかって。
その時だけの、ちょっといいなって思ったくらいの気持ちで言ってるんじゃないかって…。
どうしても確信が持てなかった…西野君はその人達とは違うのに…」
「……」
「でも、今、今日の事があって、ああ、やっぱりこの人は本気だったって。
嘘じゃなかったって。こんなに私なんかのために頑張って走って、倒れるまで…必死に…うぅ…。
でも、私は試しちゃった。西野君の事を本気で信じてなかった。
だから、マラソン大会で本気で走って、なんて言っちゃった…」
さっきよりも勢いを増した涙が白い頬をを伝う。でも、今は慰める時じゃないと判断した。
彼女の話を聞かなくてはいけない時だと。
「う…デ、デートとか、そういう事を言ってくるかもって…何となく思ってた。
それで、練習して、頑張ってる西野君を見てるのが楽しかった。う、嬉しかったの…。
ああ、私のために頑張ってる。本気なんだなって、いい気分になってた…。
でも、そのせいで西野君が…倒れちゃって…私、どうしようって思った。
私の勝手な気持ちのせいで、もし、大変な事になったらどうしようって。
告白を断って、傷つけて、落ち込ませて、今度は体調悪いのに必死に走らせて、最後には失神させちゃって、
なにかあったらどうしようって…。私、なんて酷い事ばかりしてるんだろうって…。それで…う…うぅ…」
「……」
「…ゴメンね…。こんな人間なの、私。ホントはね、西野君に好かれるような子じゃないんだよ?
嫌になったでしょ?」
「…今は?」
「……え?」
「…今は、信じてくれるんだろう? 俺の気持ちを」
「……え? あ、う、うん…信じる。ホントだよ?」
「じゃあ、こっち向いて?」
「あ、え?」そう言って、俺は彼女の方に向き直り、彼女の方を両手で掴んでこっちを向かせた。
「…あ…」彼女は驚いて、俺を見る。泣き腫らした目。それでも彼女は綺麗だった。
むしろ、涙がさらに彼女の美しさを引き立てているように思えた。
「俺、君の事が好きだよ。今でも、変わらず。いや、あの時よりもっと。ずっと」
「…え?」見開かれる彼女の瞳。
「俺と、付き合って欲しい」あの時とは違い、今度は穏やかな、落ち着いた気持ちだった。
「ええ? だ、だって、嫌になったでしょう? 嫌いになったでしょう? 私の事…」
「誰がそんなこと言ったの?」俺は笑って言った。
「だ、だって、私西野君を試すような事したし、
前に告白して貰った時だって、西野君の事信じてなかったんだよ?」
「今は信じてるんだろう?」
「そう…だけど、だってあんなに走らせちゃって、倒れるまで、病院に運ばれるほど。
そ、それに…」
「それに、何?」
「えーと、…えーと…」
「…どうにかして否定材料を探そうとするなって。卑下しないの。自分を」笑って言う。
「私なんかでもいいの?」
「あのな、試すような真似は確かに良くないが、仕方ないだろう?
そんな事情があったなら。そんな事を何回か経験してりゃ、疑い深くなるのも仕方ないじゃん。
でもそれで、疑われて嫌だと思う人もいるかもしれない。
けど、本当に好きだったら相手の事を許してあげられるはずだ。多少の事は。
片瀬は好きな人の事でも何も許してあげられないの?」
「……」強く首を振る彼女。
「…で?」
「…え?」
「…どうですか? 僕は。ダメですか?」
「……う、嘘じゃないよね?」
「片瀬がそう思ったんだろ?」
「う、うん」
「じゃあ、片瀬が決めるんだ。自分の意思で。俺という人間を判断した上で」
「…ええと…」少しの沈黙。
「わ、私、…今まで誰とも付き合ったことないから、迷惑かけちゃうかも知れないよ?」
「俺もだからお互い様だ」
「あ…そうか…」
「うーむ、まだるっこしいな…。焦れてきた。よし、最後な。もう一回だけ言う。
それに答えてくれ。それに片瀬が答えなかったらこの話はナシな?」
俺は強気に出た。このままじゃ話が進みそうにないから。
それに何故か、強い確信があった。今度は大丈夫だと思えるような。
「ええ…? ちょ、ちょっと待って…」
「だーめ。イエスかノーで返事して。沈黙はノーな?」
「で、でも…」
「問答無用。では最後。…行きます」
「ああ…」うろたえる彼女。オロオロしている。それも可愛い。俺は少し意地悪かもしれない。
「好きだ。俺と付き合ってくれ」
「……」
「3・2・1…」カウントする俺。
やがて彼女は、
「……ぃ…」
「…聞こえない、やり直し。…俺と付き合ってくれ」
「…は、は…い…」
「…イエスだね?」
「…う、うん」
「いいんだな?」
「…は、はい」
「片瀬さんは俺の彼女、俺は片瀬さんの彼氏って事になりますが、いいですね?」
「……いい…です…」
「じゃあ、片瀬からも改めて俺にお願いして貰えない?」
「…え?」
「出来るだろう? 付き合うんだから」なんだか片瀬を苛めたくなる。こんなにしおらしい子だったのか。
「あ…うん。えーと、…至らない所もある…ありますが、わ、私の事を…宜しくお願いします…」
そう言って彼女は膝の上に手を付き、深々と俺に頭を下げた。
「ぷっ…あははははは!」
「え? ど、どうしたの?」
「いや、凄い古風だね、いつの時代の人かと思ったよ。あははは。
ふつつかものですが、ってやつだな。あはは」
「ああ…うう…、ひ、ひどいよぅ…」恨めしげに俺を見る俺の彼女。
「ごめんごめん。いや、でも良かった、うん。ようやく…だな」
「…うん」
「そう言えば聞いていい?」
「え? な、なに?」
「片瀬はOKしてくれたけど、俺のこと好きなの?」
「あ……う、うん…」
「本当に?」
「ほ、本当…です」何故か敬語な俺の彼女。
「いつからさ?」
「え、あ…。…ほ、本当は…」モジモジしながら言う。
「うん」
「前に告白してくれた時には、もう…好きだった…と思う…」
恥ずかしさに耐えられなくなったのか、言い切った後は下を向いてしまった。
「…そういう事か…」
「え?」
「いや、わかったよ。なんであの時、君が泣いてたのか。好きだけど、信じるのが怖くて、
自信がなかった。だから断らざるを得なかった。本心ではOKだったけど。
で、本気かどうか確かめたくて、マラソン大会の話を持ち掛けて、確認したかった。
断られても尚、好きでいてくれるかも知りたかった。って、事でしょ?」
「…うん。…全部その通り…」
「遠回り…したな。俺達」
「…うん…。ごめんなさい…」
「いや、もういい。願いは叶ったから。もういい。今が、これからが大事。
それに、思えば前のことも無駄じゃなかった…と思う。
前に断られた事が今、受け入れて貰えた事に繋がってるんだと思う。そう思わない?」
「うん…思う」
「あのね? ひとつだけいい?」彼女は小さな声で言う。
「何?」
「その、お願いなんだけど…」
「いいよ。言ってみ」
「嘘…つかないで欲しいな。私が、言うのもなんだけど…。
やっぱり、信じていたいから。ずっと」
「まぁ、それだけ嫌な思いをしてきてるからね、ろくでもない奴のせいで。
うん。いいよ。約束する」
「うん。ありがとう…」柔らかな笑顔。見たかった笑顔。
「覗きの時、嘘ついたような気もするが、あれはナシな?」
「え? あ、あの友達庇ってついたやつ?」
「そう。あの時はまだ付き合ってなかったし」
「…うん。あれは仕方ないもんね…。ふふっ、思い出しちゃった。
…でも、あれが始まりなんだよね。私、あの時、真面目な、いい人だなって思った」
「そうなの?」
「うん。それから感想文のことがあって、見学とファーストフードで喋ったのがあって、
…その頃かな? あ、この人いいかもって思ったのは」
「俺と同じ頃だったのか。意識し始めたのは…」思わぬ偶然に嬉しくなる。
「…そう。だから、最初の告白のとき、見学した帰りの日から好きになったって言われて、
ドキッとした…。交換日記しようって言った時には、多分、もう…好き…だったと思う…」
「そう…か。嬉しいな…」
「ふふっ、…ありがとう…」
この上なく、優しく甘い時が流れる病室。
「そうだ、肝心な事忘れてた。あーゴホン」わざとらしく咳払いをする。俺なりの決意の準備だった。
「?」きょとんとした顔で見詰める彼女。
「これからは…片瀬…じゃなくて、…み、みき…」再度の告白よりもよっぽど緊張した。
「…あ…名前…で?」はにかむ美樹。
「…嫌だった?」恐る恐る聞く。
「ううん…嬉しい…」
「じゃあ、かた…じゃない。…美樹も呼んで?」名前を呼ぶだけなのに、どうしてこんなに恥ずかしいのか。
それは多分、特別な事だったから。呼び名の変化が意味するものが。
「ひ、ひさし…くん」遠慮がちに、初めて俺の名を呼ぶ美樹。
「……」俺は黙った。この愛しさを言葉で表現するのは無理だと思った。
言葉で今の気持ちを完全に表すことは、未熟な自分には不可能だと理解した。
…だから。
ベッドの淵に腰掛ける。裸足の足に病室の床は少し冷たかった。美樹との距離が殆どなくなる。
窓から差す夕日によって、茜色に染まる俺と美樹と部屋と世界。
椅子に座っている彼女の肩を優しく掴む。しばし見つめ合い、額を合わせる。互いの鼻が当たる。
「…くすぐったい…」美樹は照れて言うが嬉しそうだ。
美樹の瞳に俺が映る。が、俺の姿は消える。彼女が目を閉じたから。
涙の跡が残っていたが、もう今は涙を流させる事はないだろう。
俺も美樹に倣って目を閉じる。優しく手を握る。美樹が握り返してくる。
近づく身体と、顔と、唇。…そして。
————俺達はほんの数秒間だけ、口が利けなくなった。
————世界の色が変わる。
俺の目はどうかしたのだろうか。何だか景色の様子が違って見える。
病室の窓から見える世界の色は、こんなにも鮮やかだったのだろうか。
目が覚めて、病室の窓の外を見た俺は思った。
なんて事のない、街の景色だけど何か違って見える。
まるで、昨日とは違う景色を見ているようだ。
今まで俺の目に映っていた景色は色を失っていたのだろうか、それほどまでに色彩は鮮やかだった。
赤はより激しく情熱的に、緑はより穏やかに、青はより爽やかに、黄はより華やかに、
そして、白はより優しさを増して俺に微笑んでいるかのように見えた。
心持ちだけで見える景色の色まで変わってしまうのだろうか。
昨日の夕方の事を思い出し、思わず顔がにやける。
美樹は俺を受け入れてくれた。好きだといってくれた。俺の彼女になってくれた。
その事実を考えると、頭がぼーっとする。が、いつまでもこうしているわけには行かない。
「…よしっ!」
俺はベッドから勢い良く飛び起きた。こんな所からはもうオサラバだ。
「あ、来てたんだ…」学生服に着替え、病院の外に出ると彼女は待っていた。
「あ、おはよう…尚くん…」ひさしくんの声がやや小さくなる。
まだ、彼女には呼び慣れていないのだろう。初々しい照れが感じられる。愛しかった。
「あ、お、おはよう、…美樹」しかし、それは俺も同じだったようだ。
「病院の中で待ってれば良かったのに」
「うん…なんとなく、病院の雰囲気って馴染めなくて…」
「ああ、確かにあんまりいい感じじゃないしね」
「それより、もう大丈夫? …身体」
「全然問題ない。至って快調。…ちょっと筋肉痛はあるけどな」
「ふふっ。頑張ってたからね」
昨日の夕方、あの後、彼女と一緒に登校すると約束した。
美樹は中々帰りたがらなかった。母親が、着替えやら、鞄やら持って戻って来ると言ったら、
「ご挨拶しなきゃ」などと言い出した。
「あれにはびっくりしたな」歩きながら俺は言う。
「だって、当然じゃない。か、彼女なんだから…」胸にじーんと来る想いがあったがごまかした。
「いや、俺としては恥ずかしくてね…。まぁ、近いうちにすればいいよ」
「うん」
俺はそっと美樹の手をつないだ。
美樹が少し驚いて俺を見るが…すぐに笑顔。俺も。
「でもなんか夢みたいだ」
「何が?」
「昨日の今頃はまだ片瀬…って呼んでたのに、今は手をつないで一緒に登校してるんだもん」
「あ…そう言えば」美樹は静かに微笑む。
「俺は…なんて幸せなんだろう。信じられない。夢みたい」
正直に胸の内を伝える。
「大袈裟なんだから…もう」
「いや、昨日からさ、変なんだよ」
「変? 何が?」
「何て言うか、落ち着かないんだ。そわそわするし、
気持ちが高揚してる。妙にテンションが高いんだ。
今までこんな事はなかったんだけどね。多分…浮かれてるんだろうな。嬉しすぎて」
「恋の熱病だね?」
「病原菌は君だけどな」
「ひどーい!」笑って怒る彼女。
「ごめん、ごめん、冗談…」俺はじゃれながら言う。
「あ。そろそろ手、離した方がいいかも」学校に近づいた頃、俺は言う。
同じ学校の生徒の姿を見かけるようになってきた。
「あ…そうね…。まだ、恥ずかしいもんね…?」
「うん…流石にまだちょっと…ね。からかわれるだろうし…」
「うー…」少し唸って不服を訴える彼女。
「仕方ないだろう? 美樹だって恥ずかしいって…」手を離したくないのは俺も同じだったけど。
「うん…。じゃあ、後でまた…ね?」
「ああ」
そう言って二人、並んで歩いた。
「じゃあ、またあとで…」それぞれの教室に近づいた頃、美樹が言う。
「あとって、休み時間?」
「あ、ひ、昼休み用ある?」何故か思い出したように慌てて言う美樹。
「? いや、ないけど?」
「じゃ、じゃあ一緒に…ご飯…いい?」伺いを立てる様な表情で。
「…当たり前だろ?」
「! うん!」笑顔に花が咲いた。
昼休み。俺は美樹の教室の前で待つ。
「あ、尚くん!」周りに人がいるのにも気付かず、美樹は笑顔で寄ってくる。
「…声でかいぞ…」
「あ…。ご、ごめんなさい」
「いや…行こう」
美樹のクラスの女子が驚いて…ひそひそ話。内容は聞かなくても大体わかる。
まぁ、いずれ人には知られる事だ。俺はなるべく気にしないようにした。
「ぷはー。やっと落ち着ける…」中庭は生徒はまばらで、俺達は備え付けのベンチに座る。
俺は深い溜息を吐いて言った。
「どうしたの?」
「いや、ちょっと…朝、教室行ったらさ、皆に拍手されて、熱烈歓迎を受けちゃって…。参ったよ…」
「あ、マラソンの?」
「うん。何か、みんな心配したんだって。感動したとかって言ってた人もいたな。
冗談じゃないよ。こっちはリタイアしたっていうのに」
「ふふ、私のクラスでも話題になってたよ」
「マジで?」
「うん、走ってて倒れるのって皆、はじめて見たみたい。…私もだけど」美樹は笑う。
「それでさらに…」俺は続けた。
「何?」
「俺が運動部でもないのに川原で特訓してたのを、誰かが見てたらしく…」
「うんうん」
「それが教師に知れ渡って校長と、体育教師が感動したらしい。
おまけに、体調悪いのに必死で走ったのも」
「…それで?」
「どうやら、後日、俺だけ別に表彰があるらしい。
努力賞だか、敢闘賞だか、特別賞だか知らないけどそういう感じの。HRで担任が言ってた」
「すごーい!」美樹は驚いて喜ぶ。
「でな、その知らせ聞いた時、また教室が拍手喝采…。何故か俺は立たされて、頭を下げてた。
おまけに秋田のバカは「西野コール」の音頭まで取り出す始末。あの宴会部長め…」
俺はぐったりした表情で恨めしげに言う。
「あ、それ聞こえた…。いきなり沢山の声で、
「に・し・の!に・し・の!」って。ふふっ、秋田君らしいね?」
「あいつは盛り上がれば何でもありだからなぁ…」
「でも、凄いよ。10位は無理だったけど、結局入賞じゃない。ふふっ」
「あー。そうか。一応、約束は果たした事になるか…。
でもなぁ…なんかブービー賞みたいだよ。小学校の「良く頑張ったで賞」みたいな」
「あんまり嬉しくないの?」
「うーん。まぁ、貰える物は貰っとくさ。どうせだから。
ただね、予想以上に目立ってしまって、照れくさいんだよ。
しかもそれがリタイアで得た評価ってのが…ね」
「奥ゆかしいね。尚くんらしいな」美樹は誇らしそうに言う。
「まぁ、でも約束は果たした。これで。晴れてデートですよ、片瀬さん」
「あ…、そ、そうだった…」絶対この人は今まで約束を忘れていただろう。
「OK?」
「う、うん」
「…ちなみに、賞もらえなかったらデートはナシだった?」悪戯の虫が騒ぎ出した。
「え? そ、そんなわけないよ!」
「でもなー。10位以内って約束だったからなー。やっぱしない方がいいかなぁ…」
「え? ちょ、だ、ダメだよそんなの!」うろたえる彼女。
「…冗談だって」笑って言う。
「え? ・・・も、もう! 意地悪…!」
「ははっ、ごめんごめん」
「…で、俺パン買って来ようと思うんだけど」
「あ、ちょ、ちょっと…まって…?」
「? うん」
「こ、これ…」バッグから包まれた四角い箱。…もしや。
「俺に?」
「う、うん…」緊張して渡す美樹。
包みを解いて箱の蓋を空ける。
「…わあ。サンドイッチだ…」
四角い箱に綺麗に区画されたサンドイッチ。丁寧に、均等に整列されている。
これだけでも、手間が掛かっているのがわかる。
「ど、どうぞ…」
彼女は魔法瓶を出して、琥珀色の熱い液体を注ぐ。紅茶だった。
「これも? いつもは魔法瓶なんて持って来ないよね?」
「う、うん…。きょ、今日は特別に…」ほんのり染まる頬。
「…じゃあ、頂きます」
「め、召し上がれ…」お決まりの常套句を交わす俺達。
美樹は身じろぎもせず、じっと俺を見詰める。なんだかこそばゆい。
再び頭の中で悪戯の虫が蠢動し始める。ひとつ掴んで口に入れ、咀嚼する。…直後。
「う…うう、こ、これは…!? ううう!!」そう言って俺はうずくまり、腹を押さえ苦しみ出す。
「え? ちょ、ちょっとどうしたの?」驚愕の表情を浮かべ青ざめる美樹。…ひっかかった。
「う………、うまい…」
「ええ?」
「いや…、非常に上手い。美味。おいしい。とても」俺は得意げに笑って言う。
「え? …あ。も、もう! また騙した〜!」今度は赤くなる美樹。
「ははは。非常に古典的だが、引っ掛かったね。ははっ」
「もう! そんなバカな事ばっかりして! ベタベタじゃない!」
「俺は基本に忠実なんだ。これは王道だ。お約束だ。古から伝わる愛の儀式なんだ。
彼女が作ってくれた最初の手料理を食べた男は、必ずこれをやらなくてはいけない。
真実の口に手を入れたら、必ず引っ張られなきゃいけないのと同じだ」
「私はオードリーじゃないもん…!」
「じゃあ、次は缶ジュースを後ろからほっぺたに付けて「ひゃっ、冷たい!」だな」
「もう!」非難しながらも彼女は楽しそうだった。目は怒っていない。
「でも、うん。美味しいよ、ホントに」
そう言って俺は食べ続ける。紅茶も上品な甘みで食欲を刺激した。
「そう? ほ、ほんと?」
「ああ、美味しい。料理上手なんだな、美樹は」
「え? そ、そう? 嬉しいな、やった…」胸を張る彼女。
「でもさ、これって作るの大変だったんじゃない?」
「え? どうして?」
「いや、綺麗に並んでたし、パンも上手にいい色に焼けてる。生でなく、焦げてもなく。
おまけにパンの耳も丁寧に切られてるみたいだし…」
「…あ、ちょ、ちょっとだけ頑張っちゃった…かなぁ…?」恥ずかしそうに言う。
「いや、ちょっとどころじゃないな、これは。凄く手間が掛かってる。うん、嬉しいよ。ありがとう」
「えへへ。どう致しまして…」彼女はぺこりとお辞儀する。
昼休み。至福の昼休み。このまま終わらなければいいのに。
俺は爽やかに晴れた空を見上げて願った。
「ヘイ、YO! そこのカレシ〜。こっち来いYO!」
「…今度は何だ。リズム感のないラッパーよ」
「いやいや、まだストリートデビュー前だからしょうがない。
そ・れ・よ・り・も!」猫撫で声で近づいてくる。
「…気持ち悪さは極めてるんだけどだな」
「えへへぇ…。君に話しあるんだけどな〜?」
「わかったわかった。こっちへ来い」放課後、俺は秋田と教室を出た。
「で? どうなの?」
「…何が?」
「言わせる気? 女に恥をかかせるの? 酷い!」
「何だそのテンション」
「ああもう、じれったい! 吐け! このコソ泥がぁ! お前が盗ったんだろうが!」
「何も盗ってねえよ…」
「いーや、盗ったね。盗んだね。それは何かって? 彼女のハートをさ!」
「じゃ、また明日な」
「おう、また明日。…って、待てルパ〜ン!」
「なんだよ、もう。うるせえなぁ…」辟易としながらも毎度のやり取りに俺は笑った。
「はぁはぁ、ち、ちょっと待てよ。俺一人で騒いでバカみたいじゃないか…」
「何を今更」
「いや、だから。頼むよ、教えてくれよ〜。ひー君ってば〜」俺にすがりつく秋田。
「袖を掴むんじゃない。お前はダイヤモンドに目が眩んだ女か。あとひー君はやめろ」
「で? で? で?」
「…お陰様で。上手く行った」
「…マジで?」秋田の細い目が見開かれる。
「超大マジ」
「か、片瀬と? あの片瀬と?」あの、の部分を強調する彼。
「他に誰がいる」
「……いつからよ?」
「…昨日…だな。お前が病院から帰った後」
「あああ、俺が帰った後に〜!? お、お前らは? ふ、不潔!! イヤ! 恥ずかしい!」
「…何を妄想してるか知らんが、大した事は起きてないぞ?」
「そうなのか? 告白だけか?」
「ノーコメント」
「ままま、まさか…」
「うるさい。大それた事は起きてないと言っただろう。…察しろ」
「はぁ〜〜〜。…お前も遂に彼女持ちかぁ…」
「何言ってんだ。お前だって彼女いたじゃんか、ちょっと前までは」
「まぁな、でもそうかぁ…。片瀬かぁ…いいなぁ…」
「そうなのか?」
「当たり前だ。片瀬だぞ? 片瀬を羨む女はまずいないだろうが、お前を羨む男は腐るほどいる」
「…悔しいが言い返せない…」
「うちのマドンナも手が付いたか…」
「嫌そうだな。お前も好きだったのか?」
「いやいや、とんでもない。恐れ多いよ。憧れてはいたけどね。
そんな大それた事が出来るお前は凄い。ていうか、お前絶対解かってない。片瀬の人気」
「そんな事はないって」
「いや、まぁ、多少は知ってるだろうけどさ。多分ビビると思うよ。
嫌がらせとかはないだろうけど、知ったらがっくりする奴もかなりいるんじゃないかなぁ?」
「………」
「あーいや、違う。脅かすつもりはない。けど、知っといた方がいいよ。
実は、体操部覗き禁止令が出来たのも片瀬のため」
「そうなのか?」
「ああ、あいつが来るまでは覗きなんて殆どなかった。
それが、禁止されるくらいにまで増えたんだよ。つまり、片瀬に告白できなくても、
見たいとか思ってる奴がわんさかいるってわけ。
告白とか、手紙渡す奴なんて氷山の一角。その下には思いも伝えられない奴が沢山いる。
まぁ、そういう人と、君は付き合う事になったわけだ。気を引き締めないとな」
「…だからどうした」
「へ?」
「確かに俺の思ってたよりも人気はあるみたいだな。でも、そんなの関係ない。
あいつが好きなのは俺だけだ。あいつと付き合ってるのは俺だ。俺だけだ。
俺達の間に、誰の割り込む余地もない」何故か熱くなった。
「おお…。ど、どうしたんだお前…?」
「ああ、いや、ちょっと」
「…ふうん…」
「? 何?」
「いや、良かった。安心した。それだけ言い切れるなら、大事に想ってるなら大丈夫だよ。
いやぁ、お前なんかかっこ良かったぞ」
「よせって…」俺は照れて頭を掻いた。秋田に熱くなっても仕方ない。
「ま、しっかりな。応援してるよ。って、もう帰るのか?」
「いや、彼女が部活終わるの待つ。図書室でも行こうかと」
「俺も行くよ。ヒマだし」
「騒ぐなよ?」
俺達は夕日に染まる校舎を並んで歩いた。秋田はしきりに、
「いいなぁ…。…いいなぁ…」などと言っていた。
「あ、おーい!」体育館から出てきた美樹が俺に気付いた。大きく手を振る。嬉しそうに。
俺は座っていた花壇から離れ、彼女に近づく。空にはまだ夕焼けが残っていた。
「お疲れ」
「ありがとう、図書室にいたの?」
「ああ、いい時間潰しになるよ。今さっき出てきたところ」
「ふふっ、本沢山あるもんね。…じゃあ、かえろっか?」
そう言って彼女は俺の腕に自分の腕を絡ませる。
「うん。…しかし、若干の問題が発生している」
「え?」
「そこだ」そう言って俺は花壇の暗がりに指を差す。学生鞄がはみ出している。
誰かが花壇の向こう側にしゃがんで隠れている。
「いやぁ…どうも…えへへ」
「あ、秋田君?」美樹は慌てて俺から腕を離す。
「…帰れって言ったんだけど…」俺は美樹に済まなさそうに言う。
「あ…」
「あ、いや、片瀬ごめんな。どうしても、気になってさ。友の恋路が」
「嘘付け。この芸能リポーターが」
「酷い! 何もそこまで言わなくても…ちょっとした好奇心と野暮じゃない!」
「野暮だと自覚してるあたりにタチの悪さがある」俺は溜息を付いた。
「いやあ、でもいいねー。青春だねー」秋田は嬉しそうに言う。
「行こう、美樹」
「え? いいの? ほっといても…」
「構わないよ。それに…多分、ほっといてもついて来る」俺は美樹を促し、歩き始めた。
「待ってー。置いてかないで〜」予想通り、彼は憑いて来た。
「で、で、で? どっちから告白したの?」リポーターの拷問のような尋問が続く。
「えーと…」
「美樹、答えなくていい。相手はハイエナだ」
「うわー、美樹だって! もう名前で呼び合ってるんだ! 早やー!
え? じゃあ、何? 片瀬も名前で呼んでるの?」
「え? う、うん…」
「だから答えなくっていいって…」
「なんだよ〜、俺は片瀬に聞いてるんだから邪魔すんなっての!
って、今日はちょっと離れて歩いてるけど、やっぱ普段は手とかつないじゃうんだ?
そういや、さっきも腕組んでたしね」
「あ、あれは…」
「いつもはああなの?」
「いつもって言っても、今朝からだけど…」律儀に照れながらも答える美樹。
「…誰のせいで、わざわざ離れて歩いてると思ってんだ!」
俺は遂に秋田の尻を蹴っ飛ばした。加減はしたが。
「痛い! 片瀬見た? この暴力男を。普段は大人しいけど本性はこれよ?」
「ふふふっ…」
「ちょ、笑ってる場合じゃないって…」秋田は言う。
「…仲良いんだね、二人って」
「……」
「……」男達の沈黙。
「ふざけて、笑って、じゃれ合って、楽しそう。ふふっ、仲良しの男の子達を見るのっていいね」
「……」
「……」男達の羞恥。
秋田と見詰め合う。二人とも、気まずい視線が泳いでいる。
「わははは」
「あはははは」
何故か俺達は笑った。多分照れ隠しだろう。美樹の指摘があまりにストレートだったから。
「?」美樹だけが取り残されている。
「まったくあのバカは…」ファーストフードの店で俺は毒づく。
「ふふっ、でも面白かったよ。楽しいね、秋田君って」
「まぁ、芸人みたいなもんだから。それを取ったら何も残らないからね」
「ひどーい。あはは。でも、いい友達持ってるんだね。尚くんは」
「…まぁ、否定は出来ないかな、残念ながら。…いい奴ではあるね、認めたくはないが」
「またまた、強がっちゃって」
「……世話にもなったからね。美樹との事でも」
「そうなの?」
「ああ、相談に乗ってもらった。色々と。全部は話してないけど」
「へぇ。キューピッドなんじゃない? 私達の」
「かもね、見た目はゴリラみたいだけど」
「もう! あ、でも似てるかも。ふふふっ」
邪魔者のいなくなった店内で、俺達は話に花を咲かせた。
「じゃあ、また明日」美樹が言う。
「うん。あ、じゃあ、あの分かれ道に明日」
「あ、明日も一緒に学校行くの?」
「だめかな…?」
「ううん、嬉しい」
「…良かった」俺達は微笑んだ。
そろそろお別れかと思ったが、美樹は帰ろうとしない。
周囲をキョロキョロ見詰めている。誰か探しているのだろうか。しかし、近くには誰もいない。
「え?」
美樹は突然俺の目の前まで来て、
———口付けた。唇に。やや慌てたが、俺は静かに目を閉じ彼女の華奢な背中を抱いた。
「……好き」小さな声で、でも真剣な声で彼女は言った。
「うん…」俺は美樹の優しく身体を包み答える。
美樹を抱きしめたまま空を見上げる。今夜は残念ながら、星も月も見えなかった。
それでも、俺は満足だった。夜空に輝きがなくても寂しくない。
今はもう、ふたつも光を持っていたから。
朝も昼も夜も消える事のない輝きを、心と腕の中に抱いていたから。
「やばっ…遅れてる…!」俺はクォーツの腕時計の正確さを呪った。
夕べは緊張であまり寝れなかった。少し寝坊した俺は待ち合わせ場所へ急いだ。
付き合い始めてから初めての日曜日。
俺達は約束どおり、初めてのデートを迎える。
駅前で待ち合わせ。俺達の家は駅3つ分程しか離れていなく、一緒に出かける事も出来たのだが、
昨日の夜の電話。
「ふふっ、明日楽しみだね。デート」
「うん、どこに行こうか?」
「どこでもいいよ。あんまり予定を決めないで行くのがいいかな…」
「わかった。じゃあ、どうする? 家まで迎えに行こうか?」
「うーん、待ち合わせに…しない?」
「? いいけどどうして?」
「うんとね、待ち合わせの方が、デート…って感じがする…」
「ああ、そうかも。わかった。じゃ、明日の10時に駅前でどう?」
「うん!」
自分から決めといて遅れるなんて。
それでも10分程度だが、遅刻は遅刻だ。ようやく目的地に辿り着いた俺は彼女の姿を探した。
休日の駅の周りには人が多く、他にも待ち合わせている人も多かった。
「…ごめんなさい。待ち合わせをしてるから…」聞きなれた声。すぐ後に聞き慣れぬ声。
「えーいいじゃん、遊び行こうよ〜?」
…美樹だった。知らない若い男に言い寄られている。俺は二人に近づく。
「美樹? どうしたの?」
「…あ! 尚くん。えーと…」
「…なんだよ、彼氏いるのかよ〜。悪かったね、じゃ」そう言って彼は去った。
「今のって…もしかして…」
「……うん」美樹はみなまで言わなくとも聞きたいことを理解してくれた。
「ナンパ…か。初めて見た…。…って、そんな場合じゃない。
ご、ごめんな!? 俺が遅れたばっかりに!」俺は心から詫びる。
「い、いいの。もう大丈夫だから」
「でも俺がもっと早く来てれば…」
「違うの。あの人で…、ふ、二人目…だから…」
「え? じゃあ、その前にも?」
「う、うん…」恥ずかしそうに頷く美樹。
「…凄い…。い、いつもこうなの?」秋田の指摘を改めて思い出す。
やっぱり、俺は彼女の凄さをまだまだ理解していなかった。
「ううん、いつもは無視したり、走って逃げたり…。
でも今日は待ち合わせだったし、ここから動けなかったから…」
「あ〜俺が気が利かなかった。やっぱ、家まで迎えに行くべきだった!」
「いいの、私が待ち合わせにしてってお願いしたんだから」
「でもさ…」
「だからいいの。楽しかった。尚くん待ってるの。ナンパは…ちょっと迷惑だったけど」
複雑な表情で微笑む美樹。
「…美樹…。よしっ! じゃあ、仕切り直しな?」弾かれたように言った。
「え?」
そう言って俺は美樹から離れ、彼女から見えなくなる距離まで移動してから再び現れた。
「…ごめん、遅くなって。待った?」
少し戸惑っていた彼女だったが、
「…ううん、今来たとこ。……これで…いいのかな?」
「完璧です」俺達は笑った。
それから俺はデパートの中で美樹の買い物に付き合った。
洋服を大体近くの量販店で安くて適当なものを、深く考えもせずに買っていた俺には敷居が高かった。
こじゃれたテナントのショップをまわる度、場違いな緊張感に襲われたが美樹はお構いなしだ。
相当買い物慣れしている。しかし、美樹が洋服を試着する度、俺に見せてくれるのは楽しかった。
「洋服好きなんだ?」買い物の途中で俺は尋ねる。
「うん、大好き。買い物も好きなんだ」実に女の子らしい回答。
そう言えば、美樹は俺から見ても垢抜けている。お洒落と呼ばれる部類だと思う。
着ているものも同年代の女の子と比べると高級感がある。お嬢さんなのだろうか。
学校にいる時は俺は学ラン、美樹はセーラー服だったから気にならなかったが、
なんだかまたひとつ、釣り合わない要素を発見してしまった気がする。
「ね? 尚くんのも買おうよ?」
「え? お、俺はいいよ…。良く解からないし、…高そうだし…」やんわりと固辞する。
「そんなに高いのばかりじゃないって。あ、ここなんかいいんじゃない?」
そう言って美樹は俺を同じデパートの中の店に連れて行く。こんな所、足を運んだこともない。
「これから寒くなるから、セーターがいいかな? う〜ん、ブルゾンの方が気回しが利くかなぁ?」
美樹は既にコーディネートまで考えている。殆ど独り言だ。
彼女は洋服をひとつ手にとって、
「これなんかいいんじゃない? 似合うと思うよ、ラインが綺麗だし」
「…ラ、ラインって何?」
「あ、こっちかな。カバーオールの方が好き?」
「か、かばーおーるって…。…何をカバーしてるの?」
……拷問だ。美樹は丁寧にファッション用語を解説してくれるが、全く頭に入らない。
曖昧な相槌を繰り返すだけの俺。お洒落で綺麗なショップの中で、
お洒落で綺麗な女の子に振り回されてうろたえる冴えない男の図。
「うーん、やっぱりこういうのは着ないとね。すみません、試着させてもらえますか?」
「ええ、どうぞ」柔らかな店員の返事。
俺達の滑稽な様子を見ても丁寧な接客が変わらないあたり、プロだ。
「…て、俺着るの?」そうだった。今試着するのは美樹じゃない。
「いいから。はい」そう言って美樹は真新しい上着を持って俺に着させようとする。
逃げられない。諦めた俺は袖を通した。すかさず店員が全身鏡を俺の目の前に持ってくる。
鮮やかだ。美樹と店員はまるで10年来の友達の様な阿吽の呼吸を見せた。
「…お」俺は鏡に映った自分の姿を見た。相変わらず冴えない高校生の顔が映っていたが、
首から下はそれなりだった。美樹のセンスに間違いはなかった。
「…どう?」
「似合ってる…様な気がする。なんとなくだけど…」俺は遠慮がちに言った。
「えへへ、こういうの似合うと思ったんだ」美樹は自慢げに言う。
タグを見ると、高校生にも手の届かない値段ではなかった。
彼女の罠は周到だった。
「いい買い物できて良かったね」遅い昼食を取りながら、美樹は嬉しそうに言う。
「…うん。恥ずかしかったけど。まぁ、いい経験になったような気もする」
「そうそう、その調子。また行こうね?」
「そんなに何度も買えないけどな」俺は紅茶を飲みながら言った。
「も〜。でも楽しいでしょ? 何だか違う自分になった気がしたでしょ? 服を変えただけで」
「まぁ、…少しは…」実際その通りだったので否定できない。
「でも、なんだかなぁ。プリティー・ウーマンの男女の役が入れ替わったみたいだよ…」
「プリティー・ボーイだね。尚くんは」彼女はおかしそうに笑う。
「…やめてくれよ…」俺は恥ずかしくて目を逸らした。
「あ〜。いいもの見つけちゃった!」夕暮れも近づいた頃、彼女は大きな声を挙げて言った。
「…今度は何?」新たな未知なる恐怖に備え、俺は身構えて言った。
「えへへ。これこれ」そう言って彼女は俺を引っ張る。ゲームセンターの方に。
「いいものって、プリクラ?」彼女は筐体の前で止まる。
「撮ろう?」
「……」
「嫌なの? 撮った事ないの? 今流行ってるじゃない?」
「…前に一度だけ。男だけで撮った事がある」
「苦手なの?」
「写真は…見るのはいいんだけど撮られるのはあんまり…」
「大丈夫、プリクラと写真は違うもん」笑って言う。
安心して私の胸に飛び込んで来いと言わんばかりの表情だ。
どこがどう違うのか是非説明してもらおうと思い、口を開きかけたが、
「……ダメなの?」少し悲しそうに、上目遣いにおねだりする。
「…その顔は卑怯だ…。ああもう、わかった。撮りますよ」
「やった!」一瞬にして顔が綻ぶ。現金なんだから。
「動いちゃダメだよ〜。ここのね、穴を見るんだよ?」
「わかった」
そう言って彼女は俺に寄り添い、俺の片腕を抱き締める。…プリクラも悪くないかも。
俺は彼女の柔らかさと暖かさを感じてそう思った。現金なのはお互い様だった。
「はい、あげる」そう言ってプリクラの半身を俺に渡す。
「何か変な顔だなぁ、俺」
「だって、動くからだよー」美樹は実に綺麗に写っている。とは言え、元々素材が違うか。
なんとなく、上手く俺達を表現している写真のように思えた。
初デートは順調に過ぎていく。気付けば夜も始まっていた。
「そろそろ帰らないと、送ってくよ」
「…あ、そうか。うん、そう…だね」美樹はどことなく元気のない返事。
「考えてる事は同じだよ。でも、もう遅いし、明日も会えるから…」
「そうだよね? うん、帰るよ」
俺は美樹と手をつないだまま、夜の道を歩いた。
「あ、ここ」指を差す美樹。白い指が指し示したのは綺麗なオートロックのマンションだった。
賃貸なのか、買ったのかはわからなかったが、高い物件である事は間違いない。
「じゃ…また明日な」
「うん、また明日」そう言って美樹はマンションのエントランスに消えた。
「また明日…」美樹がいなくなってからも、俺はもう一度呟いた。
「おーい、西野〜。待って〜」
「うるさい、話しかけるな。…俺だって辛いんだ」
「ひ〜君冷たいよ〜。美樹ちゃんに言っちゃうよ〜?」
「……」俺は無視して黙々と走る。
体育の時間、今日は数クラス合同で行われていた。校庭を男子がゾロゾロと走る。
「な〜、なんで体育の時間までマラソンなのよ〜? こないだマラソン大会やったばっかじゃんよ〜」
千鳥足の酔っ払いのような走り——もはや走りとも呼べない、歩みで秋田は愚痴を言う。
「俺に言うな。文句は教師に言え」
「あああ〜サボればよかった〜。…せめて女子がいればやる気も違うのに〜」呪詛のように恨めしく呟く彼。
俺は無視して置き去りにした。
苦行の様な授業はやっと終わった。皆一様に疲弊している。
休み時間、校庭近くの水飲み場は喉を枯らした男子達でごったがえしてる。
「ダメだなこりゃ〜。ああ、水飲みたいのに…」大して走ってないくせに秋田は言う。
「そうだな。俺、裏門の方の水飲み場行って来る。多分あんま使われてないだろう」
「あっちまで行くのか? 面倒だな、俺はここでいいよ。空くのをもうちょい待ってるわ」
「わかった」俺は歩き出した。
校舎の裏、普段は人も通らないような一角にやや古びた水飲み場はあった。
誰もいない。が、それはいつもは誰も使っていないという事だ。衛生面が少し心配になった。
「大丈夫かな…?」
俺は不安な気持ちで蛇口を捻る。透明な水が流れ出す。少なくとも、見た目は大丈夫そうだ。
何より、激しい喉の渇きに目の前の誘惑は断れなった。俺は大口を開けて水を飲む。
すると、やや遅れて誰か———同じ色の体操着を着ていたので、
さっきまで一緒に走っていた同じ学年の生徒だろう、別の男子もここに水を飲みに来ていた。
俺は水を飲み終わり、教室に向かい歩き始めた。ちょうど後から来た彼も給水を終えて、顔を上げた。
「なぁ、おい」呼び止められた。
「ん?」反射的に俺は彼のほうを向く。髪を派手な茶色に染め、ピアスを耳にいくつも付けている。
いわゆる、不良と呼ばれる人間。小柄だったが、整った顔立ちをしていた。
女子にはモテそうなタイプに見えた。俺みたいな垢抜けないタイプとは正反対に見える。
「お前、西野だろ? 確か」ぶっきらぼうに言う。顔は見た事があったが、名前は知らなかった。
同じ学年の生徒であることは知っていたが。
俺は同じクラスの生徒と、仲のいい人間以外の名前はあまり知らなかった。
「そうだけど、えーと…」名前が出てこない。
「ちっ、…荒川だよ、荒川。知らねーのかよ、お前」吐き捨てるように言う。
自分が有名人で、学校の誰もが知っていて当たり前だとでも思っているのだろうか。
「あー、そう、荒川だっけ…。で、何か用?」俺は適当に相槌を打つ。
「…お前、片瀬と付き合ってんだって? マジか?」
「…まぁ、そうだけど」既に、俺と美樹が付き合っているのは学校では周知の事実だった。
「…噂はマジみてーだな。片瀬がねぇ…、お前と? ふうん…?」ニヤニヤと笑っている。
不愉快に、口元を歪めている。
「話はそれだけ? じゃあ、俺行くから」
「まぁ、待てって。じゃあさ、こんな話知ってるか? 片瀬の」
「え? 何?」食いついたのが失敗の元だった。
「お前、あいつともうやったのかよ?」
「……は?」
「だからぁ、お前、片瀬ともうやったのかって聞いてんだよ」
「……なんでそんな事、答えなきゃいけないんだ?」
「なんだ、まだなのかよ。くくっ…じゃあ、知らねーか。はははっ」下卑た笑い声。
「…何が?」
「俺、あいつとやったんだけど。ちょっと前に」意地悪そうに、誇らしげに言う。
「……」
「悪りーな、先に頂いちまって。いい身体してたぜ? あいつ。胸もデケーしよ!」
「悪いが信じられない。そんな話は聞いたこともないし、
彼女は今まで誰とも付き合ってない。誰とも付き合ってないのにそんな事を簡単にする人じゃない」
「あははは。やっぱ馬鹿だなおめー。ちったぁ頭使えよ、童貞」あからさまに敵意を剥き出しに。
しかし、どこまでも人を侮蔑する事だけは忘れないようだ。荒川は続ける。
「付き合ってなくてもセックスなんか出来るっつーの。知らねーのかよ?」
「…何が言いたい…」
「…レイプだよ。レイプ。無理やり犯ってやったんだよ、あいつをな。
な? だからお前に言うわけねーだろ? 片瀬が」
「……やめろ」心が黒く、どす黒く侵食されていく。———憎しみによって。
「あ? なにお前、その口の利き方。 シメるぞ? あんま調子乗ってっと。
…まぁ、今はお前のもんなんだから、せいぜい大事にしてやれよ?
けどそのうち、あいつもおめーみてぇなダセー奴に愛想が尽きたら、俺のとこにでも来るんじゃね?
いや、俺が今から行ってお前から奪っちまうってのもいいかな?
そしたらお前どうするよ、なあ? 泣く? 泣いちゃう? 「返して下さ〜い!」って。ぎゃははは!」
———血が爆ぜた。
もうこれ以上、この男に喋らせておくわけにはいかない。
理性という名の枷を引き千切る。俺の脈拍はレッドを振り切った。
一気に荒川に向かって飛び込んで行く。
「あ…!?」目を見開き、仰天して固まる彼。反撃など全く予想していなかったようだ。
俺は奴の体操着の前の襟首を掴み、力任せに校舎の壁に背中から叩き付けた。
鈍い音が空の下に響く。
「がっ! ぐぅ…!」叩きつけられた荒川は俺の腕を振り解こうとする。が、俺の腕は解けない。
俺は構わず、彼の服を掴んだまま首元を捻り上げた。小柄な彼は上に引っ張られ、爪先立ちになる。
「て、てめぇ…!」
そう言って荒川は俺の顔面に殴りかかった。が、俺はよろけもせずその拳を受ける。
爪先立ちではパンチに力も入らないし、彼は小柄で痩せていた。腕力もさほどなかった。
痛いことには変わりないが、アドレナリンに支配された俺の身体を黙らせるほどの効果はなかった。
俺は彼の顔に顔近づける。10cm程の距離で言う。
「…お前の与太話を信じるほど、俺はおめでたくはない。好き勝手に、誰にでも言ってろ。
だがな、お前がこれからもし、美樹に何か、あいつを傷つけるような事をしてみやがれ」
「あ、ああ? 傷つけたら…なんだ…ってんだ…?」
まだ虚勢を張る余力はあるようだ。しかし、目には怯えの表情が浮かんでいる。
「———殺す。お前を」
自分でも驚くような、低くて冷たくドスの聞いた声。
「! な、なんだ…と?」呼吸が苦しいのだろう、声が掠れている。
「出来ないと思うか? 俺は嘘付きじゃない。…お前と違ってな」
そう言って俺は更に絞り上げた腕に力を込める。苦悶の表情に歪む荒川の整った顔。
「うぅ…や、やめ…ろ…わ、わかった…から…」ようやく白旗を揚げる彼。俺は手を離した。
荒川は地面に崩れ落ちる。大きく肩を動かし、足りなくなった酸素を求め苦しそうに呼吸している。
抵抗する意志はもうなさそうだった。ちょうどその時。
「にしの〜。どこ行った〜。おーい、ひーく〜ん。授業もう始まるよ〜。…って、あ、あれ?」
俺を探しに来たのだろう。秋田だった。
「ちょ、ど、どうしたんだ、お前ら!?」俺と荒川の只ならぬ姿を見て驚いて言う。
「秋田…」俺は彼を見る。体内の血はまだたぎっている。
「ち…。くそ…」そう言って荒川は走り去った。俺達から逃げるように。
「なんだ? け、ケンカか? 今の?」
「…なんでもない…」
「何でもなくないだろう!? あ、お前血出てるじゃんか!?
殴られたのか、あいつに? 平気かよ、おい!?」そう言って顔の傷の具合を見ようと近づいてくる。
「うるさい! 触るんじゃねぇ!!」俺は叫んで秋田の手を振り解く。
「っ! …ご、ごめん…」俺の剣幕に驚いて小さく謝る秋田。
「あ…」瞬間、沸騰していた血が冷え始める。冷静になってくる。
「いや、待て秋田…。悪かった。…ちょっと…頭に血が昇ってて…ごめん」
「……お、おう…。と、とにかく座れよ。あ、まず血を洗った方が…いいんじゃない?」
恐る恐る提案する。彼は少し怯えている様にも見える。
いつでも底抜けに明るい彼に、そんな接し方をされるのは嫌だった。その原因が自分にあったとしても。
俺は水飲み場で口を洗った。唇が切れていて、そこから血が流れていたようだった。
大した怪我ではなかったが、唇は少し腫れていた。
「いてて…」傷口が染みる。俺は顔をしかめた。
「も、もう大丈夫か?」
「あ、ああ、大した傷じゃない」
「いや、そうじゃなくて、お前に話しかけても平気…か?」
「あ〜、うん。いや、さっきはごめん、興奮してたから」
「そ、そうか…。しかし、お前がキレたところ初めて見たぞ? 普段大人しい奴がキレると怖えーのな?」
「……」
「何があったのよ? さっきのあいつと」
「授業、もう始まってるんだろ?」
「まぁね。いや、次、化学じゃん。で、教室から移動するのにお前の姿はないし、
おまけに制服も机の上に置いたまま。まだ着替えてもいない、授業もう始まるってのに。だから探しに来たのよ。
さっき、こっちの水飲み場行くって言ってたから。
で、見にきたらお前は口から血流してるし、もう一人は地面にうずくまってるし」
「…悪いな。わざわざ探して貰って。授業、始まってるんだろ? 行きなよ、俺も着替えていくからさ」
「……世の中には授業より大事な事もある。授業よりも大事な時がある。今はそれだと思うんだ。
少しずついろんな意味がわかりかけてるけど〜♪ 決して授業で教わった事なんかじゃない♪と、歌った人もいる」
「…尾崎かよ…。サボりたいだけじゃないのか?」笑って言った。笑える程までに、心は落ち着いてきた。
「ならいいよ、僕行くもん、…おベンキョーしに」そう言って立ち上がろうとする。
「ああ、わかった悪かった。感謝するって。友よ」俺は正直に彼に従う事にした。
「…というわけなんだよ」思い出すのも腹立たしかったが、俺は事の顛末を説明した。
「…なるほど。…そりゃあ、お前もキレるわな。まぁそんな事だろうとは思ったけど」
「そう?」
「そうだよ。だって、お前がケンカするのなんて初めて見たもん。あんなにキレてたのも」
「…うん。あんなに怒ったのは初めてだ。…ケンカしたのも。
まさか、自分から手を出す事になるとは思わなかった…」
俺は人と争うという経験自体が少なかった。怒る事も嫌いだった。
小さい頃から遡ってみても、言い争いさえ殆どした事がない。
「でも、相手が荒川じゃあ。どうせまた、ろくでもない事言われたんでしょ?」
「知ってるの? 荒川」
「まぁねぇ。まぁ、ヤンキーグループの一人だよ。俺はヤンキーとも割と仲良いけど、荒川は嫌い」
はっきりと言い切る秋田。珍しい。彼がそこまで嫌悪をはっきるさせるとは。
大体、人の悪口はあまり言わない男だった。
「なんつーか、セコいんだよ、あいつ。強い奴にはへーこらしてるけど、
弱い奴、普通の真面目な奴には、えばり散らしてる。こないだも大人しい奴を苛めてたらしいな」
…納得。奴のやりそうな事だ。
「いやね、ヤンキーったって、ウチの学校はのんびりだけど、校則は結構厳しい。
髪型とかはわりと自由だけど、いじめとかやってバレれば退学にもなる。暴力には厳しい。
だからヤンキーも校内ではさほど問題起こさないし、そのリスクを考えての事か、いじめも殆どしない。
だけど、ああいう奴もいるんだよ、中には」
「……うん」
「まぁ、被害者か、誰かが言えば退学になるんじゃね? そのうち。
まぁ、見つからないようにやるあたりが荒川なんだろうけど」
「美樹の事は…」
「デマだよ。まぁ、口は達者な奴だから。頭は悪いけど。それに、あいつに女襲う度胸なんてないって。
なんでお前にそんな事言って絡んできたのかは知らないけどね。
というか、片瀬の方が強いんじゃないの? 下手したら。お前、荒川と取っ組み合ってたんだろ?」
「美樹と取っ組み合った事はないけど、そうかも…」俺達は笑った。
「でも、報復とかないかなぁ。あいつが仲間集めたりして。それがちょっと心配…」
秋田が心持ち、神妙に言う。
「それは心配ないよ。報復はない。俺の側から言わない限り、表沙汰になる事もない」
「? どうして?」
「…あいつと話してみて解かった。あと、秋田の話を聞いて確信した。
あの手のタイプはやたらとプライドだけは高い。弱い、臆病な奴に限ってそうだ。半端な不良ってやつだよ。
遊び半分にからかうつもりで絡んだのに、自分がやられそうになったなんて絶対に言わないよ。
まして俺みたいな普通の奴を相手に。しかも一対一なわけだし、こっちから絡んだわけでもないし。
手を出したのは俺が先だけど、話を聞けば誰でも怒るだろう。
手を貸す奴なんていないよ。ヤンキーでも。
いや、ヤンキーなら尚更、そういう筋道の立たない事には手を貸さない。
この話が広まったら、困るのは荒川の方だよ。
学校からも、ヤンキーの中にも居られなくなるんじゃないか」
「それもそうだな。まぁ、運がいいのか悪いのか…」
「でも多分、あいつも美樹に惚れてたんじゃないのかな?」
「どうもそんな気がするな。だから言ったじゃないか。気を引き締めろって。
片瀬の人気、やっと理解した?」
「……うん。…骨身に染みて」
「大変だぞ? 大丈夫か? やっていく自信あるのか?」
「むしろ、より強固に。…何が何でも守ってみせる。必ず」迷う事のない決意を言葉にして表した。
「…ひー君かっこいい〜!」
「首絞めるぞ…」秋田は大袈裟に逃げた。
「とりあえず、教室で待ってろ、消毒液とか持ってくるから。お前は着替えてな」
「いやいいって、自分で行くよ、保健室くらい」
「おバカさ〜ん。唇腫らして「ケンカしちゃいました先生〜」って、入ってくのか?」
「あ…。…で、でも、どうやって?」
「俺はこの学校に知らない事はない。薬のありかも、棚の鍵の隠し場所も知ってる」
「……凄い。でも勝手に持ち出しちゃ…」
「すぐに、ちゃんと元に戻す。まぁ、上手くやるから任せとけって」
そう言って秋田は保健室に向かって行った。
俺はその後ろ姿を見送り、頼もしい背中を見て思った。
———どこまでも友達思いで頼りになる、気の利く優しい奴だ。
普段の発言の90%は下らない事ばかり言っているが、こちらが彼の真実の姿だと俺は知っている。
俺は憎まれ口ばかり叩いているが、一度として彼を疑った事はない。今も。
思わず、胸の奥が暖かくなった。目が潤んでくる。
俺は多分、学校で一番幸せだった。頼りになる友達と、優しくて可愛い彼女に恵まれていた。
ベクトルは違っても、秋田と美樹は共に学校の人気者だった。
放課後、あの後はどうにか平穏な学園生活に戻った。
腫れた唇について人に聞かれたが、秋田と激しくじゃれ合ってたらこうなった、と言ったら皆笑った。
俺達はしょっちゅう二人で悪ふざけをしていたから、皆は妙に納得していた。
授業が終わり、美樹の部活が終わるのを待つつもりで図書室に向かう。が、その途中。
「…尚くん!」美樹に後ろから声を掛けられた。
「あれ? 美樹ー。部活行かないの?」
「ちょ、ちょっと来て?」そう言って俺の手を引く。何が何だかわからないが従った。
そう言って、俺達は校舎の人気のない教室に入る。
「で、美樹、部活は…?」
「休んだの。具合悪いからって。それよりも…。…ああ! 本当に怪我してる!?」
「え? ちょ、おい…」美樹は俺の顔を覗き込んで泣きそうな顔で叫んだ。
「ケンカしたのね? そうなのね? 私の事で…」
「秋田…か?」他に知る物はいない。
「……うん、さっき聞いた…」
「あのバカ本当に…」
「バカじゃないよ!」
「え?」
「何でケンカなんかするの? 何で私に言わないの?
私、尚くんが知らない所で傷ついてるのなんていや…!」目が潤んでいる。…いけない。
「やや、ちょ、ちょっと待って。どこまで聞いたのさ? 秋田から」
「…尚くんが、…私の事を馬鹿にされて、侮辱されて、それで怒ってケンカになったって…」
「それだけ? そこまで?」
「うん…。 っ! まだ、あるのね!?」
「あ…いや…」しまった。彼女は鋭い。というか、俺が迂闊だった。
美樹は教室に並べてある机の椅子に座った。…言うしかないか。強い意志が大きな瞳に宿っている。
「実は…」俺は話し始めた。
「…そう、そんな事…言ったんだ…。私が、荒川…君に…」
「そんな話聞いたらもう、キレるしかないって。普通の男なら」自己弁護。
「…でも…怪我…しちゃって…」
「でも、お陰であいつを黙らせる事は出来たし、今後は二度と俺達に近づかないよ。きっと。
それはいい事じゃないか。俺達にとっては」
「…うーん…。そう、かなぁ…?」
「大体、美樹だって腹立たないの? そんなデマを俺に言われてさ。
美樹の事だって侮辱してるんだよ? あいつは」
「…ま、まぁ…言われてみれば…嫌だな…。…凄く」
「だろ? 罰せられて当然。悪い人にはお仕置きしなきゃいけないのですよ。この世の中は」
「……」黙る美樹。
「どうしたの?」
「あのね? 荒川…君でしょ? その人って…」
「そうだよ? 知ってるの?」
「うん。あの…私がこの学校に来て、最初に告白してきた人。去年に」
「ええ!? あ、あいつが?」
「……う、うん…」小さく頷く美樹。
「あの、「とりあえず付き合ってみればいいじゃん」って言った奴?
それで、断られてから三日くらいで別の女と付き合ってたっていう!?」
「そ、そう…」
「……凄い偶然…。いや、待て。…偶然じゃないか…」
「? どうして?」
「あいつはまだ美樹の事を好き…というか、あいつの好きなんて大した気持ちじゃないだろうけど、
今でも忘れてないんだよ。それと、俺を妬んでるのさ。もしかしたら、悔しいのかもしれない。
モテるはずの自分が振られたのに、俺みたいな奴が美樹と付き合ってるから。
多分、未練と嫉妬の両方だな。それで、俺にちょっかいを出してきた。ってとこだろう」
「そう…かな?」
「ああ、バカの考えそうな事だ。そんな嘘付いたってすぐにバレるのに。まったく。
信じるとでも思ったのかね。俺が打ちのめされるとでも思ったのかね」
「……本当に?」
「当たり前だろ!? …まさかと思うが、事実って事は…」
「あ、あるわけないじゃない! 違うもん…! だ、誰にも触らせて…ない…って、
も、もう…な、なんでこんな事…を」
「あ、いや、美樹が「本当に?」とか、言うからさ…」
「あ、ご、ごめん…」差し込む夕日のせいだけではなく、赤くなる俺達。
「……」
「……」何となく気恥ずかしくて、沈黙。
「…でも、ある意味、荒川も必要な存在だったか…」
「え? どうして?」
「だって、あいつのお陰…ってのも変だけど、そのせいで美樹は告白を断るようになった。
真面目な奴から真剣に告白されても断るくらい頑なに。
もし、荒川がいなかったら、美樹は好みの人の告白を受け入れていたかもしれない。
でも、荒川のせいで、俺と付き合うまでに誰も受け入れなかったからこそ、今の俺達がある…のかも…」
「あ…」
「なんか、凄いね…。人って…」俺は感慨深げに呟く。
「うん。…なんだか、不思議な感じ。縁って…」
「まぁ、俺達にとっては全ての縁が良い方向に作用されたって事だよ。
俺達はきっと、結ばれるべくして結ばれた、運命の二人ってやつだ。運命の恋なんだよ」
最後は冗談ぽくおどけたつもりだったが、美樹は照れも、笑いもしなかった。
外したかな? 俺は美樹の顔を見た。
「……運…命…」何だか難しい顔をして考え込んでいる。
「み、美樹?」俺は美樹の肩を軽く揺らす。
「…うん。運命…。そうよ! うん、運命だったの! 私達は…!」
「……み、き?」美樹は興奮気味に言う。ヒートしている。
「…そう。そうよ、私がこの学校に来たのも、荒川君に告白されたのも、
彼がいい加減な人だったのも、その後の告白を全部断ったのも、
尚くんが体操部を覗いていたのを私が見つけたのも、それを私が逃がしたのも、
その後友達になって交換日記をして告白されたけど、
断っちゃってでもマラソン大会で頑張って倒れちゃったけど、
もう一度告白してもらって付き合う事になって、
今日尚くんがケンカしちゃったけどそれがあの荒川君だった…。
その荒川君のせいで、私達は付き合えたとも言える…」
「…うん。凄い! こんな偶然ないもの…! 奇跡よ! きっと私達は決まってたの!
出会う事と、好きになる事と、付き合う事が! ねぇ、そう思うでしょ? 尚くん!」
「……へ?」立ち上がって熱弁を振るう彼女の迫力に圧倒されるばかりで。
「思うでしょ!?」間近に迫った美樹の上気した顔。
「は、はい…」とりあえず勢いに飲まれ頷いておく。
「やっぱり、運命の人だった…!」そう言って美樹は笑顔で俺に抱きついた。
「ちょ、おい…」戸惑ったが、悪い気はしかなった。柔らかい身体の感触と、いい匂いがした。
「…あ」
「? どうしたの?」美樹は俺を見詰めて尋ねる。
「いや…荒川の言ってた事、一個だけ当たってた…」
「なに?」
「…あいつ、美樹の胸は…大きいって…」
「……」美樹の頬に朱が差す。俯いてしまう。
「あ、ご、ごめ…」俺は慌てて謝ろうとした。けれど。
「…胸…やっぱり大きいかなぁ…?」美樹はそう言って自分の胸に手を当てる。
「え……」
「…やっぱり荒川君も大きいと思ったんだ。…尚くん…も」
「あ…いや…その…」
「体操部でも、大きいって…。クラスの女の子にも大きいって…、羨ましがられた…」
「あー、そ、そうなのか…」
「普段は邪魔…なんだけどな…。肩も凝るし、体操してる時も邪魔だし…。
胸が動かないようにきつくするのも苦しい…のに…」
「あ、ごめん。そんなつもりじゃ…」
「…ううん。いいの。身体の事は仕方ないもの。望んでこうなったわけでもないし。
でもね? みんな、特に女の子は羨ましいって言うの。大きい方が男の子に喜ばれるって…。
それで…尚くんも、…胸が大きい子の方がいい?」
そもそも、俺達はなんでこんな会話をしているんだろう。俺は話の展開に取り残され気味だった。
「……え、あ、いや、俺は…」
「正直に言って? お願い。嘘付かないで…」哀願するように美樹。裏切れるはずもなかったから、
「お、大きい方が…好きだ…」ありのままを答えた。
「…ほ、本当に…?」美樹は少し嬉しそうに。
「ああ、本当だ。大きい方が…好みだ。それが全てって訳じゃないけど…」
「そうなんだ…良かった…。胸の大きい子が嫌いだったらどうしようかと思った…」
「そんな事で嫌いになったりしないよ」俺は宥める様に笑って言う。ちょっと調子に乗り始めた。
「でさ、美樹はバスト何cmなの?」
「え…ええ? い、言えないよ、そんな事…」
「美樹のことは何でも知りたいんだよ。それに、隠し事はなしなんだろう?」
「で、で、でも…」オロオロしている。もう一押しかもしれない。
「嘘付かないでね? こんな事は美樹にしか聞かないし、聞けない。…で、何cmなの?」
完全なセクハラだったけれど、知りたいという知的性的探究心には勝てなかった。
「はちじゅう…な…な…せん…ち…」蚊の鳴くような声とはこういう声の事なのだろうか。
「87cmか。カップは?」
「ええ? カ、カップも…?」
「正直に。数字なんかよりも、カップ数の方が遙かに大事なんだ」何故か俺は必死だった。
「ひ、尚くんがエッチになってるぅ……」少し怯えている。俺の目は血走っていたかもしれない。
「教えてくれたらこの話はもうしないから。…さあ」
「…うぅ…。…ぃ…かっぷ…」
「え? ディー?」
「Eカップ!」堪え切れないように言い切った。
「Eか…。凄いな…。あ、もしかして、まだ成長中とか?」
「え? な、何で解かるの?」
「やっぱり。いや、高校生くらいの間は女の子の身体も成長するからね。当然胸も。
それでもしや、と思ったのさ。そうかぁ〜、成長中かぁ…。将来性も充分だな…。今でも充分大きいけど。
もしかしたらFに届くかもしれない。…でもFまで行くと大きすぎて形が崩れるか…?
…大きさと美しさのバランスから考えると、現状がベストかな…」一人、理想の胸について語る。
「…な、なんでそんなに詳しいの…?」美樹が恥ずかしそうに聞く。
「今まで黙っていたが…女性の胸には結構熱い男なんだ。俺は」言い切ってしまうともう恥ずかしくなった。
「し、知らなかった…」
「まぁ、あんまりおおっぴらに言う事じゃないしね。言い訳っぽいけど、大体、男は胸が好きなんだよ」
「じゃあ、私の胸も?」
「ああ、俺は…好きだ。美樹の大きい胸が。大きくてよかった。小さくなくて」
先程までの羞恥はどこかに置いて来てしまった俺だった。
「えへへ…。ちょっと嬉しい…かも…。
でも尚くん、そんなに沢山女の子の胸を触ってたの?」
「ば、ばか言うんじゃないよ。ないよ、触った事なんて」慌てて答える。
「ホント? だって、すごく熱っぽく語ってたから。胸の事」
「いや、それは理想というか希望と言うか。現実はさっぱりだよ。
それに、知ってるじゃないか美樹は。俺が誰とも付き合った事がないのを。そんなモテないって」
「あ、そうか…」とりあえずは納得してもらえたようだ。俺は自分を諌めた。
若さに任せ、調子に乗ってしまった。幻滅されていないか心配だった。
「へ、変な話になっちゃったね…」俺は取り繕うように言う。
「今日は尚くんの色んな新しい事が知れて良かった。…思ってたよりもエッチだったし」
悪戯っぽく、はにかむ美樹。
「そ、それは…もういいって…」頭を掻いて照れ隠しをする。
「…でも、もうケンカなんてしないでね?」
「うん。ごめん、もうしない。約束するよ」
「でも、ちょっと嬉しかったかな…? こんな事言っちゃダメだけど。
初めて本気で怒って、初めてケンカをしちゃったんでしょ?」
「…うん…」
「そんなに、怒ってくれるんだね。そんなに…大事に想ってくれるんだね。私の事。
ちょっと…嬉しい」声は徐々に小さくなるが、ちゃんと聞こえた。最後まで。
「美樹…」
気付けば俺達は身を寄せ合っていた。どちらからともなく。
誰にも邪魔させない。何者も遮る事は出来ない。
俺達は絶対に離れる事はない。美樹を抱きしめながら、俺は強く心の中で誓った。
良かったら「いいね」してください。誰でも「いいね」出来ます!