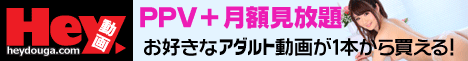学園風景&亜由美Hシーン
「あ、達也くん、今帰り?」
放課後、達也は廊下で亜由美に呼び止められた。
「そうだけど、どうしたの?」
「別に、ただ聞いてみただけ~」
そう言って笑ってみせる亜由美は達也の幼なじみだ。幼稚園以来、もう15年来の友達ということになる。
ただし特別な関係というわけではない。幼なじみで仲のいい友達。それ以上でもそれ以下でもない。
「亜由美ちゃんは部活?」
「ううん、今日は休み」
美術部に属する亜由美はその可愛らしいルックスで男子からの人気も高い。そんな亜由美と仲良く話せるというのは達也にとっても嬉しいことだったのだが…
「今日はソンヨンとデートの約束してるんだ」
今ではソンヨンの彼女というのが、達也にとってはどうしようもない『現実』だった。
「ねえ、ソンヨンがどこ行ったか知らない?」
亜由美が教室を覗き込むが、ソンヨンの姿は見えない。
「さあ…約束忘れて帰ったんじゃない」
ソンヨンの事を聞かれて面白くない達也は適当に答える。
「まさか忘れるわけないと思うんだけどなー……」
「お、小野じゃんか」
現れたのは悠樹だった。
「あ、神崎くん。ねえ、ソンヨン知らない?」
「ああ、ソンヨンなら職員室にいると思うぜ。何か先生と話してたな」
「そうなんだ、ありがとっ。じゃ達也くん、またねー」
安心したように亜由美は小走りで職員室の方へと行ってしまった。
「おーい、廊下は走るなよー…って聞いてないか」
平和な日常の、平和な光景。どこにでも見られるようなありふれた学園の一ページ。
そんな中、いつも通り元気のない男が一人。
「なあ達也、元気出せって。お前が亜由美ちゃん好きなのはわかるけどさあ」
「す、好きじゃないって別にっ」
「考えてもみろ。相手はソンヨンだぞ?お前が勝てる相手だと思うか?」
「だから別に何も思ってないって!」
否定するが、それが嘘だということは達也自身が一番よく分かっていた。
亜由美ちゃんが韓国人に盗られたという現実が、達也の胸を抉えぐる。
最初に亜由美とソンヨンが付き合ってると知ったときは、「なんで韓国人なんかと…」と思った。悔しくて悔しくてたまらなかった。そんな達也に唯一できることは、これは仕方ないことなんだと思い込んで自分を慰めることだけだった。
ソンヨンは凄い。自分なんかソンヨンに勝てる部分はひとつも無い。
日本人が韓国人に負けるのは、仕方のないことだから…と。
………………………………
数時間後、とあるホテルの一室。
長い足を投げ出すように枕にもたれかかって座るソンヨンと、うつ伏せになってその股間に顔を埋める亜由美の姿があった。
「んっ…んっ…んんっ…ちゅっ…」
亜由美がソンヨンのペニスを口に含み、懸命に奉仕する。
時おり漏れる声からは健気な必死さが感じ取れ、何とも言えず可愛かった。
「んっ…んむっ…んんんっ…」
亜由美にとってソンヨンは初めての彼氏である、もちろん抱かれたのもソンヨンが初めてだ。
ソンヨンに処女を捧げたのが3ヶ月前、それ以来こうして週1~2回程度のペースで2人は夜を共に過ごしていた。
「こらこら、歯がチクチク当たってるぞ」
「うう…ごめん……」
ソンヨンに言われるまま、教わるままに奉仕する亜由美。この舌使いも含め、ベッドの上での亜由美の『振る舞い』は全てソンヨンから教わったものだった。
「んむっ…んっ……」
目いっぱいに口を広げて太い肉棒を咥え、舌のザラリとした部分で惜しげなく亀頭を舐める。 時おり上目遣いで、愛する彼氏の顔を確認しながら。
「うん、気持ちいいぞ」
ソンヨンが亜由美の頭を優しく撫でると、嬉しそうにまた奉仕を再開する。
(…やっぱり日本の女の子は、可愛いな)
韓国人男性と日本人男性の優劣は比ぶべくもないが、女性は優劣が付け難いというのがソンヨンの考えだった。確かに脚の長さやスタイルの良さは韓国人女性に軍配が上がるが、一方の日本人女性は可愛らしい子が多く、魅力という点では決してヒケを取らない。
韓国人女性は綺麗で日本人女性は可愛い。ソンヨンが好きなのは後者だったりするのである。
「んふぅ…またおっきくなってる…」
ソンヨンのペニスが亜由美の口の中でさらに大きくなる。
「うん、もういいぞ」
そう言ってソンヨンが亜由美の頭を離すと、口から飛び出たペニスがバチンと勢いよく腹を叩いた。
亜由美の唾液にコーティングされた赤黒い亀頭が臍を隠し、腹筋の割れ目に食い込む。
「でもソンヨンのって、ホントに大きいよね…」
亜由美がついさっきまで自らの口で奉仕していたモノをさすりながら言った。
「はは、何を今さら」
「ねえ、韓国人のここって、日本人とは比べ物にならないくらい大きいんだよね?」
「ああ」
「で、ソンヨンはそんな韓国人の中でもかなりおっきい方なんだよね」
「そうだな」
「それってさ…実は普通に凄くない?」
「まあな」
「なんか…余裕って感じ?」
コンプッレクスなど何処にもない自信の塊のような男、それがソンヨンだった。世界一の教育レベルを誇る韓国で競争に勝ち抜き、18歳という若さで100人を超える日本人女性に種を付けてきたという実績が、溢れんばかりの自信を醸成していた。
「よいしょっ…と」
亜由美が枕元からコンドームを取り出す。
「でもこれ、いつも見てもすごいパッケージだよねぇ」
「わかりやすいだろ」
亜由美が手に取ったコンドームのパッケージには、デカデカと太極旗がデザインされていた。日本人と韓国人はペニスのサイズに違いがありすぎるため、日本人用には日の丸が、韓国人用には太極旗が描かれているのだ。
日本人用のLサイズよりも韓国人用のSサイズのほうが大きいことは言うまでもない。ちなみにソンヨンが普段使っているのは韓国人用Lサイズ、通称キングサイズと呼ばれるものである。日本で売られていながら、「この製品は韓国人をはじめとする外国人のためにつくられたものであり、日本人には大きすぎます。絶対に使わないでください」とまで記載されている。
そんな日本人には使用不可能なコンドームを、亜由美は慣れた手つきでクルクルと目の前のペニスに装着する。もちろんこれも、ソンヨンに教えられた技術だ。
「うんしょっ、と…はい。できたよぉ」
「よし」
ソンヨンがぐっ、と亜由美を引き寄せる。
「あっ…」
そしてくるりと亜由美の体を反転させ、後ろから腰を掴む。すると亜由美は全く抗うことなく、むしろソンヨンが挿入しやすいように両肘をついて尻を高く浮かせた。
「っ……」
ソンヨンはパチンパチンと尻を叩いてから、自慢のモノを入り口に擦りつける。挿入前のちょっとした挨拶のようなものだ。
「よし、濡れてるな」
指先で目指す穴の濡れ具合を確認してから、
グググッ、と力強く腰を突き出した。
「ヒッ…っ…………」
亜由美が目を大きく見開き、何かに耐えるような表情をした。ソンヨンにこれまで何度も貫かれ、今ではその穴はソンヨン用に強引に拡げられていたとはいえ、この挿入の瞬間ばかりはいつになっても痛みを伴った慣れない感覚が全身を襲うのだった。
「……」
一方ソンヨンは、亜由美の体が逃げないようにとその腰を強くひきつけ、冷酷なほどの無表情でじわじわと腰を進めていた。
「うっ…ぐっ…あっ……ダメっ…ちょっと…待ってっ…」
そんな亜由美の言葉を無視し、それどころか無意識のうちに逃げようとする亜由美の腰をさらにひきつけながら、ソンヨンはゆっくりと腰を進める。
「ああああっっ!!はああああっ!!」
一瞬大きな悲鳴をあげると、亜由美はハアハアと口で息をしながらだらんと体を前に倒した。
その隙にソンヨンは腰を送り込み、さらに奥深い場所を目指す。
「あはっ!…あはっ!…はっ…はああっ…!」
苦痛とも快感とも取れる息が連続して漏れる中、ようやくペニスが最奥へと到達した。
「ふぅ…俺のが亜由美の一番奥に当たってるのがわかるか?」
「あああっ!うっ、うんっ…わかるよっ…!」
ペニスが最奥まで届いているという充足感。そんな現代の日本人が忘れてしまった心地よい感覚をソンヨンはじっくりと楽しむ。
「あっああっ!!…ああっ!…うっ!うあぁっ、あっ、はっ、あああっ…!」
ソンヨンのピストンに合わせて小刻みに可愛い声が上がる。
「あっあっあっ……っあーーっ!…っっっ!」
より力強くねじ込むと、亜由美はベッドに身体を倒し尻だけを上げた状態になった。その格好は、強い男の精子を心から望んでいるようで。
「はうううっ…あんんっ…あうっ!!へぁっ、ああああぁぁっっ!!」
いろいろと動きながら形を変えて攻めると、その度に悲鳴に近い絶叫が響く。そんな姿を、ソンヨンはあくまで冷静に見下ろしながら腰を送り続ける。
相手が喘ぎ乱れるほどより冷静になるのが、このイ・ソンヨンという男のある種サディックティックな性さがだった。
「ああっ…!ああっ…!ああっ…!ああっ…!」
ドスドスと深いピストン運動に切り替えると、亜由美は早くも限界といった雰囲気。とはいえ日本人男性ならもうとっくにに果てているだろう時間が経過していることもまた事実だった。
「あっ、あっ、あはぁっ、あっ、ああっ、あはあぁっ!」
その後しばらくの間、亜由美は達也や他の友達には決して見せない姿をこの韓国人に晒し続けた。
日常1.オフィス
東応高校から2駅ほどの所にある小さなビル。
ビルという言葉を使ってもいいのかと思ってしまうほどこじんまりとしたその建物がある土地はもともと都の所有地だったのだが十数年前に某韓国企業に無償で貸し出されてからは、警察も都の職員も立ち入ることのできない『小さな要塞』と化した。
同様の場所は全国各地に何百と点在しているのだが、その実態は謎のベールに包まれている。わかっているのはそれらの場所で韓国人が何らかの活動を行っている、ということだけである。
「あ、ソンヨン君。お疲れ様」
ソンヨンが入ると受付の女性、カン・ハヨンが声をかける。
「あれ、今日はハヨンさん一人ですか?」
「ヘリンはちょうど休憩中よ」
「休憩中って、常に休憩中でしょここ」
「あはは、確かに」
笑いながらハヨンは同意する。実際フロアには2人以外に人影はなく、誰かが入ってくる様子もない。また、誰かが間違って入ってくるような設計にもなっていない。なのでハヨンの主な仕事はここで本や雑誌を読むことと言っても過言ではなかった。
「そういえば、この前ヘリンが怒ってたよ。ソンヨンの奴、最近はメールも全然返さないって」
「ははは、それはメールの内容問題なんじゃないですかね」
怒らせとけばいいんですよ、とソンヨンは笑いながら答える。
「ところで今日はどういったご用件?」
「ちょっと時間があったんで、スケジュール確認でもしとこうと思いまして」
「今はどのくらいのペースで種付けしてるんだっけ?」
「最近は週休2日のペースで、1週間で5人をローテーションって感じですね」
「さすが主席、真面目だね~」
ソンヨンは韓国一の名門であるソウル中学を主席で卒業した実績を持つ、文字通りのスーパーエリートなのだ。
「そういえば、日本人の彼女とはうまくいってるの?」
「まあ、一応は」
「あれ、何か歯切れ悪いなぁ」
「いやいや、うまくいってますよ」
「私の周りもみんな驚いてたよ。ソンヨンが日本人の彼女つくるなんて信じられないって」
「ははは…」
笑ってごまかすソンヨン。確かに韓国にいた頃は、日本人の彼女をつくることになるとは自分でも想像してなかった。
日本の女性は可愛い。日本の男にはもったいないレベルだ。それがソンヨンの結論である。
「夜は手加減してあげなさいよ。君の体は色々と凶暴なんだから」
「…知ったようなこと言わないでください」
苦笑いしながらソンヨンは差し出されたカードキーを受け取る。
「そうだ、今度受付の女の子たちで飲み会があるんだ。ソンヨン君も来ない?」
「受付の女の子で?」
「ヘリンはもちろん、ミンジにソユンに…スミンでしょ、それからソヒョンも参加するわよ」
「はは、考えときますよ」
「失礼します」
「あら、ソンヨンじゃない」
最上階(といっても5階だが)の一室。ソンヨンの突然の訪問にも、オフィスの責任者パク・ヨンアに特に驚いた様子はなかった。
「どうしたの突然?」
「少し時間があったんで暇つぶしに仕事の確認でもしようかなと思いまして」
「今日の仕事は?」
「時間がずれました」
言いながらソンヨンは適当な席に座り、デスクにあったパソコンを起動する。
「仕事のほうは絶好調みたいじゃない」
「そうですか?俺は別に普段通りですが」
「クライアントの評価は上々すぎるほど上々よ」
「それはよかった」
ヨンアが言っているのは、ソンヨンの種付けに対する相手女性からの評価のことである。韓国人が日本人に行っている種付けは政府が関与しているとはいえ、事業主体はあくまで民間企業だ。現在は10社を超える韓国企業が日本に現地法人を設立し、顧客(=日本人女性)獲得競争にしのぎを削っている。
「お、発見」
ソンヨンがパソコンに記録されている自身の評価を確認する。5点満点の評価、平均評価は4点台中頃だがソンヨンの平均評価値は4.8台をつけていた。
「これだけ評価されると、頑張った甲斐があったと思えますね」
「おかげでソンヨンへの依頼が殺到よ」
画面を切り替え依頼者のページを確認すると、そこにはソンヨンに種付けを望む希望者の名前がびっしりと並んでいた。
「それにしても…」その莫大な女性の数を眺めながらソンヨンが言う。「俺たちが来るまで、日本の女性はずっと我慢させられてたってことがよくわかりますね」
「確かにそうよね」
メスはオスと違い、一生の間に産める子どもの数が限られている。なので遺伝子学的な観点からも、メスはオスに比べてより遺伝子の『質』を求める傾向がある。
とはいえ、日本人女性のほとんど全てが自国の男に見向きもせず韓国人男性に群がるという光景は、異常という他なかった。
「この様子だと、全額自己負担になっても傾向は変わらないでしょうね」
種付けは医療行為とみなされ、その費用は全て税金で賄われている。それどころか韓国人の種付けによって子どもが産まれた場合には、500万円の一時金と月額5万円の養育費が20年間支給されることになっている。つまり女性は無料で種付けを受けることができ、出産後も手厚い保障が約束されているのだ。これらの制度は韓国政府の強い意向によって制定されたが、もちろんその費用を負担するのは韓国政府ではなく日本政府である。韓国人の子どもを産み、育てるために使われている税金は毎年1兆円を超える。
そんな『少子化対策』の結果、独身のまま韓国人男性に種付けしてもらい子どもを授かるというライフスタイルはもはや一般的になりつつある。いまや女性は独身貴族を謳歌しながら、金銭的な不安もないままに子どもを授かることができるのだ。昨年生まれた赤ちゃんのうち父親が韓国人であるという、いわゆる『韓流ベビー』の割合は統計を取り始めて以来始めて全体の4割を超えた。このペースでいけば3年後には過半数に達し、10年後には2/3を超えると言われている。しかも韓国政府は『日本救済』の名のもと派遣人員を今後も増加させていくという方針を打ち出しており、そのペースはさらに早まるという予測もある。
100年後には純粋な日本人は絶滅している…そんな声すらも聞かれるようになっているのだ。
「それはそうと」ヨンアがソンヨンに言った。「最近、ちょっと若さに任せて楽しみすぎじゃない?」
「とは?」
「評価自体は相変わらず高いけど、もう少し優しくしてほしいっていう意見もちらほら見られるわよ」
「ははは…」
ベッドの上での自分を省みてソンヨンは苦笑する。確かに最近は強引に好き放題やっている…気がする。
「ソンヨンのは大きいんだから、ちゃんと相手をいたわってあげないとダメよ」
「まあ、気をつけます」
ついさっきも同じこと言われたばかりだな、と苦笑いするのだった。
良かったら「いいね」してください。誰でも「いいね」出来ます!