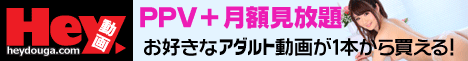・・木村が来てやがて二週間近くになる。
優子も木村と初めて会った時は、正直いって好印象ではなかった。
といっても、弟の雄一のように木村に対して薄気味の悪さとか、心を動揺させるほどの悪寒を
持ったというのではなく、女として異性として見た感じが、自分のの好みのタイプではなかったと
いうのが正直な印象だった。
痩身で肌の色も赤黒く、顎の細い精悍そうな顔つきに特別な違和感もなかったが、弟の雄一が
感じたのと同じように、何か人の心まで見透かしてくるような鋭い眼光には、少したじろぐものは
確かにあった。
が、母がすでに好きになっている男である。
自分の対象物ではないという事実が、優子の興味をさらに半減させていたから、しばらくの間の
ただの同居人と思うだけだった。
ただ、危惧することが一つあった。
年齢が自分とは四つしか違わないのだ。
その男が母の愛人としてだけならいいが?という危惧だった。
木村が家に来て数日後に、優子はすぐに母に尋ねた。
「お母さん、まさか本気であの人と再婚なんて考えていないわよね?」
少し詰問口調だった娘の言葉に、母の早智子はたじろぎの表情を見せながら、
「そ、そりゃ・・年齢のこともあるからお母さんも軽々しくそのことは口に出せないわ。彼ともそんな
話はしてないし・・・」
とそう応えた。
「恋人同士でずっといればいいじゃない?・・私も四つしか年の違わない人をお義父さんなんて呼
べないし」
ダメ出し的にそういって、母の二の句を遮るように優子は話を打ち切った。
母と木村が長く付き合うことに、優子自身は何も異論はなかった。
私は私でいつか自立し、きっとこの先誰かと恋にも堕ち、結婚して普通の生活をしていくのだと、
優子はそれこそ普通にそう考えていた。
身長は百五十五センチで、体重は身長から丁度百を引いた数字で、よくいえばポッチャリ型のや
や太めの体型だが、色白で顔も美人型の母親似で、その母親にはあまりない愛嬌もえくぼもある。
これまでに恋愛めいたことも何度か経験している。
勿論処女でもなく、男性経験も何人かはあった。
親を疎かにすることはしないが、自分は自分だと優子は思っている。
誰かに干渉されるのも、また干渉するのも嫌だった。
母は母で好きにすればいいというのが優子の考えだ。
母の恋人の木村にも、何の思いも関心もなかった。
まかり間違って木村を義父と呼ぶのが嫌なだけだった。
母と木村が男と女になって、夜の布団の上で身体を絡め合っている時の、特に母の喘ぎ声が、台
所一つ隔てた優子の室にも、雄一の室ほどではなかったがかすかに漏れ聴こえてきていた。
好き合った男と女が同じ布団に寝ているのだから、そうなるのは仕方がないと、優子はさもわかっ
たようなふりをしてやり過ごしていた。
ある日、母の一際高い声であからさまに男女の性器をはしたなく交互に呼び続ける声を聴いた時、
心の中でひどく母を蔑んだことがある。
娘から見ても普段は理知的でそれなりの節操も備えていると思っていた母だった。
優子は思わず耳を塞いだ。
しかしその後、ベッドに寝ていた優子の身体に異変が生じた。
母のはしたない声を耳にして、唐突に身体の奥底のどこかがズキンと疼いたのだ。
その疼きが何なのかは、間もなく全身の体温が上がり始めてきていることで何気にわかった。
これまでにも何度か体験している自慰行為が頭に浮かぶ前の、予兆の時のようなそれは妖しい疼
きだった。
長い期間、優子は自慰行為に耽ることはなかった。
母のいつまでも終わらないはしたない喘ぎ声で、優子の女の身体の導火線に唐突に火が点いたの
だった。
ベッドの中で片手が嫌々ながらという動きで乳房に触れた。
優子の乳房はそれなりに豊満である。
頬のえくぼもそうだが美形の母に勝てるのは乳房の豊かさもそうだった。
手で乳房を交互に撫で擦るように揉む。
体温がさらに上がってきているような気がする。
手がパジャマのボタンを外しにかかる。
その手が乳房の柔らかい肌に直接触れる。
「はぁ・・・」
と布団の中で小さく声が漏れる。
乳首をなぞるように摘まむと、すでに固いしこりになっていた。
乳房を揉みしだきながら、身体を少し折り曲げるようにして、優子はもう一方の手を下腹部のほうへ
下げていった。
その手はいきなりショーツの中に入った。
指先に恥毛の感触があり、すぐに割れた肉襞に到達した。
肉襞を割り開いた指が、中から溢れ出た滑りとした液体の洗礼をしとどに受ける。
体験的にいうと、優子は行為の時の愛液は激しいほうだ。
「あぁっ・・・」
自分のその部分から溢れ出た愛液の激しさを指に感じ、それが優子の気持ちをさらに昂めた。
居間で母を抱いている木村の顔が唐突に優子の頭に浮かんだ。
どうして?
と自問自答して、急いで頭の中から木村の赤黒く精悍な顔を払しょくしようとする優子だが、その思
いとは裏腹に彼の顔が鮮明になった。
まるで自分が母の恋人である木村に抱かれているような錯覚に優子は陥っていた。
乳房を揉み続ける手と、下腹部の恥ずかしい個所を上下に何度もなぞるように擦る手の動きが早く
強くなり出していた。
相手はもう木村でよかった。
今の優子には恋人もいない。
職場も含めて自分の周囲に男性を意識させる人間は皆無に近かった。
木村の切れ長の目や尖った顎がさらに鮮明に、優子の閉じた目の中に浮かんでいた。
「あぁっ・・き、木村さん・・」
と優子は木村の名を呼んで全身で喘いだ。
そこに母の一際高い声が耳に入った。
「お、お尻・・・木、気持ちいいっ!」
夥しく濡れそぼる下腹部の愛液が、さらにどくんと一つの塊のように溢れ出たような気がした。
「あぁっ・・・き、木村さんっ・・・ゆ、優子にも」
わけのわからない気持ちになって、優子は布団の中で屈めていた身体を逆海老のように一気に反
らせた。
優子は汗にまみれて上気した顔を、まるで息絶えるようにがっくりと項垂れさせた。
その夜から優子は深夜になると、これまでとは違う行動をとった。
母と木村の情交は二人がいる時は、ほとんど毎夜繰り返された。
自分の体内から溢れ出した恥ずかしい愛液で、優子は先夜、ショーツだけでなくパジャマのズボンと
布団のシーツまでを夥しく濡らせてしまった。
ベッドの下腹部のあたりにバスタオルを敷いた。
そして優子は全裸で布団の中に入り、それまでは冷静にただ聞き流すだけだった母と木村の情交の
声に耳と神経を集中させるようになったのだ。
そして優子は母と木村の情交に呼応するかのように、淫らな自慰行為に溺れた。
もう一つの変化は、家の中でたまに鉢合わす木村を見る目も変わった。
それまではほとんど無視に近い状態で、言葉を交わすこともなく接していたのだが、時折、木村の背中
や顔に短く視線を向けることがあった。
狭い台所で木村とすれ違ったりした時、それまでは全然気にもならなかった彼の煙草の臭いまでが鼻に
つくようになった。
木村を好きになっている?
そう自分に問いかけると、木村は母の恋人という事実が、頭を否定に向かわせる。
しかも木村はもうしばらくすれば、この家からいなくなるのだ。
どうして自分がそうなってしまったのかは優子にはわからなかった。
そういえばあの自慰行為に思わず耽ってしまった時、私は生理の始まる前だった。
生理前症候群?
確かにあのあくる日の昼に生理が始まったのだ。
だからあれから後の自慰行為も、乳房を自分で揉みしだくだけの日が数日続いた。
優子はそう無理に思い込むことにして、木村のことを優子は深く考えようとはしなかった。
そんなこんながあって木村が来てから、正確にいうと十二日目の午後だった。
その日は優子は先週の休日出勤の代休で、母も木村も弟の雄一も仕事に出かける時はまだベッドの中
だった。
夕食を会社の同僚と一緒にするという約束以外、何も予定のない一日だった。
昼近くまで優子はベッドの中でむさぼり寝た。
何かの物音で優子は目を覚ました。
玄関のドアの開くような音だった。
寝ぼけ眼のまま優子はベッドから上体を起こした。
玄関の鍵は家族しか持っていない。
母か弟が何かの用で帰ってきたのか?
室のドアのほうに目をやってしばらく様子を見た。
母か弟なら声をかけてくるはずだ。
廊下を歩く足音が聴こえた。
優子の室を通り過ごして、足音は台所のほうにあっけなく消えた。
もしかして泥棒? いや泥棒の足音ではない。
寝惚けていた目が一気に覚める。
優子は緊張した面持ちでベッドの上にしばらく座り込んでいた。
数分が過ぎて廊下を歩く足音がした。
玄関口のほうに近づいてくる。
誰かは知らないが玄関を出て行くのか?
足音が止まった。
「優子・・ちゃん?」
思わず心臓が止まりそうになる声音だった。
考えてもいなかった男の声だった。
木村の声だ。
木村がどうして? 鍵は持っていないはずだ。
優子の心臓の高まりはさらに増した。
息が詰まりそうでしばらく声が出せなかった。
木村がもう一度優子の名を呼んできた。
精悍な顔つきとは不釣り合いなくらいに柔らかい声だった。
「は、はい・・?」
ようやく優子は息を整え、かすれた声で返事を返した。
「俺さ・・家に免許証と財布忘れてな・・で、お母さんに家の鍵借りて取りに来たんだよ」
「・・そ、そうですか」
「それで、優子ちゃんが今日は休みで家にいるって聞いたから、ちょっと似合わねぇんだけど、マロンヘッセ
のシュークリーム買ってきたんで、食べないかな?って思って」
思ってもいない木村の言葉だった。
マロンヘッセというのは市内にある洋菓子店で、そこのシュークリームが優子の好物だった。
多分、母からの入れ知恵だというのはわかる。
「そこのフルーツジュースも買ってきたから・・・どう? よかったら一緒に食べないか? こう見えて俺も結構甘
党なんだよ」
またしても木村からの予期せぬ言葉だった。
優子の胸の高まりはまだ静まってはいなかった。
「・・あ、後で頂くから・・冷蔵庫に」
優子はどうにかそう言葉を返した。
「一緒に食べよう。もう昼だし・・・それに、ちょっと話もしたいし」
木村の声音はずっと穏やかで優しいままだった。
それから二度ほど、優子は木村からの誘いをそれとなく断ったのだが、彼は諦めることなく柔らかい声で誘
い続け、根負けするかたちで、
「・・じ、じゃ・・・着替えますから」
と不安な気持ち半分で承諾したのだった。
この時期の普段の部屋着ならTシャツと短パンだったが、優子は無意識ながら、ジーンズと長袖のシャツと
カーディガンに着替え、ウエットティッシュで顔を拭いて化粧を終え、静かな足取りで室を出た。
台所に入ると居間の戸は開いていて、炬燵机の上に紙袋から出されてシュークリームとフルーツジュースの
カップが並べて置かれていた。
机の長い部分に作業服の上着を脱ぎTシャツ姿の木村が、薄い唇から白い歯を覗かせて精一杯の歓待の表
情で、座ったまま身体を振り返らせながら迎えていた。
「すみません・・」
緊張の表情をまだ崩せないまま、優子は室の中に入り、敷かれている座布団の上にゆっくりと腰を下ろした。
木村を斜め右前に見る位置だった。
優子は長く木村の目を見ることができないで、ハスキーな優しい声で気遣うように話しかけてくる木村に短い
相槌的な言葉で応えるだけだった。
優子が机に置かれた柔らかいシュークリームとフルーツジュースに手を差し伸べたのは、少し時間が経ってか
らで、木村は終始柔らかい気遣い口調で他愛のない口調で喋り続けていた。
優子の緊張がほぐれ出したのは一時間近く経ってからのことだった。
木村は自身の今の仕事のことや母と知り合った経緯などを、所々で屈託のない笑顔を見せながら、変わらぬ
柔らかい口調で話した。
母との交際のきっかけは、母の勤務する老人ホームへの出入りもあったが、ある時市内の山裾の道での偶然
の出会いがあってからということだった。
雨のひどく降る日で、母が在宅訪問の帰りで、木村も配送の途中で、母が車をエンストさせて途方に暮れている
時に出くわしたというのだ。
車の修理は十分ほどで木村が直してくれたのだが、雨で服がずぶ濡れになった彼を母は自分のホームまで連
れ帰り、代わりの着替えを用意してくれたのが交際のきっかけだということだった。
フルーツジュースがなくなりかけた時には、優子もかなり打ち解けた気分になっていて、木村の巧みな話術で男
女の恋愛論まで話は及んでいた。
窮屈に正座していた優子の膝もいつの間にか崩れていた。
「優子ちゃん・・・」
唐突に木村が姿勢を正すように座り直してきて、急に真剣な眼差しになっていってきた。
「はい・・?」
「こんなこというと・・・優子ちゃんに怒られるかな?」
「え?何ですか?」
「いや、やっぱり・・止めとくわ。・・ごめんな」
「気になるわ・・いいからいってください」
そんな会話が数回続いた後で、木村から出た言葉に、優子は思わず声を失った。
「君のお母さんと、こんなことになっていて・・・いいにくいんだけど」
と言葉を一度切ってから、
「俺さ・・・優子ちゃんと初めて会った時からね・・・君のことが・・何ていうか・・好きになったっていうのかな」
と真剣な目で優子を見据えながらいってきたのだ。
まるで予期していなかった木村からの思わぬ告白に、優子は声を失い忽ち首から上を赤く染め狼狽の表情を露
わにした。
木村からの突然の告白に、気恥ずかしさに顔を俯けたままにしている優子が時折顔を上げると、彼の切れ長の
目はいつも優子を正視していた。
彼は優子への思いを、その風貌容姿とはまるでかけ離れたような穏やかな口調で、饒舌にゆっくりと言葉を切って
彼女に向けて話した。
優子はしかし木村の言葉のほとんどを覚えていなかった。
狼狽と動揺がさらに増幅し、平たくいえば優子の気持ちを完全に舞い上がらせていたのだ。
それはまるで木村から催眠術にかけられているようだった。
ふと気がつくと、優子のすぐ前にまで木村が迫っていた。
木村がつけているのかコロンのような臭いが、優子の鼻腔をかすかに刺激した。
座ったまま後ずさりしようとした優子の片手を木村が握った。
骨ばった木村の手の感触が、優子の手を通して蜂の針のように彼女の心を痺れさせていた。
優子は木村の手を強く振り払うことができなかった。
木村の上体が素早く動き、顔が一気に優子の顔の前に近づいていた。
木村のコロンの臭いがさらに強くなり、それに混じって整髪料かトニックのような臭いまでが、優子の鼻腔にさらに強
い刺激を与えてきていた。
キスされる!
優子は咄嗟に身の危険を感じた。
しかし何故か顔を反らせることも、身体を後ろに引くこともできなかった。
他愛もなく優子の唇が木村の唇で塞がれた。
木村の片方の手が優子の後頭部に優しくかかっていた。
木村の舌が優子の口の中へゆっくりとした動きで侵入してくる。
歯を擽るように木村の舌は優しく動いた。
優子の脳裏に突如、母の夜の時のはしたない喘ぎ声が思い浮かんだ。
そして母のその声はすぐに消え、優子の夢想が勝手に膨らんだ。
母の熟れた身体を激しくつらぬいている木村の精悍な顔と、まだ見たこともない引き締まった裸身が浮かんでは消え、
消えては浮かびしていた。
塞がれた口の中で、優子の歯を割って木村の長い舌がいとも容易く侵入してきた。
簡単に優子の怯え気味の舌は木村の舌に捉えられた。
舌を舌で長く弄ばれ息がしにくくなっていた優子の無防備だった乳房に、木村の手が唐突に伸びてきた。
「ううっ・・・」
優子は一瞬だけ目を大きく見開き、呻くような声を上げて、それから意識を失くした・・・。
つづく
良かったら「いいね」してください。誰でも「いいね」出来ます!