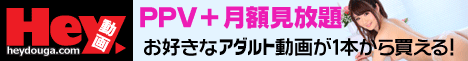天使の子守歌
1
山本里子は硝子戸を開けて眼下に展がるコンビナートの灯りにぼんやりとした眸をおとす。そこには、何千と言う光が、まるで恐山の夕暮れに燃える霊を招くローソクの火のように見える。その灯りは命を持ったように揺れている。風が走り炎を滲ませているのだ。灯りが揺れているように見えるのは、里子の眸が涙で潤んでいるからかも知れない。里子はあと少しで三十になろうとしているが、小柄で肉付きがいいから二十四五にしか見えない。頬に小さく沈む笑靨と僅かに斜視している眸が、可愛らしさと艶めかしさを漂わせていた。
ー辛いわ・・・こんな時、子供達がいてくれたらどんなに気が紛れるだろう。
母のところに預けている子供達のことを思う。新しい熱い涙が溢れ頬をつたっている。里子は涙をぬぐおうともせずに眺めている。その眸に灯りが溢れている。肩が小刻みに上下している。西から吹き上げてくる風は、工場の煙と化学製品からでる独特の饐えた匂いを、里子の住む小高い山に林立する市営住宅へと這い上がらせてきていた。裏山の木立が、枝葉を擦り合わせる悲鳴がしていた。
-あの灯りが夫を奪った。あの事故さえなかったら・・・。
二年前に製油所の脱流装置が爆発したときに巻き込まれて死んだのだった。下請けの社員だった夫は、僅かの慰謝料で命を引き換えたのだった。
高校を出て医院に勤める傍ら、看護婦の勉強をしていた里子の前に、夫は白馬に乗った王子さまのように現れた。直ぐに恋に落ちた。男が出来ると、最初の目的は消え、男との家庭を夢見るようになった。この人の赤ちゃんが欲しいと思うようになった。それは、里子が父のない家庭で育ったと言うことがそう思わせる原因になっているのかも知れなかった。小学校の時に、父は亡くなっていた。兄が父の役を担ってくれたが、やはり父のようには行かなかった。兄も結婚すると、構ってくれなくなった。異性に憧れる、その気持ちは強かった。父のように、夫のように優しくしてくれる男が欲しかったのだった。山本潤二は、里子の男性観にぴったりの男だった。とくかくわがままを包むように受け止めてくれた。看護婦の国家試験に落ちたのを機会に身内だけを呼んで形ばかりの式を挙げた。欲しいと思っていた子供は中々出来なかった。だけど、毎日毎日が彼女に取ってはかけがいのない日々であった。幸せと言う思いで見る世の中が総て美しく色鮮やかに彩られて見えた。二十三の時に、初めて懐妊した。優しかった夫が前にもまして優しくなり、里子の身体を気づかってくれるようになった。なんだかこの幸せが怖いように思えた。最初の子が出来て一年が過ぎ次の子が産まれた。四年間出来なかったのが嘘のように出来始めると怖いくらい妊娠した。年子では育児に困ると言うので、長男と次男の間に出来た子は中絶をした。夫は産むように言ったが、長男を産んだ後、里子は産後に体調を崩していたので首を縦には振らなかった。夫も里子の気持ちを判ってくれ中絶をしたのだった。次男を産んで一年目に、夫は事故に巻き込まれたのだった。賑やかであった家庭が火の消えたように静かになったが、それを知らない子供達ははしゃぎまわっていた。その姿を見る度に余計に哀しみが溢れてきた。人間の命がこんなに安いものだと言うこともその時に知った。途方に暮れた、前途が灰色の雲で覆われているのを感じた。
冷たい風に晒されベランダに立っていた里子の耳に、階下から嬰児の泣く声が立ち昇るように聞こえてくる。耳を傾ける。その泣き声はどこか身体の調子の悪い子供が母に訴えようとしている響きがあった。三階なら、狐のような顔に厚く化粧を乗せた口やかましい民子の部屋だ。あの人は子供の泣き声で体調の変化の判る母親ではない。別の部屋であって欲しい。
-子供達は元気だろうか・・・。
三歳と五歳のやんちゃの盛りでもある。スキンシップを一番大切にしなければいけ時期でもある。来年は下の子が幼稚園、上の子が小学校。子供達を引き取ってと里子は胸の裏に想いを馳せる。その想いは一層焦燥感と現在の立場を不安にさせる。
里子は一ケ月に一度は母のもとに預けている子供達に会いに帰っていた。もうその一ケ月が来ようとしているのだ。次の土曜日には帰ろう、でも、母に兄にどのように言えばいいのだろうか。お金を持って帰らなくては母も困るだろう。兄は良い顔をしないだろう。そのお金がないのだ。心も足も重い。子供達の笑顔が遠のく。逸る気持ちも萎んでしまう。もう雪が覆っているだろう。子供達に真新しい手袋の一つも買ってやりたい。が、ホームヘルパーの給金は安く生活費と付き合いで殆どが消えてしまう。だけど、その中から少しずつ食べる物を切り詰めて貯金をしていたが、来年の事を思うとどうしても礼服が欲しく、安かったからついつい後先の考えなく買ったのだった。そのために子供への送金まで手を付けてしまっていた。
「うちが元気な内はどうにかおまえの子らの面倒もみてやれる。が、もう年じゃけえなぁ。息子や嫁の顔色をうかごうて今じゃ小そうなって暮らしとる。うちは辛い。内孫と外孫が喧嘩をして、内孫が悪いとわかっとっても外孫を叱らにゃならん・・・。物の分別が判るだけに里子の子供達がどのように育つか心配でならん。一日も早う引き取ってくれ」
前に帰った時に母が涙を浮かべて言ったのだった。
「うん。私しだってどうにかしょうと一生懸命なんよ。もう少し待って」
その時、母にもうこれ以上甘えられないと思ったが、哀願したのだった。
「里子、今は昔のように町へ出稼ぐことものうなった。山に苗木を植え、僅かの水田に米を植えても食えりゃせん。今年一杯はどうにか世話をしてやるけえ、来年は引き取ってくれ。小学校に幼稚園、そうなりゃおまえの元に置くほうがええ。うちの奴もこの頃では川ぞいの町に出でパートをしとるんじゃ。スーパーで馴れんレジーを打っとる。それでようよう生活しとるんじゃ。早うええ人を見付けて再婚するか、子供達と一緒に生活が出来る金が貰えるところへ勤めてくれ」朴納の兄が重い口を開いて言った。
「うん、考えとるんよ。来年の春までにはどうにかしょうと考えとるんよ。・・・でもな、看護婦の免許でもありゃ・・・。なんの特技も身に付け取らんけぇ・・・」「夜の仕事があろうが」
「それは考えたわ、でも子供達のことを考えたら」
「里子、別れて寂しい思いをさせることと、子供達と一緒に生活することとを・・・」
「私は」
「誰も好んで夜の仕事はしてはおらんじゃろう。が、そうせいでは一家が一緒に生活出来んから、食べてはいけんから」
「おにいちゃん、夜二人の子供達を部屋に残して・・・。私はどんなに貧しゅうてもかまわん、一杯の粥を啜りおうても子供達との時間を大切にしたいんよ」
「だったら尚更じゃろうが。ここにおいとっては余計にその時間は持てまいが。子供達に取って何が一番欲しいか、親の愛じゃ。親の姿じゃねえど。生活するために何をして稼ごうが・・・」
「私は怖い。子供達の目が・・・」
「それは違う。子供達のために働く、そのことが母の生き方なら子供は・・・。そう考えるおまえの心の方が働く人を差別しておる事になるぞ」
「うん、判った。ように考えてみるけえ」
優しく諭すように言った兄の言葉に対しても、里子は何らかの答えを持って帰らねばと考えていた。この一ケ月近く考えたが、結論は出ていないのだった。ホームヘルパーを辞め、ホステスになることはたやすいが、果たして自分がホステスに向くかと考えると勇気がなかった。
ー辞めたい。
里子は遠くへ眸差しを投げて呟く。心の迷いがヘルプに戸惑いと自信のなさで現れていた。一つ一つが心に引っ掛かり前に進めなかった。いつもなら笑って済ませられることも、自己中心的に物事を考え相手の行動がどこから出てきているか、その心を見付けようとはしなかった。
今朝起きた時、里子の心は重かった。安木老人のところにヘルプに行く日になっていたからであった。安木老人は最初の頃は里子の行うヘルプに総て手を合わせて感謝の心を現していた。上品な顔立ちで、白髪の頭を丸く刈り、いつもきちんと着物を着ていた。言葉遣いも礼儀正しく、穏やかな目は潤んでいるような輝きがあった。だんだん馴れてくると、里子を見るその目の光が少しずつ変わってきた。それは男が女を見る欲望の色に代わり、里子は裸を見られているような恥ずかしさを感じるようになった。それで、いつしか身を庇うと言う本能が芽生え始めていた。怖い、そう思うとヘルパーは勤まるものではない。だから、その視線を避けるようにしてきたのだった。
里子はホームヘルパーとして七名を担当し、その人たちに週二回の宅訪スケジュールを消化しなければならなかった。先週のこと、安木老人はじっと里子を見詰め、「里子さんはいつ見ても美しいですのう。女の盛りと言うところですなぁ。他の男がほっとかんじゃろう。その白い肌が男を狂わしよるじゃろう。そんな人に介護してもろうて私は本当に幸せ者じゃと思うておりますんじゃのじゃ。いつもすいませんな・・・」
と言いながら手を握りに来たのだった。
「この手は一体誰の手なのかしらね。もう悪戯が出来ぬように縄で縛っておきましょうかね」
と、以前の里子なら軽口を叩いていなすところを、厭らしいものでも避けるように払ったのだった。そのようなことがあったし、今日は安木老人を風呂に入れる日に当たっていたので、余計に憂欝だったのだ。鏡に映す顔が何だか暗く見え、少し濃い目に化粧を乗せたのだった。生活の苦労が心の在り方を換え、余裕のなさが不信感を産み出していた。それが表情にもろに出て、硬く生気のない顔にしていた。
安木老人だけは違うと考えていただけに先週の振る舞いは意外であった。他の老人達は、里子に隙があれば手を握ろうとしたり、お尻を、乳房を悪戯しようと狙っているだけに油断をすることはのだが、安木老人だけはと心を許していただけに腹が立ったのだった。里子はその日安木老人を邪慳にしたことを少し後悔した。そして、仲よくしなければと考えたのだが、裏切られた思いはぬぐいさることは出来ず心に沈殿した。
ーやはり安木さんもただの男なんだわ。
と里子は認識を新たにしようとしたが心に引っ掛かるものがあった。それは何か里子にも判らなかった。ヘルパーは心を閉ざしては出来るものではない。互いに心を開き見せ合って始めて本当のヘルプが出来るのだ。
ーああ、私は疲れている。でも、私を待つていてくれる人達がいる。このことが、あの人の夢だった。
「金を貯めて老人の人達のユートピアを造るんだ。リハビリーの設備やいろいろのカルチャーセンター、出てもいいし入ってきてもいい自由なんだ。僕は物療士で、君は看護婦で、安心して過ごせる場所なんだ。人間が人間として、生きて行ける所なんだ。水が飽くまで澄んでいて、空気も色なんかない綺麗なものなんだ。太陽が作る日溜りで老人が日向ぼっこをしているんだ。いつも笑いがはじけているんだ」
眼をきらきらとさせてあるときこれが夢なんだと言って里子に語ってくれたことがあった。その時の夫の顔が楽しそうであったことを思い出すことが出来る。
ーやらなければ、私はその夢の一かけらを担っているんたから。
里子は鏡の中の自分に言い聞かせるようにして立ち上がった。
安木老人は先週のことなど忘れたかのような顔で迎えてくれた。眼が笑っていた。里子は努めて平静を装いいつもと変わらぬ態度で接した。風呂を沸かし、洗濯物を洗い、掃除をし、食事を作る。短時間に色々なことを一辺にしなくてはならないのだった。
安木老人は交通事故の後遺症で半身不随になっていた。が、右手と右足は使えたので、里子が行かないときには壁を伝ったり、松葉杖を使ったりした身の回りの事はしていた。里子は安木老人の体調を看て一週間に一度湯を使わせるのだった。一人で風呂に入り転んでそのまま寝たきりになることもあるので、先に先に湯を使わせるようにしていた。その日以外は湯に浸したタオルで丹念に全身を拭くのだった。
里子は安木老人に肩を貸し、腰を手で支えながらゆっくりと風呂場へ向かった。
「すいませんの」と優しく口にする言葉の裏で肩から乳房に手が降りていた。里子はピクンと身震いがしたがここで逃げるとひっくり返ってしまうのでなすままに任せていた。
「里子さんの匂いは何とも言えませんな」
安木老人は鼻を啜りあげて匂いを嗅ぎ回っていた。里子は腰に回した手の力を抜いた。安木老人は前につんのめりそうになった。里子は急いで力を入れた。その拍子に安木老人が獅噛み付いてきた。そして、手が里子の腰に回り確りと抱き込まれた。体臭と体温が里子に伝わってきた。
風呂場までその姿勢で連れていき、脱衣所で安木老人の寝衣を脱がせた。パンツが僅かに持ち上がっていた。今までにもこのようなことはあったがそれを嫌らしいと思って見たことはなかった。だが何故か里子はそれを意識して急いで眼を反らせた。
「まあ、おじいちゃん元気の良いこと。これで何人の人を泣かせたのかしらね」
と今までは冗談も言えたのに、その軽口は出なかった。手を湯の中に入れて掻き混ぜながら加減を見た。手桶に湯を汲み肩に流してタオルに石鹸を付けて洗った。
「里子さん、前も洗ってくださらんかの」
安木老人の歯の抜けた口元が緩んでいた。
「おじいちゃんが洗ってください」
里子はきっぱりと言った。
「そう言わんと」
安木老人は起用に身体を動かせて前を里子の方に向けた。
「仕方がないわね」少し躊躇したがそう言って、首筋から胸へ腹へと下に向けて洗った。ー七十にもなっても未だ元気なのね。若い男のとは違って、老人のは・・・。 里子はそう思いながら見た。しばらく手を止めた。
「どうです。男と言う動物はいつまで経っても性欲は枯れませんのじゃ・・・。里子さんのように美しゅうて色気がある人に見られていると余計にこいつは張り切りますんじゃ・・・。男は哀れですの」
安木老人はそう言ってふと寂しいそうに眼を伏せた。ーそうよ、まったく。もういい加減に男の役目を終わらせてあげればいいのに。静かに余世を送らせてあげればいいのに。
と創造主に対して呟いた。そして、起立する男根を洗った。
「もっとゆっくり、丁寧にやって貰えませんかの」
恍惚とした表情をしている安木老人の声が口から漏れて、エコーのように響いた。
里子は身体が熱くなってくるのを覚えた。この二年間孤閨を守り男を迎え入れたことがないのだ。性欲もある。女の喜びを知った健康な身体なのだ。
「おじいちゃん、我がままを言わないでください」
里子の声は掠すれた。
「でもな、こいつが未だ役に立つと思うと生きている望みが湧き、まだまだ大丈夫じやと言う気力が起き、生きる希望が持てますのじゃ。こいつがこのようにならんようになったらと思うと、そん時のことを考えますと、生きておる意味がのうなりますのじゃ・・・。じゃけえ、男は悲しいですの」
寂しく定まりのない瞳を宙に泳がせながらしみじみと言った。
里子は嫌らしいと言う感情は何処かに消えて、憐憫の情が頭を持ち挙げてきた。手の中で包みゆっくりと泡の中でほぐすように洗っていた。
「ええ気持ちですらあ。ひっさ忘れておった喜びですらあ。いつも思うておったことです。男が考えていることは、それも私のような年寄りが考えることは、女を自由にすることと、何時お迎えが来るかと言うことでしての。夜一人で寝とりますと死への恐怖が忍び寄って囁きますのじゃ。早う来い、早う、天国はいつも花が咲き乱れ、全裸の女が舞い踊り、まるで竜宮城じゃとの。・・・でもそれは死への甘い誘いでの、たわごとでの。・・・やはり生きとってこの腕で胸で女を抱き締めたいと考えにゃあ、夜は寂しゅうてなかなか寝つかれませんわの。・・・男はさもしいですの。煩悩の虜になって」
安木老人の詠うような切なげな吐露が続いていた。
「おじいちゃん、そんなことばかり考えていないで、気晴らしに庭に出て歩いたり、本を読んだりしていなくては、身体も頭も駄目になりますわよ」
里子の口から優しさに溢れた励ましに言葉が出ていた。
「そうでしょうな・・・でもな、里子さんのことを考えると何も手につきませんのじゃ。明日は来てくれると思うと、前の日から心が浮きたってなかなか眠られません。まどろんだと思ったら、里子さんの夢を見とるんじゃ。近頃ではお恥ずかしいことですが、毎晩のように夢を見ますのじゃ・・・。男は情けないですの」
安木老人の瞳が哀願しているように光っていた。里子はその言葉に引きずられのめり込みそうになった。心はさざ波がうち寄せるように揺れていた。それはホームヘルパーとしての感情ではなく一人の女の母性のようであった。
安木老人の身体にくまなく湯をかけて泡を流し、
「さあ、湯に入りましょう。ゆっくりと温もってください。私はお布団をしまい、床を敷いておきますからね」 と言って安木老人を立たせて湯舟に入れ立ち上がろうとしたとき、安木老人の手が里子の手を掴んでいた。
「おじいちゃん、いけませんよ」
と強く戒め、手を振り払おうとしたが安木老人の力は強く里子の身体のバランスが崩れた。里子は湯舟に落ちそうになった。その拍子に洗い場に転んでしまった。慌てて立とうとしてまた転んだ。衣服は濡れてしまった。安木老人の染みの浮いた手が里子の乳房を強い力で掴んでいた。逃げようとして身をよじった。スカートがめくれ肉付きのよい白い大腿があらわになった。そこえ安木老人の手が忍び込んだ。その動作は半身不随の人かと疑るほど早かった。ああっと思う間の出来事であった。
「おじいちゃん、なにをするんですか」
里子は逃げようと身をかわしながら言った。
「すいませんの、少しの間です・・・。許して下され・・・綺麗ですの、滑らかですの。・・・男はだらしがないですの、しょうがないですの」
落ち着いた声であった。
「おじいちゃん、やめて・・・。こんなことをするとここには二度と来ませんよ」
里子は安木老人の手を叩きながら言った。
「そう言わんと、年寄りを可哀そうじゃと思うて・・・」安木老人は里子の言葉に耳を貸さずに、手を里子の身体に這わせながら言った。手から逃れようと身をよじればよじるほど、それは指の動きに反応している恰好になった。
ー私の女が男を欲がっている。
陶酔が心とは裏腹に身体を痺れさせていた。足先に力が入り、頭がファとしていた。
「この身体は宝物じゃ、神と仏が創りたもうた至高の美じゃ。・・・男はいつまで経ってもその美を凌辱する獣じゃ」
里子の耳に安木老人の吐息が吹き込まれていた。その言葉を消えそうな意識の中で聞いていた
ーどうしょうと言うの、どうすればいいの。これでいいの、このままでいいの。きっといけないわ・・・。
里子は混濁の中で呟いたが、それは頭の中にある理性の戸惑いと、快楽との葛藤が呟かせたもののようであった。
「勘弁して、これ以上進んだら、おじいちゃんも私も駄目になるわ」
里子は首を振りながら理性を呼び覚まさせてそう言い、跳ね退けて逃げた。
冷たい大気が衣服を通して肌を撫でていた。が、身体は火が点いたように熱かった。里子は呆然と庭を眺めていた。風が立ち、庭に転がる枯れ葉を舞い挙げていた。木立ちの影が足元に落ちていた。
「里子さんどうにかしてください。もう私は伸びそうじゃ」
安木老人の声で里子は我に返った。早く出してあげなくては、のぼせたら大変。里子はホームヘルパーに返っていた。安木老人は、真っ赤な顔をして湯舟につかっていた。
「もう悪戯はしませんね」
「ああしません。このとおりじゃ・・・・。男は惨めですの」
安木老人は、叱られた子供が顔の前に手を合わせて謝る仕草をした。
里子は安木老人に手を貸して湯舟より出し、洗った衣服を着せた。
「里子さん、すいませんの。勘弁して下されの、ついつい魔がさして・・・。男はいつまで経っても駄目ですの。灰になるまでこの思いはどうにもならんのですかの。・・・男は辛いですの」
布団に横になった安木老人は庭の景色を眺めながら言った。里子にはその姿が哀れに映った。
里子は自分に油断がありつけ込まれる隙があったことを自覚していた。子供のことで焦っている。心が定まっていない。今までにはこのような事はなかったと考えていた。
身を刺すような風を肌な感じ、里子は硝子戸を閉める。里子は安木老人の立ち振る舞いに腹がたっが、むしろ、自分の女の性を辛いと思い哀しいと思うのだった。
ーあなたがいれば、こんなとき・・・。あなたが欲しい・・・。愛されたい。
里子はそう呟いた。新しい涙が眸に溢れ、頬に流れる。硝子戸の向こうに夫の顔が映っているように見えた。
ホールヘルパーは一人暮らしのお年寄りへのヘルプが殆どであった。今日のように安木老人とまでは行かないが、貞操の危険を感じたことはしばしばであった。男と女がいれば、そこには理性を乗り越えて介在してくる誘惑の衝動がうまれてくることは歴然としていた。一日中なにもしなくて布団の上に身を横たえ考えることは、嘗ての生きてきた過去の思い出でありその中で遊び疲れると、今度は命のある限り果たそうとする性への本能の闘争なのである。
「今真剣に考えなくてはならないのは、お年寄りのセックスなのよ。その事を考えないで老人福祉は出来ないところまできているのよ。若い人の考えで性欲はないとか汚いとかと考えての福祉なら、それはお年寄りの方にとっては迷惑のほかの何物でもないわ。一人の人間として扱い、ゆり篭から墓場までの福祉だと言うのなら、食欲、物欲、性欲を満足させてあげなくては嘘よ。それでこそ終身福祉なのよ。福祉は選挙のときのお題目であってはならないのよ。ヘルパーを増やしたり、宿泊預かりをしたって、それは一時的な解決であって、慣れると直ぐ不満が募るだけ。それより、お年寄りが力を持ち、どんどん政府にこうして欲しい、ああしてほしい、こう在らねば駄目だと言う提言が通る世の中にしなくては駄目だわよ。つまり、アメリカのグレートパワーのようなもの。こうして欲しいからではなく、こうしろと言える力が必要なのよ」
と、小寺公子が熱つぽく語ったことがあった。公子は里子より若かったが、ヘルパーとしては先輩であった。「私など、時々触らせてあげているのよ。そうする事が生きがいになり、自己回復になればいいことだもの」
と公子は平然と割り切った言い方をした。その公子の言葉を里子は驚いて聞いたのだった。なんと言って言いか言葉がなかった。
「私は本当にホームヘルパーてなんだか判らないのよ。ホームヘルパーと言う職業が、学生や、婦人会の人達のボランティアの枠と同じであっていい筈はないわよ。可哀そうとか不自由だからと言う考えで事を起こされたのでは、お年寄りも私達もやってられない。甘やかすもんだから後がやりにくくて困るのよ。それならもっと専門的に、真剣に考え行動をしてくれなくてはね。非情に考えれば考えるほど、差しのべる手も多くなのものだし、縋りついてくる手は拒めないわよ。私はお年寄りのあそこを手で慰めてあげたことはあるわよ。そうお年寄りの方も望んでいたし、私もしてあげたかったから」
公子は黒目勝ちの大きな瞳を悪戯ぽく動かせて言ったのだった。ホームヘルパーの野暮ったい紺の制服が、公子の若い肢体に着けられるとぴったりとフィツトしよく似合った。行動が優先するのは若さと言うものだろうか。看護婦をしていた経験でお年寄りの思いが分かり、身体が、心が読めると言うのだろうか。扱い慣れていると言うのだろうか。それだけだろうか。里子には公子の言動は少し行き過ぎではないかと思うのだが、その事は、ホームヘルパーとして勤める里子にも頷けることであった。だが、大きな問題でもあるだけに一言の元に否定することは出来なかった。そして、お年寄りが望むことなら叶えてあげたいと言う気持ちは里子の中にもあったのだった。
色々と思いを巡らしながら、里子は硝子戸越しに張り着いたような風景を見つめていた。
ーよかったのよ。よかったんだわ。おじいちゃんもその事で満足をしてくれたんだし、・・・この私だって・・・。でも二度と起こしてはならないことだわ。
里子の心の中には、少しずつ優しい思いへと移行する感情があった。それは安木老人によって鎮まっていた身体に火を点けられ、一時にも溺れそうになった性の業火に対しての自己弁解のようでもあった。金曜に今週最後の安木老人へのヘルプがある。その時どのように対処しようかと思うと心は揺れる。
ー女もまた同じよ。私のように女の喜びを知った女は尚弱いわ。男の胸が無性に・・・。でも、私は公子さんのようには割り切ることは出来ないわ。
里子は眼下に拡がる魂に似た灯りを眺めながら思う。遠くからサイレンの音が近ずいて来ていた。階下でざわめきが起こった。里子は思いを振り払うように、カーデ
ーガンを肩にかけてドアを開けた。
2
安木老人をヘルプをする日の朝、里子は公子に先日のことを打ち明けたのだった。里子は迷っていたのだった。公子はそれを聞いて笑いながら、
「いいじゃないん、それで。他の人達はどうだか知らないけれど、私なら積極的に慰めてあげるわよ。どうてことはないじゃないん。処女でもないんだし、それで喜んでくれるのならお安い御用よ。してあげたら、する方だって満更ではないんだし・・・。私って少し可笑しいのかな、それとも変質者なのかも知れないわね」
と、公子は分厚い唇から饒舌に言葉を並べた。
「でも・・・。」
「大丈夫、性欲のあるうちは心配はないわ。男が女を、女が男を求めるのはこれはもっとも自然な姿ただし真理と言うものよ。いいって、流れに、なすがままにたくするのよ。その方が疲れないし楽だわよ」
公子は溌剌とした顔で言って、
「それは若い男の方がいいにはいいわよね」
と、言葉を付け加えて肩をすぼめて笑った。里子も頬を歪めて返した。
「公子さんお願いがあるの。少しお金を貸して欲しいの」里子は公子がヘルパー相手に金を貸していることを思い出して声を落として言った。迷う心が子供達の顔を見ることで切り替えることが出来るかも知れない。そのためにはお金がいる。
「幾ら位」
「二万円」
「いいわよ、でも十一だわよ」
「といち・・・」
「ええ、十日に一割って事なの。それでもいい」
里子は公子の逞しさに飽きれると言うより羨望の念が湧いていた。
「構わないわ」
「そう」公子はバツクを手繰り寄せて開けて、財布を取り出し慣れた手付きで数えて、
「はい、一万八千円」と言って里子に手渡した。里子は判らないと言う風に顔を公子に向けた。
「ああ、二千円は利息として頂いたからそうなるのよ」はっきりとした口調で言って、手帳に書き込んでいる。あっけにとられて里子は公子を見詰めた。
ー女が一人で生きていくためには、公子のように強くなりきっぱりと割り切らなくてはいけないのだわ。まして私には二人の子供がいるんだから尚更だわ。ホームヘルパーを続けていると、子供達を手元に引き取ることは出来ない、なんとかしなくては・・・。その奮切りが欲しい。
里子は公子から受け取ったお金を財布に入れて礼を言った。
「私ってがめついでしょう。でもこうでもしないと女が一人では生きてはいけないのよ。・・・。私が看護婦をしていた頃、好きな男が出来て、母の反対を押し切って東京へ逃げたの。挙げ句の果てに捨てられ、帰ってみれば母は死んでいた。だからせめて、母のお墓を造ってやりたいと思って、それに、母に親孝行が出来なかった分をお年寄りにと思って・・・。私がこんなことを言うと何だか金貸しが言い訳をしているようで・・・。困たことがあったらお互い様、弱い者は助け合わなくてわね。これも偽善だわね」
公子はそう言って逃げるように外へ出て行った。里子は公子の後ろ姿を見送った。影を重そうに背負った姿であった。それぞれの過去が人間の上に乗っかり様々な蔓陀羅を織り込んでいることを知るされた思いがした。
薄暮のことを昔の人は、逢魔が時と言った。その頃外で遊んでいると人さらいに逢うと言って、子供に言い聞かせ、仕付けをしたものだった。その母の言葉を思い浮かべながら、自転車を急がせていた。他のヘルプに時間を取られ遅くなったと安木老人の家に急いでいたのだった。
ーただ今日のところは様子だけを見て帰ろう。
いつものように裏木戸を開けて庭の踏み石伝いに部屋に近ずいた。安木老人は部屋の灯りを点け、上半身を起こして庭を見ていた。裸木になった庭木の枝の下をかいくぐりながら進む。陽が落ちて辺りは暗やみになっていた。安木老人の部屋から漏れる明かりが枯れ葉のそよぐ辺りにまで届いていた。安木老人は里子に気付いたのか硝子窓の向こうでにっこりと微笑んでいた。その笑いは飽くまで明るかった。先日のことなどもう忘れたと言う笑いのように見える。里子はその笑いに救われた思いがした。子供達に会えると言う心の変化が、里子に余裕を与えているようだった。
部屋に上がって、
「おじいちゃん、元気そうね」と努めて明るく笑って声をかける。
「はい。この前のようなことがあったので、今日は来てくれんかもしれんと思うとったところです。・・・あの時はすいませなんだなあ。・・・男は哀しいですの」
と安木老人は不安そうな瞳を里子に向ける。
「いいんです、私も・・・。おじいちゃん仲良くしてね。・・・さて、今日は何をしましょうかね」
「里子さん、今日は何もせんで、時間があれば少し話の相手をして貰えませんかの」
安木老人の瞳は穏やかな光であった。
「はい」里子は素直に応じる。
「あのう、すいませんが、応接間にアルバムがありますのじゃ。机の左側に硝子戸の入った本棚があります、その下の段に、赤いビロードの表紙の物がありますから、それを持って来てくれませんかの」
里子は荷物を置いて、廊下の突き当たりの応接間に入った。硝子戸の立派な本棚が壁に埋め込まれ、ぎっしりと金文字の背表紙の本が並んでいた。一番下の段にアルバムはあった。それを大事に抱えるようにして部屋に帰る。
「これですの」
「はい。私のように年を取りますと、物忘れが非度うなりましての、長年連れ添うたバアさんの顔も思い出せませんのじゃ。写真を見て、ああこんな顔をしとったじゃなあと思い、写真を映した頃の記憶を辿って、その頃に帰り遊んでおりますのじゃ」
そう言いながらアルバムをめくる。里子の後ろから覗き込む。安木老人の若い頃のものや、安木夫人のもの、前の大戦で戦死されたと言う息子さんのものなどが、どれも赤く焼けたものであった。
「バアさんは未亡人でな、私が下宿をしておった家に帰っておったんじゃ。いつしか男と女の関係が出来てしもうた。どちらが誘うたと言うわけではないんじゃ。自然にそうなっとった。互いに何か目に見えん糸が引きあっとったんかもしれんの。バアさんは不幸な女での、なんと言うてええんか、男なしでは生きられん女じゃつた。いや、バアさんを不幸とか哀しいとかと言う言い方は可笑しいかもしれん。性に取り憑れた女とでも言うた方がええのかもしれん。私と一緒になっても他の男とよう遊んだもんじゃ。そんたんびに泣いとった。別れてくれ、殺してくれといいよった。でも、私は別れなんだ。私はバアさんが好きじゃつたし、ほんに愛しとった。そんために、バアさんは罪の呵責に責めたてられながら生きた、一生。・・・忘れることの出来ん性の喜びと、私への愛の背信に心を痛めながら・・・辛かったろう、苦しかったろう。・・・誰もが捨てろ、別れろと言うたけど、そんなもんではなかった。一度愛を誓いおうた二人が、そう簡単に誓いを破れるものではねえ。バアさんは病気じゃった。見捨てることは出来んかった。バアさんが苦しんだだけ私も同じように苦しんだわ。砂をかんだわ。・・・人間の性に対しての執着はどこまで行っても際限はねえ・・・それが人間の本性かもしれん、そう思うたもんじゃ。案外バアさんは女として幸せな生涯を送ったのかもしれんと、今では思うようになっておりますのじゃ。だけどな、バアさんに感謝し取ることは、バアさんが私より先にあの世に逝ってくれたことじゃ。バアさんより私が先に逝っとりゃ、バアさんは一体どうなっとるじゃろう。着物の裾を絡げて街を歩いとるかもしれん。その姿を想像すると先に逝ってくれたことがバアさんのせめてもの愛のようにも思えても来る。・・・夫婦て妙なものじゃ。他人の目からは判らんものじゃ。それで、二人だけが分かりおうとったらええのかもしれん」
安木老人はアルバムの中の安木夫人にじっと視線を張り付けながら語った。語ることでその当時のことを思い出しているらしい、また、里子に物語を聞かせているようでもあった。深く沈んだ声であった。
「おじいちゃん、そんな・・・」
里子は安木老人のことを考えると言葉が喉に絡んだ。初めてしらされる安木老人の人生の縮図だった。
「里子さんに、バアさんの若かった頃の姿を見てしまったんです。この前のことは・・・許して下されの。里子さん、早うええ人を見付けて再婚しなされ、男も女も一人では生きられん。それは不自然と言うものじゃ」
「おじいちゃん」
里子は安木老人に労るような視線を投げる。
「バアさんも里子さんによう似た顔と肉付きのええ身体をしとった。外から帰ってきて、泣きながら武者振りついて私を求めた。バアさんの股からは男の精液が流れて伝っていた。そんなバアさんを私は抱いた。バアさんを気が触れ取ると言うのなら、この私は鬼じゃ・・・。男も女も・・・女も男も哀れな生き物ですの」
里子は安木老人の肩が大きくまた小さく揺れるのを見ていた。心の慟哭が現れていた。
「おじいちゃん、可哀そう」里子は口の中で言った。聞いている里子も胸に痛みがこみ上げていた。指で目元の涙を拭いて、安木老人の前に回った。
「そんなに憐れんだ眸で見なさんな。バアさんも私も幸せじゃったと思うとります。私もバアさんの所に行ったら力の限り抱きしめて、バアさんの乳房に顔を埋めて泣いてやろうと考えておりますんじゃ」
安木老人は明るく笑顔を浮かべて言った。その安木老人の心を考えればこみ上げてくる涙があった。涙が幾重にも頬を濡らした。胸を締め付けられた。真実の言葉の重みは里子の心の臂に吸い込まれた。それが段々と積み重なってゆき身体が硬直したようになっていた。人間の哀しさ、寂しさ、脆さ、はかなさ、弱さ、その真実が里子の身体に覆い被さりその中でもがいていた。これほどの激しい愛もあるだろうか、そして、これほど醜い現実もあるだろうか。里子の悩みは安木老人のそれに比べたらどれほどの重さだろう、深さだろう。
「この前の里子さんの裸はほんに美しかった。まるで天女のようじゃった。あのときは私は鬼になっとりました。だが、嬉しかった。まだ鬼になる元気があると言うことが・・・。里子さんには悪かったが・・・。里子さん、私はいつ鬼になるかもしれん。努めて自制しようと心掛けるが、あんたがバアさんに似とるから昔を思い出して鬼になるかもしれん。・・・私は怖いんじゃ、私の心が・・・。そして、里子さんがここに来てくれんようになるかもしれんと言うことが怖いんですのじゃ」
大粒の涙が染みの浮いた頬に流れ醜く映る。
「いいんですよ。おじいちゃんが鬼になれることが元気の証。遠慮なく言ってください。私の中にも鬼の部分がありますもの」
里子は先日の身体を走った快感を思い出していた。女の部分が男を欲しがる時がある。亡夫に悪いとは思いながら素敵な人を見れば抱かれてみたいと思うときもある。身体が熱くなるときもある。その思いが鬼のなせる技なのかも知れない。鬼はみんなの心に棲んでいるはずだ、と思うことで負担を軽くしようとしていた。
「いいえ、私は後悔しておりますのじゃ。私に同情してくださらんでもええ。里子さんが私のことを憐れんで言ってくださるのは嬉しいことですが、あなたを失う事の方が辛いことです」
「失いませんわ。これから私の出来ることがあれば何でもします。遠慮なく言ってください。私は喜んで致しますから」
辛いと思った先日のことが、安木夫人の生き様を知ったことで変わろうとしていた。与える喜びが里子の心に溢れるように湧いていた。
「それはいけません、甘えられませんわの」
「いいえ、甘えてください」
大きくかぶりを振りながら言った。
「男は狡い、まして、年寄りは醜くて狡いものですぞ」 そう言う安木老人を里子は駄駄をこねる子供を見るような優しい眸で見詰めた。一回り萎んだように映っていた。
「いいではありませんの。この前のような悪戯は困りますが、私に出来ることがあれば何でも言ってください」 この言葉は安木老人への慰めではない。ホームヘルパーとしての任務なのだと思いながら言った。
ー介護するお年寄りの過去を知らないで何が出来ると言うの。心の障害を取り除くこともヘルパーの役目ではないかしら。私はその事を忘れていたのだわ。
と、今までヘルパーとして欠落していたことを後悔していた。
「それでは、例えば、ここで里子さんの裸が見たいと言ったらどうしなさる」
「それは・・・」里子は突然の攻撃に後ろにしざった。
「それみなされ、出来んことが多い。男を甘やかしてはいけません。年寄りをからかって出来もしない事を口にしてはなりませんぞ」
安木老人の一段落とした低い声が部屋に響いた。里子は一度発した言葉に対して言い逃れの出来ない立場にあることを認識した。鬼になれと言うのか。性鬼になれと。この前、安木老人に掴まれた乳房が急に痛み、身体が熱くなるのを感じた。
「どうてことないじゃないの、喜ぶのだったらして上げたら。私達ヘルパーは、ボランティアの奉仕と違うのよ。プロなんだから、とことん面倒を見るのが当たり前なのよ」
「私は時々、慰めてあげるのよ。自然に逆らうことは出来ないもの、真理の前では人間従順でなくては、素直でなくてはね。必要としているから与える、単純でいいじゃないの」と、言った公子の声が耳の奥で繰り返し繰り返し鳴った。
「ホームヘルパーて一体なんだか判らないのよ。だから、手探りで前に進んで行くしかないわ。こうだと言う方程式がない今、私達がその基本を作っていかなくてはね」
「今の老人福祉で忘れられ無視されているのはお年寄りのセックスなのよ。お年寄りにもその願望があり、欲望はあるのよ」
公子が尚も里子の耳に囁き掛けてきていた。
「いいえ出来ます。おじいちゃんがそうして欲しいと言うのなら」
里子は顔を赤らめて必死になって言った。
「やめなされ、心を偽らん方がええですぞ。いやいやなら・・・。これは言葉の遊び、ただ言葉のやりとりで充分ですのじゃ」
安木老人はアルバムに視線を落としたが、ゆっくりと顔を庭に向けた。部屋から流れ出る明かりが庭にぼんやりと広がり暗さを解かしていた。大きな蛾が飛んだように見えた。が、それは風の悪戯で、枯れ葉が舞ったのだった。
里子はそっと立ち、ユニホームのボタンに手をかけた。一枚一枚ゆっくりと脱いでゆく。そのたびに全身を今まで感じたことのない悦楽が走った。
ー私は裸を見られるんだわ。おじいちゃんが見て喜んでくれるのだわ。
それは不思議な感覚であった。肌を露にするところがほてった。忘我の中の行為のように思えた。少女の恥じらいにも似ていた。見詰められると言うことが、これほど血を湧かせ内奥から喜びを引き出すとは考えられなかった。恥じらいは喜びへと昇華していった。最後の薄物を取り脱いで衣服の下へ忍ばせた。
安木老人には里子の脱ぐ姿が、硝子戸に映って良く見えていたのだった。里子は手で胸を押さえ前を隠した。安木老人は静かに振り返った。
「あなたは・・・ほんとうに・・・ありがとう、ありがとう。天使じゃ、天使様がこのわが屋におりて来て下さった。美しい・・・ほんに美しい」
安木老人にそう言いながらまじまじと見詰められると、里子の身体がジーンと痺れたようになった。里子は全身に忘れていた性の快楽が蘇って震えだした。それは、夫との交合によって与えられた喜びより遥かに大きく深かった。
「あなたも鬼になられるか。誰にもどこかに鬼が棲んでいると聞いたが・・・美しい鬼じゃ。ほんに美しい鬼じゃ」
安木老人はそう感嘆して股間に手を這わせた。里子は昂りを感じ濡れ始めた。腰の力が抜けて膝が酔ったようにもつれた。膝まづいてしまった。里子は催眠術でもかけられたように、安木老人のそばに躙り寄っていた。そして、自然に安木老人の股間に手が伸びていた。安木老人がそれに応え、里子の全身を揉みしだき、唇を這わせた。里子は海の中で何もかも忘れて安らぐ。
里子は安木老人の頭を膝に乗せて顔を見詰めた。穏やかな解放感が顔の表情の中に浮かんでいた。まるで子供のような無邪気さが漂っていた。
外は暗く風の音だけが通り過ぎていた。外灯に何か白いものが懸命に身をぶつけているように見えたが、それは大きな牡丹雪が風に弄ばれている風景であった。
里子はコートの襟を立て帰りを急いだ。
ーこれで何でも出来る。鬼になることを恥ずかしいと思っていた時には何をする勇気も湧かなかった、今なら何でも出来る。これで子供を手元に引取リ一緒に暮らせる。
里子は白い息を吐きながら思った。身体の中にみなぎる何か判らない力を感じていた。「里子さん、ありがとう。後悔はしとりませんかの」
「はい。今までの重たい身体がなんだか軽くなったようで、悩んでいたことが馬鹿みたいな気がします」
安木老人との会話が風の音の中でしていた。
窓の外は今日も何千と言う光の乱舞であった。まるでダイヤモンドをばらまいたように神々しく光っていた。里子は窓を開けて新しい風を部屋の中に導いた。そして、すがすがしい気分で胸一杯に吸い込んだ。
里子は鏡の前に座り顔を映す。頬にうっすらと赤みが刺している。肌に潤いが見える。が、小皺が目の縁に刻まれている。もう若くないのだと思う。今しておかなくてはならないことをしておかなくてはと心に訴える。
里子はバッグを鏡の前に持ってきてひっくり返す。その中に見慣れぬ封筒が入っているのを見付ける。開封する。中には壱万円札が二枚入っていた。里子は驚いて、そして、どうなっているのだろうと考える。ああ、と声を上げる。きっと安木老人がと思う。
「男は狡いよ。まして年寄りは醜くて狡い」
安木老人の声がこだまのようになって耳に伝わってきた。
ふと、里子は安木老人が語った安木夫人との生活は嘘ではなかったかと思った。でも、それならそれでいい。私は鬼になれたんだもの。恥ずかしいと言う気持ちを捨てることが出来たんだもの。と里子は思った。このお金をもって明日子供達に逢いに帰ろう。
外は風が雪を弄び、雪は風に翻弄されながら自然の調和を保っているようであった。風の音は里子の心に子守歌のように忍び込んでいる。
良かったら「いいね」してください。誰でも「いいね」出来ます!