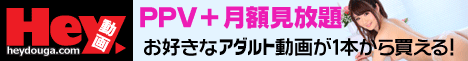36
香苗 「……ん……」
カーテンの隙間から光が差し込んでくる。
部屋の空気は朝のしっとりとした感じとは違う。
それになんだか少し頭が痛い。
こんなに目覚めが悪いのは久しぶりだ。
香苗 「……ん~今何時…?」
ベッドの上でゴソゴソと動きながら時計を手にする香苗。
香苗 「……えっ!?もうこんな時間!?」
時計の針の位置を見て思わず香苗はそう声を上げた。
なんと香苗が起きたのは昼の12時だったのだ。
どうりで身体の感じがいつもと違う訳だ。
こんなにも眠りこけてしまうのは、香苗にとって珍しい事。
いつもは必ず祐二より早く起きて、朝ご飯や祐二が仕事に行くための準備をしていた。
香苗 「はぁぁ……ダメよ……こんな事じゃ……。」
昼まで寝てるなんて、なんだか自分がだらしのない人間になってしまったかのよう。
若干の自己嫌悪に陥りながらべッドから起きてリビングへ行くと、そこにはいつも通りの光景があった。
静まり返った一人だけの空間。
部屋は汚れてないし、洗濯物も溜まってない。
香苗 「……。」
寝坊はしてしまったけれど、寝坊をしたからといって何か困る訳ではなかった。
祐二は今日も居ないし、まだ帰っても来ないのだから。
1人でいるのはたったの1週間。でもまだその内の1日しか経っていないと思うと、なんだか凄く長く感じる。
何もする事がないというのは、寂しい事だ。
いつもより長く寝ていたからなのか、身体がだるい。
気持ちを切り替えて目をしっかり覚まそうと、香苗はシャワーを浴びるために浴室へと向かった。
昨日は結局夜中まで自慰行為をしていた。
祐二が居ないからダブルベッドの上でいつもより大胆に。
でも自分で刺激を与え快感を感じても、何か物足りない。
足りないと足りないと続けているうちにいつのまにか夜中になり、最後は疲れていつのまにか眠っていた。
シャワーを浴び終わり、浴室から出た香苗は身体にバスタオルを巻きキッチンで水を飲んでいた。
普段ならキッチンやリビングまでバスタオル一枚なんかで出てくるような事はしない香苗。
しかし今それができてしまうのは、1週間ずっと1人きりというある種の開放感を感じているからかもしれない。
香苗 「……。」
ふと香苗はその場でバスタオルを解き広げてみた。中はもちろん裸だ。
キッチンで裸になっている自分。家電や調理器具のステンレス素材の部分に自分の裸が映る。
もちろんこの部屋には他に誰も居ないのだから、大した事ではないかもしれない。浴室や寝室で裸になる事とそんなに変わらないはず。
でもなんだかステンレスに映っている自分の姿が物凄く卑猥に見えて、香苗はすぐにバスタオルを身体に巻きなおした。
香苗 「……私……イヤらしい……」
昨日は中島もバスタオル一枚で玄関まで出てきた。
あのバスタオルの中も、やはり同じように裸だったのだろうか。
今でも頭から離れないあの中嶋の上半身裸姿。
香苗は目を閉じて、今一度じっくりとその映像を思い出してみる。
逞しい肉体、特に腹筋の割れ方は凄かった。そしてヘソの辺りから下へと向かうように体毛が生えていたのを覚えている。
夫の祐二はどちらかといえば体毛は薄い方だ。だからあんな所にまで毛が生えているという事が香苗にとっては少し衝撃的でもあったのだ。
きっとあの毛並みは下へ向かえば向かう程濃くなっていくのだろう。
でもそれ以上はタオルがあって見えなかった。
あのタオルの中はいったいどんな風になっているのだろうか。
そんな卑猥な好奇心が、昨日の夜から香苗の頭を支配していた。
今のところ、その全てが祐二とは違う印象である中嶋の肉体は、やはり下半身も祐二とは全く違うのだろうか。
香苗 「……ハァ……」
そんな事を考えていたら、シャワーを浴びてサッパリしたにも関わらず、また身体が熱くなってきてしまった。
自然とタオルの中へと移動していく香苗の右手。
香苗 「……ゥン……」
しかしその時、香苗の耳が微かな音を察知した。
思わずその場で動きを止める香苗。
目を閉じてその音に集中するように耳をすます。
香苗 「……」
聞こえる、微かな声。
昨日はなかった男女の声が、また聞こえてきているような気がした。
香苗はバスタオル一枚の姿のまま、カーテンが閉まっている窓際まで移動した。
香苗 「……」
やっぱり聞こえる。
中嶋は今日も女性を連れ込んでいるようだ。
それが分かった瞬間から香苗の鼓動は急激に速くなり、身体もカァっと熱くなっていった。
今まで常習的に続けてきてしまった盗み聞き。しかし今回の興奮は今までとは違っていた。
なぜなら香苗は昨日、中嶋の肉体を見てしまったのだから。
それによって隣からの声を聞きながらの想像はよりはっきりしたものになる。
……今隣で中嶋さんといっしょにいる人は、あの身体に……あの逞しい身体に激しく抱かれるんだ……
……今隣に居る女性は、中嶋さんのあのバスタオルの中まで見ているのかもしれない……
昨日の夜から香苗がずっと妄想してきた事を、その女性は今から体験してしまうのかと思うと、なんだか妙な気分だ。
香苗は自分でも気付かない内に下唇をぐっと噛んでいた。
香苗 「……。」
夢中になっていた。中嶋に。
もはや香苗の身体は、隣から聞こえる声をもっと近くで、もっとはっきりと聞きたいと勝手に動いてしまう。
そして同時に求めたい快感。
せめて、せめて擬似的な快感でも!
香苗は一度寝室に戻って取って来たピンクローターを手にして、再び窓際にしゃがみ込む。
カーテンを少しだけ開けて窓も少しだけ開ける。
するとスーッと涼しい風が入ってくる。その風を感じて、あと一歩出ればそこは外の世界なのだという事を全身で理解する。
外の空気がバスタオル一枚だけの身体に当たる事が、なんだかとても新鮮でもあり、開放感を感じつつも、香苗は羞恥心を刺激され、興奮を煽られているような気分だった。
香苗 「……?」
しかし、いつもなら窓を開ければある程度はっきりと聞こえる隣からの声が、今日はあまり聞こえない。
今日に限って、隣は窓を開けていないのだろうか。
耳をすませば微かに聞こえる気がするが、やはり聞えにくい。
……聞えない……ハァ……どうして今日は窓閉めてるの……
そんな何かもどかしさの様なものを感じる香苗。
もっとちゃんと聞きたい……もっと近くで感じたい……そんな欲求が、欲望が、香苗を通常では考えられない大胆な行動に移させる。
ガラガラ……
人一人が通れる程にまで窓をゆっくりと開けた香苗。
もう何も考える余裕などなかった。
今の香苗は、ただただ本能のままに行動しているだけなのだ。
香苗 「……。」
息を潜め、香苗はしゃがんだままの体勢からベランダに足を一歩踏み出した。
そう、香苗はなんとバスタオル一枚だけの姿でベランダへと出て行ってしまったのだ。
37
ドキドキドキドキドキドキ……
香苗 「ハァ……ゴク……」
呼吸は荒くなり、胸の鼓動はまるで全力疾走の後のように速くなっていた。
落ち着かせようにも、自分で自分の身体をコントロールする事はできない。
肩や背中、そしてバスタオルの中にまで入ってくる外の空気が、自分が今ほぼ裸の状態であるという事を再度教えてくる。
身体に纏っているのは一枚のバスタオルだけ。
もちろんそれがどうしようもなく心許なく、そして恥ずかしいのであるが、しかしだからといって香苗は部屋に戻ろうとはしなかった。
まだ昼間の時間帯で外は明るい。
だがこのしゃがみ込んでいる体勢ならば壁に隠れているので誰かにこの格好を目撃される事はないだろう。
見られる事はない。しかしこれはもう限界ギリギリの行為だ。
それは香苗が妄想で思い描いた淫らな行為を、現実世界で実行できる限界の境界線である。
そう、これは1人の女性である香苗の、絶対に人には知られてはいけない秘め事なのだ。
この秘め事は他人にはもちろん、家族である夫の祐二にも決して知られてはいけない。
香苗が1人で一生胸の中にしまい込み、墓場まで持っていかなければいけない事。
しかしこの一見清楚な人妻が抱えている淫らな秘め事には、1つ厄介な特徴があった。
それは人に知られてしまうかもしれないという境界線、そこに近づけば近づく程、そこから得られる興奮が大きいという事だ。
身体の奥から興奮を掻き立てられるようなものがその境界線にはあり、そしてそれは香苗を誘惑する。
淫らな自分が他人にバレるかバレないか、ギリギリの綱渡りを今、香苗はしているのだ。
なんて刺激的なんだろう。
なんて気持ちイイんだろう。
自分でも今まで知らなかった脳の部分を刺激される、それがこんなにも気持ち良いものだったなんて。
もうすでに香苗はその綱渡りを始めてしまっている。
一度スタートすればもう後戻りはし難い。
これ以上進めばもう戻れなくなってしまうかもしれないのだ。しかしそれでも香苗は綱を渡る足を止める事はできなかった。
まだ見えないもっと先、そこに今以上に興奮できるものが待っているかもしれない。
そんな誘惑が、危険な所へ行く香苗の気持ちを駆り立てているのであった。
香苗 「……。」
ベランダに出ると、やはり部屋の中から聞いていた時とよりは隣の声が聞こえる。
しかしまだ先日までの窓を開けている状態で聞こえてきていた音量には程遠い。
香苗はしゃがみ込んだまま、さらにその声音をしっかり聞き取ろうと、中嶋達が居る部屋側の壁に近づこうと移動する。
なるべく音を立てないようにゆっくりと慎重に。
左手でバスタオルの結び目を掴み、そして右手には卑猥なオモチャを持って。
香苗 「……。」
中嶋達に一番近いであろうそのポジションに移動すると、少しだけ聞こえる声がハッキリとしてきた気がする。
もう現状でこれ以上聞き取りやすい場所は考えられない。
まだまだ聞き取りにくい事に変わりはないが、もうすぐそこ、壁越し数メートルの所で女性があの中嶋に抱かれようとしている、それだけで香苗の興奮を高ぶっていった。
手に汗握る状況、その言葉の通りピンクローターを握る香苗の手は汗を掻いていた。
香苗 「……ハァ……」
香苗はその場で左手をゆっくりとバスタオルの中、女性の一番大切な部分にもっていく。
指先で自分の秘部をそっと触ってみると、そこはすでに淫らな汁が外に溢れ出るほど濡れていた。
指が特に敏感な部分に少し触れると、香苗の口からは「ァンッ……」という甘い声が自然に漏れる。
凄く敏感になってる。
昨日の夜よりもさらに。
今ここを激しく刺激したならば、きっともの凄い快感に得られるだろう。
そんな予感を全身で感じた時、香苗はその快感を求めずにはいられない。
香苗 「……ン……これ……」
右手に握ったピンクローターを見つめる香苗。
もう何度も使ってきたこの大人のオモチャ。
使用している最中はこれがある程度の音を放つ事を香苗は知っている。
携帯のバイブ音と同じような、あの低周波の震動音。
当然、その音が中嶋達の居る所まで聞えてしまうのではないかという事が心配である。
……だけど……使いたい……
このローターは自分の指だけでは決して得る事のできない快感を与えてくれる。
その刺激に香苗はドップリとハマってしまっており、最近ではこれがなくては香苗の自慰行為は成り立たないと言っていい程だ。
……弱なら、弱ならきっと聞えないはず……
ローターには回転式のスイッチがあり、右に回せば回すほど、その震動は大きくなっていく。
最弱の震動音ならば小さいから隣までは聞えないだろう。
なにせ窓は閉まっていて、向こうで発せられている声がこれ程聞こえにくいのだから。
……大丈夫……大丈夫……
香苗 「……ゴク……ハァ……」
ある種のスリル感が快感に変わっていく。
香苗は少しの間考えた後、手に持ったピンクローターを自分の秘部もっていき、一番敏感な部分である陰核にそれを当てた。
香苗 「……ハァ……ン……」
そして香苗は目を閉じ、意を決してゆっくりとそのスイッチを回した。
38
ブゥーーーー……
香苗 「……ンアッ!ハァ……ン……ン……」
いつもよりも一際大きく感じる快感が香苗の全身に広がる。
細かな震動が陰核を刺激し始めた瞬間、香苗は一瞬甘い声を発したが、その後は口をつぐんで漏れそうになる声を押さえ込むようにして我慢した。
ローターから発せられる震動音は低く小さい。これなら隣の部屋、しかも窓が閉まっている状態なら聞こえる事はやはりないだろう。
香苗 「ン……ァ……ン……」
陰核からの快感を感じる度に柔らかな秘肉がヒクヒクと反応しているのが自分でも分かる。
その割れ目からは今にも濃厚な涎が垂れてきそう。
……ハァ……これ…今までで一番気持ちイイかも……
それはやはりベランダという室外で、しかもバスタオル一枚だけしか身に纏っていないという状況が快感のスパイスになっているからであろう。
「……ァ……ァ……ァ……」
隣からは女性のリズミカルな喘ぎ声が微かに聞こえ始めていた。
それを聞いて香苗の興奮度も比例するように上昇していく。
……今、抱かれているんだ……あの中嶋さんに……あの逞しい身体に……
……どんな風にしてもらっているんだろう……
香苗は目を閉じて思わず想像してしまう。
女性があの逞しく太い腕に腰を掴まれ、男のモノを挿入され、そして激しくそれを出し入れされている光景を。
きっとそうなんだ。
今までの女性達も、まるで我を忘れたように喘ぎまくっていた。
中嶋に挿入され、激しく膣内を刺激されているのだろう。
……中ってそんなに気持ちイイのかな……
今まで声を聞いてきた限り、女性達は挿入されてからのSEX自体に快感を感じているようだった。
しかしそれはまだ香苗には分からない感覚であり、想像し難い事でもあった。
なぜなら香苗は、自慰行為にしろ祐二とのSEXにしろ、快感は主に陰核から感じていたからだ。
だから前戯での愛撫はある程度気持ちよくても、祐二のモノが膣に入ってからは正直特に気持ち良いという事はなかったのだ。
でもそれが普通だと思って何も疑問など抱いていなかった香苗。SEXとはそういうものだと思っていたのだ。
しかし隣で行われている中嶋達の性行為を盗み聞きするようになってからは違う。
まだまだ自分の知らない事がいっぱいあるという事を、中嶋達から教えられている気分だった。
「アッアッあああ!!スゴイッ!……ハァ…ハァ……」
窓を閉めているにも関わらず、一段と大きくなった女性の声がハッキリと聞こえるようになってきた。
……凄い声出してる……そんなに気持ちイイのかな……
……膣(なか)に入れてもらって、そんなに気持ちイイのかな……
隣の盛り上がりに興奮を煽られながらそんな事を思った香苗は、バスタオルの結び目を掴んでいた左手を離し、自然とその手を秘部の方へ移動させる。
今まで自慰行為で指を膣に入れるなんて事はした事がなかった香苗。
それは何となく、自分の膣に指を入れる事が怖かったからだ。
でも今は試してみたい。
何となく膣の中が物足りないというか、寂しい。
膣を何かで満たしてもらいたい……。
香苗 「ハァ……ン……ハァ……」
右手でクリ○リスに震動するローターを当てたまま左手の指を膣にゆっくりと挿入してみる。
クチュ……
香苗 「ハァ……凄い……濡れてる……」
香苗の十分すぎる程濡れた秘部は、香苗の細い指を容易に呑み込んでいった。
しかし、やはり自分の細い指では特に圧迫感というものは感じなかった。
……まだ……物足りない……
香苗はもう少し奥まで指を入れてみようと、体勢を変えて脚を少し広げてみた。
が、その時
香苗 「………キャッ!」
突然ハラリと下に落ちたバスタオル。
結び目から手を離していたからか、体勢を変えた事でそこが解けてバスタオルが取れてしまったのだ。
つまり香苗はその瞬間、ベランダで全裸になってしまったという事だ。
香苗 「はっ……イヤ……」
恥ずかしそうに顔を赤くし、慌ててバスタオルを拾って再びバスタオルを身体に巻こうとする香苗。
一瞬とはいえ、ベランダで、外で裸を晒してしまった事で香苗の羞恥心は高ぶった。
香苗 「ハァ……ハァ……」
しかし次になぜか香苗は、身体にバスタオルを巻こうとする手を止めてしまった。
香苗 「………」
顔を真っ赤にしたまま、乱れたままのバスタオルを直そうとしない香苗。
香苗は戸惑っていた。
今一瞬裸になってしまった時、何か胸の奥から熱いものが込み上げてきたような感じがしたのだ。
何かよく分からないが、なぜか一瞬、香苗にはそれが気持ちよかったように思えた。
もしかして今、自分は新たな快感を発見してしまったのかもしれない。
それに気付いた時、興奮状態である今の香苗は、それに手を出すのを我慢する事などできないのだ。
香苗 「ハァ……ハァ……」
少し息を荒くしながら、再度周囲を見渡す果苗。
周りに高い建物はない。ベランダの壁もある。バスタオルを巻いた姿だろうとなんだろうと、しゃがんでいれば誰かに見られる事なんてない。
それをもう一度確認した香苗は少し考えた後、ゆっくりとその手で自分の身体からバスタオルを外していった。
……ハァ……私……裸になっちゃう……こんな所で……
そしてバスタオルを外して裸になっていく時、香苗はその快感をハッキリと感じたのであった。
外気が直接肌に当たる。
特に胸やお腹、そして股間の辺りにスースーと空気が当たるのを感じると、自分が外で全裸になってしまっているのだという事がよく分かる。
香苗は手に持ったバスタオルを部屋の中に入れて、バスタオルから手を離した。
今手にしているのはピンク色の卑猥なオモチャだけ。
ピンクローターだけを持った全裸の人妻がベランダにいる。
今はまだそれほど実感はないが、ここまでやってしまっている香苗は後から自覚せざるを得なくなるだろう。
自分が〝変態〟だという事を。
39
香苗 「ハァ……ハァ……」
ドックン……ドックン……
何も身に着けていない真っ裸で外に居るというのに全く寒くない。
いや、むしろ暑いくらいだった。
熱い血液が高鳴る心臓の音と共に全身に広がり、顔は額から薄っすら汗を掻くほど火照っている。
ヴィーーーン……ヴィーーーーン………
完全に勃起したクリ○リス、そこに当てているローターが静かに震動を続けているが、香苗はその震動だけでは足りなくて、ローター自体を指で動かしてクリ○リスに擦り付けてように刺激していた。
香苗 「ハァ…ン……ンァ…ァ……ハァ……」
声を殺すように、そして時々控えめに甘い声を漏らす香苗。
クチュクチュと膣に挿入して掻き回すように動かしている方の細い指は、もう粘着質な液体でべチャべチャに濡れている。
隣からは相変わらず中嶋に責められている女性の声が聞こえ、その声も段々と切羽詰ったものになってきていて、香苗の興奮もそれにつられるようにして大きくなっていく。
激しくて長いSEX。聞えている女性の声から察するにもう何度も女性は中嶋に絶頂に導かれているようだった。
それに対し香苗はまだ一度も絶頂には達していない。
それは絶頂を迎えた時に思わず声を出してしまいそうで怖かったからだ。
やはり万が一でもその声を聞かれ、この事を知られてしまうのは嫌だ。
そんなわずかに残っている自制心が香苗にギリギリの所でブレーキを掛け、絶頂に達しそうになる寸前で刺激をするのを止めさせていた。
イキそうになったら止め、少し落ち着いたらまた刺激を始め、またイキそうになったら止め……それの繰り返し。
しかしそんな事を繰り返していると、やはり絶頂に達したい、イキたいという欲求も香苗の中で大きくなっていく。
刺激を再開してから絶頂の寸前にまで到達する時間も徐々に短くなってきていて、何かちょっとでも大きな刺激を与えられたら絶頂に達してしまいそうなくらいに身体は敏感になっていた。
……ハァ……イっちゃいそう……イキたい……イキたい……
そんな思いで頭の中がいっぱいになる。
正直なところ、隣で中嶋に激しく責められている女性が羨ましかった。
理性も全て無くしてしまうくらいに思う存分に感じている、そんな風に私もなりたい。
しかしそう思う一方で、それが現実には不可能であるという事を香苗はよく自覚していた。
今隣の女性が浸っている世界は、自分がどうやったって足を踏み入れる事のできない、いや、踏み入れてはいけない領域であるのだ。
だからこそ歯痒かった。
もう自分の人生ではそれを体験する事なんてできないし、今の人生を壊してその世界に入っていくなんて事はできない。
……そんな事……絶対できない……
香苗ができるのは、こうやって密かに盗み聞きをして非現実的な世界を少しだけ味わう事くらい。
自分には無縁の世界。
……だけど……もうちょっと……もうちょっとだけ……近づきたい……その世界に……
そんな事を頭の中で巡らせながら、ローターを持つ香苗の手は、そのローターをゆっくりと膣口へと近づけていた。
……これ……膣(なか)に入れたら……どうなるんだろう……気持ちイイのかな……
自分の指じゃ物足りない。膣からの刺激が欲しかった。隣の女性はきっと膣で感じているんだ。
……私も膣で感じたい……
香苗に新たな快感を教えてくれたこの震動するローターを中に入れたら、また新たな快感を知れるかもしれない。
しかしそんな好奇心と欲求が生まれる一方、もしこれ以上の快感が来たら声を出してイってしまいそうで怖かった。
だから香苗は膣口にローターの半分だけを入れた所で、躊躇して止めていた。
細かく伝わってくる振動がやはり気持ちよくて、ヒクヒクと蠢くヴァギナは〝早くそれを全部入れて〟と言っているようだったが、それはどうしてもここではできない。
香苗 「ハァ……ン……」
もうそろそろ部屋に戻って、ベッドの上で声を出して絶頂を迎えようか。もう限界だ。何度も絶頂寸前で止めてきた事で溜まりに溜まって大きくなったもの、それを早く解放したい。
しかし香苗がそんな事を考え始めていた時、思いがけない事が起きた。
……ガラガラガラッ!!!
香苗 「……っ!?」
隣から窓を勢いよく開ける音が聞こえたのだ。
そして同時に今までよりもクリアでハッキリとした中嶋と女性の声が聞こえてくる。
「え~ホントに外でするのぉ?イヤ、恥ずかしぃよぉ。」
中嶋 「いいから早く出ろって。あ、だけど声は我慢しろよ、隣まで聞こえちまうからな、お前声デケェから。」
「ン……無理だよそんなの……英治凄いもん……。」
中嶋 「ダメだ、我慢しろ。ほら早くそこに手付いて、ケツこっち向けろって。」
「もぅ……誰かに見られちゃうかもしれないよ……」
中嶋 「そのスリル感が良いんだろ。」
ドキドキドキドキドキ……と、香苗の胸の鼓動は今までになかった程に速くなっていた。
中嶋達もベランダまで出てきたのだ。中嶋と女性は、この壁のすぐ向こうにいる。
もしベランダから身体を乗り出し、壁横から顔だけ出してこちらを覗き込まれたら……一瞬そんな事が頭を過ぎり、香苗は軽いパニックになった。
なにせ今の自分は、何も身に着けていない全裸姿なのだから。
急激に上昇した緊張と興奮。
……どうしよう……どうしよう……あっ!これ止めないと…音が……
微弱な震動を続けるローターは小さいけれど振動音を発している。もしかして中嶋達に聞えてしまっているかもしれない。
そう思った香苗は慌ててスイッチを切ろうとした。
しかしスイッチを切ろうと身体を少し動かした瞬間、さらに思いがけない出来事が香苗を襲う。
香苗 「……アッ!!」
その瞬間、香苗は思わず声を我慢しきれずに上げてしまった。
なんと膣口に半分だけ入れていたローター、自身の愛液でヌルヌルに濡れていたローターが指から滑って膣内に全て入ってしまったのだ。
絶頂寸前の状態が続いてた香苗の敏感な身体は、突然襲ってきたその刺激に反応を隠す事はできなかった。
香苗 「ンッ……!!」
……あああ……ダメ……アア…イッちゃいそう……ダメッ……
中嶋 「……ん?なんだ?今なんか変な声聞こえなかったか?」
……うそ……ああ……中嶋さんにバレちゃう!……どうしよう……もうダメ…ァア…早くスイッチ切らないと……イッちゃう……声出ちゃう……
中嶋に勘付かれそうになった事で完全にパニックに陥ってしまった香苗は、急いでローターのスイッチ部分に指を当てた。
もうあと数秒、いや、あと一秒でもこの震動による膣内への刺激が続いたら、身体はあっという間に絶頂に達して香苗はあられもない声を出してしまうだろう。
そして、恐らく今までの人生の中で一番切羽詰まったこの状況の中で、香苗はさらにとんでもない過ちを犯してしまうのだった。
パニック状態のまま慌ててローターのスイッチを切ろうとした香苗は、そのスイッチを右に勢いよく回してしまったのだ。
そう、右に。
ローターのスイッチは左に回すと弱く、そして右に回すと強くなるのだ。
ッヴィーーーーーッ!!!!!!!!!
香苗 「ぇ…ンハァッ!ッアアアアッ!!!」
その瞬間、大きな震動音と、我慢しきれずに漏れた香苗の喘ぎ声がベランダに響いた。
40
香苗 「ン…ぁはあああ……アア……」
突き抜けるように快感が全身に広がり、一気に頭が真っ白になった。
身体を反らせ、顔は天を仰ぐ。
ローターのスイッチを間違えて最も強い振動に切り替えてしまった香苗は、膣の中から伝わる強烈な刺激に瞬く間に快感絶頂に導かれた。
自分自身で焦らしに焦らしていた絶頂の快感は香苗の想像を遥かに超えていて、半開きに開いた口から漏れる声は我慢する事ができなかった。
いや我慢しようと考える思考能力さえ、その強烈な快感は香苗から奪ったのだ。
香苗 「ぁぁ……ハァ……ンァ……ハァ……」
香苗の身体は全身を硬直させた後、そこからの反動を起こすようにして一気に脱力した。
全身に力が入らなくて、絶頂の余韻に身体はビックンビックンと反応する。
そして絶頂に達した事を示すかのようにギュウっとキツく締まった香苗の膣からは激しく震動するローターが押し出されるように出てきて、そのままベランダに落ちた。
ガタガタガタガタガタ……!!!
落ちた瞬間にローターはけたたましい音を響かせる。
香苗 「ハァ…ぁ……」
……ああ……イヤ……ダメ……
ローターが立てる大きな音を聞いて快感に思考力を奪われていた香苗に再度危機感が戻っていく。
このままでは中嶋達にバレてしまうという危機感が。
そして香苗は快感の余韻に酔う朦朧とした意識の中、なんとかローターを拾い上げた。
「ちょっと何今の音、変なの聞こえなかった?」
中嶋 「ああ、聞えたな、確かに。」
「やだ……そこに誰かいるんじゃないの?」
中嶋 「フッ……いるのかねぇ…ちょっと確認してみるか。」
……ダメ!!……見られちゃう!!……
手に卑猥なオモチャを持ち、顔を火照らせている、裸姿の香苗。
こんな姿を見られたら女としての人生が終わってしまう。
香苗は急いでローターのスイッチを切り、慌てて部屋に戻ろうとする。
しかしまだ快感の余韻が大分身体に残っていて思うように力が入らない。特に下半身がまだガクガクと震えて上手く動いてくれない。
……はぁぁ……戻らないと……戻らないと……
香苗は力の入らない身体で四つん這いになって必死に部屋の中へと戻って行った。
そしてなんとか部屋の中に入った香苗は、急いで少しだけ開いていたカーテンと窓を閉めた。
香苗 「ハァ……ハァ……ハァ……」
静まり返った部屋で、荒い息遣いだけが聞こえる。
冷たいフローリングの床に裸のままペタンと腰を下ろした香苗の額は、大量に吹き出た汗でビッショリと濡れていた。
ドクドクと依然速いままの高鳴る鼓動。
急激に高まった緊張と興奮、そして快感絶頂の余韻はまだ続いている。
……ハァ……どうしよう……中島さんに、気付かれちゃったかもしれない……
香苗の痴態を直接目撃される事はなんとか免れたものの、あのローターの震動音と自分が発してしまったあられもない声に、何も思われないはずがない。
中嶋達に知られてしまったのではないかという恐怖感とまだ冷めない興奮が入り混じり、胸が押し潰されそうな程苦しい。
香苗 「ハァ……ぅ……」
香苗は裸姿で座ったまま、両手で顔を覆う。
禁断の領域にまで手を伸ばしてしまった事を、今更ながら後悔していた。
しかしその一方で香苗があの興奮と絶頂による深い快感に今も魅了されている事も確かだった。
それは人間の本能的な部分なのかもしれない。
最高の興奮は危険と隣り合わせなのだ。
女性として恥ずかしさの限界に達する所、ある種の危機感を感じる所に最高の性的興奮はある。
香苗の身体が今も震えているのは緊張や危機に直面したからだけではない。
香苗の身体は悦びに震えていたのだ。最高の興奮を味わった悦びに。
窓を閉めた外からは何やら中嶋と女性の会話が微かに聞こえていたが、何を話しているのかはよく聞き取れなかった。
そしてどうやら中嶋達は結局ベランダでは行為に及ばず、部屋の中へと戻っていったようだった。
香苗 「……ふぅ……」
それを耳で確認した香苗は1つ息を吐く。
もちろんそれは少しの安心から出た息であったが、まだ不安と心配が残る複雑なため息でもあった。
非現実的な世界に浸っていると時間の流れ方がいつもと違うような感じがする。
祐二が出張に出て2日目の今日、今はまだその昼の時間帯。
そう、まだまだ非日常的なこの時間は続くのだ。
香苗の人生を変える事になるこの一日は長い。
41
午後の時間、香苗はずっと落ち着かない様子で部屋で過ごしていた。
本来なら読書や映画鑑賞など、1人でいる1週間を有意義に過ごすつもりで居たのに。
まさかこんな事になってしまうなんて。
しかしそれは自ら招いた事、あんな痴態を犯した事からの結果だ。
あの後、もう一度シャワーを浴びて服を着た香苗。
今思い出しただけでも、顔がカァっと熱くなる。自分で自分がした事が信じられない。
ベランダであんな事、しかも裸で……。
どうかしていた。
しかし今回ばかりは自分の中の後悔だけでは済まされない。
……ん?なんだ?今なんか変な声聞こえなかったか?
あの時の中嶋の反応、きっと気付かれてしまったに違いない。
自分の発してしまったのは明らかに甘い快感に溺れる女の声だったのだから。
しかし確信は持てない。
もしかして〝気のせいだった〟という事で済ませて、何も気にしていないかもしれない。
だけど怖かった。
もし次に顔を合わせる事になった時、中嶋はどんな目で自分を見てくるのだろう。
そしてどんな言葉を掛けてくるのだろう。
それが怖くて、部屋から一歩も出れない。
もし部屋を出た所で隣に居る中嶋と顔を合わせる事になったら……。
性的に興奮状態だった時は中嶋を、中嶋の身体を求めている自分がいた事は確かだった。
決して恋愛感情ではないと香苗は自身に言い聞かせているが、あの激しいSEXと雰囲気から伝わってくる中嶋のフェロモンに魅了されている自分は確かにいた。
しかし冷静になった今は、中嶋に対しては警戒心からくる恐怖感しか抱いていない。
とにかく中嶋が怖かった。中嶋と会ってしまう事が。
中嶋に会った瞬間に、自分の中の何かが崩れてしまいそうで。
香苗 「……。」
もう夕方の時間。
晩御飯は昨日の物が残っているが、なんだかちっとも食欲が沸いてこない。
時計を眺めながら、早く時間が過ぎて欲しいと願うばかりの香苗。
こんな1週間はすぐに過ぎて、祐二に早く帰ってきてほしかった。
きっと祐二が帰ってきてくれれば、凄く安心できると思う。
いつも当たり前のように祐二が帰ってきてくれていた、安心感に満ちた日常的な日々が、今はとても恋しい。
もちろん祐二の事はいつも頼りにしていたけれど、まさか自分がこんなにも祐二という存在に依存していたなんて思わなかった。
1週間という長い間の出張で、初めて香苗はそれに気付き、自覚したのであった。
祐二がいかに自分にとって大切な人であるかを。
香苗 「……祐二……」
香苗がちょうどそんな事を考えていた時だった。
テーブルの上に置いてあった香苗の携帯電話、その着信音が突然鳴り始めた。
♪~~♪~~♪~~……
その音を聞いて急いで携帯を手に持った香苗。
……この着信音……
この音はある人専用に設定してある音なのだ。
そして画面に出ている名前を見て思わず香苗は笑顔になる。
そう、香苗の思いが伝わったのか、その相手は祐二だったのだ。
香苗 「……も、もしもし?」
祐二 「おお香苗、元気にしてるかぁ?」
1日ぶりに聞く祐二の声。
たった1日会わなかっただけなのに、なんだか凄く久しぶりに聞いたような気分だった。
そして相変わらず祐二の声は優しくて、それだけで香苗は少し安心感を持てた。
香苗 「うん、元気。はぁ良かったぁ……祐二……」
思わず漏れた、香苗の気持ち。
祐二 「ん?ハハッ……へぇ、俺が居なくて寂しかった?まだ1日しか経ってないのに。」
香苗 「え?あ……ち、違うわよ!ただちょっとね……うん……こっちは1人の時間を有意義に過ごしてますよぉ、うん。」
香苗はすぐに強がるような部分がある。もちろん甘える時には甘えるのだが。
香苗 「祐二は?仕事順調?」
祐二 「あぁ、順調だよ。これからこっちの人に美味しい店に連れて行ってもらうしな。」
香苗 「え~何それ祐二だけズル~イ!」
祐二 「付き合いだよ付き合い。これも仕事の内さ。」
先程までの不安に満ちた気分とは打って変わって明るい気持ちになる、そんな祐二との楽しく幸せな会話は続いた。
他愛もないいつも通りの会話だったが、祐二の大切さを実感していた時にタイミングよく掛かってきた電話が、香苗はとても嬉しかった。
少し乙女チックかもしれないが、なんだかやっぱり運命的に祐二とは結ばれているような、そんな感じがしたのだ。
しかし、香苗にとってのそんな幸せな会話は15分程で終わった。
香苗 「あ、うん、じゃあね。身体に気をつけてね。」
香苗は最後に何気ないように装っていたが、内心は正直もっと祐二と話していたいという気持ちがあった。普段なら違ったかもしれないが、今日は特にそう思ったのだ。
でも香苗がその気持ちを表に出す事はなかった。
あまり祐二に心配掛けるような事はしたくなかったし、たった1日会わなかっただけでこんなにも寂しがっている自分を、なんとかく見せたくなったから。
祐二 「おお、じゃあ戸締りとかしっかりして寝ろよ。あ~あと何かあったらすぐ電話しろよ。」
香苗 「うん……わかったぁ。」
祐二 「じゃあな、また明日電話するから。」
香苗 「うん……じゃあね。」
そうして2人を繋ぐ電話は切れた。
先程までは時間の流れがあんなに遅く感じたのに、祐二との電話はあっという間であったように感じる。
香苗 「はぁ……」
電話が終わり、静まり返った部屋で漏れたため息。
再び時間が元に戻った事を感じた瞬間、その落差に思わずため息が出てしまったのだ。
……また寝る前に電話したら迷惑になっちゃうかな……祐二きっと疲れてるだろうしなぁ……
電話を切ってからすぐにそんな事を思ってしまうのは、まだまだ香苗の心が安心感で満たされていない証拠だったのかもしれない。
携帯を手に持ったまま香苗は、その画面に映る祐二と撮った写真をじっと眺めながら、まだ耳に余韻が残っている祐二の声を思い出していた。
もう外は暗い。
香苗 「あ……もうこんな時間、晩御飯どうしようかな……」
いつの間にか夜になっていた事に気付いた香苗は、食欲がない自分と相談するようにそんな事を呟く。
そしてキッチンに移動して冷蔵庫の中を見ていた、その時だった。
祐二との電話で少し薄れてきていた香苗の中にあるあの不安感、それが一気に膨れ上がる出来事が起きる。
ピンポーン……と、インターホンの呼び出し音が部屋に鳴り響いたのだ。
香苗 「……えっ?」
こんな夜に……誰……?
なんとも言えない、背中がゾクゾクするような嫌な予感が香苗の頭をかすめた。
42
香苗 「……どうしよう。」
インターホンモニターのボタンを押すのが怖かった。
もし今感じている嫌な予感が当たってしまったら……。
そんな事を思いながら香苗がなかなか出る事ができないでいると、もう一度ピンポーンと呼び出し音が鳴る。
なんだか急かされているような気分で、香苗は恐る恐るインターホンモニターのボタンを押した。
そしてモニターにドアの外にいる人物が現れる。
香苗 「あっ……」
それを見た瞬間にそう声を上げた香苗、予感は的中してしまっていた。
モニターに映った人物はやはり中嶋だったのだ。
中嶋 『こんばんわぁ!中嶋ですけど。』
少し大きい中嶋の声がスピーカーから聞こえる。
しかしモニターのボタンは押したものの香苗はなかなか声を出してそれに応える事ができなかった。
昼間に盗み聞きをしていた時のように胸の鼓動が早くなり、緊張で声が胸の辺りで詰まってしまう。
それにもし昼間の事で変な事を聞かれたらどうしようという思いもあった。
中嶋 『あれ?奥さん?もしも~し!』
香苗 「……。」
中嶋 「昨日のタッパお返しに来たんですけどぉ。」
香苗 「えっ?」
中嶋のその言葉を聞いて香苗はハッとして思い出した。
そうだ。昨日カレーを中嶋の所へ持って行った時にタッパごと渡したのだった。
中嶋はそれを返しに今来た。それは普通に考えてみればごく当たり前の行為。
恭子だって前に隣に住んでいた人だって、料理を持って行った次の日にはタッパを返しに来てくれた。
未だに中嶋に対しての警戒感はあるが、それなら出ない訳にはいかない。
香苗 「ぁ……あの……ちょっと待っててください。」
香苗は緊張気味に震えた声でそうモニターに向かって応える。
中嶋 「なんだ、やっぱ居るんじゃん。」
中嶋のその声を聞いた後モニターの前から離れた香苗は、洗面台の鏡で自分の顔と格好をチェックしてから玄関に向かった。
しかし玄関まで来て、ドアノブに手を掛けた所で香苗の動きは止まってしまう。
香苗 「……。」
このドアを開ければ目の前にあの中嶋がいるのだ。
そう思うと、やはり緊張してしまう。
しかし逆に少し冷静に考えてみるとなんて事は無いかもしれない。
ただタッパを返してもらうだけ、それだけなのだから。
タッパ受け取り、そしてそれだけできっとすぐに帰ってくれる。
香苗 「……ふぅ……」
自分を落ち着かせるかのように1つ深呼吸をしてから、香苗はゆっくりとそのドアを開けた。
中嶋 「ん……おお、こんばんは。」
香苗 「こ、こんばんは……。」
予想通りというか当たり前なのだが、ドアの向こうには中嶋が居て、笑顔で挨拶をしてきた。そしてそれに香苗も応える。
一目見た中嶋の姿、身体はやはり大きく逞しい。
それに男らしい独特のオーラを感じる。
中嶋 「いやぁ、昨日はありがとうございました。カレー超美味かったですよ。」
香苗 「そ、そうですか……それならよかったです。」
中嶋 「やっぱり奥さん料理上手なんですねぇ。」
香苗 「そ……そんな事……」
早くタッパを渡してもらって帰ってほしかった。
香苗はずっと斜め下を向いて中嶋の顔を見ることができない。
顔が熱い。きっと今自分は顔が真っ赤になっている。
そんな顔、中嶋に見せたら簡単に心の中を見抜かれてしまいそう。
中嶋 「……ところで奥さん、今日はずっと部屋に居たんですか?」
香苗 「……ぇ……?」
何気なく出てきた中嶋からのその問いに香苗は戸惑った。
なぜ突然そんな事を聞いてくるのか。
中嶋 「いやまぁ、あれでしょ?旦那さん出張なんでしょ?」
香苗 「ぇ……えぇ……。」
中嶋 「ずっと1人で部屋にいるんじゃ、奥さんも退屈でしょう?」
香苗 「ぇ……あの……」
中嶋 「退屈だったんでしょう?奥さん。」
香苗 「……それは……」
そうニヤニヤと笑みを浮かべながら言ってくる中嶋。
そんな中嶋の言葉に対して香苗は目が泳ぎ、明らかに動揺を見せている。
どう考えても中嶋はある意図があってそう聞いてきているのだと、香苗にも分かったからだ。
中嶋 「いやねぇ、俺も恭子がいなくて退屈してるんですよぉ。」
香苗 「わ……私は別に……えっ!?」
香苗が思わずそう驚きの声を上げたのは、香苗が少しだけ開いていたドアを、中嶋が手で強引に開けてきたからだ。
そしてドアを開けたかと思うと次の瞬間、中嶋は身体をドアの間に割り込ませるようにして玄関の中にまで入ってきたのだ。
香苗 「え、あ、あの、中嶋さん?」
中嶋 「旦那さんが居ないと寂しいでしょう奥さん、ちょっと色々と話しませんか?ほら、この前の食事会以来ちゃんとした会話してなかったじゃないですか、俺達。」
香苗 「で、でもあの……そんな突然……。」
中嶋 「ハハッ、いいじゃないですか、そんな気を使う事ないですよ、仲の良いお隣同士。ほら、俺酒持ってきたんですよ。」
そう言って手に持っているコンビニの袋に入った缶ビールを香苗に見せると、中嶋は靴を脱いで勝手に香苗達の部屋の中へと上がり込んでいく。
香苗 「ちょ、ちょっと中嶋さん、困りますそんな勝手に。」
中嶋 「大丈夫ですよ、つまみもちゃんと買ってきましたから。」
香苗 「そ、そういう意味じゃなくて……ホントに困ります中嶋さん。」
そんな香苗の言葉を無視するかのように、中嶋はドカドカと廊下を進んで行ってしまう。
……うそ……イヤこの人……なんなのよ……
常識を超えた中嶋の行動。
その全く予想外の展開に香苗は困惑し、心は大きく動揺していた。
43
中嶋 「へぇ~やっぱ綺麗にしているんですねぇ部屋。恭子の部屋も綺麗だったけど俺が住み始めてからは結構散らかってましてねぇハハッ。」
ついにリビングまで入ってきてしまった中嶋は、そう言いながらテーブルにビールの入った袋を置く。
そして香苗に何の断りもなくソファに腰を下ろした。
中嶋 「いいソファですねこれ、なんだか高級そうだ。」
香苗 「あ、あの……困ります中嶋さん……ホントに。」
立ったままの香苗は困惑しきった表情で中嶋に対しそう言った。
〝警察を呼びますよ〟そんな言葉が、もう喉まで出掛かっている。
しかし香苗はそんな大それた事をそう簡単にはできない。
隣人とのトラブルで警察を呼ぶなんて、やはりマンションの他の住人の目も気になる。
それにこの中嶋は大切な友人である恭子の恋人。その関係を変に拗らせてしまう事にも抵抗を感じる。
香苗 「……。」
中嶋 「ほら、奥さんも座ってくださいよ。まずは乾杯しましょう。」
ビールの缶を袋から2本取り出し、香苗の前に笑顔で差し出す中嶋。
ただただ困惑する香苗の気持ちなど気にも止めない様子で、中嶋は余裕の表情で愉快そうにしている。
香苗 「な、中嶋さんっ!いい加減にしてください!」
あまりに身勝手な中嶋の態度についに香苗はそう声を張り上げた。
しかしそんな香苗の声を聞いても、中嶋の態度は変わらない。
中嶋 「ハハッ!いい加減にしてくださいかぁ……ふーん……」
中嶋はニヤニヤと笑みを浮かべながらそう呟くと、缶ビールをプシュッと音を立てて開け、それをグビグビと流し込むように飲む。
そしてビールを半分程一気に飲んだ中嶋は、テーブルに缶を置いた後、ゆっくりとその口を開いた。
中嶋 「いやぁ奥さん……いい加減してほしいってのはこっちのセリフですよ。」
香苗 「……ぇ……」
中嶋 「困るんですよねぇ、毎日毎日、僕のプライバシーを侵害するような事をしてもらっちゃ。」
香苗 「……ぇ……ぁ……」
突然言われた中嶋からのその言葉に、香苗は言葉を失った。
まるで心臓を鷲掴みされてしまったかのように、香苗はその場で固まっている。
中嶋 「ねぇ?そうでしょう?奥さん。」
香苗 「……な……何を……」
まるで容疑者にでもなってしまった自分が中嶋に尋問されているような気分。
中嶋 「ハハッ!何をって事ないでしょ奥さん。知ってるんですよ、俺は……へへ……まぁとりあえずここに座ってくださいよ。」
香苗 「……。」
自信満々、余裕たっぷりの中嶋が言っている事が何を指しているのか、香苗には容易に想像できた。
もちろん、昼間のあの事を言っているのだろう。
やはり知られてしまっていたのだ。
昼からずっと、そうでない事を願っていた。しかし現実はやはり違っていた。
香苗は信じたくなかった。今のこの厳しい現状を。
夢なら覚めて!と、香苗は心の中で何度も叫んだ。
中嶋 「大丈夫ですよ奥さん、ほら、まずは一杯飲んで、心を落ち着かせましょう。」
不安げな表情で、言われるがままに中嶋から差し出された缶ビールを受け取り、ソファにゆっくりと腰を下ろす香苗。
香苗 「……。」
中嶋 「ほら、飲んでください。話はそれからです。」
香苗 「……。」
香苗は無言のまま、中嶋に言われた通りにビールに口を付けた。
ほろ苦い味とさわやかな炭酸が喉を通る。そしてアルコールにそれ程強くない香苗の身体は、ビールが通った部分がアルコールに反応して熱くなっていくのを感じた。
中嶋 「遠慮せずにどんどん飲んでくださいね。」
中嶋はそう言いながら近づいてきて、香苗が座っているすぐ横に再び腰を下ろす。
中嶋 「でもよかったですねぇ奥さん、ちょうど旦那さんが出張で。俺もあの事を旦那さんに言うのはちょっと気が引けますから。」
香苗 「……。」
依然、無言のままの香苗の頭の中には、祐二の姿が思い浮かんでいた。
……祐二……助けて……
そんな思いを抱く一方、中嶋が言っているのがあの事であるならば、祐二には絶対に知られたくないという気持ちも当然香苗にはあった。
中嶋 「奥さんも知られたくないでしょう?旦那さんには。」
香苗 「……中嶋さん……」
中嶋 「あの事は、今夜俺達だけで解決しましょう。それでいいですよね?」
そして中嶋はそう言いながらゆっくりと手を伸ばし、その大きな手で香苗の太腿辺りをそっと触った。
44
香苗 「……や、やめてください……中嶋さん。」
中嶋からのセクハラ行為に香苗は逃げるように身体を離そうとしたが、中嶋のもう片方の腕に肩を抱き寄せられるようにして捕まえられているので逃げらない。
太腿の上を擦るように動く中嶋の腕はやはり太い。その筋肉質で太い腕が、女性である香苗の力では、例え本気で抵抗しても全く適わないであろう事を物語っていた。
中嶋 「本当に止めてほしいと思っているんですか?」
香苗 「……お、思ってます……だから止めてください。」
香苗の声は震えている。
祐二以外の男性に気安く身体を触れている事への不快感。
そしてこれからどうなってしまうのだろうという恐怖感で香苗の心の中は埋まっていた。
繰り返し後悔の念が溢れてくる。
なぜあんな危険な綱渡りを続けてしまったのか。
なぜ絶対に入ってはいけない領域にあそこまで近づいてしまったのか。
中嶋 「では確認なんですけどね、奥さん、昼間ベランダで何をなさっていたんですか?」
香苗 「……。」
中嶋 「……ん?どうなんです?」
香苗 「……それは……」
中嶋 「答えられませんか?」
香苗 「……。」
ただ顔を赤くして俯くだけの香苗。
中嶋は意地悪そうにニヤニヤと笑いながら香苗の耳元に口を近づける。
中嶋 「じゃあ……俺が教えてあげましょう。」
香苗 「……」
中嶋 「……オナってたんでしょ?イヤらしい声出しながらさ。」
自分の痴態、逃れようの無い真実を中嶋の口から突きつけらた香苗。
耳まで赤くして、目は潤み、今にも涙が零れそう。
中嶋 「聞えてましたよ、奥さんのイヤらしい声。……あの時、イッたんですか?」
香苗 「……ぃ…イヤ……」
中嶋 「へへッ……ベランダでイク時は特に気持ちイイんですか?奥さん意外に大胆なんだなぁ、真面目そうに見えるのに。」
そう言いながら中嶋は口から長い舌をネットリと伸ばし、香苗の耳を舐め始めた。
耳元でのネチョネチョとした音と、中嶋の舌のネットリとした感覚に香苗はすぐに拒絶反応を見せる。
香苗 「ン……ァ……イヤッ!イヤです……やめて……ン……」
中嶋 「耳を舐められるのは嫌いですか?それにしては敏感な反応ですねぇ。」
香苗の身体をしっかりと掴んでいる中嶋は、香苗の抵抗を物ともせずに耳舐めを続ける。
香苗 「ン……ハァ……やめて…ホントにやめてください中嶋さん!」
中嶋 「素直になりましょうよ奥さん。俺にはわかっているんですよ。」
香苗 「ハァハァ……何が……ですか?」
あたかも自分の事を全て理解しているかのような中嶋の口ぶりに、香苗はすぐに聞き返す。
中嶋 「不満をもっているのでしょう?旦那さんに。」
香苗 「……そんな事……私は……」
中嶋 「満足している?旦那さんとのSEXに。」
香苗 「……ぇ……」
祐二とのSEX……
祐二に不満など持っていなかった、結婚してからずっと。
でも、どこかで歯車が狂い始めてしまった。
そう、この中嶋という男に出会ってから。
この人に出会わなければ、普通で幸せな生活を続けていたに違いない。
そして今のように、1人の女性としてこんなに追い詰められた状況になる事もなかったはず。
中嶋 「溜まっているのでしょう?そして奥さんの中に溜まっているものは旦那さんが相手では解消できない。違いますか?」
香苗 「……イヤッ……」
認めたくなかった。
これを認めてしまえば、まるで祐二が、この中嶋よりも男性として劣っていると認めてしまうようなものだ。
中嶋のようなこんな男に、祐二の事を馬鹿にされたくない。
祐二の事を世界の誰よりも愛している。香苗の中で、その気持ちに揺るぎはなかった。
中嶋 「もう認めちゃえばいいじゃないですか。旦那とのSEXに満足できなくてオナってましたってさ。」
香苗 「……そ、そんな……事……」
中嶋 「そんな事ない?本当に?旦那さんで満足しているんですか?」
香苗 「あ、当たり前です……。」
中嶋 「ハハッ本当かなぁ?」
相変わらずニヤニヤとした表情で中嶋は、香苗の太腿を触っていた手を、さらに内腿の方へと進めていく。
中嶋の手が脚の付け根に近づいてきた時、香苗の拒絶反応はピークを迎えた。
香苗 「も、もうイヤっ!離して!早く出て行ってくださいっ!」
今までよりも強く抵抗する香苗。中嶋の太い腕を両手で持って、精一杯押し退けようとする。
必死だった。
先程の祐二との電話で気付いたのだ。やっぱり祐二といっしょにいる事が自分にとっての幸せだと。
祐二との幸せな夫婦生活を壊されたくない。
中嶋 「嫌ですよ、離しません。せっかく奥さんと2人きりになれたんだから。」
香苗 「ハァ……イヤ!放して……ハァ……」
中嶋の腕の中で必死にもがく香苗は息を切らしながらも、まだ抵抗をやめない。
中嶋 「頑張りますね奥さん。奥さんの旦那さんへの愛が本物だという事は分かりましたよ。」
その言葉を聞いて、香苗はやっと抵抗の力を弱めた。
香苗 「じゃ、じゃあ早く放してください……。」
中島 「いいですけど、1つ条件があります。」
香苗 「……条件?」
中島 「えぇ。その条件を奥さんが飲んでくれれば俺は部屋に帰るし、昼間の事も今夜の事も全て忘れます。あの事は俺と奥さんだけの秘密、誰にも言う事はありません。旦那さんにもね。」
香苗 「本当……ですか?」
中島 「もちろん。綺麗サッパリ忘れます。奥さんも忘れればいい。全てを無かった事にするんです。」
香苗 「……それで、条件っていったい何ですか?」
中島 「フッ……それはですねぇ……へへ……」
香苗 「……?」
中島 「それはですねぇ、奥さんの身体を今夜一晩だけ俺の好きなようにさせてほしいんです。」
香苗 「……ぇ……」
中島 「要は俺と今夜、一発SEXしてくださいって事です。」
45
香苗は言葉を失っていた。
……中嶋さんと……
それは香苗が隣の部屋の声を聞きながらずっと妄想してきた事。
現実ではない、別世界での話であったはずの事。
しかしそれを今、中嶋の口から直接言われたのだ。
中嶋 「どうです?1回だけ試してみませんか、旦那さん以外の男の身体を。」
香苗 「……な……何を言ってるんですか……そんなの……。」
できるはずない。
……私には……祐二がいる……
結婚式も挙げて、これまで幸せに暮らしてきた。
そんな事をしてしまえば、それが全て崩れていってしまう。
香苗 「お……おかしな事言わないで下さい……だ、大体、中嶋さんには恭子さんがいるじゃないですか。」
中嶋 「恭子?あぁ恭子の事なら気にしなくていいですよ。恭子は知ってますから。」
香苗 「知ってる……?」
中嶋 「俺がこういう男だって事をですよ。」
香苗 「そんな……そんなのおかしいですよ……。」
中嶋 「何がおかしいんです?価値観は人それぞれ、男女関係もそれぞれじゃないですか。」
香苗 「……だけど……」
香苗には全く理解できない事だった。
いやもちろん実際学生時代などでも浮気癖のある知人はいたが、その時から香苗はそういう人達の価値観が理解できなかった。
恋人ではない人と身体の関係を持つなんて全く理解できない事。
だから香苗はずっとそういった人間と世界からは距離を置いて生きてきた。
そんな事をしたら自分が自分でなくなってしまう。
中嶋 「奥さんも一度体験してみましょうよ、俺達の世界を。」
香苗 「……私は……違いますから……私はそんな……」
中嶋 「そんな女じゃない?よく分かってますよ、奥さんは真面目な人だ。旦那さん一筋ですもんね。」
香苗 「……。」
中嶋 「だけど、1日だけ別の世界を体験するのも良いんじゃないですか?別に減るものじゃないし。」
香苗 「……そんなの……」
中嶋 「誰にもバレませんよ。」
香苗 「……ぇ……」
中嶋 「さっきも言いましたがこれは俺達だけの秘密ですから、大丈夫です。」
香苗 「……。」
中嶋 「明日になればまた日常が戻ってきます。ね?少し味見するだけくらいの気持ちで。ちょっとしたお試し体験ですよ。」
中嶋は香苗の耳元で呪文のようにそう語りかける。
抵抗を止めた香苗は中嶋の腕の中で、それを聞いて少し考え込んでいる様子だった。
明日になれば戻ってこれる。そんな都合の良過ぎる中嶋からの提案が、頭の中を駆け巡り、香苗を誘惑していた。
あの世界に少し足を踏み入れてしまったがために中嶋に知られてしまった、香苗の痴態。
しかし後悔の念を感じている今でも、その世界が香苗の身体の奥にある、性への好奇心を刺激している事は確かだった。
一度その世界に入っても、帰ってこれる。祐二との幸せな生活も壊す事はない。
性の快楽に憧れるもう1人の香苗にとって、それはとても魅力的な事であるのかもしれない。
まさに普通ではありえない夢のような話。
しかし今の香苗は普通ではありえない話であっても乗ってしまいそうな程、冷静さを欠いていた。
中嶋 「奥さんは今までもこれからもずっと旦那さんを愛している。それでいいんです。今日の出来事は夢だと思えばいい。」
中嶋は香苗の肩を抱いたまま、香苗の髪を大きな手でそっと撫でる。
香苗は自然と目線を上げ、中嶋の目を見つめる。
中嶋の目は、まさに獲物を狙う、飢えた猛獣のような目だった。
しかしそんな目が、香苗の女としての本能を熱くさせていた。
身体の奥から沸々と沸いてくる、欲望。
香苗 「……夢……?」
中嶋 「そう……夢です。夢から覚めれば、奥さんが昼間やっていた事も今晩の事も、全て消えてなくなる。」
香苗 「……でも……」
中嶋 「でも?」
香苗 「でも私……あなたの事、嫌いですから……。」
自分が愛しているのは夫の祐二で、中嶋ではない。
その事を再度香苗は声に出して中嶋に伝えた。
そしてそれは同時に、香苗が自分自身に言い聞かせた言葉でもあった。
自分の心に、祐二との決して切れる事のない愛を再確認させたのだ。
中嶋 「ハハッ、いいですよ、嫌いでも。今日は心を外しておけばいいですから。」
香苗 「…………きゃっ……」
そう言って中嶋は香苗の身体をさらに近くに抱き寄せる。
そして片手を香苗の顎に添えて自分の顔の方へ向かせる。
中嶋 「俺に身を委ねてくれればいいですからね。」
香苗 「……ン……イヤ……」
中嶋 「大丈夫です。すぐに嫌だなんて言えなくしてあげますから。」
ゆっくりと近づく二人の唇。
魅惑的な世界への扉が開いていく。
ついにその世界に入っていく自分を許してしまう香苗。
そして中嶋は、香苗の震える唇を奪った。
46
唇が触れ合った瞬間から、それが今まで香苗が経験してきたキスとは大きく違っている事がすぐに分かった。
下唇に吸い付いてくる感覚。そしてすぐに中嶋は舌を使ってくる。
最初は抵抗するように口を懸命に閉じて舌の侵入を拒んでいた香苗だったが、いつしかゆっくりとその口を開いて受け入れてしまう。
上手なキスとはこういうキスの事を言うのだと、香苗は中嶋に教えられているような気分であった。
香苗 「ン……ン……ァ…ン……」
ひたすら受身である香苗の口内で、ヌメヌメと犯すように舌を動かす中嶋。
……ああ……祐二……
今日一日だけ心を外せば良いなどと言われても、そう簡単にはいかない。
香苗の心の中にはやはりまだ祐二がいた。
中嶋の唇が触れたと分かった瞬間、祐二の顔が思い浮かび〝やっぱりダメッ!〟と反射的に両手で中嶋の胸を押し返すような仕草をしたが、分厚い胸板はその抵抗に対してビクともしなかった。
そして今では舌の侵入まで許してしまっている。
唇を奪われているという感覚。しかしそれだけじゃない。
香苗の頭の中で祐二の事を考える思考力さえ、中嶋の濃厚なキスは徐々に吸い取っていく。
唇だけじゃない。何か大切なものまで中嶋に奪われていくような感覚。
そんな香苗の閉じた目からは、涙が零れていた。
ピチャ……クチャ……ピチャ……
香苗 「ン……ハァ……ン……ァ……」
段々と激しくなっていくディープキス。
異物が入ってきた事で分泌が加速する唾液。
お互いに増えていく唾液が絡まり合い、よりネットリとしたキスに変わっていく。
ハァ……ン……ハァ……ンハァ……
激しい息遣い。
酸欠で頭の中が麻痺するような感覚が、じんわりとした快感に変わっていく。
抵抗をやめた香苗の手は中嶋の胸に添えているだけの状態だ。
今の香苗はもう、明らかに中嶋の巧みなキスに酔っている。
それを察した中嶋は、ずっと香苗の太腿を擦っていた手を少しずつ上へと移動させていく。
そして中嶋の大きな手が、香苗の胸の膨らみを服の上から揉み始めた。
香苗 「ゥン…フゥ……ン……ぁ……」
香苗がソファの上で横になるようにゆっくりと中嶋に倒されていったところでやっと口を解放される。
唇が離れる時、その間には2人の混ざった唾液がネットリと糸を引いていた。
香苗 「んはぁっ……ハァ……ハァ……」
中嶋 「はぁ……奥さん、興奮してきたでしょ?」
中嶋はそう言いながら、香苗が身につけている服に手を掛け脱がさせようとする。
が、香苗は咄嗟にそれを拒もうと中嶋の腕を掴んだ。
香苗 「ハァ……ぁぁ……ダメ……ンン……」
しかし再び中嶋に唇を奪われ、口内の舐め回されると、中嶋の腕を掴む香苗の手の力は抜けていってしまう。
ン……ピチャ……ンハァ……ンー…フゥ…ハァ……
中嶋のディープなキスはまるで魔法のように香苗の中に残った僅かな抵抗力も奪っていく。
香苗 「はああ……イヤ……」
中嶋は抵抗が弱まった香苗の、下に身に着けていたスカートを慣れた手つきで手早く下ろしていく。
そして香苗の脚からスカートを抜き去ると、スカートを床へ落とした。
露わになる薄ピンクの上品な下着。
中嶋 「へぇ~結構高そうな下着付けてますねぇ奥さん。……さて、上はどうなってるのかな。」
中嶋は続いて流れる様な動きで香苗のブラウス、そのボタンへと手を伸ばす。
香苗 「……イヤ……」
その時も香苗はボタンを外そうとする中嶋の腕を掴むが、その力は微弱なもので中嶋の行動を到底止められるようなものではなかった。
中嶋 「奥さんは嫌々と言いながら全然抵抗しないんですね?へへ……可愛い人だなぁ。」
香苗 「……。」
1つ2つとテンポ良く外されていくボタン。
あっという間にその全てが外され、中嶋にブラウスの前を左右に大胆に広げられる。
中嶋 「お~……肌綺麗ですね。」
顔を赤くしながら横に背けたまま、香苗は黙っていた。
そんな香苗の胸の膨らみを、今度はブラジャーの上から揉み始める中嶋。
中嶋 「こうやって旦那さん以外の男に胸を揉まれるのって、どんな気分なんですか?」
香苗 「ン……ぁ……知りません……そんなの……ぁ…」
中嶋 「またそんな事言っちゃってぇ。結構敏感に反応してるじゃないですか。さて、中はどうなってるのかなぁ」
香苗 「ぇ……あっ嫌っ!」
香苗がそう声を上げた頃にはもう遅く、ブラジャーは中嶋の手によってグイっと上にズラされてしまった。
乳房がブラジャーの締め付けから解放されたのが分かる。
そこを見てニヤニヤとイヤらしく笑っている中嶋の目。
……ぁぁ……恥ずかしい……
ここまで中嶋の思うがままに流されてしまっていると自覚しているにも関わらず、香苗はその中嶋の動きも、流される自分も止める事はできなかった。
中嶋の動きは慣れていて、とても手際が良いように思えた。
気付いたら服を脱がされていた。そう感じてしまう程、中嶋は女性の扱いが巧い。
きっと今までの女性も、皆この中嶋のテクニックに酔ってきたのだろう。
そして今、自分もその中の一人になってしまっている。
そう思うと、香苗の身体はさらに熱くなった。
47
中嶋 「へぇ~……これまた綺麗なオッパイしてますねぇ。……ていうか奥さん、ハハッ、すっげぇ乳首立ってますけど?」
香苗 「ぇ……イヤッ……」
中嶋の指摘に香苗は恥ずかしそうにして、胸を隠すように身体を横に向かせる。
中嶋 「嫌々とか言いながら胸揉まれて感じてるんだもんなぁ、奥さんのここは結構敏感なんですか?」
中嶋の言葉の1つ1つが香苗の羞恥心を刺激する。
この状況に全く余裕が持てない自分に対し、余裕たっぷりといった感じの中嶋の態度。
香苗の中にいるもう1人の淫らな自分の存在を、そんな中嶋に少しずつ見抜かれていくような感覚が恥ずかしかった。
中嶋 「ちょと味見させてもらいますよぉ。」
小粒ながらも固く勃起した香苗の乳首に口を近づけた中嶋は、舌を大きく出してそれを舐め始めた。
香苗 「ン……ァ……ンッンッ……イヤ……ァ……ハァ……」
舌先で乳首を転がすようにベロベロと舐める。
中嶋の唾液に濡れテカテカと光沢を放つ乳首は、その固さをさらに増していく。
そして中嶋は同時に、大きな手で柔らかな乳房全体を大胆に揉み始める。
中嶋 「奥さん胸責められるの好きでしょ?いつも旦那さんにちゃんとやってもらってますか?こうやってさ。」
勃起した乳首を歯で軽く挟み引っ張る中嶋。
すると、決して祐二の愛撫では感じた事のない、痛みに近い鋭い快感が香苗の身体を襲った。
香苗 「ン……っんはぁ!」
責めに対して敏感に反応する香苗の身体を楽しそうに弄ぶ中嶋は、次のステップに進むため、片方の手をゆっくりと下へと移動させていく。
胸からお腹、ヘソ、下腹へと指先でなぞるようにして移動させる。
中嶋の指が通る場所がこそばゆいようで、香苗は身体をモジモジと動かす。
香苗 「はぁぁ……ダメ……そっち……」
徐々に下へと移動していく中嶋の手の動きを察知し、咄嗟にそう口から漏らす香苗。
中嶋 「何がダメなんですか奥さん、こっちもしてほしいでしょ?」
香苗 「ハァ……ァァ……」
中嶋の指は止まる事なく、そのまま股の中心の割れ目まで到達してしまう。
そしてその指は下着の上から、上下に割れ目をなぞるように動きだす。
中嶋 「ん~あれ?奥さん、下着濡れてますよ?」
中嶋の言うとおり、香苗の下着は染みをできる程に濡れていた。
香苗 「……ハァ……イヤ……」
下着の底の部分を指が押さえつけると、その染みはジワジワと広がっていく。
中嶋 「あ~ぁ、ハハッ、奥さん濡れすぎだって。」
中嶋は若干呆れたような表情でそう言った。
中嶋 「下着、これ以上汚れるの嫌でしょ奥さん。」
そう口にした時にはすでに、中嶋の両手は香苗の下着に掛かっていた。
中嶋 「奥さん、ちょっと腰浮かしてくれませんか?」
香苗 「……ィ…イヤ……」
中嶋 「腰を浮かしてください。」
香苗 「……。」
中嶋 「奥さんほら、腰を浮かしてください。」
香苗 「……。」
再度中嶋にそう言われ、香苗は数秒間黙り込んだ後、ゆっくりと腰を浮かせた。
そしてその瞬間、中嶋の手が一気に香苗の下着を引きずり下ろしす。
香苗 「……ぁぁ……」
なぜ中嶋の言うとおりにしてしまったのかは、香苗自身も分からなかった。
ただ、そうしないと先に進まないと思ったから。
しかしそれはつまり、香苗が心のどこかで思っている、この後の中嶋との展開を期待しているという気持ちの表れでもあったのかもしれない。
中嶋 「あ~ぁ、奥さん、凄く濃いのがベットリ下着に付いてますよ。」
香苗の脚から抜き取った下着の底部分を広げて見ている中嶋。
香苗 「い、嫌っ見ないで下さいそんなのっ。」
顔を真っ赤にして中嶋から下着を取り返そうとする香苗。
しかし香苗のそんな動きよりも早く、中嶋は下着を床に投げ捨ててしまう。
そして中嶋は起き上がってきた香苗をもう一度ソファに押し倒すと、そのまま香苗の細い脚を手で掴んだ。
中嶋 「そんな格好にまでされて今更恥ずかしいも何もないでしょう奥さん。」
香苗 「……。」
中嶋 「今からはただ素直に気持ち良くなればいいんですよ。まぁ強がる奥さんも面白いからいいですけどね。」
香苗 「……。」
見下されているような感覚だった。
中嶋の前で理性を保とうする自分と、もう全てを曝け出したいと思っている自分。
こんな状況になっても、まだ理性を保とうとする自分がいる限り、香苗は中嶋に心まで許してしまう訳にはいかないのだ。
中嶋 「さて、いつまで奥さんは強がっていられるかなぁ……へへ……。」
中嶋はそう楽しそうに言うと、香苗の脚を掴んでいた手で股を強引に広げさせた。
48
香苗 「ハァ……ダ……メ……」
強引に広げられた香苗の股の中心に、中嶋の手がゆっくりと近づいてくる。
中嶋 「そういえば奥さん、昼間イヤらしいオモチャ使ってたでしょ?」
香苗 「……ぇ……。」
中嶋 「聞えてたんですよ、音がね。どこで買ったんですか?やっぱりネットですか?」
香苗 「……。」
答える事なんて香苗にはできない。
本当なら、ローターを使っていた事さえ認めたくなかった。
中嶋 「オモチャを使うと、やっぱり気持ち良いんですか?」
香苗 「……もう……聞かないで下さい……」
中嶋 「そっかぁ、ベランダでオモチャ使ってオナってたのかぁ、とんだ変態ですね奥さんは。」
香苗 「……」
〝変態〟という言葉が香苗の胸に突き刺さる。
ショックだった。
認めたくもないし、まさか自分の人生で人に〝変態〟などと言われる日が来るなんて夢にも思っていなかった。
中嶋 「ここを、刺激してたのでしょ?」
そう言って香苗の敏感な箇所、陰核を指で刺激する中嶋。
香苗 「アアッ……」
その刺激に対して香苗の身体はビクンと反応を示す。
中嶋 「ハハッ、奥さん、かなり感じやすいみたいですね。これではオモチャにハマっちゃうのも無理はないですね。」
香苗のクリ○リスは乳首同様、固く勃起していた。
そこを軽く触るだけで香苗の身体はビクンビクンと反応する。
今まで自分で触ってもそこまで敏感に感じる事はなかったのにと、香苗自身戸惑っていた。
中嶋に股を広げられ、クリ○リスを触られている。その事が香苗の身体をいつも以上に敏感にさせていたのだ。
身体の反応は自分で抑えようと思って抑えられるようなものじゃない、陰核を刺激されるたびに身体が勝手に反応してしまう。
そして反応する度に体温が徐々に上がってくるのが分かる。下腹部が、熱くなっていく。
香苗 「ンッンッンッ……ハァ……ン…ハァ……」
中嶋 「随分と気持ち良さそうですね、奥さん。」
そう指を細かく動かし続けながら聞く中嶋。
香苗 「ンッ……あっあっ……イヤ……ンッンッ……」
中嶋 「まだ嫌だなんて言ってるんですか、仕方ないですねぇ。では一度イかせてあげましょうか。一度イってしまえば奥さんの考えも変わるかもしれない。」
香苗 「ハァ……イヤ……そんなの……」
香苗は脚を閉じようと力を入れ、最後の抵抗を見せるも、中嶋の手に簡単にそれを抑えられてしまう。
中嶋 「ここからこんなにダラダラ涎垂らしながら嫌だなんて言っても説得力無いですよ。」
そう言って中嶋は香苗の膣口の入り口に指をあてる。
香苗 「ハァ……ハァ……ああ………」
そしてクチュゥっと音を立てて香苗の膣内に中嶋の太い指が沈んでいく。
中嶋 「あ~ぁ、グチョグチョ、すげぇなこれ。」
クチャ……クチャ……クチャ……
膣内に入れた指をゆっくりと動かし始める中嶋。
そしてそれを動かす度に粘着質の卑猥な音が部屋に響く。
香苗 「ん……ハァ……ん……ハァ……」
中嶋 「あ~濃いなぁこれ。本気汁だなこれは、白濁してるし。ねぇ奥さん、ケツの穴まで垂れていっているの自分でわかります?」
香苗 「ハァ……イヤ……ん……あっ…ァ……」
ケツの穴……そんな所まで中嶋に見られている事が、どうしようもなく恥ずかしい。
そして中嶋に言われたとおり、肛門の方へトロトロとした濃厚な愛液が流れているのは、香苗自身も肛門から伝わる感覚から分かっていた。
中嶋 「はぁぁ……エロいマ○コだなぁこれは。奥さん、そろそろ指増やしますよ。」
今まで一本だけ入れていた指を、今度は二本に増やして再び膣に挿入させていく中嶋。
しかし倍の太さに変わっても、香苗の濡れた秘部はそれを容易に呑み込んでいった。
香苗 「……ああ……ン……ハァァ……」
中嶋 「二本の方が太くて好きみたいですね奥さんは。……じゃあちょっと、激しくしていきますよ。好きなだけ感じてください。」
グチュグチュグチュグチュ……!!
香苗 「ンッンッ……あっあっあっこれ……ハァァ…アッアッアッ……」
中嶋 「ここが特に感じるみたいですね。」
香苗の膣内で感じやすいポイントを早々に見つけだした中嶋は、二本の指でそこを重点的に刺激する。
香苗の反応もより大きくなり、膣はグイグイと収縮し中嶋の指を締め付ける。
中嶋 「凄いですね奥さん、濃いのがどんどん溢れてきますよ。」
グチャグチャグチャグチャ……!
香苗 「ああ……ンッンッ…あっあっあっ……ハァァああ……」
中嶋 「もう、嫌なんかじゃないでしょ?」
香苗 「んぁあ……アッアッアッアッ……ンッンッンッ……はああ……ダメ……ああ……」
中嶋 「いい反応だ……そろそろイきそうみたいですね。いいですよ、思う存分イってください。」
そう言ったのを切っ掛けに、中嶋の指の動きは一気にその激しさを増した。
出典:メンメンの官能小説
リンク:http://menmen1106.blog130.fc2.com/category16-9.html
良かったら「いいね」してください。誰でも「いいね」出来ます!